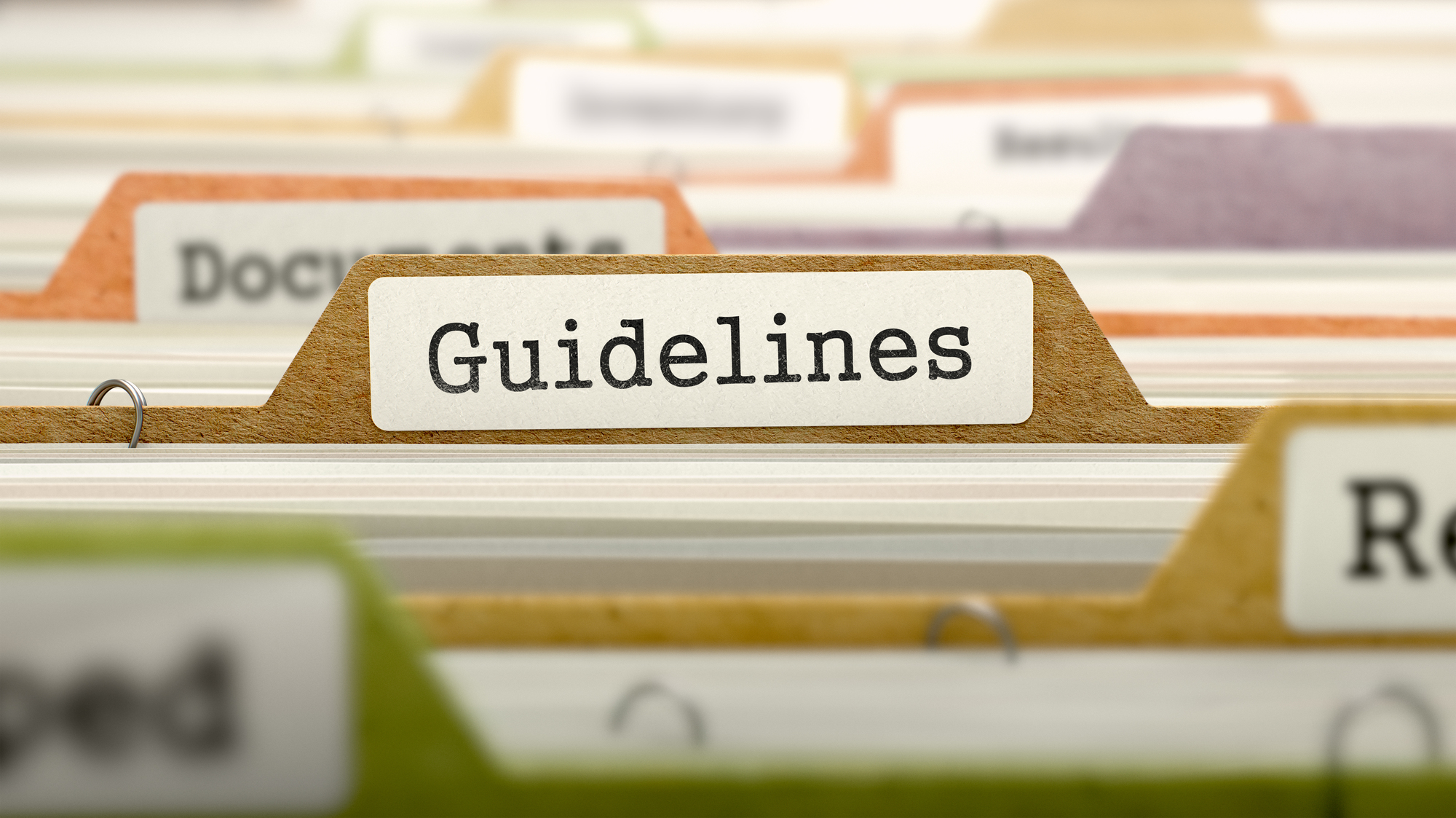DESとは何か?経営者が知っておくべきメリットとデメリットを解説
企業が財政難で倒産の危機に陥った際、再建支援の選択肢として『DES』が用いられます。債務の株式化で財務改善が期待できる一方で、新たな株主による経営への干渉や法人税の増加などのデメリットもあります。慎重に検討を重ねた上で実行しましょう。


企業の財務状況が悪化した際、再建のための選択肢として「DES(デット・エクイティ・スワップ)」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。しかし、具体的にどのような手法で、自社の再建やM&Aにどう活用できるのか、正確に理解するのは難しいと感じていませんか。
DESとは、企業の債務(Debt)を株式(Equity)に交換(Swap)する財務改善手法です。
この記事では、DESの基本的な意味から、メリット・デメリット、M&Aや事業承継における具体的な活用スキーム、さらには税務・会計上のポイントまで網羅的に解説します。
本記事を最後までお読みいただくことで、DESへの理解が深まり、自社の状況に合わせて最適な財務戦略を検討する一助となるでしょう。
ぜひ、M&Aや事業再生を成功に導くための知識としてお役立てください。
DESとは何か?

経営不振の企業を立て直す手段の一つに『DES(デット・エクイティ・スワップ)』があります。DESと同様の目的で活用される『DDS(デット・デット・スワップ)』との違いも把握しておきましょう。
DESの意味
『DES』は『Debt Equity Swap』の略称で、日本語では『債務の株式化』と呼ばれることがあります。三つの英単語はそれぞれ下記のような意味です。
- Debt:債務
- Equity:株式
- Swap:交換
つまり、経営不振や過剰債務に陥っている企業の債務を、債権者が『株式』と交換することで財務改善を図る手法です。負債が減り、弁済義務のない資本が増えるため、企業は経営を立て直すことができます。
後述しますが、株式化の方法には、債権者が保有債権を『現物出資』する方法と、新たに資金を拠出して『金銭出資』する方法の2つがあります。
DDSとの違い
DDSは『Debt Debt Swap』の略称で、既存の債務を返済順位の低い『劣後ローン』へと切り替える手法を指します。
DESとDDSの違いは、以下のように表現できるでしょう。
- DES:債務を『株式』に交換する
- DDS:債務を『別の債務』に交換する
劣後ローンとは、返済順位が通常の債務より後回しになる代わりに、金利が高めに設定されているローンです。
経営不振で企業が倒産した際、劣後ローンの返済はほかの債務の返済の後に回すことができます。
劣後ローンの中で、一定の条件を満たしたものは、負債でも『自己資本』と見なされます(資本的劣後ローン)。融資先企業を返済能力で格付けした『債務者区分』が改善されるため、銀行から追加融資を受けやすくなるのです。
債権者が金融機関の場合は、中小企業ではDDSが選好される傾向が指摘されていますが、DESが採用される事例もあります。

DESの2つの種類
DESは、現金の有無によって「現物出資型」と「金銭出資型」に分けられます。
日本で多く用いられるのは現物出資型ですが、金銭出資型は疑似DESとも呼ばれます。
それぞれの手法には特徴があり、手続きの流れも異なります。
現物出資型
現物出資型DESとは、債権者が保有する「債権」そのものを現物として出資し、対価として債務者である企業の新株を受け取る方法です。
帳簿上での振り替えが中心で、現金の払い込みは発生しません。企業側は、出資された債権を出資金とみなし、債権者に株式を交付します。
この方法は、特定の第三者に新株を引き受けさせる「第三者割当増資」の一環として実行されるのが一般的です。
金銭出資型
金銭出資型DESは、まず債権者が債務者に対して現金で出資(増資)を行い、債務者はその払い込まれた現金を原資として、既存の借入金を返済する方法です。
債権と株式の直接交換は行われませんが、結果は現物出資型と同じになるため、疑似DESとも呼ばれます。
この手法では、「第三者割当増資の手続き」と「債務返済の手続き」の両方が必要となり、現金の移動が伴う点が現物出資型との大きな違いです。

DESのメリット

DESは、債務を株式に転換することで、債権者と債務者の双方にメリットをもたらす可能性があります。債務者にとっては財務体質の改善が大きな利点ですが、債権者にとっても将来的なリターンや経営への関与といったメリットが期待できます。
債権者側
債権者にとっての最大のメリットは、貸倒損失になるはずの債権を、将来価値を持つ可能性のある株式に換えられる点です。
企業の再建が成功すれば、株価の上昇によるキャピタルゲインや配当収入を得られる可能性があります。
また、株主として経営に参画し、再建プロセスを監督したり、経営判断に影響を与えたりすることも可能になります。
債務者側
債務者である企業側のメリットは、財務体質を根本から改善できる点です。
貸借対照表の負債の部に計上されていた借入金が、純資産の部の資本金に振り替えられるため、自己資本比率が向上し、財務の安全性が高まります。
また、借入金の元本返済や利息の支払いが不要になるため、キャッシュフローが大幅に改善し、資金繰りの安定化に繋がります。
これにより、金融機関からの追加融資を受けやすくなる効果も期待できます。


DESのデメリット

DESは財務改善に有効な一方で、債権者・債務者双方にとって考慮すべきデメリットも存在します。
債権者は株式の価値変動リスクを負い、債務者は経営の自由度が低下する可能性があります。
実行にあたっては、これらのリスクを十分に理解することが不可欠です。
債権者側
債権者側のデメリットは、債権という確定したリターンを放棄し、価値が変動する株式を保有することになる点です。
企業の再建が計画通りに進まなければ、株式の価値が下落し、結果的に投資回収ができないリスクがあります。
また、再建中の企業は配当を出さないケースが多く、インカムゲインが期待できない可能性も高いでしょう。
さらに、保有する株式の比率によっては、経営への影響力が限定的になることもあります。
債務者側
債務者である企業側にとっては、新たな株主の登場により、経営の自由度が下がる点が大きなデメリットです。
債権者が大株主となった場合、株主総会を通じて経営方針に大きな影響力を持つことになります。
これにより、創業オーナーや既存経営陣の意思決定が制約される可能性があります。
特に、議決権の過半数を第三者に握られると、経営権そのものが脅かされる事態も起こり得ます。
また、資本金の増加により、法人税の負担が増える可能性がある点にも注意が必要です。


M&A・事業承継におけるDESの活用スキーム

DESは、単なる企業再生の手法にとどまらず、M&Aや事業承継の場面でも有効なスキームとして活用されます。
オーナーからの借入金の整理や後継者の負担軽減など、幅広い目的に応用できます。
スキーム①:オーナーからの借入金を整理し、M&Aを円滑に進める
中小企業では、オーナー経営者が会社に資金を貸し付けている「役員借入金」が多く見られます。M&Aの際、役員借入金は買い手にとって負債となり、価格低下や交渉の障壁となる場合があります。 そこで、M&A実行前にDESを活用し、役員借入金をオーナー経営者の株式に転換します。
これにより、会社の負債が減少し、財務状況が改善されるため、買い手は安心してM&Aを進めることができます。結果として、好条件での売却が期待できるでしょう。
このスキームは、買い手にとっては返済義務のある負債が消え、財務的にクリーンな会社を買収できるという大きなメリットがあります。
一方、売り手であるオーナーにとっては、役員借入金という債権を株式に換えることでM&A交渉の障壁を取り除き、取引を成立させやすくすることが最大の目的です。
結果として、会社全体の企業価値が向上し、円滑かつ有利な売却につながる可能性があります。
スキーム②:後継者の財務的負担を軽減する
事業承継において、後継者が先代経営者から株式を買い取る際、その資金調達が大きな課題となることがあります。特に多額の役員借入金がある場合、後継者が返済義務を負うため、負担はさらに増します。
DESを活用して役員借入金を株式に転換しておくことで、後継者が引き継ぐ負債をなくすことができます。
このスキームは、後継者にとっては会社の財務が健全化され、株式取得後の経営に専念しやすくなるというメリットがあります。
一方、先代経営者にとっては、回収の不確実性があった貸付金を株式という資産に換えることで、相続計画を立てやすくなる側面があります。
ただし、先代経営者は債権を価値変動リスクのある株式に換えることになるため、承継後の会社経営がうまくいかなければ、資産価値が減少するデメリットも考慮する必要があります。
スキーム③:相続税対策として活用する
オーナー経営者が亡くなった場合、会社への貸付金(役員借入金)は相続財産として相続税の課税対象となります。
この貸付金は額面通りに評価されるため、多額の相続税が発生する可能性があります。
生前にDESを実施し、この役員借入金を非上場株式に転換しておくことで、相続税対策になる場合があります。
非上場株式の評価額は、会社の業績や純資産などに基づいて算定されるため、貸付金の額面評価額よりも低くなるケースがあるからです。
これにより、相続財産の評価額を圧縮し、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。



DESの税務上で考慮すべき4つのポイント
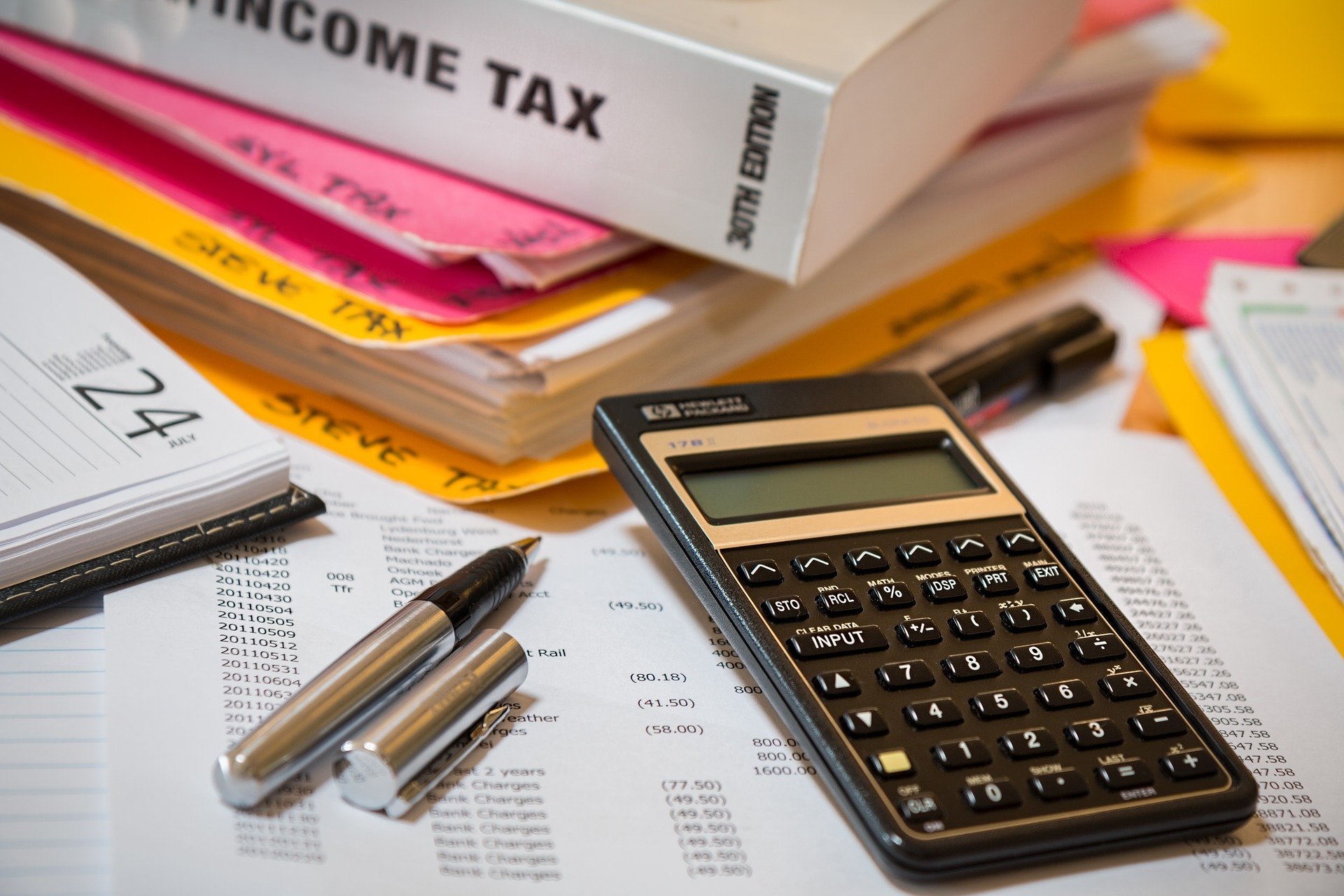
DESを実行する際には、税務上の取り扱いに細心の注意を払う必要があります。
特に、債務消滅益の発生に伴う課税リスクや、資本金の増加による税制上の影響など、事前に理解しておくべき重要なポイントがいくつか存在します。
ポイント①:適格現物出資と非適格現物出資の違い
現物出資型のDESは、税務上「適格現物出資」と「非適格現物出資」に分類され、どちらに該当するかで課税関係が大きく異なります。
適格現物出資:100%親子会社間の増資など、完全支配関係に限って認められます。
この場合、債権は簿価で評価され、譲渡損益の計上は繰り延べられるため、課税は発生しません。しかし、DESがこの要件を満たすケースは稀です。
非適格現物出資:適格現物出資の要件を満たさない、すべての現物出資が該当します。
一般的なDESはこちらに分類されます。
この場合、出資される債権は時価で評価されます。
債権の額面と時価に差額がある場合、債権者には譲渡損益、債務者には債務消滅益が生じ、課税対象となる可能性があります。
ポイント②:債務消滅益の発生と課税リスク
非適格現物出資において、出資される債権の時価が額面を下回る場合、その差額は「債務消滅益」として債務者側の益金に算入され、法人税の課税対象となります。
例として、額面1,000万円の債権が時価700万円と評価されると、300万円が債務消滅益になります。
ただし、会社に繰越欠損金がある場合は、この債務消滅益と相殺することが可能です。税負担を軽減するには、繰越欠損金の有無を確認することが重要です。
ポイント③:資本金が1億円を超えた場合の税制上の注意点
DESで資本金が1億円を超えると、税制上の取り扱いが変わるため注意が必要です。
資本金が1億円以下の法人は、法人税法上「中小法人等」として扱われ、軽減税率の適用や交際費の損金算入枠の拡大など、様々な優遇措置が受けられます。
しかし、DESによって資本金が1億円を超えると、これらの優遇措置が適用されなくなり、税負担が増加する可能性があります。
DESを計画する際は、増資後の資本金の額が税務に与える影響を十分に検討する必要があります。
ポイント④:「みなし贈与」と判断されるケース
DESにおいて、発行される株式の時価が、出資された債権の時価を大幅に上回る場合、その差額が他の株主への「みなし贈与」と判断され、贈与税が課されるリスクがあります。
これは、特定株主(債権者)に不当に有利な条件で株式を発行すると、他株主の持分価値が相対的に増加したと見なされるためです。
このような事態を避けるためには、第三者である専門家による株価算定を行い、発行する株式の価値が適正であることを客観的に示すことが重要です。




DESの流れ

DESを実際に行うには、債権者と債務者の合意形成から法的な手続きまで、いくつかのステップを踏む必要があります。
特に、株主総会での承認や法務局への登記など、会社法に則った手続きを正確に進めることが求められます。
債務者と債権者の合意形成
まず初めに、債務者である企業と債権者の間で、DESの実行について基本的な合意を形成する必要があります。
具体的には、対象となる債権の額、発行する株式の種類(普通株式か種類株式か)、株式数、株価の算定方法といったDESの主要な条件について交渉し、双方が納得する形で合意書などを取り交わします。
株主総会の特別決議
DESは通常、第三者割当増資の手法で行われるため、債務者企業は株主総会を招集し、その承認を得る必要があります。
募集株式の発行は会社の重要な意思決定であるため、非公開会社では原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法199条2項、309条2項5号)。
公開会社では通常、取締役会決議で足りますが、有利発行に該当する場合は株主総会の特別決議が必要になります。
債権者による申し込み
株主総会で承認された内容に基づき、債権者は株式引受の申し込み手続きをします。
債権者は株式引受証などの書面に必要事項を記入し、企業に提出することで株式を引き受ける意思を示します。
目的物の給付
債権者からの申し込みを受け、企業は株式の割当を行います。
現物出資型DESでは、債権者が合意した債権を企業に出資します。金銭出資型では現金を払い込みます。
変更登記
株式が発行され資本金が増加した場合、企業は法務局で変更登記を申請する必要があります。
効力発生日(現物出資日)から2週間以内に、発行済株式数や資本金の変更を登記します。
この登記をもって、一連のDESの手続きは完了となります。


DESの会計処理と仕訳方法

DESが実行された際、債務者である企業側では、負債と資本の変動を会計帳簿に正しく記録する必要があります。
ここでは、現物出資型DESにおける基本的な会計処理と仕訳例を解説します。
仕訳のポイントは、消滅する「借入金」を借方に、増加する「資本金」や「資本準備金」を貸方に計上する点です。
例えば、額面1,000万円の借入金をDESにより株式に転換する場合、仕訳は次の通りです。
会社法上、増加する資本の2分の1までは「資本準備金」として振り分け可能なため、ここでは資本金と資本準備金に半額ずつ計上する仕訳例を示します。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 借入金 | 10,000,000円 | |
| 資本金 | 5,000,000円 | |
| 資本準備金 | 5,000,000円 |
また、前述の通り、債権の時価が額面を下回る場合は、差額を債務消滅益」として貸方に計上します。
例えば、額面1,000万円の借入金に対し、時価700万円の株式を発行した場合、差額の300万円が債務消滅益となり、仕訳は以下のようになります。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 借入金 | 10,000,000円 | |
| 資本金 | 3,500,000円 | |
| 資本準備金 | 3,500,000円 | |
| 債務消滅益 | 3,000,000円 |

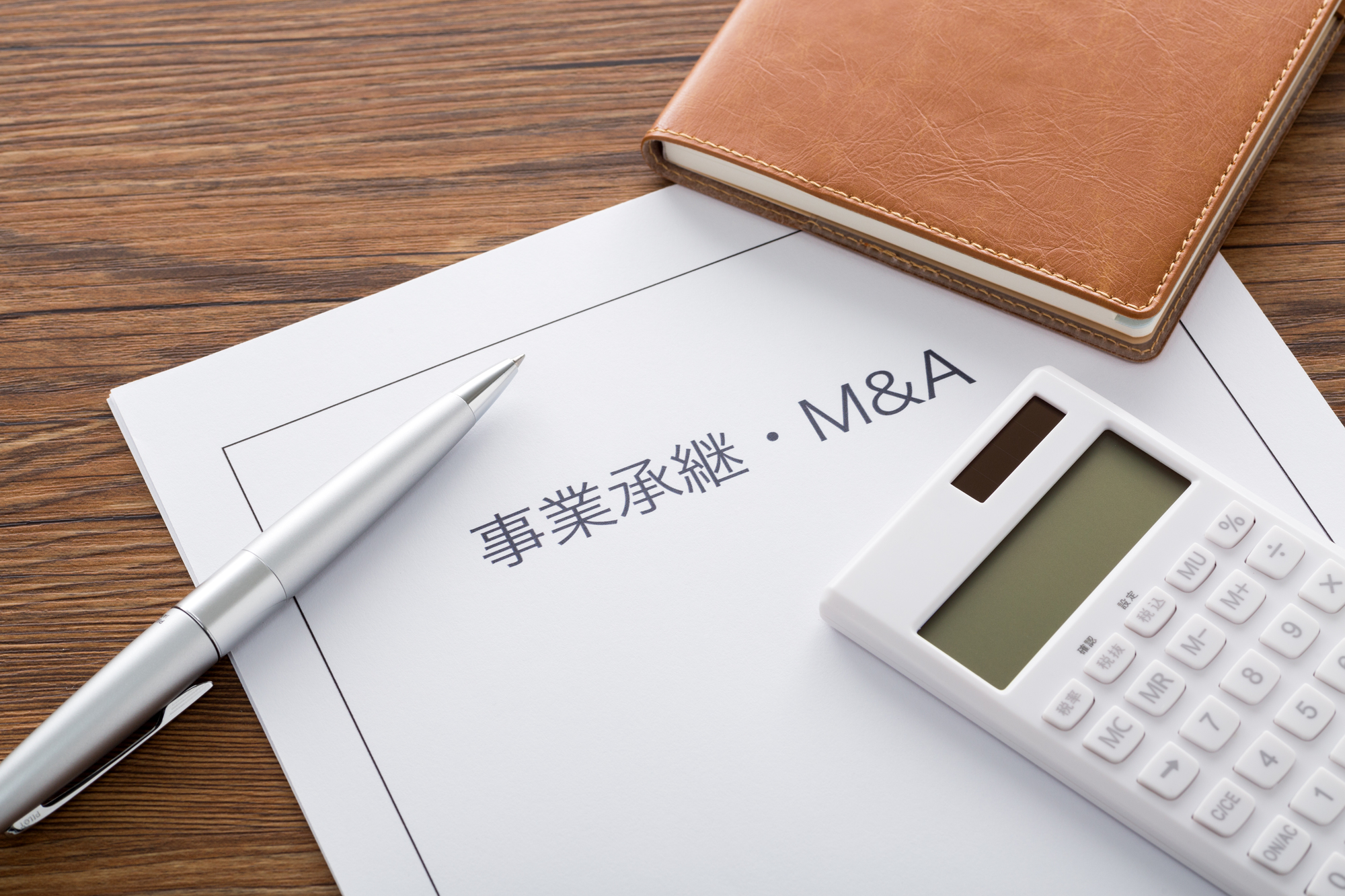
DESに関するよくある質問

ここでは、DESに関して経営者やM&A担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
Q. DESとDDSとの違いは何ですか?
A. DESは債務を「株式(資本)」に交換するのに対し、DDSは債務を返済優先順位の低い「劣後ローン(別の債務)」に交換する点に違いがあります。
DESは負債を削減しますが、DDSは負債の性質を変える手法です。
Q. DESと通常の増資との違いは何ですか?
A. 通常の増資は、出資者から「現金」を受け入れて新株を発行します。一方、現物出資型DESは、「債権」という金銭以外の資産を出資の対象とする点が大きな違いです。
Q. DESの主な目的は何ですか?
A. DESの目的は、過剰債務を削減して財務体質を改善し、事業再生を支援することです。負債を削減し自己資本を増やすことで、資金繰りを安定させ、対外的な信用力を回復させます。
M&Aや事業承継を円滑に進める目的でも活用されます。
Q. DESの仕訳はどのように行いますか?
A. 債務者側では、消滅する「借入金」を借方に計上し、増加する「資本金」や「資本準備金」を貸方に計上します。債権の時価が額面を下回る場合は、その差額を「債務消滅益」として貸方に計上します。

まとめ
企業の債務を資本に交換するDESは、経営難に陥った企業を再生するために有効な手段です。
負債が減って自己資本が増えれば対外的な信用力が増し、資金調達でも有利になるでしょう。
一方で、第三者の株主の影響力増大や、税負担の増加といったデメリットにも留意が必要です。
特に債務が多い企業では大量の株式発行が必要になり、結果的に経営権を第三者に握られるリスクが生じます。
DESの実行を検討する際は、そのメリットとデメリットを深く理解し、自社の状況に与える影響を多角的に分析することが不可欠です。
最適な判断を下すためには、M&Aや税務に精通した専門家へ相談することをお勧めします。