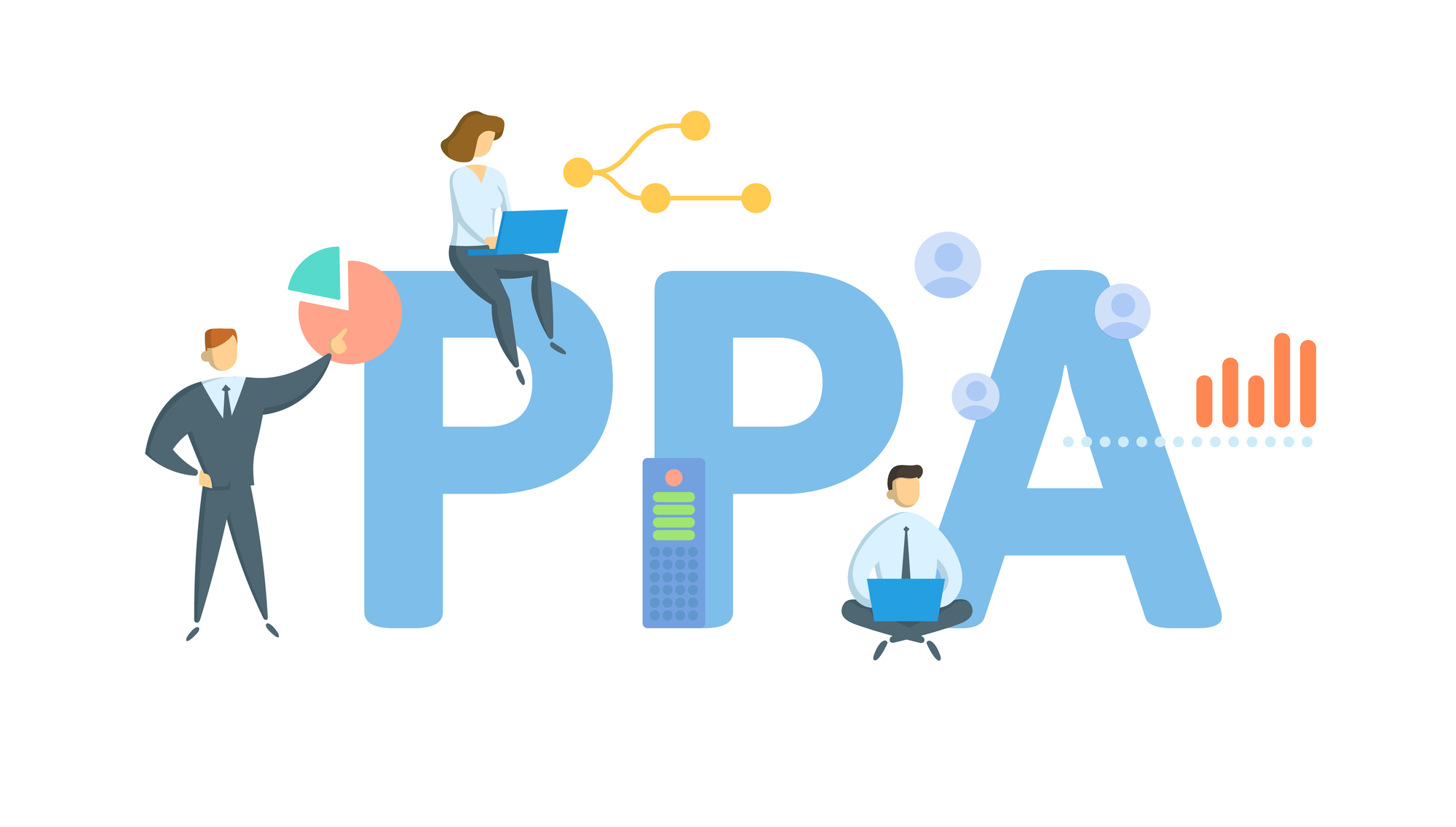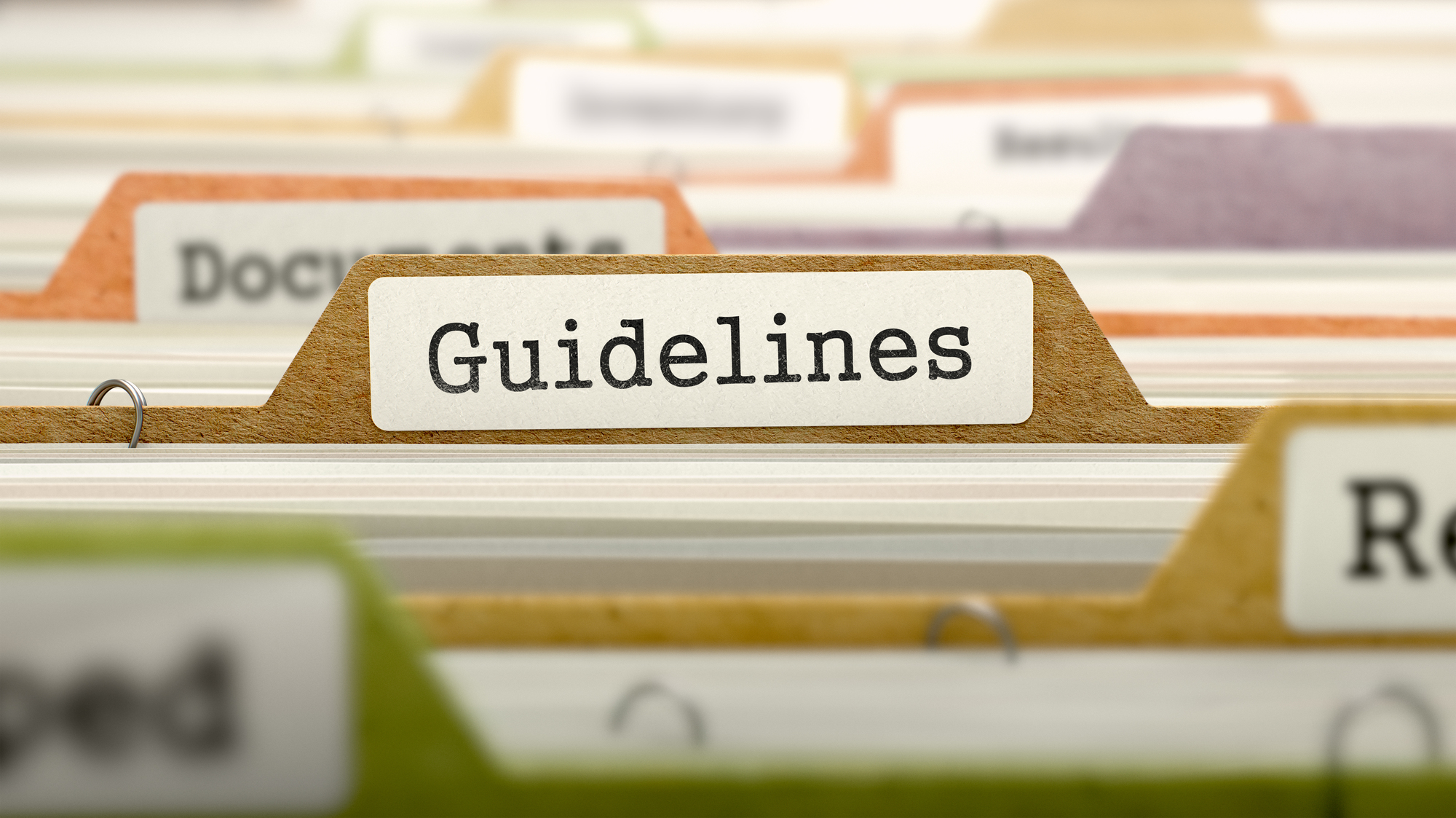EBITDAの読み方は?指標の意味や計算方法、活用場面を解説
企業経営やM&Aにおいては、企業の収益性をできるだけ正確に把握することが求められます。EBITDAという財務指標を使うと、『本業での儲け(キャッシュベース)』を簡単に算出することが可能です。計算方法や活用シーンを解説します。


EBITDAを理解しよう

『EBITDA』は企業価値を評価する指標の一つです。税金や減価償却費などを差し引く前の利益であるため、本業の真の収益力が把握できるといわれています。
財務指標の一つ
EBITDAは簡単にいえば、営業利益に減価償却費を加えた数値です。企業が純粋に事業で稼いだキャッシュ額が分かるため、基準の異なる企業の収益力を比較・検討する際に用いられます。
例えばグローバル企業では、国ごとに税率や金利、会計基準が異なります。同じ土俵で収益性を比較するためには、EBITDAという指標を用い『キャッシュベース』で見る必要があるのです。
また、減価償却費を差し引く前の収益が分かることから、製造業では『設備投資額の影響を除いた収益力』を分析することが可能です。
EBITDAは、『Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation』の頭文字をとったもので、それぞれの意味は以下の通りです。
- Earnings Before Interest Taxes:利払い前・税引き前利益
- Depreciation:有形固定資産の減価償却費
- Amortization:無形固定資産の減価償却費
読み方は「イービットダー」など複数
決まった読み方はなく、『イービットダー』『イービットディーエー』『イービッタ』『エビーダ』など、人によって読み方が変わります。
EBITDAを直訳すると『金利支払い前・税引き前・減価償却前・その他償却前利益』となります。正しい日本語訳はないため、日本語に訳さずにEBITDAとそのまま表記されるのが一般的です。
EBITDAの計算方法
EBITDAには複数の計算方法があります。代表的な二つの方法を比べてみましょう。
- EBITDA=当期純利益+支払利息+税金+減価償却費
『当期純利益』とは、事業年度に計上される全ての収益から、全ての経費やコスト、税金などを差し引いた企業の最終利益です。EBITDAは、この最終利益に『税金』と『減価償却費』を足し戻します。もう一つの簡易的な計算式と比べてみましょう。
- EBITDA=営業利益 + 減価償却費
簡易的な計算式には、営業外収益(雑収入や受取利息など)や特別利益、特別損失が反映されません。これらの収益は企業の営業活動に直接は関係がないため、計算に加えない方が企業の真の実力が分かりやすいといわれています。


EBITDAで分かること

営業利益に減価償却費を戻したEBITDAでは、企業のキャッシュベースの実力が分かります。EBITDAを使うメリットや活用シーンを紹介します。
減価償却の影響を受けず収益性を把握できる
製造業では設備のメンテナンスのために多額の設備投資を行います。大型の設備投資をすると減価償却費が大きくなるため、投資後の数年間は減価償却費の計上によって営業利益が少なくなるのが通常です。
一方、メンテナンスを行わない製造業の場合、減価償却費は少しずつ減っていくため、実際には業績が伸びていなくても営業利益が増えているように見えます。
EBITDAは、設備投資から生じる減価償却費の影響を排除できるため、キャッシュをどれくらい稼いでいるのかが把握できます。
融資や投資などの場面で利用される
EBITDAはキャッシュベースの指標であるため、融資や投資などの場面で多く活用されます。
例えば企業に対して融資する際、EBITDAの計算式に企業の情報を当てはめて算出すれば、融資対象とするべきか否かを比較的早い段階で決めることが可能です。
また、自社の資金繰りやM&Aにおいて企業価値を確認する際の指標としても活用できます。利息の支払いや借入の返済がEBITDAを下回っていれば、キャッシュが問題なく回ると判断できるでしょう。


EBITDAの使い方

EBITDAに関連した指標には、『EBITDAマージン』や『EV/EBITDA倍率』があります。どちらも企業経営やM&Aでよく用いられるため、定義や計算方法を覚えておきましょう。
EBITDAマージン
『EBITDAマージン』とは、売上高(主とする事業活動によって得られる売上の合計額)に対するEBITDAの割合です。簡潔に表現するならば、売上高のうちEBITDAをどのくらい稼げるかを表します。
- EBITDAマージン=EBITDA ÷売上高
EBITDAマージンの値が大きければ大きいほど、儲けも大きいことを意味します。M&Aでは、『企業の真の稼ぎ力』や『経年推移』を見る上で欠かせない指標といえるでしょう。
売上における割合であるため、売上規模が異なる複数企業の収益力を比較する際にも使うことが可能です。
EV/EBITDA倍率
『EV/EBITDA倍率(イーブイ/イービッダー)』は、EV(企業価値)がEBITDAの何倍になっているかを示す指標です。M&Aでは、買い手が売り手の企業価値を評価する際に活用します。
- EV/EBITDA倍率=EV÷EBITDA
別名を『簡易買収倍率』といい、数値からは、『買収金額を本業収益で回収するためにどのくらいの期間が必要か』が分かります。
EVは『Enterprise Value』の略称で、企業が稼ぐ将来のキャッシュフローの現在価値のことです。
日本語では『企業価値』や『事業価値』といい、『株式時価総額+純有利子負債-非事業用資産+少数株主持分』で算出します。
一般的に、EV/EBITDA倍率が低ければ低いほど、買収案件が割安であることを意味します。M&Aでは、売り手企業と類似した上場企業の数値を参考に評価を行うのが一般的です。


まとめ
EBITDAは、企業の収益力を比較する際に用いる指標です。税率、減価償却などに影響されないので、多国籍企業や多額の設備投資が必要な製造業の収益性を測る際に用いられる傾向があります。
EV/EBITDA倍率を用いれば、『買収金額を回収するまでの期間』を割り出すことも可能です。経営やM&Aでは、EBITDAやEBITDAマージンをはじめとするさまざまな指標を活用して、現状をできるだけ正確に把握することが大切です。