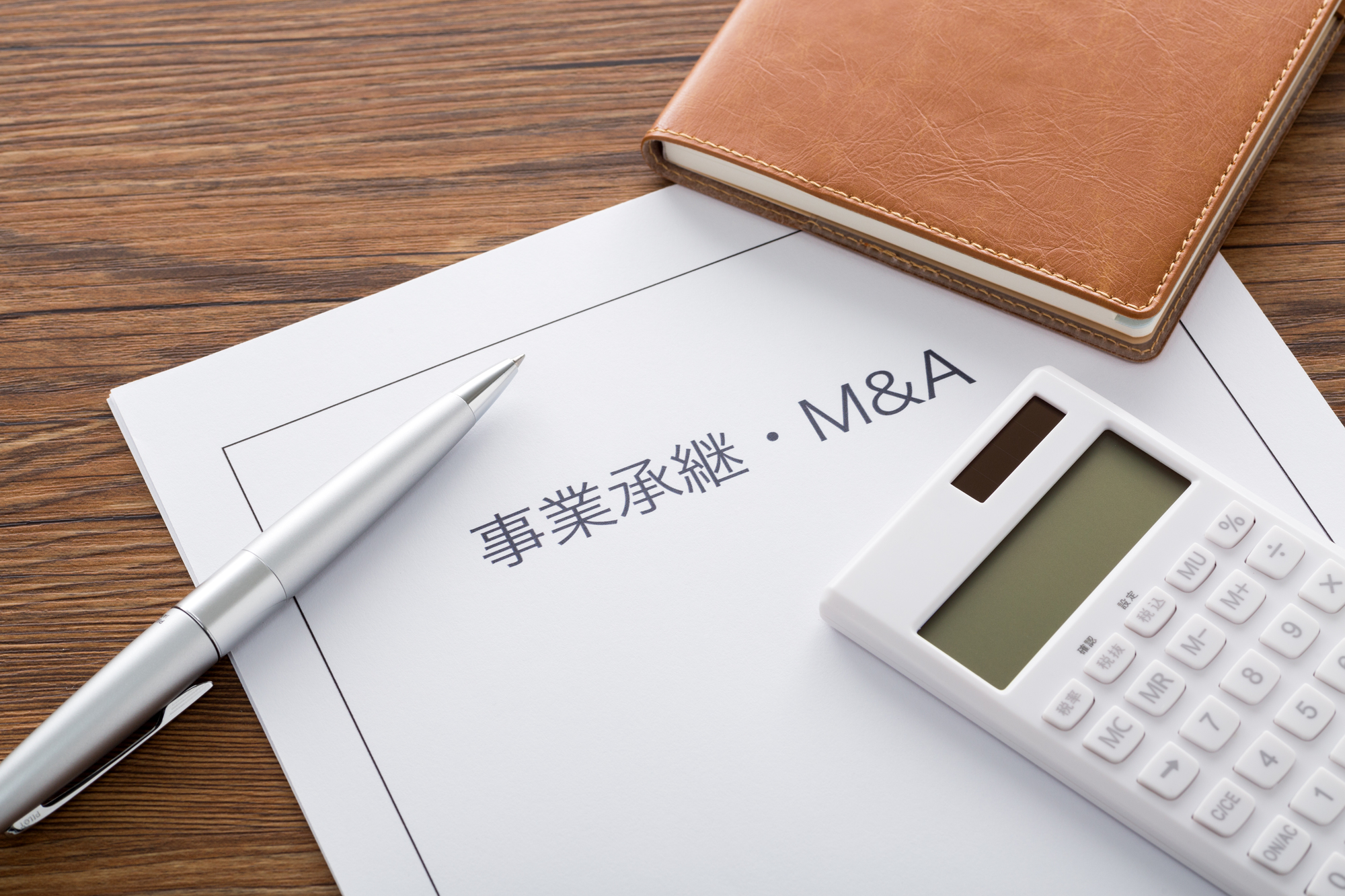
M&A手数料・成功報酬の相場は?計算方法と会計処理・コストを抑えるポイントを解説
M&A手数料の種類とそれぞれの相場、具体的な計算方法から、会計処理、さらにはコストを抑えるための実践的なポイントまで、網羅的に解説します。手数料の基本を理解し、賢いM&Aの第一歩を踏み出しましょう。
M&Aを検討する際、手数料がどのくらいかかるのか、その内訳や相場が不透明で不安に感じていませんか。
M&Aの手数料は、取引規模や契約形態によって変動しますが、多くの場合「レーマン方式」と呼ばれる計算方式に基づく成功報酬が中心です。
この記事では、M&A手数料の種類とそれぞれの相場、具体的な計算方法から、会計処理、さらにはコストを抑えるための実践的なポイントまで、網羅的に解説します。
本記事を読むことで、手数料体系の全体像を理解し、自社に合ったパートナー選びやコスト管理に役立てることができます。
まずは手数料の基本を理解し、賢いM&Aの第一歩を踏み出しましょう。


M&A手数料とは|定義と基本的な仕組み

M&A手数料とは、M&Aの成立をサポートする仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)などの専門家へ支払う報酬の総称です。
手数料は、M&Aを円滑に進めるための対価であり、専門的な知識やネットワーク、交渉力を利用するための必要コストです。
M&Aで専門家に支払う手数料は、その専門家の立場によって「アドバイザリー費用」と「仲介手数料」に大別されます。
「アドバイザリー費用」は、売り手か買い手のどちらか一方の専属アドバイザー(FA)として、依頼者の利益最大化を目指す活動への対価です。
一方、「仲介手数料」は、売り手と買い手の間に立ち、中立的な立場でM&Aの成立をサポートする仲介会社へ支払う費用を指します。
両者の役割は異なりますが、計算方法や支払い時期はアドバイザリー契約と仲介契約で大きく変わらないのが一般的です。
手数料が発生するタイミングは、契約内容によって異なりますが、一般的には相談時、業務委託契約の締結時(着手金)、基本合意の締結時(中間金)、そして最終契約の成立時(成功報酬)といった複数の段階に分かれています。

M&A手数料の種類と相場
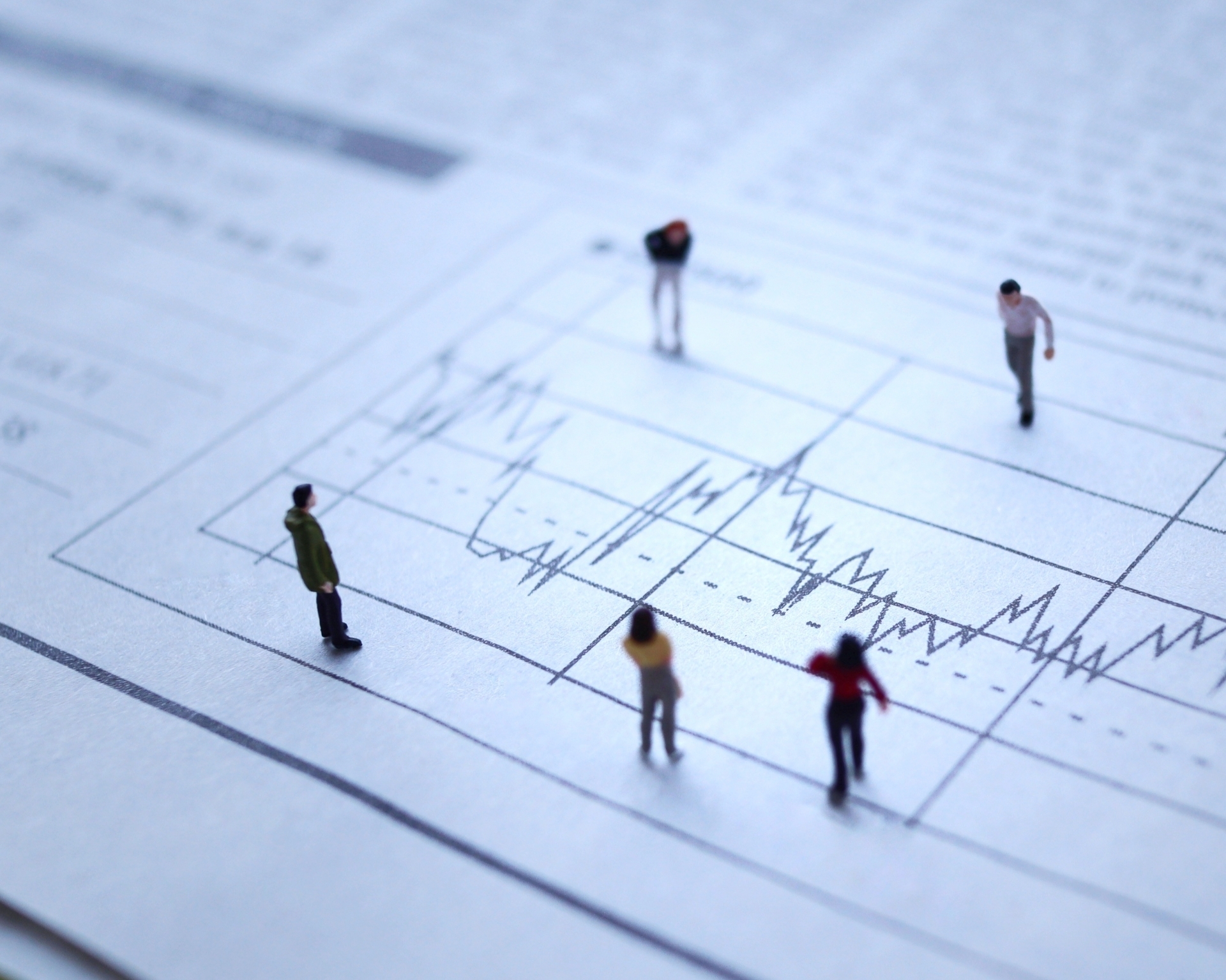
M&Aを進める過程では、複数の種類の手数料が発生します。
相談料から着手金、中間金、そして最も大きな割合を占める成功報酬まで、各手数料の発生タイミングと、役割を理解することが重要です。
ここでは、それぞれの内訳と特徴を詳しく見ていきましょう。
相談料
相談料は、M&A仲介会社やFAに初めて相談する際に発生する費用です。
多くの仲介会社は、実現可能性や進め方を確認できる初期相談を無料に設定しています。
ただし、一部のコンサルティングファームや金融機関では、専門家としての時間を確保する観点から、相談料が有料となるケースもあります。
有料の場合は、数万円から数十万円程度が相場ですが、事前に料金体系を確認することが不可欠です。
着手金
着手金は、M&A仲介会社と正式に業務委託契約を締結する際に支払う一時金です。
この費用は、M&Aの対象となる企業の分析、資料作成、候補先のリストアップといった初期業務の対価として支払われます。
着手金の相場は50万円から200万円程度ですが、近年では無料とする仲介会社も増えています。
注意点として、着手金はM&Aが成立しなかった場合でも原則として返金されないため、契約前に返金の可否や条件を必ず確認しましょう。
中間金(中間報酬)
中間金は、M&Aのプロセスがある程度進展し、売り手と買い手の間で基本的な条件が合意に至ったタイミング(基本合意契約の締結時)で支払う報酬です。
成功報酬の金額の10%~20%程度が相場とされています。
中間金が設定されている場合、M&Aが成立するか否かにかかわらず支払わなくてはなりませんが、成立した場合は最後に支払う成功報酬から中間金を差し引くケースが多いです。
中間金を設定する目的は、M&Aアドバイザーの継続的な業務遂行を担保し、安易な交渉離脱を防ぐ点にあります。
着手金と同様に、最終的にM&Aが成立しなくても返金されないケースが多いため、契約内容の確認が重要です。
デューデリジェンス費用
デューデリジェンス(DD)費用は、買い手側が売り手側の企業価値やリスクを詳細に調査するために発生する費用です。
この調査は、財務、法務、税務、ビジネスなど多岐にわたるため、公認会計士や弁護士といった外部の専門家に依頼するのが一般的です。
費用は調査の範囲や企業の規模によって大きく異なり、小規模案件なら数十万円、大規模案件では数千万円に及ぶこともあります。
基本的には買い手側が負担しますが、売り手側も調査に対応するための準備として、専門家に依頼する費用が発生することがあります。
リテイナーフィー(顧問料などの月額固定料)
リテイナーフィーは、M&A契約期間中に月額で支払う顧問料です。長期案件や複雑なM&Aで設定されるケースが多いです。
相場は月額30万円~100万円程度で、アドバイザー業務の対価となります。
ただし、リテイナーフィーは成功報酬とは別にかかるコストであり、総額が大きくなる可能性があるため、特に中小企業のM&Aでは採用されないケースも増えています。
成功報酬(レーマン方式)
成功報酬は、M&Aが最終的に成立した際に支払う最も主要な報酬です。
成功報酬については、中小M&Aでは仲介会社が売り手・買い手双方と契約を結び、各々から成功報酬を受け取る「双方代理」が一般的です。
報酬額はM&Aの取引金額に応じて変動し、その算出方法として「レーマン方式」が広く採用されています。
レーマン方式は、取引金額が大きいほど料率が低減するスライド式体系です。
例えば、以下のような料率が設定されます。
| 譲渡金額 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超~10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超~50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超~100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
このとき、譲渡価格が3億円の場合、成功報酬は「3億円 × 5% = 1,500万円」となります。 譲渡価格が15億円の場合は、「5億円 × 5% + 5億円 × 4% + 5億円 × 3% = 2,500万円 + 2,000万円 + 1,500万円 = 6,000万円」といった計算になります。
「取引金額」の定義は仲介会社ごとに異なり、「企業価値」「移動総資産」「譲渡価格」などが基準となります。
どの基準が採用されるかによって手数料額が大きく変わるため、契約前に必ず確認が必要です。
近年はM&A手数料体系の多様化が進んでいます。
特に小規模なM&Aにおいては、多くの仲介会社が「最低報酬額(ミニマムチャージ)」を設定しており、その相場は500万円~2,500万円程度です。
一方で、着手金や中間金を無料にし、M&Aが成立した場合にのみ報酬が発生する「完全成功報酬制」を採用する仲介会社も増えています。


M&A手数料の会計処理・税務処理
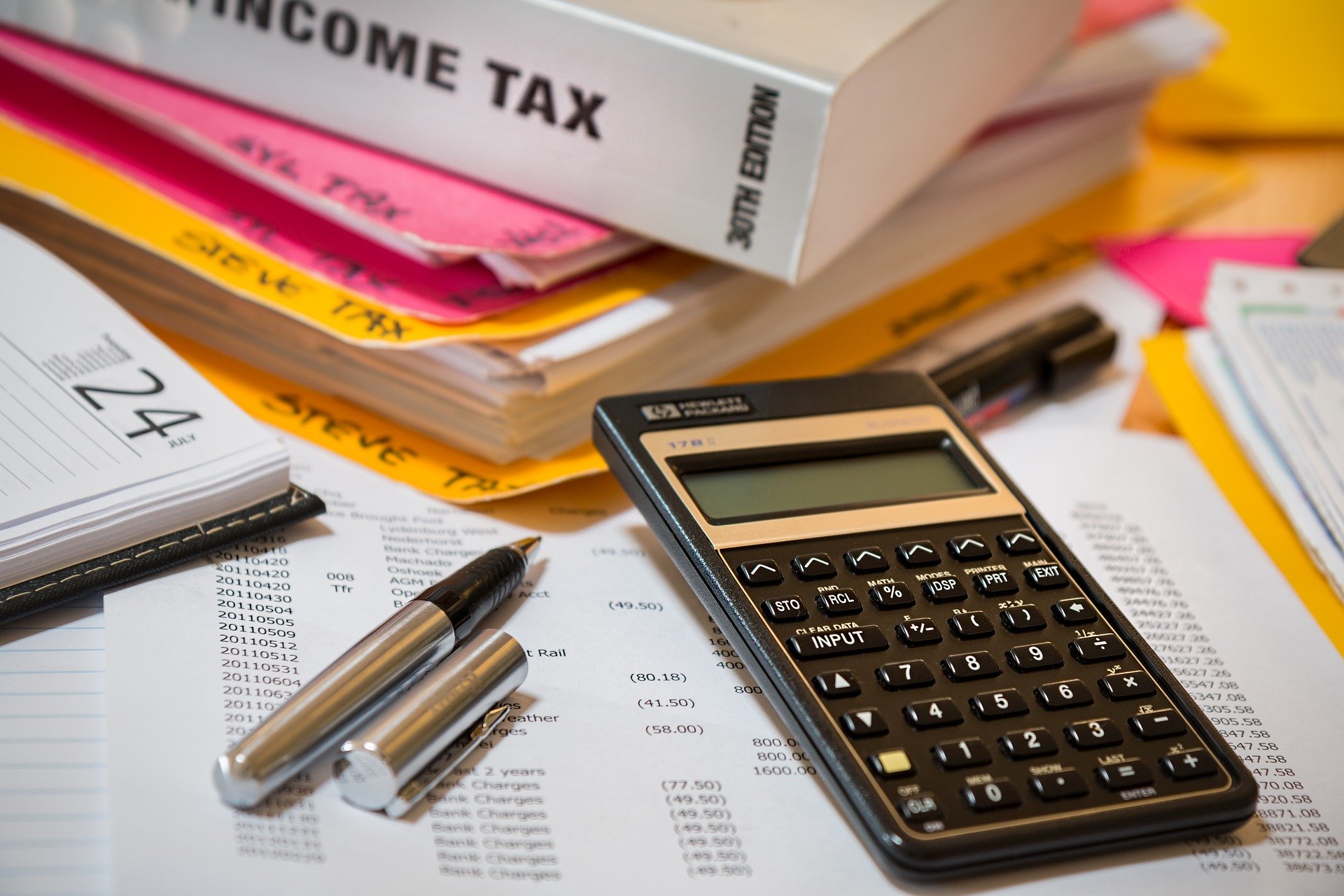
M&Aに伴う手数料は、会計・税務上で適切に処理する必要があります。
ここでは、手数料の勘定科目や具体的な仕訳方法、税務上の損金算入の可否など、実務で必須となる知識を解説します。
正しい処理は、将来の税務リスク回避に不可欠です。
手数料の勘定科目・仕訳方法
成立したM&Aで支払った手数料については買い手は、株式の取得価額に手数料を含めて計上(取得原価算入)するのが原則です。
一方、売り手企業の場合は、株式の売却にかかった費用として、売却損益を計算する際に譲渡費用として計上します。
成立しなかった場合、その内容に応じて適切な勘定科目で仕訳します。
仲介会社への着手金や中間報酬は「支払手数料」、弁護士や公認会計士へのデューデリジェンス費用は「支払報酬料」や「業務委託料」などで処理されます。
税務上の取扱いと経費算入
税務上、売り手側が支払った手数料は、株式の譲渡費用として、個人株主の場合は譲渡所得から控除できます。
買い手側が支払った手数料は、原則として取得した株式の取得価額に含まれるため、その時点では損金になりません。
ただし、M&Aを検討したものの成立に至らなかった場合に支払った費用(デューデリジェンス費用など)は、その事業年度の損金として算入できます。また、国内の事業者への支払いについては消費税の課税取引となります。


M&A手数料を安く抑えるポイント

M&Aを成功させるためには、手数料を適切に管理し、コストを最適化することが重要です。
以下に、手数料を安く抑えるための具体的なポイントをいくつか紹介します。
仲介会社の手数料体系を比較検討する
仲介会社ごとに、レーマン方式の料率、成功報酬の基準(譲渡価格か移動総資産か)、最低報酬額は大きく異なります。
複数の会社の料金体系を比較し、自社の取引規模や希望に最も合った会社を選ぶことが、コスト削減の第一歩です。
料金だけでなく、含まれるサービス範囲(資料作成支援、交渉代行など)も確認しましょう。
成功報酬型を選び着手金を抑える
着手金や中間金が無料の「完全成功報酬制」の会社を選ぶことで、M&Aが不成立に終わった場合のリスクをゼロにできます。
初期費用を抑えられるため、初めてM&Aに取り組む企業や小規模案件で有効です。
ただし、成功報酬の料率がやや高めに設定されている場合もあるため、総額での比較が重要です。
契約前に見積もりを詳細に確認する
契約を締結する前に、必ず書面で詳細な見積もりを依頼しましょう。
成功報酬の計算基準が何であるか、デューデリジェンス費用やその他の実費が別途発生するのか、追加費用の有無などを明確にすることが、想定外の出費を防ぎ、トラブルを回避につながります。
競合する仲介会社に相見積もりを取る
複数の仲介会社から相見積もりを取ることは、手数料の妥当性を判断し、価格交渉を行う上で非常に有効です。
他社の見積もりを提示することで、より有利な手数料率や条件を引き出せる可能性があります。
ただし、単なる価格の安さだけでなく、担当者の専門性や業界への知見も見極める必要があります。
専門家を直接活用して中間コスト削減
デューデリジェンスなどを仲介会社を介さずに、自社で直接、弁護士や公認会計士に依頼することで、仲介会社に支払う中間マージンを削減できる可能性があります。ただし、自社で専門家を探し、各専門家と個別に連携を取る手間が発生するため、M&Aに関する知見が一定程度ある場合に有効な手段と言えるでしょう。
補助金を活用する
中小企業庁が実施している「事業承継・引継ぎ補助金」など、M&Aにかかる費用の一部を国が補助してくれる制度があります。
専門家への依頼費用(仲介手数料やデューデリジェンス費用など)も補助対象経費に含まれているため、公募要領を確認し、活用できる制度がないか検討してみましょう。
M&Aプラットフォームを活用する
近年、オンライン上で売り手と買い手を直接マッチングするM&Aプラットフォームが拡大しています。
仲介会社を介さずに交渉を進められるため、手数料を大幅に抑えることが可能です。
代表的なプラットフォームである「TRANBI(トランビ)」は、売り手は無料で案件を登録でき、買い手も低額のシステム利用料で多くの案件にアクセスできるため、小規模なM&Aに適した有効手段です。



仲介会社・アドバイザリー会社ごとの手数料体系比較

M&Aの仲介会社は数多く存在し、それぞれ手数料体系に特徴があります。
ここでは、代表的な企業の料金体系を比較します。(※2024年時点の一般的な情報であり、詳細は各社にご確認ください)
日本M&Aセンター
東証プライム上場の業界最大手で、中堅・中小企業の事業承継M&Aに強みがあります。
全国の地方銀行、信用金庫、会計事務所と広範なネットワークを構築しており、地方の優良案件にも強いのが特徴です。
手数料体系は、着手金(100万円~)が必要で、成功報酬はレーマン方式を採用しています。
最低報酬額も比較的高めに設定されていますが、その分、経験豊富なコンサルタントによる手厚いサポートと、質の高いマッチングが期待できます。長年の経験で培われたノウハウと信頼性で、安心してM&Aプロセスを任せたい経営者に適しています。
M&Aキャピタルパートナーズ
東証プライム上場のM&A仲介会社で、着手金・中間金が無料の「完全成功報酬制」を強みとしています。
M&A成立まで費用が発生しないため、依頼企業はリスクを抑えて検討できます。特に中規模から大規模な案件に定評があり、専門性の高いコンサルタントが専任で担当し、企業の価値を最大限に高めるための戦略的なアドバイスを提供します。
売り手企業の利益最大化を追求する姿勢が明確で、質の高いサービスが求められる案件で高い評価を得ています。相談から成約まで一貫したサポート体制も魅力です。
ストライク
東証プライム上場の独立系M&A仲介会社です。
公認会計士や弁護士などの専門家が多く在籍し、専門的な知見に基づいた質の高いサービスを提供しています。手数料体系は着手金が必要なケースが多いですが、比較的低めの設定です。
成功報酬はレーマン方式を採用しています。また、日本最大級のM&A専門メディア「M&A Online」を運営しており、業界情報の発信力と情報収集力に強みがあります。インターネットを活用したマッチングにも早くから取り組んでおり、幅広いネットワークを活かした提案が可能です。
M&A総合研究所
東証グロース市場に上場しており、近年急速に成長している仲介会社です。
最大の特色は、着手金・中間金が無料の「完全成功報酬制」と、AIやDXを活用した高いマッチング精度とスピードです。独自のAIアルゴリズムを用いて最適な候補先を迅速に抽出し、最短3ヶ月で成約した実績もあります。
手数料は成功報酬のみで、レーマン方式の料率も業界内で競争力のある水準に設定されています。スピード感を重視し、テクノロジーを活用した効率的なM&Aを求める経営者にとって、有力な選択肢となるでしょう。
TRANBI(トランビ)
国内最大級のM&Aマッチングプラットフォームであり、従来の仲介会社とは一線を画すサービスです。
売り手は無料で自社の案件を匿名で登録でき、全国の買い手候補から直接アプローチを受けることができます。
買い手は月額制の料金で、登録されている多数の案件を自由に検索し、交渉を進めることが可能です。
仲介者が介在しないため、成約時の手数料が不要または低額で、コストを大幅に抑えられます。
特に小規模な事業譲渡や個人事業主のM&Aに適しており、自ら交渉を進めたい経営者にとって非常に有効なツールです。



M&A手数料に関するよくある質問(FAQ)

Q:手数料の妥当性を判断する基準は?
A:単なる金額だけでなく、提供されるサービスの範囲や質、担当者の専門性や実績を総合的に評価することが重要です。複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することで、妥当性を判断しやすくなります。
Q:仲介手数料は誰が払う?支払いタイミングは?
A:仲介会社が売り手と買い手の双方から手数料を受け取る「双方代理」が中小M&Aでは多いですが、利益相反の懸念もあるため注意が必要です。支払いのタイミングは、着手金、中間金、成功報酬など、契約内容に応じて複数回に分かれます。
Q:小規模M&Aや譲渡価格が低い案件の手数料は?
A:多くの仲介会社では「最低報酬額」が設定されているため、譲渡価格が低くても「最低報酬額」(数百万円~2,500万円程度)が発生します。コストを抑えたい場合は、M&Aプラットフォームの活用も有効です。
Q:会計仕訳・勘定科目はどう処理する?
A:M&Aが成立した場合、買い手側は仲介手数料やデューデリジェンス費用は株式の取得原価に算入し、売り手側は譲渡費用として計上するのが一般的です。
Q:仲介手数料の消費税取り扱いは?
A:日本国内のM&A仲介会社に支払う手数料やアドバイザリー費用は国内における役務の提供に該当するため消費税が課税されます。一方で、株式の譲渡自体は非課税です。見積もりを確認する際は、税抜価格か税込価格かを必ず確認しましょう。
Q:途中解約時の費用発生有無と返金規定は?
A:着手金は原則返金不可とされる事例が多い一方、中間金や違約金の扱いは契約条項に依存します。中途解約条項と返金条件を事前に確認し、説明を受けておきましょう。
まとめ
本記事では、M&Aの手数料について、その種類、相場、計算方法、会計処理、税務上の扱い、コストを抑えるポイントまで解説しました。M&Aの手数料は決して安価ではありませんが、その仕組みを正しく理解し、自社に合ったパートナーを選ぶことで、コストを最適化することは十分に可能です。
特に、成功報酬の算出基礎となるレーマン方式の基準や、最低報酬額の有無は、最終的な支払額に大きく影響します。
複数の仲介会社から詳細な見積もりを取り、提示されたサービス内容と費用を徹底的に比較検討することが、納得のいくM&Aを実現するための鍵となります。会計・税務面での正しい処理と合わせ、無駄のない計画的なM&Aを進めていきましょう。







