
M&Aの種類を徹底解説!目的別の選び方やスキーム比較ガイド
M&Aの手法についてお悩みはありませんか?自社の目的や状況に適したスキームの選択がM&Aを成功に導きます。判断基準を確立し、最適な手法でM&Aに臨みましょう。
「M&Aを検討しているが、どの手法が自社に合うのか分からない」「種類が多すぎてメリット・デメリットを比較するのが難しい」と悩んでいませんか。M&Aの成功は、自社の目的や状況に最適なスキーム(手法)を選択できるかどうかに懸かっています。
本記事では、M&Aの代表的な8種類のスキームについて、仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れを詳しく比較・解説します。
さらに、目的別の選び方から契約・デューデリジェンスのポイント、注意点まで、実務的な知識を網羅的にご紹介します。
この記事を最後までお読みいただくことで、複雑なM&Aスキームの全体像を理解し、自社の課題解決に繋がる最適な手法を見極めるための判断基準が明確になるでしょう。ぜひ、貴社のM&A戦略における意思決定にお役立てください。


【全体像】M&Aスキームの主な種類の分類

M&A(Mergers and Acquisitions)と一言でいっても、その手法(スキーム)は多岐にわたります。
まずは全体像を掴むために、M&Aの定義とスキームの分類方法について解説します。
広義のM&Aと狭義のM&A
M&Aは、直訳すると「合併と買収」ですが、その範囲は解釈によって異なります。
- 広義のM&A:企業の合併・買収に加え、経営権の移転を伴わない「資本提携」「業務提携」なども含まれます。
- 狭義のM&A:経営権の移転を伴う「合併」と「買収」のみを指します。
本記事では、主にこの「狭義のM&A」に焦点を当て、代表的なスキームを解説していきます。
スキームの分類軸
1.「買収」か「合併」か
- 買収:対象企業の法人格は維持されたまま、買い手が経営権を取得する手法です。株式譲渡や株式交換などがこれにあたります。
- 合併:複数の企業が法的に一つの会社に統合される手法です。少なくとも一つの会社は消滅します。
2.譲渡対象が「株式」か「事業」か
- 株式を対象とする手法:売り手企業の株式を取得することで、会社全体の経営権を承継します。株式譲渡や株式交換が代表例です。
- 事業を対象とする手法:会社の一部または全部の事業に関する資産・負債・契約などを承継します。事業譲渡や会社分割がこれに該当します。
これらの分類を理解することで、各スキームの目的や特性が明確になります。
本記事では、これらの分類を踏まえながら、代表的な8つの手法を詳しく見ていきます。

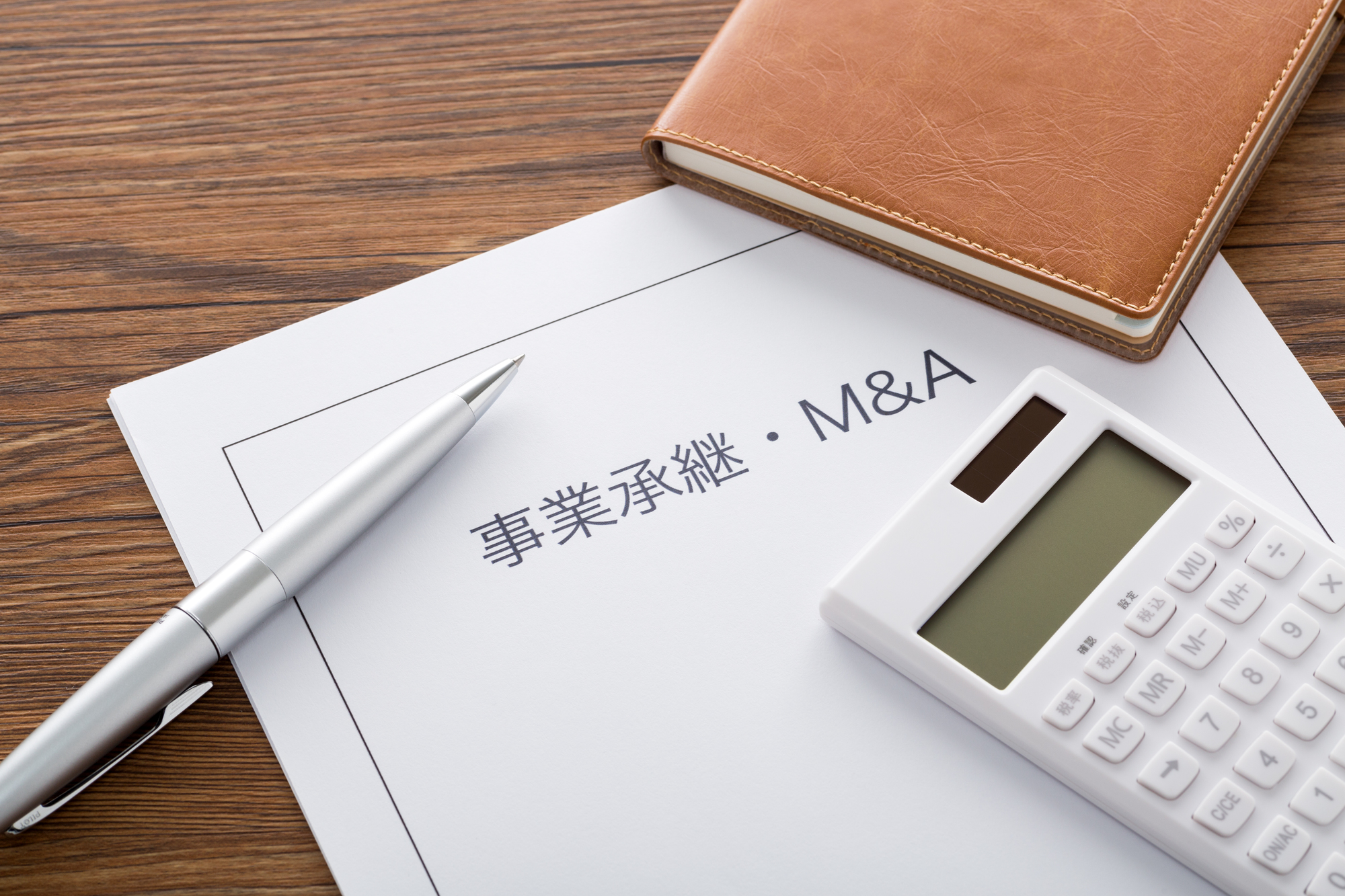
【種類別】M&Aの主要8スキームを徹底解説

M&Aの成功は、目的に合ったスキームを選択することから始まります。
ここでは、中小企業から大企業まで幅広く活用されている主要な8つのM&Aスキームについて、それぞれの特徴、メリット、デメリットを掘り下げて解説します。
1. 株式譲渡
株式譲渡は、売り手株主が保有する既存株式を買い手に売却し、経営権を移転させる手法です。
手続きが比較的シンプルで分かりやすいため、特にオーナー経営者が株主である中小企業の事業承継などで最も多く用いられています。
メリット
- 手続きの簡便さ:株主と買い手の二者間での合意を基本とし、株式譲渡契約の締結と株主名簿の書き換えで手続きが完了するため、他の手法に比べて迅速に実行できます。債権者保護手続きが原則不要な点も利点です。
- 会社の独立性維持:会社の法人格はそのまま維持され、株主が変わるだけなので、事業運営への影響を最小限に抑えられます。従業員の雇用契約や取引先との契約関係も維持されるため、事業の継続性が高いです。
- 包括承継による引き継ぎ:許認可や各種契約関係が会社に紐づいているため、個別に移転手続きを行う必要がありません。これにより、スムーズな事業の引き継ぎが期待できます。
デメリット
- 偶発債務の承継リスク:会社の権利義務をすべて引き継ぐため、貸借対照表に記載されていない簿外債務や、将来発生しうる偶発債務(訴訟リスクなど)も承継するリスクがあります。事前のデューデリジェンスが極めて重要です。
- 多額の買収資金が必要:買い手は現金を準備する必要があります。対象会社の企業価値によっては、多額の自己資金や借入金が必要になる点が負担となり得ます。
必要な手続き
- 取締役会の承認:譲渡制限株式の場合、株式を譲渡する側で取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認が必要です。
- 株式譲渡契約の締結:譲渡価格、譲渡日、表明保証などの条件を定めた契約を当事者間で締結します。
- 対価の支払いと株式の引き渡し:契約に基づき、買い手は売り手に譲渡代金を支払い、売り手は株券(発行している場合)を引き渡します。
- 株主名簿の書き換え:株主名簿を書き換えることで、新株主は第三者に対抗できるようになります。
発生する税金
- 売り手(個人株主の場合):株式の譲渡益には、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が課税され、合計20.315%となります。
- 売り手(法人株主の場合):株式の売却益は他の利益と合算され、法人税等の課税対象となります。
- 買い手:原則として課税されません。
2. 第三者割当増資
第三者割当増資は、会社が新たに株式を発行し、特定の第三者(買い手)に引き受けてもらう手法です。
株式譲渡が既存株主から株式を取得するのに対し、第三者割当増資は会社に直接資金が払い込まれる点が大きな違いです。
完全な買収だけでなく、業務提携や資本提携の強化を目的として活用されます。
メリット
- 売り手企業の資金調達:新たな資金が直接会社に入るため、売り手企業は事業拡大の投資や財務体質の改善、借入金の返済などに活用できます。会社の成長を目的としたM&Aに適しています。
- 段階的な提携関係の構築:既存株主は株式を維持したまま、買い手との緩やかな資本関係を築くことが可能です。これにより、将来の完全子会社化を見据えた協力関係の第一歩とすることもできます。
デメリット
- 既存株主の持株比率低下:新株が発行されることで、発行済株式総数が増加し、既存株主の持株比率が低下(希薄化)します。これにより、経営への影響力や一株当たりの価値が低下する可能性があります。
- 経営権の獲得には相応の増資が必要:買い手が過半数の議決権を得て経営権を掌握するためには、既存の発行済株式総数を上回る規模の新株発行が必要になる場合もあり、既存株主の同意を得るハードルが高くなります。
必要な手続き
- 募集事項の決定:原則として株主総会決議(取締役会設置会社において定款の定めがあれば取締役会決議)により、発行する株式数、払込金額、払込期日などの募集事項を決定します。ただし、非公開会社(株式の譲渡制限のある会社)においては株主総会の特別決議が必要とされています。
- 募集株式の申し込みと割り当て:引き受け手は申し込みを行い、会社が割り当てを決定します。
- 出資金の払い込み:引き受け手は、定められた期日までに払込金額を会社の口座に払い込みます。
- 変更登記申請:効力発生日から2週間以内に、法務局で発行済株式総数や資本金の額に関する変更登記を行います。
発生する税金
- 会社(増資する側):資本金が増加するだけであり、原則として課税は発生しません。ただし、変更登記をする際に登録免許税が課せられ、資本金の額によっては法人住民税(均等割)が増加する場合があります。また、外形標準課税適用会社の場合は資本割が増加します。
- 引き受け手(買い手):株式を取得するだけで、取得時点では課税は発生しません。
- 既存株主:時価よりも著しく低い価額で新株が発行された場合、既存株主から引き受け手への利益移転があったとみなされ、贈与税などが課される可能性があります。
3. 株式交換
株式交換は、一方の会社が他方の会社の全株式を取得し、「完全親子会社」の関係を構築する組織再編の手法です。
子会社となる企業の株主は、保有株式と引き換えに親会社の株式を受け取ります。
主にグループ企業の再編や、上場企業が非上場企業を完全子会社化する際などに用いられます。
メリット
- 買収資金が不要:対価を親会社の株式とすることで、買い手は買収のための現金を準備する必要がありません。手元資金が少ない場合でも、大規模な買収を実行できる可能性があります。
- 子会社の独立性維持:子会社となる会社の法人格は維持されるため、独立した経営体制や独自の企業文化を尊重しながら、グループとしての経営戦略を進めることが可能です。
デメリット
- 手続きの複雑さ:株主総会での特別決議や、反対株主の株式買取請求権への対応、債権者保護手続きなど、会社法に定められた複雑な手続きが必要です。時間と専門知識を要します。
- 株価変動リスク:親会社株の株価が下落すると、子会社株主が受け取る株式価値も減少します。また、親会社の株主構成が変化し、既存株主の持株比率が低下する可能性もあります。
必要な手続き
- 株式交換契約の締結:当事会社間で株式交換比率などを定めた契約を締結します。
- 事前開示書類の備置:契約内容などを記載した書類を、株主総会の2週間前から本店に備え置きます。
- 株主総会の特別決議:原則として親会社・子会社双方で必要ですが、一定の要件を満たす場合は簡易手続きにより不要となることもあります。
- 債権者保護手続き:株式交換では基本的には債権者保護手続きが不要ですが、一定の場合には必要となり、その場合には、官報公告や個別催告を行います。
- 効力発生と登記:契約で定めた日に効力が発生し、親会社は新規発行した株式や新株予約権を交付するケースで変更登記が必要となり、子会社は親会社に新株予約権を取得させる場合に登記が必要となります。
発生する税金
- 子会社の株主:対価が親会社の株式のみなど、一定の税制適格要件を満たす場合は、保有株式の譲渡益に対する課税が将来の売却時まで繰り延べられます。要件を満たさない場合や、対価に金銭が含まれる場合は、その時点で課税されます。
- 法人(当事会社):税制適格要件を満たせば、資産の含み益に対する法人税の課税は発生しません。
4. 株式移転
株式移転は、1社または複数の会社が自社の全株式を新設する親会社に取得させ、完全子会社となる組織再編手法です。既存の各社は新設された親会社の完全子会社となります。
複数の企業が経営統合を行う際や、グループ経営を効率化するためのホールディングス(持株会社)体制へ移行する目的で利用されます。
メリット
- 円滑な経営統合:各社が新設会社の傘下に並列で入るため、吸収合併のような一方的支配の印象が薄く、対等な立場での経営統合を実現しやすくなります。関係者の心理的な抵抗を和らげる効果が期待できます。
- グループ経営の効率化:持株会社がグループ全体の戦略策定・資金調達・ガバナンスを担い、各子会社は事業運営に専念するという役割分担が可能になります。これにより、迅速な意思決定と効率的なグループ経営が実現できます。
デメリット
- 手続きの煩雑さとコスト: 新たに会社を設立する必要があるため、株式交換以上に手続きが複雑です。設立登記費用や許認可の再取得など、多大な時間とコストがかかります。
- 株主構成の変化:統合比率(株式移転比率)の設定によっては、旧会社の株主の議決権比率が大きく変動する可能性があります。株主間の利害調整が難しい場合があります。
必要な手続き
- 株式移転計画の作成: 株式交換の契約書に相当するものとして、新設する親会社の目的や商号、株式移転比率などを定めた計画を作成します。
- 事前開示・株主総会承認など:手続きの基本的な流れは株式交換とほぼ同様で、事前開示、株主総会の特別決議、債権者保護手続きなどが必要です。
- 新設親会社の設立登記:法務局に新設会社の設立登記を申請することで、株式移転の効力が発生します。
発生する税金
- 子会社の株主・法人:株式交換と同様に、税制適格要件を満たす場合は、株主および法人に対する課税は繰り延べられます。
- 新設親会社:設立時に登録免許税(資本金の0.7%、最低15万円)がかかります。
5. 事業譲渡
事業譲渡は、会社の事業の一部または全部を、資産・負債等を個別に特定して売買する手法です。
「選択と集中」を目的として、不採算事業やノンコア事業を切り離す際に活用されます。買い手は必要な資産・負債・契約等のみを選択して承継できる点が特徴です。
メリット
- 子リスクの限定:買い手は、譲渡対象とする資産や負債を契約で個別に特定できます。そのため、簿外債務や訴訟リスクといった不要なリスクを引き継ぐことを回避できます。
- 柔軟な事業再編:売り手は、会社自体は手元に残したまま、特定の事業だけを売却して資金化し、その資金を主力事業の強化に再投資するといった柔軟な戦略が可能です。
デメリット
- 手続きの煩雑さ:資産、負債、従業員との雇用契約、取引先との契約などを個別に移転させる必要があり、関係者から個別の同意を取り付けるなど、手続きが煩雑です。
- 許認可の再取得と税負担:必要な許認可は原則として買い手が再取得します(承継不可の許認可が多い)。また、売り手には法人税、買い手には消費税や不動産取得税などの税負担が発生します。
必要な手続き
- 取締役会決議:重要な財産の処分又は譲受けとなるため、取締役会設置会社では取締役会決議が必要です(取締役会非設置会社であれば取締役の過半数の賛成)。
- 事業譲渡契約の締結:譲渡対象となる資産・負債、譲渡価格、従業員の処遇などを定めた契約を締結します。
- 株主総会の特別決議:事業の全部譲渡や、重要な一部の譲渡に該当する場合には、株主総会の特別決議による承認が必要です。
- 個別の移転手続き:不動産の所有権移転登記、取引先との契約の再締結、従業員の転籍は個別同意が原則であり、同意取得等の手続きが必要です。
発生する税金
- 売り手:事業の譲渡によって得た利益に対して法人税が課税されます。また、建物・機械等の譲渡は課税資産の譲渡に該当し消費税が掛かりますが、土地の譲渡は非課税取引とされ、消費税は掛かりません。
- 買い手: 課税資産の取得に対して消費税の支払いが必要です(仕入税額控除の対象)。不動産を取得した場合は不動産取得税が課税され、所有者の変更登記の際には登録免許税が課税されます。
6. 会社分割
会社分割は、会社の事業の一部または全部を分割し、その権利義務を包括的に新設会社(新設分割)または既存会社(吸収分割)に承継させる組織再編手法です。
事業譲渡と似ていますが、権利義務を個別にではなく包括的に承継できる点が大きく異なります。
メリット
- 手続きの簡素化:包括承継であるため、事業譲渡のように取引先等の個別同意は不要。ただし従業員は労働契約承継法に基づく通知・異議申出手続が必要です。
- 税負担の抑制: 対価を承継会社の株式とする設計が可能で、現金支出を抑えられます。グループ内再編などで柔軟に活用できます。
デメリット
- 不要な負債の承継リスク:事業に関する権利義務を包括的に承継するため、意図しない負債や契約も引き継いでしまう可能性があります。デューデリジェンスによるリスクの把握が不可欠です。
- 債権者保護手続き: 会社分割によって不利益を被る可能性のある債権者を保護するため、原則として公告・催告が必要(簡易・略式分割では省略可)。
必要な手続き
- 会社分割計画・契約の作成:新設分割の場合は「分割計画」を、吸収分割の場合は「分割契約」を作成・締結します。
- 事前開示書類の備置:計画・契約の内容などを記載した書類を本店に備え置きます。
- 株主総会の特別決議: 原則として、当事会社で株主総会の特別決議による承認が必要です。
- 債権者保護手続き: 債権者の利益を害する可能性がある場合に必要となります。
- 効力発生と登記: 計画・契約で定めた日に効力が発生し、法務局で変更登記(分割会社)や設立登記(新設会社)を行います。
発生する税金
- 法人:税制適格要件を満たせば含み益課税は繰延べ、非適格なら譲渡課税となります。
- 株主:分社型分割で非適格の場合、みなし配当課税が生じ得ます。
- 承継会社:不動産を取得した場合は不動産取得税が課税され、所有者の変更登記の際には登録免許税がかかります。
7. 吸収合併
吸収合併は、一つの会社(存続会社)が他の会社(消滅会社)の権利義務のすべてを承継し、消滅会社は解散する組織再編の手法です。
複数の企業を法的に一体化し、経営資源の集約やスケールメリットによるシナジー効果の創出を目指す場合に用いられます。
メリット
- 早期のシナジー創出:会社が統合されることで、重複部門の統廃合によるコスト削減や技術・ノウハウの共有、販売網の相互活用などのシナジーを早期に発揮できます。
- 経営効率の向上:組織や情報システムを一本化することで、管理コストの削減や意思決定の迅速化が図れます。さらに、企業規模の拡大によって信用力やブランド力の向上も見込めます。
デメリット
- リスクの包括承継:消滅会社の権利義務をすべて引き継ぐため、簿外債務や偶発債務といった潜在的なリスクもすべて承継します。
- 組織文化の融合の難しさ(PMIの困難性):異なる企業文化や人事制度を持つ従業員同士の融合がうまくいかず、組織的な混乱や優秀な人材の流出を招く恐れがあります。PMI(Post Merger Integration:M&A後の統合プロセス)の負担が大きい手法です。
必要な手続き
- 吸収合併契約の締結:当事会社間で合併比率などを定めた契約を締結します。
- 事前開示書類の備置:契約内容を記載した書類を本店に備え置きます。
- 株主総会の特別決議:原則として、両社で株主総会の特別決議による承認が必要です。
- 債権者保護手続き:合併に異議のある債権者のために、債権者保護手続きを行う必要があります。
- 効力発生と登記:契約で定めた日に効力が発生し、存続会社は変更登記、消滅会社は解散登記を申請します。
発生する税金
- 消滅会社:税制適格要件を満たさない場合、保有資産の含み益(譲渡益)に対して法人税が課税されます。
- 消滅会社の株主:対価として存続会社の株式以外の金銭などを受け取った場合、みなし配当として所得税などが課税される可能性があります。
- 存続会社:資本金が増加する場合、登録免許税がかかります。不動産を承継した場合は不動産取得税が課税されます。
8. 新設合併
新設合併は、合併する複数の会社がすべて解散し、同時に新たに設立した会社にすべての権利義務を包括的に承継させる組織再編の手法です。
吸収合併と異なり、参加するすべての会社が対等な立場で統合することを対外的に示すことができますが、手続きの煩雑さから実務で用いられるケースは稀です。
メリット
- 対等な立場での統合:すべての会社が解散して新会社を設立するため、どちらかが吸収したというイメージがなく、対等な精神での経営統合をアピールできます。
- 新たな企業文化の構築:ゼロから新会社を設立するため、各社のしがらみを排し、全く新しい企業文化やビジョン、組織体制を構築しやすいという利点があります。
デメリット
- 手続きの煩雑さと高コスト:手続きがM&Aスキームの中で最も煩雑であり、複数の会社の解散登記と新会社の設立登記、すべての許認可の再取得などに多大な時間とコストがかかります。
- 大規模な統合作業:システム統合や業務プロセスの見直しなど、PMIの負担が吸収合併以上に大きくなる可能性があります。上場会社は一度上場廃止となり、新会社で再上場を目指す必要がある点もデメリットです。
必要な手続き
- 新設合併契約の作成:各消滅会社間で、新設会社の商号や目的、合併比率などを定めた契約を作成します。
- 事前開示・株主総会承認・債権者保護手続き:手続きの基本的な流れは吸収合併と同様です。
- 新設会社の設立登記:法務局に新設会社の設立登記を申請することで、合併の効力が発生します。同時に各消滅会社の解散登記も行われます。
発生する税金
- 各消滅会社およびその株主:吸収合併と同様に、税制適格要件を満たさない場合は、各社・各株主に対して課税が発生する可能性があります。
- 新設会社:会社の設立登記時に登録免許税が、不動産を承継した場合は不動産取得税が課税されます。



M&Aスキームの種類ごとに適した選び方・判断基準
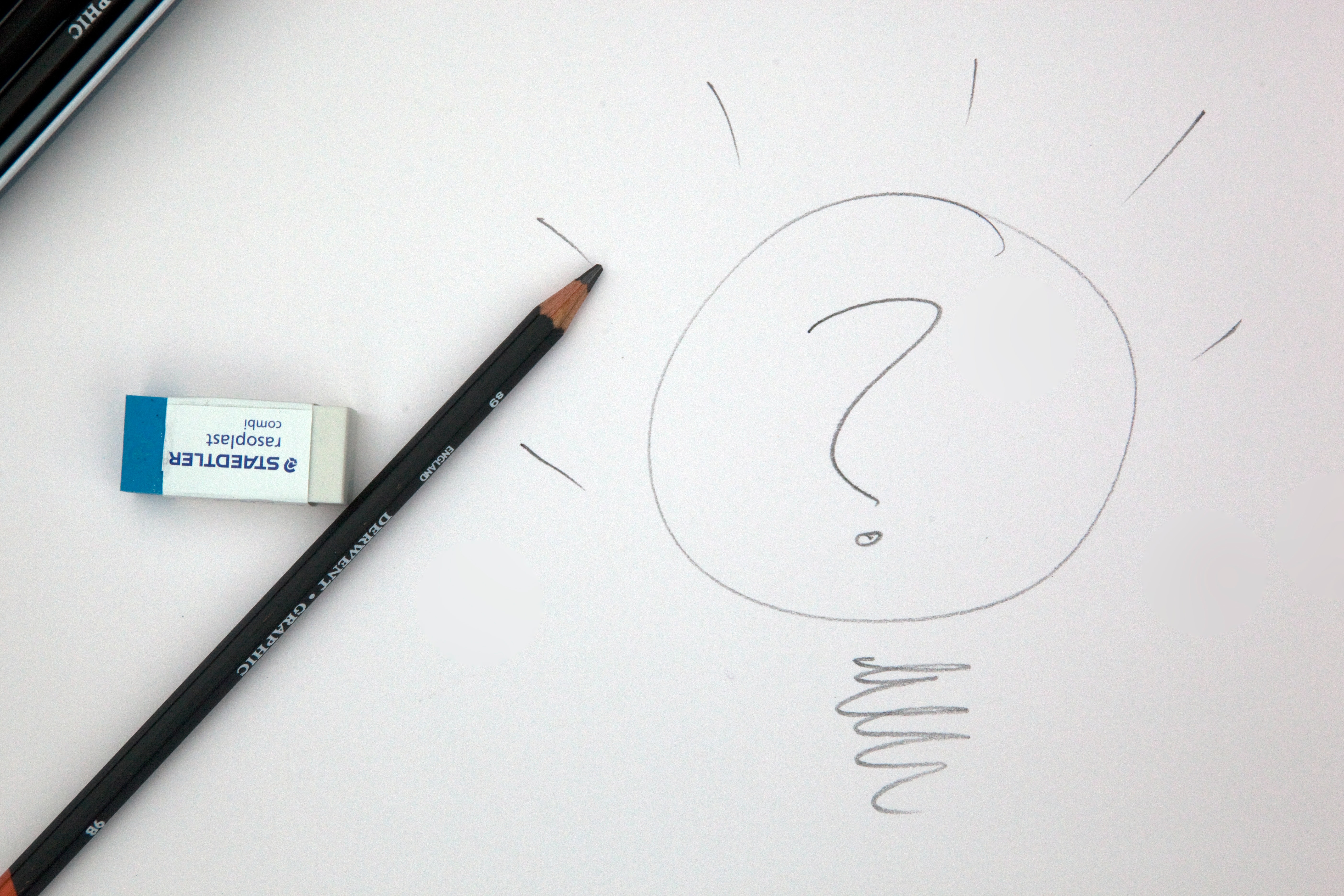
最適なM&Aスキームは、企業の目的や状況によって異なります。
ここでは、「目的」「経営課題」「税務・リスク」といった多角的な視点から、自社に合ったスキームを選ぶための判断基準を解説します。
自社の課題・目的から選ぶ
M&Aの目的を明確にすることが、スキーム選択の第一歩です。
例えば、後継者不在による事業承継が目的なら、手続きが比較的簡便な株式譲渡が有力な選択肢となります。
一方で、ノンコア事業を売却して主力事業に集中したい場合は、対象事業を切り離せる事業譲渡や会社分割が有効です。
「新規事業への参入」を目指すのであれば、会社全体を取得する「株式譲渡」や、特定の事業部門のみを取得する「事業譲渡」などが考えられます。
このように、自社の課題と目的を整理し、それに合致するスキームを絞り込んでいくことが重要です。
税務・リスク・PMI観点の選定方法
各スキームは、税務上の取り扱いやリスクの承継範囲、PMIの難易度が大きく異なります。
例えば、株式譲渡は包括承継のため、簿外債務を含むリスクを引き継ぐ可能性がありますが、事業譲渡は必要な資産・負債のみを取得するため、簿外債務リスクを回避できます。
また、合併や会社分割などの組織再編行為は、税制適格要件を満たすことで課税を繰り延べられる可能性があります。
PMIの観点では、法人格が一つになる合併は統合負担が大きい一方、株式交換による子会社化は独立性を保ちやすく、段階的な統合も行いやすい方法です。
これらの要素を総合的に比較検討し、最もバランスの取れたスキームを選択する必要があります。



M&A関連契約・DD(デューデリジェンス)の種類とポイント

M&Aを成功させるためには、スキーム選択後の実務プロセスも極めて重要です。
ここでは、M&Aのプロセスで不可欠となる契約書やデューデリジェンス(DD)の種類と、それぞれのポイントについて解説します。
M&A契約書の主要種類
M&Aで締結される最終契約書は、選択したスキームによって名称や内容が異なります。
代表的なものに「株式譲渡契約書」「事業譲渡契約書」「合併契約書」などがあります。
これらの契約書には、取引の対象、譲渡価格、クロージング(取引実行)の前提条件といった基本事項に加え、「表明保証」や「競業避止義務」などの重要な条項が盛り込まれます。表明保証とは、売り手が会社の財務や法務に関する情報が真実かつ正確であると保証する条項で、後の紛争防止に不可欠です。
DD(デューデリジェンス)の種類と手順
デューデリジェンス(DD)とは、M&Aの対象となる企業の価値やリスクを精査する買収監査のことです。
DDは調査領域ごとに、財務DD・法務DD・税務DD・ビジネスDDなどに区分されます。
財務DDでは財務諸表の正確性や収益性、キャッシュ・フローを分析し、法務DDでは契約関係や訴訟リスク、許認可の状況などを調査します。
これらのDDを通じて、買収価格の妥当性を検証し、簿外債務などの潜在的リスクを洗い出すことが、M&Aの失敗を避けるための鍵となります。




M&Aスキームの種類ごとの事例紹介
ここでは、これまで解説してきたM&Aスキームが、実際のビジネスシーンでどのように活用されているのか、具体的な事例を交えて紹介します。
自社の状況と照らし合わせることで、スキーム選択の具体的イメージを掴みやすくなるでしょう。
株式譲渡の事例 : 中小企業の事業承継事例
後継者不在に悩むオーナー経営者が、自社の全株式を同業の大手企業に譲渡し、事業と従業員の雇用を承継させたケースです。
手続きが比較的簡便な株式譲渡を選択することで、スムーズな経営権の移転を実現し、長年培ってきた技術やブランドの存続に繋がりました。
事業譲渡の事例 : 大手電機メーカーによる非中核事業の売却事例
大手電機メーカーが経営資源を主力事業に集中させるため、複数の事業部門の中から特定のノンコア事業を投資ファンドに売却した事例です。事業譲渡を用いることで、必要な資産・人材のみを残し、会社全体のポートフォリオを最適化しました。
合併・会社分割の事例 : 金融業界や製薬業界における再編事例
競争が激化する金融業界において、複数の地方銀行が経営基盤を強化するために吸収合併を行い、地域トップバンクが誕生したケースがあります。また、製薬業界では、特定の研究開発部門を会社分割によって切り出し、専門性の高い子会社として独立させることで、研究開発のスピードと効率を高める事例が見られます。
株式交換・移転の事例 : 異業種企業を傘下に収めるホールディングス化の事例
IT企業が、事業領域を拡大するためにマーケティング会社を株式交換によって完全子会社化した事例です。また、複数の食品メーカーが共同で持株会社を設立(株式移転)し、仕入れや物流の共通化によるシナジーを追求するホールディングス体制へ移行したケースも代表的です。
M&Aスキームの種類選択における注意点・リスク管理

M&Aのスキーム選択は、将来の経営に大きな影響を与える重要な意思決定です。
ここでは、選択プロセスにおいて特に注意すべき点や、潜在的なリスクを管理するためのポイントを解説します。
契約・手続き上の注意
M&Aの契約交渉では、前述の「表明保証」の範囲や、売り手の「競業避止義務」(一定期間、同種の事業を行わない義務)の内容を慎重に定める必要があります。これらの条項は、買い手を潜在的なリスクから保護するために重要です。
また、選択するスキームによっては、株主総会の特別決議や債権者保護手続きといった法的なプロセスが求められます。これらの手続きを怠ると、M&Aの効力が否定されるリスクもあるため、専門家の助言を受けながら、法規制を遵守して進めることが不可欠です。
中小企業が陥りやすい落とし穴
中小企業のM&A、特に事業承継を目的とする場合、感情的な側面が意思決定に影響を与えやすい傾向があります。
例えば、「会社を乗っ取られる」といった誤解から、第三者割当増資を選択した結果、経営権の移転が不十分となり、経営改善が進まなかったケースなどです。
また、自社の価値を客観的に評価せず、希望的観測に基づき価格交渉を進めてしまった結果、交渉が破談する例も少なくありません。M&Aを成功させるためには、客観的な視点と、自社の目的達成のために最適なスキームは何かを冷静に判断する姿勢が求められます。



M&Aスキームの種類に関するよくある質問(FAQ)

Q. 株式譲渡と事業譲渡の最も大きな違いは何ですか?
A. 最も大きな違いは、譲渡の対象です。株式譲渡は会社全体(経営権)を対象とするのに対し、事業譲渡は事業の一部または全部を個別に選択して譲渡する点にあります。これに伴い、負債の承継範囲(包括承継か個別承継か)や手続きの煩雑さも大きく異なります。
Q. 株式交換と株式移転はどう使い分ければよいですか?
A. どちらも完全親子会社関係を構築する手法ですが、親会社の作り方が異なります。既存の会社を親会社として他の会社を子会社にする場合は「株式交換」を選択します。一方、新たに親会社を設立し、既存の会社がその傘下に入る形でグループを再編する場合は「株式移転」を選択します。
Q. 中小企業のM&Aで最もよく使われる手法は何ですか?
A. 手続きが比較的シンプルで経営権を移転しやすい株式譲渡が、中小企業のM&Aで最も多く活用されています。特に、オーナー経営者が全株式を保有しているケースが多く、株主の合意形成が容易なため、事業承継の場面で広く選択されています。


まとめ
本記事では、M&Aの主要な8つの種類(スキーム)について、それぞれの仕組み、メリット・デメリット、そして目的別の選び方を詳しく解説しました。
株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割など、各手法には明確な特徴があり、どのスキームを選択するかがM&Aの成否を大きく左右します。
M&Aを成功に導くためには、まず自社の経営課題やM&Aによって達成したい目的を明確にすることが不可欠です。
その上で、各スキームの特性を深く理解し、税務や法務、PMIの観点も含めて総合的に比較検討することが重要となります。
複雑な判断が必要となるため、M&Aの専門家やアドバイザーに相談し、客観的な意見を取り入れながら最適なスキームを見つけ出してください。








