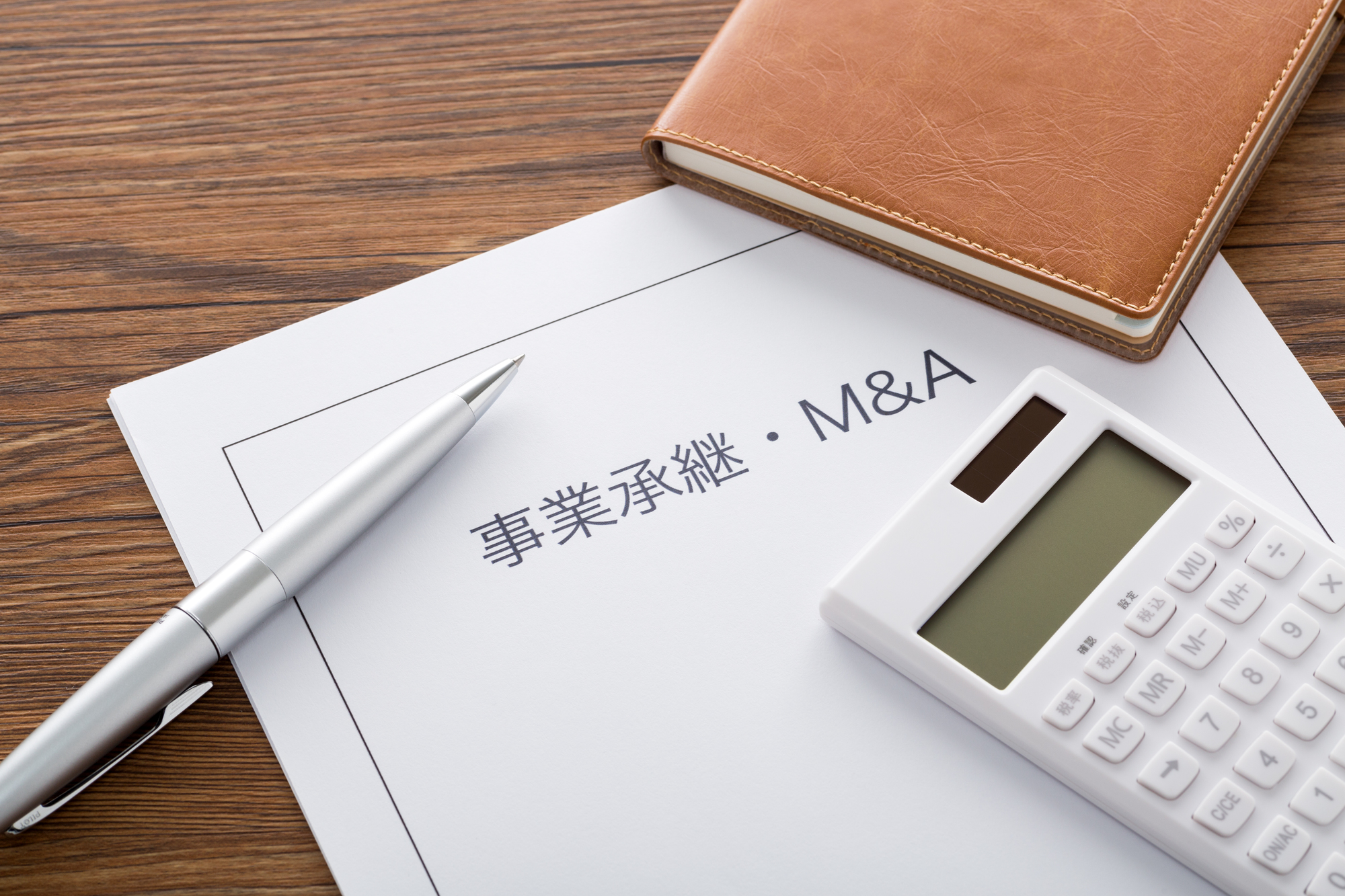
事業承継とM&Aの違いは?メリット・デメリットと注意点を徹底解説
事業承継とM&Aの基本的な定義の違いから、それぞれのメリット・デメリット、具体的な手法やプロセス、専門家の選び方までを網羅的に解説します。
「事業承継とM&Aは似ているが何が違う?」「自社の将来を考えたとき、どちらが最適?」などの悩みを抱えていませんか。
事業承継とは事業を後継者に引き継ぐ行為全般を指し、M&Aはそのための有力な手段の一つです。
本記事では、事業承継とM&Aの基本的な定義の違いから、それぞれのメリット・デメリット、具体的な手法やプロセス、専門家の選び方までを網羅的に解説します。
最後まで読むことで、自社に合った承継方法を見極め、円滑な事業引継ぎに向けた行動が可能になります。まずは両者の違いを正しく理解することから始めましょう。


事業承継とM&Aの定義と違い

事業承継とM&Aは混同されがちですが、その定義と関係性を正しく理解することが重要です。
事業承継は会社経営を後継者に引き継ぐ広い概念で、M&Aはその実現手段の一つです。
ここでは、それぞれの言葉の定義と、事業承継において引き継がれる要素について詳しく解説し、両者の関係性を明確にします。
M&Aとは?
M&Aとは、「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略称です。
具体的には、複数の企業が一つになったり(合併)、ある企業が他の企業を買い取ったり(買収)することを指します。
M&Aは、買い手には事業拡大や新規参入、売り手には後継者問題の解決や創業者利益の獲得などの目的で活用されます。
事業承継の文脈では、親族や社内に後継者がいない場合に、第三者へ会社や事業を売却する(譲渡する)ための手段として用いられます。
事業承継とは?
事業承継とは、会社の経営を現在の経営者から後継者へと引き継ぐ一連のプロセス全体を指します。
単に社長職を譲るだけでなく、経営理念、事業、資産、知的財産など経営に関わる全てを引き継ぐことを意味します。
後継者の属性によって、親族に引き継ぐ「親族内承継」、役員や従業員に引き継ぐ「従業員承継」、そしてM&Aを活用して第三者に引き継ぐ「第三者承継(M&A)」の3つの種類に大別されます。
つまり、M&Aは事業承継を実現するための選択肢の一つなのです。
事業承継で引き継ぐ要素
事業承継では、有形・無形の様々な要素が後継者へと引き継がれます。主な要素は「人(経営権)」「資産」「知的資産」の3つに分類されます。
「人」とは、経営権そのものであり、後継者となる人物を指します。次に「資産」には、自社株式や事業用資産(設備、不動産など)、運転資金といった金銭的価値のあるものが含まれます。
最後に「知的資産」は、経営理念や企業のブランド価値、特許やノウハウ、取引先との人脈といった、目には見えないが企業の競争力の源泉となる重要な要素です。
これらを一体として引き継ぐことが、事業承継の本質です。


事業承継の主な方法と特徴

事業承継は、引き継ぐ相手によって大きく3つに分かれます。特徴やメリット・デメリットは異なるため、自社に合った方法を選ぶことが重要です。
ここでは、「親族内承継」「従業員承継」「事業承継型M&A」の3つの方法について、その概要と特徴を解説します。
親族内承継
親族内承継は、経営者の子供や配偶者、兄弟姉妹など親族に事業を引き継ぐ方法で、日本の中小企業では従来最も多く採用されてきました。
メリットとしては、幼い頃から経営者の姿を見て育っているため経営理念や事業への理解が深く、他の役員や従業員、取引先からも後継者として受け入れられやすい点が挙げられます。
一方で、親族内に経営者としての資質と意欲を兼ね備えた人材がいるとは限らず、相続税などの税負担が大きくなる可能性がある点がデメリットです。
従業員承継
従業員承継とは、親族以外の役員や従業員の中から、経営能力のある人材を後継者として事業を引き継ぐ方法です。社内承継とも呼ばれます。
長年勤務してきた従業員であれば、会社の事業内容や経営理念、企業文化に精通しているため、スムーズな引き継ぎが期待できるのが大きなメリットです。
また、他の従業員のモチベーション向上にも繋がります。
ただし、後継者候補となる従業員が、株式の買取などに必要な資金を十分に用意できないケースが多いという課題があります。
事業承継型M&A(M&Aによる第三者承継)
事業承継型M&Aは、親族や社内に後継者がいない場合に、M&Aで社外の第三者(企業や個人)へ会社や事業を譲渡する方法です。
最大のメリットは、後継者不在を解決できることです。
幅広い選択肢の中から最適な買い手を探すことができ、従業員の雇用維持や事業の継続も可能です。
また、オーナー経営者は会社を売却することで、創業者利益としてまとまった資金を得ることができます。
近年、中小企業の後継者不足が深刻化する中で、この方法を選択する企業が増加しています。



事業承継型M&Aのメリット

事業承継型M&Aは、後継者問題を抱える売り手企業だけでなく、事業拡大を目指す買い手企業にとっても多くのメリットをもたらします。双方にとってWin-Winの関係を築ける可能性を秘めた手法です。
ここでは、M&Aを活用した事業承継がもたらすメリットを、売り手側と買い手側それぞれの視点から詳しく解説します。
売り手側のメリット
① 後継者の選択肢を広げられる
親族や社内に限定せず、日本全国、時には海外の企業からも後継者候補を探せるため、事業を最も成長させてくれる可能性のある相手に託すことができます。
② 従業員の雇用を維持できる
M&Aの契約において、従業員の雇用維持はしばしば契約条件に盛り込まれ、配慮が求められます。
これにより、廃業を選択した場合に失われてしまう従業員の生活を守ることができます。
③ 創業者利益として資金を得られる
会社の株式や事業を売却することで、オーナー経営者はまとまった現金(創業者利益)を手にすることができます。
引退後の生活資金や、新たな事業への挑戦資金として活用できます。
④ 製品やサービスを継続できる
自社が長年かけて築き上げてきた製品やサービス、ブランドを、M&Aによって買い手企業に引き継いでもらうことで、後世に残していくことが可能になります。
⑤ 節税効果が期待できる
会社の株式を譲渡した場合の利益にかかる税金は、他の所得税などと比較して税率が低く設定されています。
そのため、役員退職金などと組み合わせれば、税負担を抑えられる可能性があります。
ただし、節税の可否は場合によって異なるので、専門家に相談して個別にシミュレーションすることを推奨します。
買い手側のメリット
①事業規模を効率的に拡大できる
ゼロから始めるより、既存事業の買収は短期間で規模やシェアを拡大できます。
時間とコストを大幅に節約できる効率的な成長戦略です。
②優秀な人材を一括で確保できる
M&Aによって、売り手企業が抱える経験豊富な従業員や専門技術を持つ人材をまとめて獲得できます。
人材採用が困難な現代において、大きなメリットと言えます。
③技術やノウハウを獲得できる
自社にない独自の技術や製造ノウハウ、特許などを獲得できます。
これにより、製品開発力の強化や、新たな市場への参入が容易になります。
④新規事業に迅速に参入できる
許認可が必要な事業や、実績が求められる業界へも、M&Aを通じて迅速に参入することが可能です。
事業の多角化をスピーディーに進めることができます。
⑤成長分野へ低リスクで進出可能
すでにある程度の顧客基盤や事業モデルが確立されている企業を買収することで、新規参入に伴うリスクを低減させながら、成長分野へ進出することができます。



事業承継型M&Aのデメリット・リスク
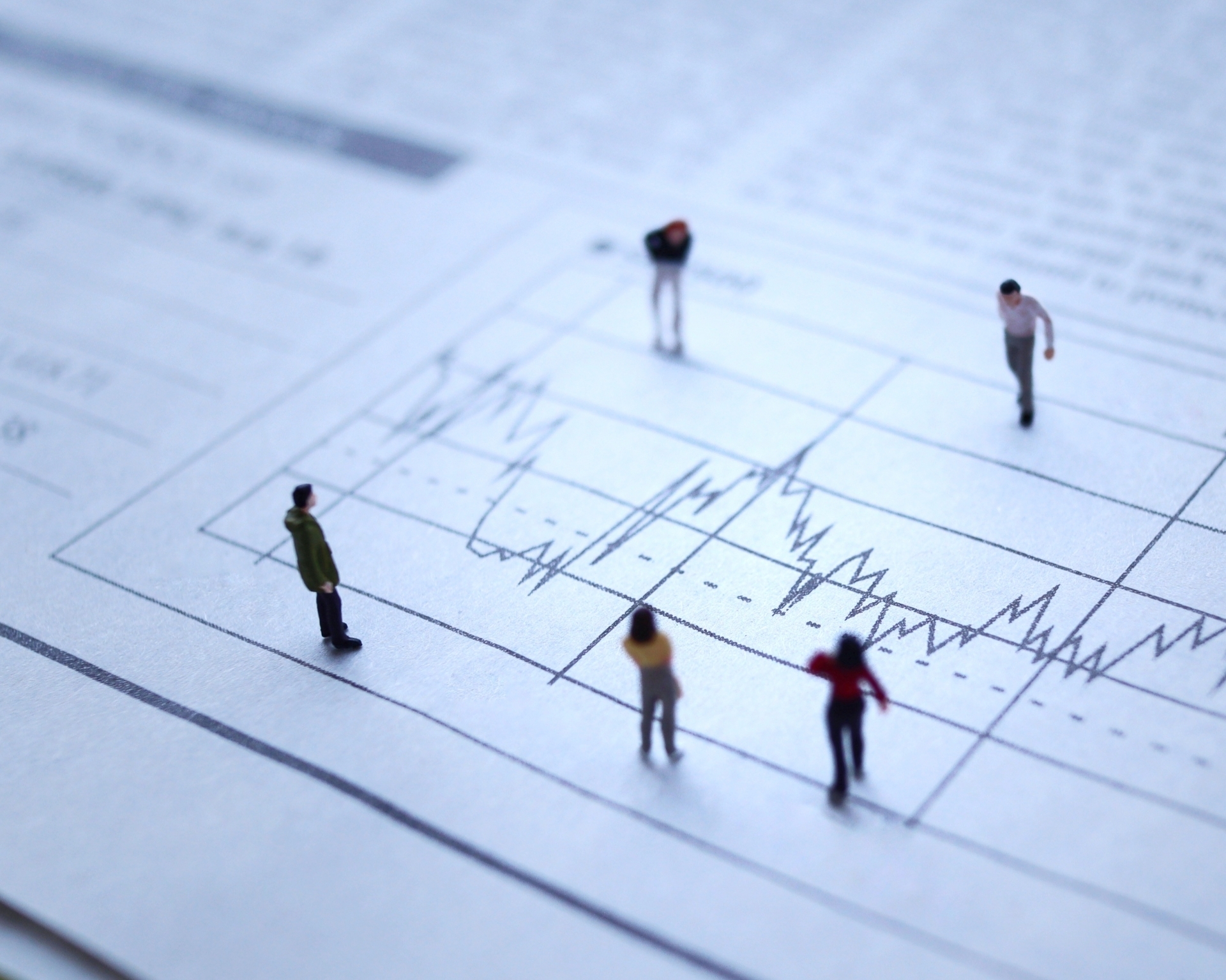
多くのメリットがある一方で、事業承継型M&Aにはデメリットやリスクも存在します。
売り手・買い手双方がこれらの点を十分に理解し、対策を講じながら進めることが成功の鍵となります。
ここでは、M&Aに伴う潜在的なデメリットを、売り手側と買い手側それぞれの視点から具体的に解説します。
売り手側のデメリット
①希望条件に合う買い手が少ない
事業価値を正しく評価し、雇用や企業文化の維持など希望条件を満たす買い手は容易に見つからない場合があります。
②買い手が決まるまで時間がかかる
M&Aの手続きは複雑で、相手選定から契約まで1年以上かかることもあります。長期戦になることを覚悟しておく必要があります。
③情報漏えいで従業員離職の恐れ
M&Aを検討しているという情報が不用意に外部に漏れると、従業員の不安による離職や取引先との関係悪化のリスクがあります。
④譲渡後に経営方針が変わる不安
買い手の方針次第で企業文化や労働条件が変わり、従業員の反発を招く可能性があります。
⑤譲渡益に対する課税負担がある
会社や事業を売却して得た利益(譲渡所得)に対しては、所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。
税負担は事前にシミュレーションして把握しておくことが重要です。
買い手側のデメリット
①簿外債務や偶発債務の引継ぎリスク
決算書に記載されていない債務(簿外債務)や、将来発生し得る損害賠償(偶発債務)などを買収後に引き継ぐリスクがあります。
②従業員の反発や離職が起こる可能性
M&A後の経営方針の変更や企業文化の違いから、主要役員や従業員が反発し、大量離職に至る場合があります。
事業の継続に支障をきたす恐れがあります。
③期待通りの成果が得られないことも
買収前に期待していたようなシナジー(相乗効果)が生まれず、投資額に見合う収益を得られない可能性があります。
事前の調査や分析が不十分だと、このリスクは高まります。
④統合後の企業文化の違いによる摩擦
異なる歴史や価値観を持つ企業同士が一つになるため、従業員間で意思疎通のずれや業務方針の対立が起こる場合があります。
⑤PMI対応に時間とコストがかかる
PMI(Post Merger Integration)とは、M&A成立後の経営統合プロセスのことです。
人事制度や情報システムの統合など、PMIの円滑化には多くの時間・コスト・労力が必要となります。



事業承継型M&Aの流れ

事業承継型M&Aは、すぐに実行できるものではありません。
専門家と連携しながら、計画的にステップを踏んで進めていく必要があります。
ここでは、M&Aの検討を開始してから、最終的に契約を締結し承継が完了するまでの一般的な流れを、4つのステップに分けて解説します。
STEP1:現状分析と承継・売却準備
M&Aの専門家に相談し、経営状況や財務内容、強み・弱みを客観的に分析します。企業価値を評価し、事業承継に向けた計画を策定します。
この段階で、売却条件や従業員の処遇をなどの希望を整理しておくことが重要です。
STEP2:M&A方針の決定
現状分析と企業価値評価の結果を踏まえ、M&Aを進めるか最終決定します。進めることを決断した場合は、M&Aアドバイザリー会社と契約を結びます。
契約後は、買い手候補向けの企業概要書(ノンネームシートやインフォメーション・メモランダム)を作成し、具体的な準備に入ります。
STEP3:買い手企業を選定・交渉
M&Aアドバイザーを通じて買い手候補企業を探します(マッチング)。候補企業が見つかったら、秘密保持契約を締結した上で詳細な資料を開示し、交渉を開始します。
複数候補と交渉し、条件が合意した一社と基本合意書を締結します。その後、買い手企業による詳細な企業調査(デューデリジェンス)が行われます。
STEP4:契約締結・承継完了
デューデリジェンスの結果、問題がなければ最終的な条件交渉を行い、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書などの最終契約を締結します。
契約内容に基づき、株式譲渡と対価決済を行い、経営権を買い手企業へ移転します。
これでM&Aの手続きは完了となり、事業承継が実現します。




事業承継型M&Aを実施する際のポイント

事業承継型M&Aは、重要なポイントを押さえることで成功率が高まります。
事前理解と計画的な進行が、トラブル回避と円満な承継に直結します。
ここでは、M&Aを検討する際に特に留意すべき6つのポイントについて解説します。
ポイント①:M&Aの専門家選びは慎重に
M&Aの成否は、パートナーとなる専門家(M&Aアドバイザー)の質に大きく左右されます。
実績、得意業界、手数料体系を比較検討し、自社に合う信頼できるアドバイザーを選ぶことが重要です。
担当者との相性も大切な要素ですので、複数社と面談し、相談への姿勢や対応の丁寧さを確認します。
ポイント②:企業価値の適切な評価と希望条件の整理
交渉を有利に進めるためには、まず自社の価値を客観的かつ適正に評価してもらうことが不可欠です。
その上で、譲渡価格や従業員の雇用維持、取引先との関係継続など、譲渡価格や雇用維持などの最低条件を事前に明確化します。
希望条件に優先順位をつけておくことで、交渉の場で迅速かつ的確な判断を下すことができます。
ポイント③:情報漏洩の徹底した管理
M&Aの検討段階で情報が漏れてしまうと、従業員の間に動揺が広がり、モチベーションの低下や離職につながる恐れがあります。
また、取引先や金融機関に不安を与え、事業そのものに悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
専門家との秘密保持契約に加え、社内共有は必要最小限に留めます。
ポイント④:デューデリジェンスへの誠実な対応
デューデリジェンス(DD)とは、買い手企業が売り手企業の財務や法務、事業内容などを詳細に調査するプロセスです。
この調査に対しては、資料を迅速に提出し、質問には正確かつ誠実に回答します。
意図的に不都合な情報を隠したり、虚偽の説明をしたりすると、後で契約違反として損害賠償を請求されるなど、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
ポイント⑤:従業員や取引先への丁寧な説明
M&Aの実施は、長年会社を支えてくれた従業員や、信頼関係を築いてきた取引先に大きな影響を与えます。
そのため、最終契約の締結後など、適切なタイミングで、経営者が直接説明を行うことが重要です。
M&Aを決断した背景や、今後の事業方針、従業員の処遇などを真摯に伝えることで、不安を解消し、円滑な引き継ぎへの協力を得られるように努めましょう。
ポイント⑥:M&A後の統合プロセス(PMI)を見据えた準備
M&Aは、契約を締結したら終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。
M&A成立後の経営統合プロセス(PMI)が円滑に進まなければ、期待したシナジー効果は得られません。
交渉段階から理念や業務、人事制度をすり合わせ、PMIを前提に準備します。



事業承継型M&Aにおける専門家・支援制度
事業承継型M&Aは、法務・税務・財務など専門知識が必要で、自社のみでの対応は難しい分野です。
信頼できる専門家と公的支援制度を有効活用することが成功への近道となります。
ここでは、どのような専門家がいるのか、そしてどのような支援制度が利用できるのかを具体的に紹介します。
専門家の選び方(M&Aアドバイザー・税理士・中小企業診断士など)
M&Aを支援する専門家には、M&A仲介会社やFA(フィナンシャル・アドバイザー)といったM&Aアドバイザーのほか、税務面でサポートする税理士、法務面でサポートする弁護士、経営全般について助言する中小企業診断士などがいます。
専門家は、M&A実績、業界知識、料金の明確さ、親身な対応の有無を基準に選びます。
支援制度・補助金・公的機関の活用
国は中小企業の円滑な事業承継を支援する制度を用意しています。
代表例の「事業承継・引継ぎ補助金」では、専門家費用や設備投資などの経費が補助されます。
各都道府県の「事業承継・引継ぎ支援センター」では、無料相談やM&Aのマッチング支援を提供しています。
公的機関を活用すれば、コストを抑えて事業承継を進められます。
事業承継・M&Aマッチングプラットフォームの活用
近年、インターネットで売り手と買い手を直接つなぐ「M&Aマッチングプラットフォーム」の利用が増えています。
仲介を介さずに交渉でき、手数料を抑えられる点が魅力です。
その代表的なプラットフォームが、国内最大級の登録者数を誇る「TRANBI(トランビ))」です。
TRANBIは、売り手は無料で案件登録でき、匿名交渉も可能です。
買い手は豊富な案件から相手を探し、直接アプローチできます。
専門家への相談も可能で、M&Aのプロセスをスムーズに進めるためのサポート体制も整っています。
全国から相手を探せる手軽さもあり、新しい事業承継の形として注目されています。


マッチングプラットフォームを活用した事業承継型M&Aの成功事例

M&Aマッチングプラットフォームを活用することで、従来では見つからなかった相手と出会い、事業承継を成功させた事例が増えています。
ここでは、3つの成功事例を「課題」「取り組み」「結果」に分けてご紹介します。
事例①:森のホテル(長野県)|大手仲介に「価値ゼロ」と評価されたホテルが、1億円近い価値で譲渡成功
長野県でリゾートホテルを経営していたオーナー夫妻は、高齢のため引退を検討。
しかし、自然災害の影響で客足が遠のき、娘たちに事業を継がせることを断念しました。
大手M&A仲介会社から「価値はゼロ円、仲介手数料2,000万円」と提示され、廃業の危機に陥りました。
藁にもすがる思いで「TRANBI」に登録し、初日に7件、最終的に21社からの問い合わせがありました。
プラットフォーム経由で紹介された専門家のサポートを受けながら、複数の候補先と交渉を進めました。
最終的に、隣県でホテル経営を新規事業として希望していた不動産会社に譲渡が決まりました。
大手仲介にゼロ円と評価されたホテルを1億円に近い金額で売却することに成功し、事業と従業員の雇用を守ることができました。
事例②:株式会社澤村製作所(茨城県)|後継者不在の製作所が、技術力を評価する同業者と出会い事業拡大
茨城県で50年続く製作所を経営する84歳のオーナーは、当初予定していた親族への承継が白紙に。
従業員や取引先にも引き受け手が見つからず、後継者不在に悩んでいました。
金融機関の紹介で複数の買い手候補と面談。最終的に、同種の事業を展開するグループ会社を持つ企業とマッチングしました。
正式なM&A交渉の前に、実際の仕事を先行して発注してもらうことで、お互いの技術力や事業シナジーを具体的に確認し、信頼関係を構築しました。
希望額である数千万円で売却に成功し、全従業員の雇用も維持されました。
譲渡後は買い手からの発注が増え、新たな設備投資も検討されるなど事業は成長を続けています。
事例③:切削・研磨加工業|数年間見つからなかった譲渡先が、プラットフォーム登録後わずか半年で成約
従業員10名ほどの切削・研磨加工業を営む70歳の社長は、体力の限界を感じ第三者への事業承継を決意。 専門機関に相談しても数年間譲渡先が見つからず、対応に苦慮していました。
信用金庫の紹介でM&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」に登録。
すると、すぐに多数の申し込みがあり、交渉がトントン拍子に進みました。
交渉においては、社員の雇用継続を最優先条件とし、相手企業の財務状況も決算書でしっかり確認。
創業者同士で事業の苦労を理解し合える人柄を重視し、相手を選びました。
登録から半年以内に、事業内容や社風を理解する企業と成約しました。
長年の懸案だった全社員の雇用を守り、自社製品の海外展開という新たな夢も託し、満足度の高いM&Aを実現しました。


事業承継型M&Aに関するよくある質問
事業承継やM&Aを具体的に検討し始めると、様々な疑問や不安が浮かんでくるものです。
ここでは、経営者の皆様から特によく寄せられる質問とその回答をご紹介します。
自社の状況と照らし合わせながら、理解を深めるためにお役立てください。
どちらが自社に向いているか見極めのポイントは?
親族内承継・従業員承継とM&Aのどちらが向いているかは、後継者候補の有無が最大の判断基準です。
親族や社内に経営資質と意欲を持つ人材がいれば、親族内承継や従業員承継が優先されます。
一方で、適当な後継者が見つからない場合は、M&Aが有力な選択肢となります。
また、業界動向、会社の成長戦略、経営者の引退後の計画も含め、総合的に判断することが重要です。
M&Aでの手数料・費用相場は?
M&Aにかかる費用は、依頼する専門家や案件の規模によって大きく異なりますが、一般的にはM&A仲介会社に支払う「仲介手数料」が最も大きな割合を占めます。
仲介手数料は、取引金額に一定料率を掛ける「レーマン方式」で算出されることが多いです。
また、最低手数料は500万円前後が多く、規模や事業者によっては2,000万円以上の場合もあります。
このほか、弁護士や税理士への費用が別途かかる場合もあります。
一方で、M&Aマッチングプラットフォームを使えば、仲介会社より費用を抑えやすい傾向があります。
M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」は、売り手は無料で登録・利用でき、買い手側が月額利用料を支払うサブスクリプションモデルを採用しています。
これにより、特に小規模なM&Aにおいては、従来の仲介手数料よりも大幅にコストを削減できる可能性があります。
承継手段選定時のトラブルリスクは?
承継手段の選定段階で起こりやすいトラブルとして、経営者と後継者候補との間の意見の対立が挙げられます。
例えば、親族内承継を進めようとしても、子供が承継を望んでいなかったり、経営方針を巡って対立したりするケースです。
また、複数の後継者候補がいると、選定を巡り親族や従業員間で争いが生じる可能性があります。
トラブル防止には、早期に関係者間で話し合い、全員が納得できる形にまとめることが大切です。
必要に応じて、第三者立場の専門家の助言も活用します。



まとめ
本記事では、事業承継とM&Aの違いを軸に、それぞれの定義からメリット・デメリット、具体的な手法や注意点に至るまでを網羅的に解説しました。
事業承継は会社の経営を引き継ぐ行為そのものを指す広い概念であり、M&Aは後継者不在問題を解決するための有効な手段の一つであることがご理解いただけたかと思います。
後継者がいれば親族内承継や従業員承継が選択肢ですが、多くの企業にとってM&Aは存続・発展と雇用維持のための有力な手段です。
しかし、そのプロセスは複雑で専門的な知識を要するため、成功のためには信頼できる専門家のサポートが不可欠です。
本記事が、貴社の将来を考える際の参考となれば幸いです。







