
事業承継を個人が行う場合の流れ。案件の探し方や譲渡金額も確認
経営者の高齢化により後継者不足が深刻化し、親族外の個人が事業を引き継ぐケースが増えています。本記事では、個人による事業承継の流れ、必要な手続き、案件の探し方、譲渡金額の目安について整理して解説します。



事業承継の現状

事業承継とは、会社の経営権や経営資産を後継者に譲り渡すことです。中小企業では後継者不足が深刻化しており、親族以外に事業を承継する『親族外承継』が増加傾向にあります。
後継者不足問題とは
中小企業では後継者不足が深刻で、経営者が高齢にもかかわらず後継候補が決まらない企業が多く見られます。
中小企業庁が公表する『令和元年度(2019年度)の小規模事業者の動向』によると、経営者の年齢と後継者未決定企業の割合は以下の通りです。
- 60代以上:49.5%
- 70代以上:39.9%
- 80代以上:31.8%
休廃業・解散した企業のうち約6割は黒字であり、後継者不在が主因でやむなく廃業する企業が多いことがわかります。
中小企業は地域の経済や雇用を支える重要な役割を担っています。経営者の高齢化が進み、黒字の企業が次々と廃業すれば、日本経済は大きな打撃を受けるでしょう。
参考:2020年版「小規模企業白書」第1部第3章第2節 経営者の高齢化と事業承継|中小企業庁
親族への事業承継が難しい理由
事業承継のパターンには、自分の親族に会社を引き継ぐ『親族内承継』、自社の社員に引き継ぐ『従業員承継』、第三者に引き継ぐ『第三者承継』があります。
かつては事業承継というと、自分の子どもや孫に引き継ぐケースが大半でしたが、近年は親族内承継の割合が減少傾向にあるようです。
その理由としては、『後継者候補に承継の意思がない』『後継者となる人材が育っていない』などが挙げられます。親族が事業を継がない理由として、キャリアの多様化や家業以外の仕事を選ぶ傾向が強まっている点が挙げられます。
後継者に会社を継ぐ意思はあっても、事業を理解していなかったり、性格的に不向きであったりすれば、経営者自らが承継を断念するケースもあります。後継者教育には時間がかかるため、何年も前から計画的に準備をしなければならないのです。
親族外承継は一般的になっている
日本政策金融公庫総合研究所のレポートによると、親族外承継の割合は小規模で約35%、中規模で約58%と高く、後継者不足の進行に伴い今後も増加が見込まれます。
親族外承継のメリットは、親族内に後継者候補がいなくても、自社にふさわしい人材が見つかる可能性が高い点です。経営方針やビジョンに理解のある従業員や役員を後継者にできれば、承継後の事業はスムーズに展開するでしょう。
従業員承継ではなく、M&Aで第三者に事業を引き継ぐ『第三者承継』も増えつつあります。
参考:親族外承継に取り組む中小企業の現状と課題|日本政策金融公庫



個人事業主がM&Aで事業承継をする意味

株式会社や合同会社といった法人格を持たずに、個人で事業を営む人は『個人事業主』や『小規模事業者』と呼ばれます。自分が育ててきた事業を第三者に譲ることには、どのような意義があるのでしょうか?
事業や人材、想いを引き継ぐ
事業承継は、経営者交代だけでなく、事業に蓄積されたノウハウや顧客基盤、価値観などを後継者へ引き継ぐことに重きが置かれます。
事業を辞めるのは自由ですが、先代から受け継いできた知恵がある場合、自分の代で途絶えてしまうでしょう。
『後世に残したい技術や伝統がある』『自分の想いを誰かに引き継いでもらいたい』『従業員の雇用を守りたい』という場合、多くの事業主は事業承継を選択するようです。
譲渡対価を得られる
事業承継の方法は複数ありますが、後継者が見つからない場合は、M&Aによって事業を売却する手法が用いられます。
M&A(Mergers and Acquisitions)は、企業や個人事業の売買・承継に用いられる手法で、近年は小規模事業者の事業承継にも一般化しています。
かつてはM&Aというと、大企業やグローバル企業が行うイメージがありましたが、経営者の高齢化や後継者不在の問題が顕在化したことで、近年は小規模事業者や中小企業がM&Aを選択するケースが増えています。
M&Aで事業を売却した場合、経営者は対価として売却金を受け取れます。老後資金や新たな事業の立ち上げ費用が確保できるのは大きな利点といえるでしょう。
経営者保証を外せる
『経営者保証』とは、金融機関から融資を受ける際に経営者個人やその家族を連帯保証人とする制度です。事業承継では、後継者が経営者保証を引き継ぐ可能性があるという理由から、後継ぎ候補がなかなか見つからないケースも珍しくありません。
中小企業庁では事業承継を推進するため、2020年4月1日より『経営者保証に関するガイドラインの特則』の適用を開始しました。特則によると、適用要件を満たし、かつ金融機関の審査にクリアした場合は『経営者保証の解除』が可能です。
また2020年4月には、『事業承継特別保証制度』が新たに設けられ、後継者候補の確保に関するハードルはさらに低くなっています。
- 事業承継時、一定の要件を満たした場合は経営者保証が不要
- 既存の借入金(経営者保証あり)は、借換によって経営者保証の解除が可能
- 経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合、信用保証制度の保証料を軽減
制度の詳細や条件は、中小企業庁のHPを確認しましょう。
参考:事業承継時の経営者保証解除に向けた、新しい支援施策が2020年4月1日よりスタートします|中小企業庁
参考:経営者保証に関する支援|事業承継・引継ぎポータルサイト



個人事業主の事業承継、法人との決定的な違い
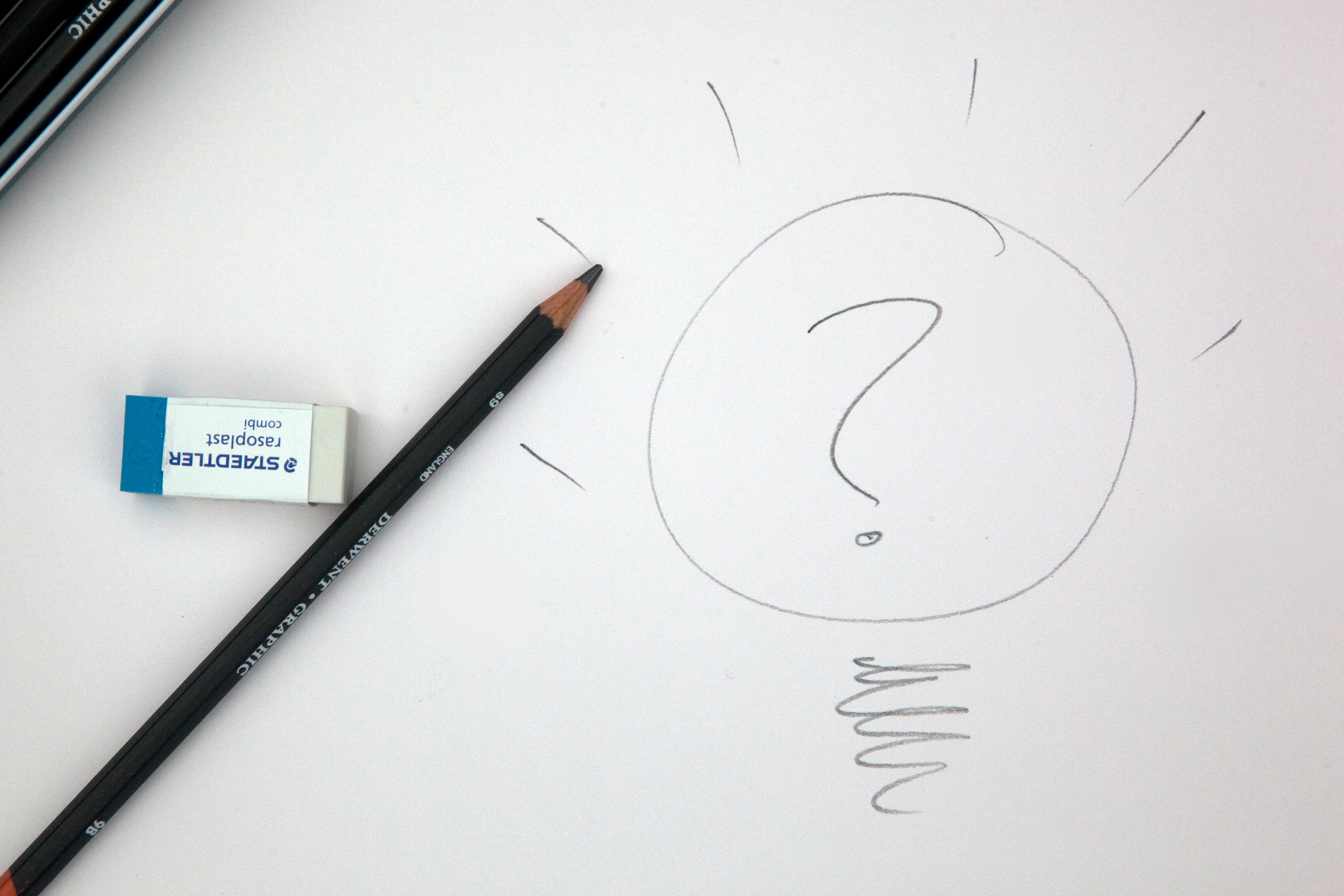
個人事業主の事業承継は、法人の事業承継と比べて、多くの違いがあります。この違いを理解していないと、「こんなはずではなかった」と後で大きなトラブルに発展しかねません。
最大の違いは、個人事業主は「経営者個人=事業」であり、法人のように「会社」という独立した人格が存在しない点です。
法人の事業承継は会社の株式を渡すことで完了しますが、個人事業主の場合は事業に関する資産や権利を一つずつ個別に引き継ぐ必要があります。この違いが、手続きの複雑さに直結します。
違い①:承継方法(株式譲渡が使えず、資産・負債の個別承継が必要)
法人(株式会社)と個人事業主の承継方法における最大の違いは、「株式」の有無です。
【法人の場合】
会社の経営権は株式の取得によって引き継げるように整理されています。後継者がこの株式の過半数を、売買、贈与、相続といった形で先代から取得すれば、会社の経営権は後継者に移ります。会社が所有する資産(不動産、機械、預金など)や負債(借入金など)、契約関係、許認可はすべて「会社」に帰属しているため、経営者が変わっても個別に移転手続きをする必要は基本的にありません。
【個人事業主の場合】
一方、個人事業主には「株式」が存在しません。事業に使っている資産(例:店舗、土地、機械、在庫商品、売掛金、営業車など)や、事業に関する負債(例:金融機関からの借入金、買掛金、未払金など)は、すべて「経営者個人のもの」です。
そのため、事業承継を行う際は、これらの資産と負債を一つひとつリストアップし、売買や贈与、相続などの方法で後継者へ個別に引き継ぐ必要があります。例えば、不動産なら法務局で所有権移転登記を行い、預金口座や新規開設(または名義変更)などの手続きが必要です。
違い②:契約関係(取引先・従業員との再契約が発生)
事業は、取引先や従業員との「契約」によって成り立っています。この点も法人と個人事業主で大きく異なります。
【法人の場合】
法人の場合、取引先との契約や従業員との雇用契約は、「会社(法人格)」と相手方との間で結ばれています。そのため、株式が移動して経営者(株主)が変わったとしても、契約の当事者である「会社」は存続しているため、契約関係は原則としてそのまま継続されます。
【個人事業主の場合】
一方、個人事業主の場合、すべての契約は「経営者個人」と相手方との間で結ばれています。経営者が変わるということは、契約の当事者そのものが変わることを意味します。このため、主要な取引先や仕入先との基本契約、店舗や事務所の賃貸借契約、従業員との雇用契約など、事業に関する契約の多くを、後継者が個人として改めて結び直す必要があります。
この際、相手方が「後継者とは契約しない」と判断するリスクや、契約条件の変更(例:賃料の値上げ、保証金の追加差し入れなど)を求められるリスクもゼロではありません。
違い③:許認可(原則、後継者が新規取得)
特定の事業を行うために必要な行政の「許認可」の扱いも、決定的に異なります。
【法人の場合】
飲食店営業許可、建設業許可、古物商許可などの許認可は、「会社(法人格)」に対して与えられています。経営者が変わっても、許認可を持つ会社自体は変わらないため、簡単な変更届出などで済む場合がほとんどです。
【個人事業主の場合】
個人事業主の場合、これらの許認可は「経営者個人」に対して与えられています。一身専属的な性質を持つため、経営者が変われば、その許認可を後継者が引き継ぐこと(名義変更)は原則としてできません。
したがって、後継者は、自身の名前でこれらの許認可を「新規」で取得し直す必要があります。許認可によっては、取得に数ヶ月かかる場合や、後継者自身に実務経験や資格などの要件が求められる場合もあります。そのため、承継スケジュールを組む上で大きなハードルになることがあります。
違い④:経営者死亡時の口座凍結リスク
万が一、経営者が急逝した場合の影響も異なります。
【法人の場合】
経営者が死亡しても、会社の銀行口座(法人口座)が即座に凍結されることはありません。会社の財産と個人の財産は法律上、明確に分離されているためです。当面の運転資金の支払いは継続できます
【個人事業主の場合】
個人事業主の場合、事業用に使っている銀行口座も、名義は「経営者個人」です。経営者が死亡すると、その口座は相続財産の一部とみなされ、他のすべての個人口座と同様に、金融機関によって凍結されてしまいます。 口座が凍結されると、従業員への給与支払いや、仕入先への買掛金の支払いが一切できなくなります。これにより、後継者が事業を引き継ぐ意思を持っていたとしても、資金繰りがショートし、事業継続が不可能になってしまう深刻なリスクがあります。


個人事業主の事業承継 3つの方法

個人事業主が事業を誰かに引き継ぐ方法は、タイミングや相手方によって、大きく分けて「生前贈与」「相続」「売買(M&A・事業譲渡)」の3つに分類されます。
方法①:生前贈与(親族・従業員へ)
これは、経営者が元気なうちに、後継者(主に親族や、長年事業を支えてくれた従業員など)に、事業用の資産(店舗、機械、在庫など)を無償で譲り渡す(贈与する)方法です。
【メリット】
経営者自身の意思によって、確実に「この人」と決めた後継者に事業を引き継げる点が最大のメリットです。経営者が元気なうちに承継を進めるため、一定期間、経営者が後継者をサポート(OJT)しながら徐々に業務を移行できます。これにより、取引先や従業員の不安も和らげることができ、相続と比べてトラブルが起きにくい、計画的な承継が可能です。
【デメリット(注意点)】
後継者には、贈与された資産の評価額に応じて「贈与税」が課税されるという点が大きなデメリットです。贈与税は税率が非常に高いため(最高55%)、無計画に行うと高額な税負担が発生します。対策として、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)の活用や、後述する「個人版事業承継税制」の利用を検討することが有効です。
方法②:相続(経営者の死亡による)
これは、経営者の死亡によって、事業用の資産や負債を相続人(主に親族)が引き継ぐ方法です。生前に事業承継の準備ができていなかったり、経営者が急逝したりした場合、この形にならざるを得ません。
【メリット】
生前に特別な準備や複雑な手続きを必要としないことが、唯一のメリットと言えるかもしれません。経営者は亡くなる直前まで事業を継続することができます。
【デメリット(注意点)】
事業用の資産はすべて相続財産として、「相続税」の課税対象となります。最大のリスクは、経営者の意思が反映されにくいことです。相続人が複数いる場合、事業に関心がなかった相続人も含めて遺産分割協議を行う必要があり、「事業用の資産(店舗など)を売りたい」と主張する相続人が現れると、事業継続が困難になります。また、前述の通り、経営者の口座が凍結され、事業が一時的にストップするリスクもあります。
方法③:売買(M&A・事業譲渡)による第三者承継
これは、親族や従業員の中に適切な後継者が見つからない場合に、外部の第三者(他の個人や法人)に事業を有償で譲渡(売買)する方法です。一般的に「M&A」や「事業譲渡」と呼ばれます。
【メリット】
売り手(経営者)にとっては、事業用資産の売却によって、まとまった譲渡対価(引退後の生活資金や、新規事業の資金)を得られることが大きなメリットです。後継者不在による廃業を避け、従業員の雇用や取引先との関係を守ることにも繋がります。買い手(後継者)にとっては、すでに顧客やノウハウがある事業を引き継ぐため、ゼロから事業を立ち上げるよりも低リスクで新規事業に参入できるメリットがあります。
【デメリット(注意点)】
当然ながら、事業を買いたいという買い手(相手)を見つける必要があります。
また、前述の「違い①~③」で説明した通り、資産・負債の個別承継や、契約の全面的な巻き直し、許認可の新規取得など、3つの方法の中で手続きが最も複雑になります。


【方法別】事業承継にかかる税金と節税対策

どの承継方法を選ぶかによって、誰が・いつ・どの税金を納めるかが全く異なります。
特に個人事業主の場合、資産が個人に帰属しているため、税負担が承継の成否を分ける重要な問題となります。
贈与・相続で活用できる節税・猶予制度
生前贈与の場合は「贈与税」、相続の場合は「相続税」が、原則として資産を引き継いだ後継者に課税されます。これらの負担を軽減・回避するために、いくつかの制度が利用されます。
代表的なものとして、まず「暦年贈与」があります。これは、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからないという基礎控除の枠です。
ただし、事業用資産(不動産や機械など)は高額なことが多く、この枠だけで事業全体を引き継ぐのは現実的に困難です。
次に「相続時精算課税制度」という制度もあります。
これは、原則として60歳以上の親(または祖父母)から18歳以上の子(または孫)への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。ただし、名前の通り、相続が発生した時にはこの贈与財産も相続財産に加算して相続税が再計算されるため、相続税の節税にはなりにくい点に注意が必要です。
また、相続の際に非常に強力な節税策となるのが「小規模宅地等の特例(相続時)」です。
これは、経営者が事業用に使っていた宅地を事業承継する後継者が相続した場合、一定の要件のもとで土地の評価額を最大80%減額できる制度です。これにより相続税額を大幅に圧縮できる可能性があります。
個人版事業承継税制(贈与税・相続税の猶予・免除)
上記のような従来の制度だけでは、税負担が重く個人事業主の事業承継が進みにくいケースもあるため、その支援策として設けられたのが個人版事業承継税制です。
これは、2019年(平成31年)から2028年(令和10年)までの10年間の特例措置として創設されました。一定の要件を満たす後継者が、贈与または相続によって「特定事業用資産」(事業用の宅地、建物、機械、器具備品など)を取得した場合、その資産にかかる贈与税または相続税の全額の納税が「猶予」されます。
さらに、後継者が死亡するなどの一定の事由が発生した場合、猶予されていた税額が全額「免除」されます。条件を満たせば、実質的に税負担を抑えた形で事業用資産を引き継ぐことも可能になる制度です。
ただし、適用を受けるには、事前に都道府県へ「承継計画」を提出して確認を受けるなど、要件が非常に厳格かつ複雑であるため、税理士などの専門家への相談が必須です。
M&A(事業譲渡)でかかる税金(所得税・消費税)
M&A(事業譲渡)によって第三者に事業を売却した場合、売却益に対する所得税などは売り手である現経営者が負担します。一方で、買い手側にも不動産取得税や登録免許税などが発生する場合がある点には注意が必要です。
主に課税されるのは「所得税(譲渡所得)」と「消費税」です。「所得税(譲渡所得)」については、事業用資産の売却によって得た利益(=譲渡価額 − (資産の取得費+売却経費))に対して、「譲渡所得」として所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。この利益は、給与など他の所得とは分離して計算されます(一部例外あり)。
「消費税」については、売り手(現経営者)が消費税の課税事業者である場合、売却する資産のうち「課税資産」に対して消費税が発生します。課税資産の例としては建物、機械、車両、営業権(のれん代)、在庫商品などが挙げられますが、土地は非課税です。この消費税は、買い手から売買代金と合わせて預かり、売り手が後日、税務署に申告・納付します。
また、買い手側にも不動産取得税や登録免許税などが発生することがあるため、事前に専門家へ相談しておくことが望ましいです。


事業承継で売り手が行う手続き

個人事業主が事業を譲渡するには、廃業届を提出して『廃業』にした後、後継者に『開業手続き』を進めてもらう流れになります。
廃業届、青色申告の取りやめ届出書等の提出
事業を引き継ぐにあたり、現在の事業主は管轄の税務署に以下の書類を提出する必要があります。
- 廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告者のみ)
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
- 事業廃止届出書(消費税の課税事業者のみ)
廃業届の提出期限は、事業譲渡の確定後1カ月以内とされています。
国税庁のHPから『個人事業の開業・廃業等届出書』をダウンロードし、廃業に関する内容を記載し、提出しましょう。
業績不振や廃業の理由で申告納税見積額が払えないと見込まれる際は、『所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書』を提出します。
参考:[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁
個人版事業承継税制は利用できる?
個人版事業承継税制とは、一定の要件を満たした場合に贈与税・相続税の納税が猶予され、将来的に免除されることもある制度です。
具体的には、先代が2代目に事業を承継し、のちに2代目が3代目に事業を承継させた場合、2代目が支払うはずの贈与税や相続税が免除されます。
2019年1月1日から2028年12月31日までに行われる相続や贈与が対象で、事前に承継計画書を提出することが必要です。
個人版事業承継税制はあくまでも贈与・相続に対する優遇措置です。M&Aによる売却は対象ではありません。


事業承継で買い手が行う手続き

事業譲渡に伴う手続きは、一般に売り手よりも買い手の方が複雑になる傾向があります 。
特に『許認可』の取得手続きは時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。許認可が得られず、予定通りに事業をスタートできなかったという事態は避けたいものです。
開業届、青色申告承認申請書等の提出
事業を引き継いだ側は、所轄の税務署に『開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)』を提出します。提出期限は、事業譲渡が行われてから1カ月以内です。
青色申告をする場合は『青色申告承認申請書』を忘れずに提出しましょう。
提出を忘れると自動的に白色申告となり、以下のメリットを享受できません。
- 最大65万円の青色申告特別控除
- 純損失の繰り越し(事業から生じた純損失を翌年以後3年間にわたって所得金額から差し引ける)
- 純損失の繰り戻し(前年も青色申告の場合、純損失が生じた年分を前年度の所得金額に繰り戻せば、所得税額の還付が受けられる)
- 青色事業専従者給与(事業にかかわる家族への報酬を青色申告者の所得から控除できる)
- 貸倒引当金の計上(金銭債権に対して一定率を貸倒引当金繰入として必要経費に計上できる)
屋号はそのまま使える?
前経営者が使用していた屋号をそのまま引き継ぐことは、一般的には可能です。開業届の屋号欄に同じ屋号を記入して提出しましょう。
ただし、元事業主が屋号を『商号登記』していた場合、同一所在地で同一商号が使えない可能性があります(商業登記法第27条)。
屋号の引き継ぎについて元事業主と合意した上で、必要に応じて法務局で商号の変更手続きなどを行いましょう。
従業員や取引先と再契約
事業譲渡で従業員や取引先を引き継ぐ場合、個別に再契約の手続きを行います。取引先については、売り手と買い手の代表者が一緒に取引先を訪問し、事業譲渡の経緯を話します。事情を理解してもらった上で再契約を進めましょう。
従業員の待遇や労働条件は、従来通りに引き継ぐのが一般的です。事業譲渡で労働条件が悪化すれば、大量離職につながりかねません。雇用保険や労災保険の手続きも忘れずに済ませましょう。
飲食店や建設業などは許認可の取得
事業承継では、許認可が引き継がれません。『許認可』とは、事業を行うために行政機関(警察署・保健所・都道府県など)から取得する許可を指します。
許認可なしではビジネスが継続できないため、事業に必要な許認可を洗い出し、取得手続きを遅滞なく済ませましょう。
例えば飲食店であれば『飲食店営業許可』、アンティークを扱うリサイクルショップの場合は『古物商許可』を取得しなければなりません。建設業・クリーニング業・酒小売業・旅館業・理美容業などにおいても許認可が必要です。


個人事業主の事業承継でよくある質問

個人事業主の事業承継は、法人と比べて手続きが複雑なため、多くの疑問が生じやすいポイントです。
ここでは、特に多く寄せられる質問と、それに対する基本的な回答をご紹介します。
Q. 借金(負債)や経営者の個人保証も後継者に引き継がれますか?
A. 借金(負債)や経営者個人の保証がどの程度後継者に引き継がれるかは、事業承継の方法によって大きく異なります。
相続による承継の場合、事業主の財産を包括的に承継するため、負債も後継者に引き継がれます。
事業譲渡・法人成りの場合、借入金は「現事業主個人の債務」のため、自動的に後継者へ移るわけではありません。債務を引き継ぐためには、金融機関の同意や債務引受契約などが必要になります。
ただし、もし負債を引き継がなければ、金融機関や取引先との関係が維持できず、実務上は、金融機関や取引先との関係を維持するために、負債も含めて引き継ぐケースが多く見られます。
また、経営者が金融機関からの融資に際して「個人保証(連帯保証)」をしている場合、事業を引き継ぐ後継者が新たに連帯保証人になることを金融機関から求められるケースが多く見られます。
Q. 事業承継を機に「法人化(法人成り)」するメリットは何ですか?
A. 主に「信用の向上」と「将来の事業承継の容易化」という2つのメリットがあります。
個人事業主のまま事業承継するのではなく、承継のタイミングで「法人成り(会社を設立し、その会社が個人事業を引き継ぐこと)」を選択するケースも非常に多いです。
一つ目の「信用の向上」とは、「個人」よりも「法人(会社)」になることで社会的信用が高まり、金融機関からの融資が受けやすくなったり、大手企業との取引がしやすくなったりするメリットを指します。
二つ目の「将来の事業承継の容易化」は、最大のメリットかもしれません。
一度法人化してしまえば、事業の資産や契約はすべて「会社」のものになります。そのため、次の世代(今回承継した後継者から、さらにその次の後継者へ)に引き継ぐ際は、「株式」を渡すだけで済むようになります。個人事業主の承継のように、資産を個別に移転したり、契約をすべて巻き直したりする必要がなくなり、将来の承継が格段にスムーズになります。
Q. 従業員との雇用契約や、取引先との契約はどうなりますか?
A. すべて「再契約」が必要です。
これは個人事業主の承継における非常に重要なポイントです。
前述の通り、個人事業主の場合、すべての契約は「経営者個人」が当事者です。
事業承継によって経営者が変わる(=契約の当事者が変わる)ため、後継者は従業員全員と「雇用契約」を、主要な取引先、仕入先、店舗の家主(大家)などと「取引基本契約」や「賃貸借契約」を、原則として一から結び直す必要があります。
この際、相手方が「後継者とは契約条件を見直したい」と言い出したり、最悪の場合「再契約に同意してくれない」というリスクもゼロではありません。
Q. 飲食業や建設業などの「許認可」はそのまま引き継げますか?
A. いいえ、引き継げません。後継者による「新規取得」が原則です。
これも非常に重要なポイントです。
許認可は経営者個人や事業所の設備などを前提として与えられているため、原則として後継者に名義変更で承継することはできません。
後継者は、自身の名前であらためて許認可を申請し、新規に取得する必要があります。許認可の種類によっては、取得に時間がかかることも想定しておきましょう。
例えば、飲食店の承継であれば、後継者が保健所に新規で営業許可を申請します。その際、店舗が最新の施設基準を満たしているかどうかが改めて審査されます。この新規取得には時間がかかるため、許認可が下りるまでの間、営業ができない期間(空白期間)が発生しないよう、専門家(行政書士など)と相談しながら綿密にスケジュールを組む必要があります。
Q. 屋号(店の名前)は後継者がそのまま使えますか?
A. はい、基本的には使えます。
屋号(例:「〇〇商店」「カフェ・〇〇」など)は、法律上、特許権や商標権のような強力な独占権ではありません。
後継者が税務署に開業届を提出する際に、同じ屋号を記載して事業を開始することは、基本的には自由です。長年親しまれてきた屋号(ブランド)をそのまま使えることは、事業承継の大きなメリットの一つです。
ただし、前経営者がその屋号を法務局で「商号登記」していたり、特許庁で「商標登録」していたりする場合は、法的な権利が関わってきます。
その場合は、トラブルを避けるために、後継者がその屋号を使用することについて、前経営者との間で合意書などを交わしておくことが望ましいです。
まとめ
小規模事業者や個人事業主の事業承継では、事業譲渡のスキームが用いられるケースが増えています。近年は、身内以外に事業を引き継ぐ『親族外承継』が一般的になっており、マッチングの方法が多様化しています。
事業主が変わったことで取引先との契約条件が見直されたり、従業員が離職したりするケースも少なくありません。事業譲渡を円滑に完了させるため、売り手と買い手は協力して手続きを進めましょう。
事業承継・M&Aプラットフォーム『TRANBI(トランビ)』には、数億円規模の大型案件から500万円以下の小規模案件まで多数掲載されています。『事業承継・引継ぎセンターの最新案件情報』もサイト内でチェックできるため、効率よく案件が探せるでしょう。








