
M&Aの買い手の目的は?メリット・デメリットと流れを徹底解説!
自社の成長戦略としてM&Aの成功の鍵は、目的を明確にし、相乗効果が見込める相手を選び、手順に沿って着実に進めることです。M&Aにおける買い手の主な目的等を明確にし、M成長を加速させる具体的な第一歩を踏み出しましょう。
自社の成長戦略としてM&Aを検討しているが、買い手として何から始め、何に注意を払うべきか迷っていませんか。
成功の鍵は、目的を明確にし、相乗効果が見込める相手を選び、手順に沿って着実に進めることです。
本記事では、M&Aにおける買い手の主な目的、メリット・デメリット、選定ポイント、手法とプロセス、費用や税金の問題まで解説します。
最後までお読みいただくことで、M&A成功の道筋が明確になり、成長を加速させる具体的な第一歩を踏み出せるでしょう。
まずはM&Aの全体像を正確に把握し、自社にとって最適な戦略を構築するための確かな土台として本記事をご活用ください。


買い手がM&Aを行う主な目的

企業が買い手としてM&Aを行う背景には、多様な経営戦略上の目的が存在します。
規模拡大だけでなく、多角化、競争力強化、イノベーション促進など目的は多様です。
ここでは、買い手がM&Aを通じて達成しようとする主な目的を5つの観点から解説します。
① 市場シェアの拡大
既存事業と同じ、あるいは類似する事業を展開する企業を買収することで、市場における自社のシェアを迅速に拡大できます。
これにより競合を吸収し価格競争を回避、発言力や価格競争力を高め、スケールメリットによるコスト削減も期待できます。
② 事業領域の拡大
自社の既存事業と関連性の高い事業を持つ企業を買収することで、相手企業が持つ顧客基盤や販路、ブランドといった経営資源をまとめて獲得し、新たな製品ラインナップやサービスを加え、事業領域を広げることが可能です。
これにより包括的なソリューション提供が可能となり、顧客単価向上や新収益源の確保につながります。
③ 新規事業への参入
ゼロから新規事業を始めるには、時間やコスト、知識が必要ですが、M&Aなら既に基盤を持つ企業を取得して短期間で参入できます。
④ 人材や技術の獲得
M&Aは、設備や顧客基盤だけでなく、優秀な人材や独自の技術、特許、ノウハウといった無形の経営資源を獲得するための有効な手段でもあります。
変化の速い市場では、人材や先進技術の獲得が競争力維持・向上に不可欠です。
⑤ 業務の効率化とコスト削減
重複する管理部門(総務、経理など)の統合や、仕入れ・製造・物流網の共通化によって、業務プロセス全体の効率化とコスト削減を実現できます。
浮いた経営資源を、新たな成長分野へ再投資できます。

M&Aの買い手側の注意点

M&A成功には、買い手側が注意すべき点があります。
潜在的リスクを事前に把握し、対策を講じることが重要です。ここでは、買い手側が特に注意すべき5つのポイントについて解説します。
注意点①:簿外債務や偶発債務の継承リスク
買収対象企業の貸借対照表に記載されていない債務(簿外債務)や、将来発生の可能性がある債務(偶発債務、例:訴訟リスクなど)を引き継ぐ恐れがあります。
事前のデューデリジェンス(買収監査)で、これらのリスクを徹底的に洗い出すことが重要です。
注意点②:許認可の引き継ぎができない恐れ
建設業や運送業など、事業運営に特定の許認可が必要な業種の場合、M&Aの手法によっては許認可が引き継がれず失効する可能性があります。
事業継続に支障が出ないよう、法的な手続きを事前に確認しておく必要があります。
注意点③:シナジー効果が発揮されない可能性
期待していたほどのシナジー効果が得られないケースは少なくありません。
計画段階での見込みが楽観的すぎたり、統合後のプロセス(PMI)がうまくいかなかったりすることが主な原因です。結果的に買収が期待外れの投資となる恐れがあります。
注意点④:買収費用が利益を上回るリスク
M&Aには、買収対価だけでなく、仲介手数料やデューデリジェンス費用などの付随費用も発生します。
これらの投資額が、M&Aによって得られる将来の利益を上回ってしまう「のれんの減損」リスクも考慮に入れる必要があります。
注意点⑤:従業員の不満や離職が起きやすい
経営方針の変更や待遇の違い、組織文化の衝突などから、買収された企業の従業員が不満や不安を抱き、モチベーションが低下したり、最悪の場合、キーパーソンが離職する恐れがあります。
丁寧なコミュニケーションを通じて、従業員の不安を払拭する努力が不可欠です。


M&Aの買い手の買収先企業の選定ポイント

M&Aの成功は、どの企業を買収するかに大きく左右されます。
自社戦略と合致し、円滑な統合が見込める相手を見極めることが重要です。ここでは、買い手が買収先企業を選定する際に重視すべき5つのポイントを解説します。
① 自社と相乗効果があるか
買収によって、1+1が2以上になる「シナジー効果」が期待できるかどうかが最も重要な選定ポイントです。
販売網の相互活用、技術の組み合わせによる新製品開発、ブランドイメージの向上など、どのような相乗効果が見込めるかを具体的に検討します。
② 財務基盤が安定しているか
買収対象企業の財務状況を分析し、健全なキャッシュフローや安定収益があるか確認することが重要です。
簿外債務や偶発債務など、潜在的な財務リスクがないかもしっかりと調査する必要があります。
③ 成長戦略が一致しているか
自社が描く将来のビジョンや成長戦略と、相手企業の方向性が一致しているかどうかも重要なポイントです。
戦略が異なると、統合後に経営方針で対立し、シナジー効果が発揮されない可能性があります。
④ 組織文化が近いか
組織文化や従業員の価値観が大きく異なる企業同士が統合すると、従業員の間に摩擦や反発が生まれ、生産性低下や人材流出の恐れがあります。
トップ面談などを通じて、相手企業の組織風土を事前に理解し、自社との親和性を確かめることが望ましいです。
⑤ 意思決定が迅速か
M&Aの交渉プロセスは複雑で、多くの時間を要することがあります。
相手企業の経営陣がM&Aに対して前向きであり、意思決定のプロセスが明確で迅速であることは、交渉を円滑に進めるために重要です。


買い手から見たM&Aの種類と特徴

M&Aには多様な手法があり、それぞれ法的手続きや買い手・売り手への影響が異なります。
手法の選択は、買収目的や対象企業の状況に応じて慎重に判断します。ここでは、代表的なM&Aの種類とその特徴を解説します。
株式譲渡
売り手企業の株主が保有する株式を、買い手企業が買い取ることで経営権を取得する最も一般的な手法です。
手続きが比較的簡便で、会社を丸ごと引き継ぐため、許認可や従業員の雇用契約も原則そのまま維持されます。ただし、簿外債務などの潜在的リスクも全て引き継ぐことになります。
株式取得(新株引受)
売り手企業が新たに発行する株式(新株)を買い手が引き受ける手法です。
買収資金が売り手企業に直接入るため、相手企業の財務強化や事業投資を目的とする場合に活用されます。既存株主の持株比率が下がる点が特徴です。
事業譲渡
売り手企業の事業の一部または全部を、買い手企業が譲り受ける手法です。
買い手は必要な資産や負債を選んで引き継ぐため、簿外債務などのリスクを限定できます。ただし、資産や契約の移転手続きが煩雑になる場合があります。
合併
複数の会社が法的に一つの会社に統合される手法です。
全ての権利義務が包括的に承継されるため、シナジー効果を早期に発揮しやすいメリットがあります。反面、手続きが複雑で統合後の組織運営に時間と労力がかかる場合があります。
会社分割
売り手企業が事業の一部を分割して新しい会社を設立し、その新会社の株式を買い手が取得する、あるいは既存の買い手企業に事業を承継させる手法です。
事業譲渡と似ていますが、税務上の取り扱いは異なります。
株式交換
買い手企業が売り手企業を完全子会社化する際に用いられる手法です。
売り手企業の株主は、保有株式を買い手企業の株式と交換します。対価を現金ではなく自社株で支払えるため、多額の資金を用意せずに済む場合があります。
株式移転
複数の企業が共同で新しい親会社を設立し、その傘下に入る手法です。
経営統合やホールディングス体制への移行を目的として利用されます。各社は法人格を維持したまま、グループ一体での経営を目指します。




買い手側のM&Aの方法と流れ
M&Aは、候補先の選定から最終統合まで複数の段階を経て進みます。
各段階で適切な判断と手続きを行うことが、M&Aを成功に導く鍵となります。ここでは、買い手側の視点から見た一般的なM&Aの流れを解説します。
手順①:対象企業のリストアップと調査
まず、M&Aの目的を明確にし、目的に合う候補企業をリストアップします。
M&A仲介会社、地域金融機関、税理士等の紹介やオンラインのM&Aプラットフォームを活用するのが効率的です。特に、国内最大級のM&Aプラットフォームである「トランビ(TRANBI)」は、買い手にとって強力なツールとなり得ます。
トランビには、後継者を探す中小企業からスタートアップまで、多様な業種・事業規模の売り手案件が常時数千件登録されています。買い手は無料登録でき、匿名で案件を検索できます。
興味のある案件を見つけた場合、プラットフォーム上で直接売り手にアプローチし、交渉を開始できる点が大きな特徴です。
これにより、仲介者を介さず、迅速かつ柔軟な交渉ができ、独自案件を見つける機会も広がります。
手順②:秘密保持契約の締結
関心企業が見つかったら、詳細情報を得るため秘密保持契約(NDA)を締結します。
これにより、相手企業の財務情報など、外部に公開されていない機密情報を入手できるようになります。
手順③:トップ面談と意向表明書の提出
売り手企業の経営者と直接面談し、経営方針やビジョン、売却理由などをヒアリングします。
双方の意向が固まったら、買収価格やスケジュールなど基本条件を記載した意向表明書(LOI)を提出します。
手順④:デューデリジェンスの実施
基本合意に先立ち、公認会計士や弁護士などの専門家チームを編成し、買収対象企業の財務、法務、税務、事業内容などを詳細に調査する「デューデリジェンス(買収監査)」を実施します。
この調査で、潜在リスクや問題点を洗い出します。
手順⑤:基本合意書の締結
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終契約に向けた基本的な条件について双方で合意し、基本合意書(MOU)を締結します。
この時点では法的な拘束力を持たないことが多いですが、独占交渉権などを盛り込むのが一般的です。
手順⑥:最終契約の締結と条件調整
基本合意の内容を基に、より詳細な条件交渉を行い、最終的な契約内容を詰めていきます。
全条件に合意したら、株式譲渡契約書(SPA)や事業譲渡契約書など最終契約を結びます。
手順⑦:クロージング(資金・株式の移動)
最終契約書に定められた条件に従い、買い手から売り手へ買収対価の支払いと、売り手から買い手へ株式や事業の移転を行います。
このクロージングをもって、M&Aの取引は完了となります。
手順⑧:PMI計画の策定
PMI(Post Merger Integration)は、M&A成立後の統合プロセスです。
クロージング前から、経営方針、業務プロセス、組織体制、人事制度などをどのように統合していくかの具体的な計画を策定しておくことが重要です。
手順⑨:PMI実行と成果モニタリング
クロージング後、策定したPMI計画を実行に移します。
統合進捗やシナジー効果を定期的に確認し、必要に応じて計画を修正して成果を最大化します。






M&Aで買い手にかかる費用・税金
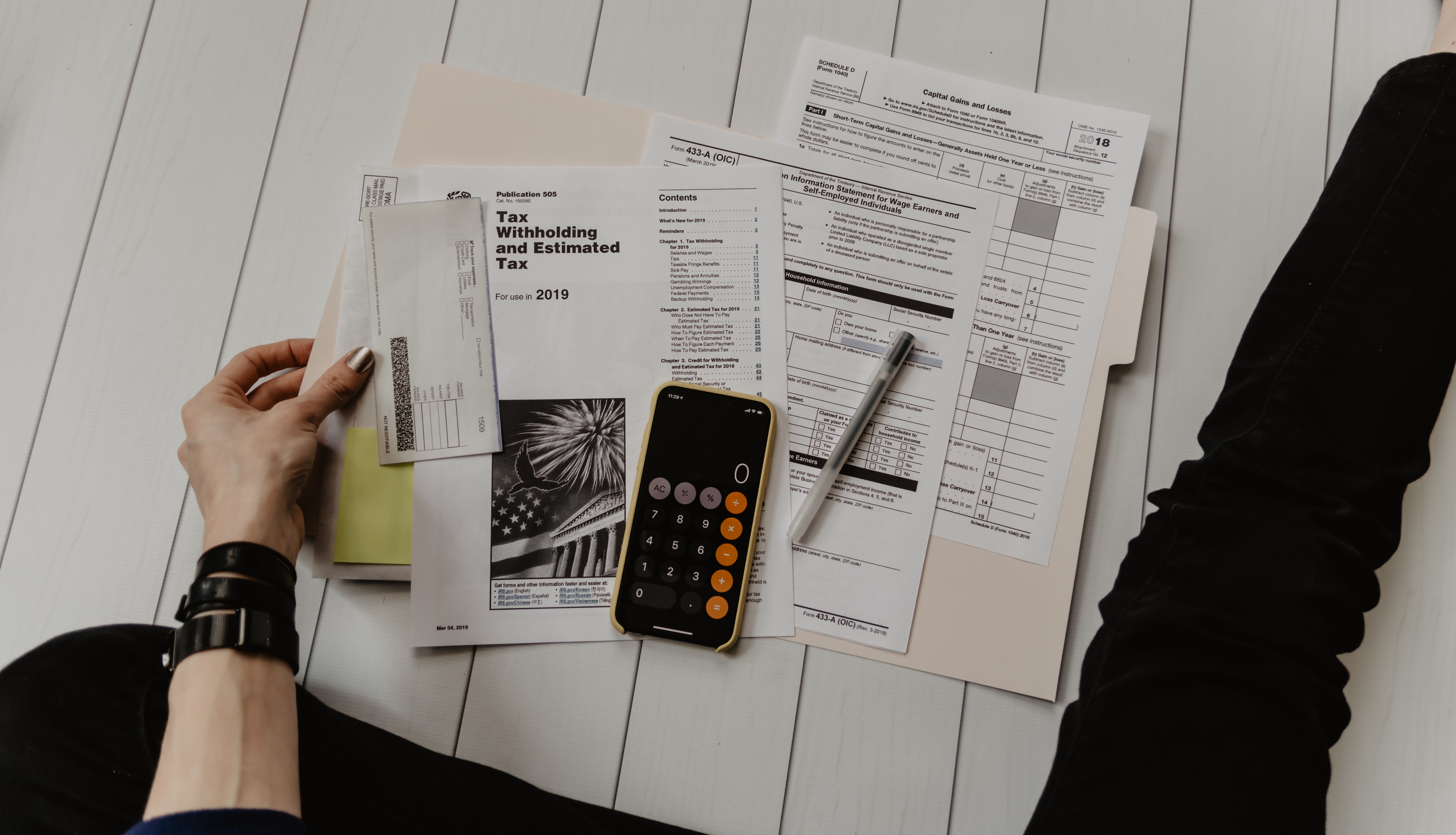
M&Aでは、買収価格以外にも多くの付随費用や税金が発生します。
資金計画のために、これらのコストを正確に把握することが重要です。ここでは、買い手にかかる費用や税金、そして活用できる制度について解説します。
M&Aで買い手にかかる費用の種類と相場
M&Aでは、専門家の協力が必要で、それに伴う手数料が発生します。
- 着手金:M&A仲介会社やアドバイザーとの契約時に支払う初期費用です。無料の場合もありますが、数十万~数百万円が相場です。
- 中間報酬:基本合意書の締結など、プロセスが一定段階に進んだ際に支払う報酬です。成功報酬の一部として扱われることもあります。
- 成功報酬:M&Aが成約時に支払う成果報酬で、最も大きな費用です。レーマン方式と呼ばれる、取引金額に応じた料率で計算されるのが一般的です。
- デューデリジェンス費用: 財務や法務の調査を専門家に依頼するための費用で、調査範囲によっては、数十万~数百万円以上かかります。
- 専門家報酬:上記以外にも、契約書の作成を依頼する弁護士や、税務処理を依頼する税理士への報酬が必要になることがあります。
M&Aで買い手にかかる税金
M&Aの手法によっては、買い手に税金が課されます。
- 消費税:事業譲渡の手法でM&Aを行う場合、譲渡される資産のうち課税資産(建物、機械、のれん等)に対して消費税が課されます。
- 不動産取得税:譲渡資産に不動産が含まれる場合、買い手には不動産取得税が課されます。
- 登録免許税:不動産の所有権移転登記を行う際に、登録免許税が必要となります。
- 印紙税:M&Aの最終契約書など、課税文書を作成する際には、契約金額に応じた印紙税が課されます。


M&Aで買い手が活用できる補助金や税制優遇
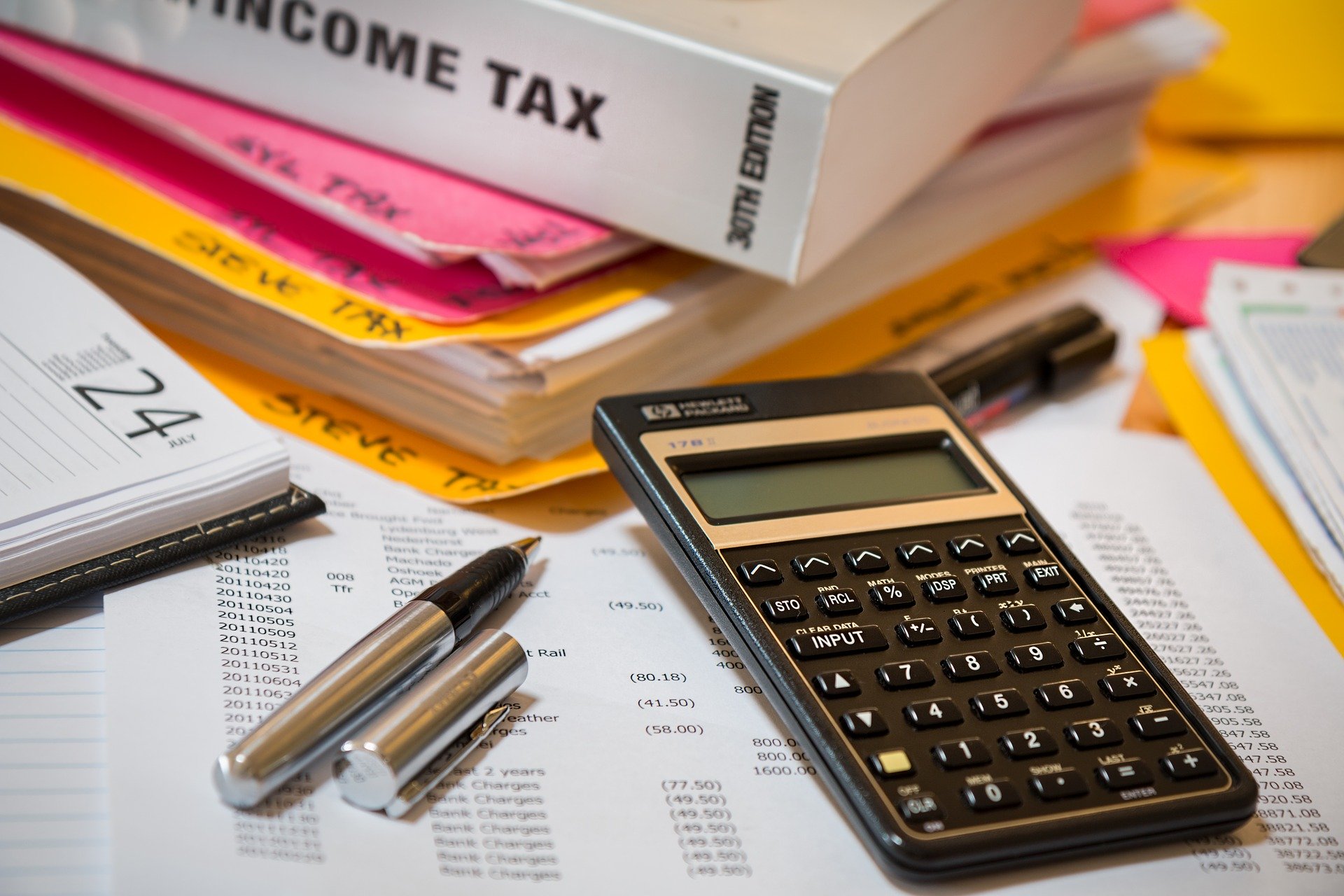
M&Aにかかる費用負担を軽減し、投資効果を最大化するためには、国や地方自治体が提供する補助金や税制優遇制度を活用することが重要です。
補助金
代表的なものに「事業承継・引継ぎ補助金」があり、M&Aにかかる専門家費用やデューデリジェンス費用、PMI(統合プロセス)費用の一部が補助される場合があります。
公募要領を確認し、自社が対象か検討する価値があります。
税制優遇制度
M&Aに関連する税制優遇をうまく活用することで、実質的な買収コストを抑えることが可能です。
代表例は、M&Aで生じた「のれん」の償却や、被買収企業の繰越欠損金の引継ぎによる節税効果です。
また、M&A後の設備投資や賃上げに対して適用される税制優遇もあります。
これらの制度は要件が複雑なため、活用を検討する際は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。


まとめ|自社に最適なM&Aを実現しよう!
本記事では、M&Aを検討する買い手の視点から、その目的、メリット・デメリット、成功のためのプロセスや注意点を網羅的に解説しました。
M&Aは、事業成長の時間を短縮し、新たな市場や技術を獲得するための極めて有効な経営戦略です。しかしその一方で、多額の資金を要し、簿外債務の継承や組織文化の衝突といった様々なリスクも内包しています。
M&Aを成功に導くためには、まず自社が「何のためにM&Aを行うのか」という目的を明確にすることが出発点となります。
その上で、自社の戦略に合致し、かつ財務や組織文化の面で親和性の高いパートナーを慎重に見極めなければなりません。
そして、デューデリジェンスによる徹底したリスクの洗い出しと、PMIによる周到な統合計画が、期待したシナジー効果を実現する上で不可欠です。
M&Aは簡単ではありませんが、正しい知識と手順、専門家の支援を得て戦略的に進めれば、企業成長を実現する強力な手段となります。








