
M&Aの税金は?スキーム別節税術と最新改正ポイントを徹底解説
M&Aの税金は、用いるスキームや売り手・買い手といった立場によって大きく異なりますが、その仕組みを正しく理解すれば、適切な対策を講じることが可能です。M&Aに関わる税金の基本から、売り手・買い手それぞれの具体的な税務、最新の税制改正、そしてすぐに実践できる節税策まで、専門的な内容を分かりやすく網羅的に解説します。
- 05 M&Aの税金対策・節税ポイント|売り手向け
- 節税方法①:役員退職金で課税所得を減らす
- 節税方法②:仲介手数料などの譲渡費用を漏れなく計上する
- 節税方法③:株式取得費加算特例を活用する
- 節税方法④:繰越欠損金を活用する
- 節税方法⑤:組織再編スキームで税率を調整
- 節税方法⑥:暦年贈与を活用して株式を移転する
- 06 M&Aの税金対策・節税ポイント|買い手向け
- 節税方法①:のれんや営業権を償却して節税
- 節税方法②:支払利息を損金に算入する
- 節税方法③:買収費用を損金として計上する
- 節税方法④:再編スキームで課税繰延を活用
- 節税方法⑤:繰越欠損金を引き継いで活用する
- 07 M&Aの税金対策における注意点
- 注意点①:節税目的のM&Aは否認リスク
- 注意点②:過大な職務対価は損金不算入の恐れ
- 注意点③:非適格分割で重課税の可能性
- 注意点④:特例適用に要件確認が必要
- 注意点⑤:税務調査対策は事前準備が重要


M&Aを検討する中で、「どの税金が、いつ、誰に、どれくらいかかるのか?」という複雑さに悩んでいませんか。
M&Aの税金は、用いるスキームや売り手・買い手といった立場によって大きく異なりますが、その仕組みを正しく理解すれば、適切な対策を講じることが可能です。
この記事では、M&Aに関わる税金の基本から、売り手・買い手それぞれの具体的な税務、最新の税制改正、そしてすぐに実践できる節税策まで、専門的な内容を分かりやすく網羅的に解説します。
本記事を最後までお読みいただくことで、自社が取るべき最適なM&A戦略と、それに伴う税金対策を明確に描けるようになるでしょう。
まずはM&Aの税務の全体像を掴み、貴社の未来を切り拓く経営戦略の一手としてお役立てください。
M&Aにかかる主な税金の種類

M&Aのプロセスでは、様々な種類の税金が発生します。代表的なものには、個人利益に課される「所得税」、法人利益に課される「法人税」、そして「消費税」があります。
さらに、不動産の移転が伴う場合には「登録免許税」や「不動産取得税」も関わってきます。これらの税金は、株式譲渡や事業譲渡などのM&Aのスキームによって、課税対象(売り手か買い手)や税率が大きく異なります。
また、売り手が個人か法人かによっても、適用される税制が異なるため、M&Aを検討する初期段階で、自社の状況と選択するスキームが税務にどのような影響を与えるかを理解しておくことが、経営戦略上、非常に重要です。


M&A税務に関する最新の税制改正と優遇措置(2025年最新対応)
M&Aに関連する税制は、経済状況や政策の方向性に応じて毎年見直されています。特に近年は、中小企業の事業承継やスタートアップの成長を後押しするための税制優遇措置が積極的に導入されています。
例えば、事業承継税制では、一定の要件を満たせば贈与税や相続税が猶予または免除される制度があります。一方で、これまでの優遇措置が縮小・終了することもあるため、常に最新の情報をキャッチアップすることが不可欠です。
2025年度の税制改正においても、M&Aを促進するための新たな措置が検討されています。これらの改正は、納税額に直接影響を与えるだけでなく、M&Aのスキーム選定そのものを左右する可能性もあります。特例の適用要件や期限を正確に把握し、税務上のリスクを避けつつメリットを最大限活用する戦略が必要です。

M&Aでかかる税金・税務の詳細と計算方法|売り手向け
M&Aの売り手側にかかる税金は、選択するスキームによって大きく異なります。ここでは、代表的なスキームである「株式譲渡」「事業譲渡」「不動産売却」「合併・分割」の4つのケースに分けて、それぞれ発生する税金の詳細と計算方法を解説します。
① 株式譲渡で発生する税金
株式譲渡は、会社のオーナーが保有株式を買い手に売却する一般的なM&Aの手法です。この際、売り手である株主が個人か法人かによって、課される税金が異なります。
個人株主の場合、株式の譲渡によって得た利益(譲渡所得)に対して、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%を合わせて約20.315%の申告分離課税が適用されます。
一方、法人株主の場合は、株式の譲渡益は他の事業利益と合算され、法人税(実効税率約29.74%)の課税対象です。譲渡所得は「売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)」で計算され、取得費をどのように証明するかが税額を左右する重要なポイントです。
② 事業譲渡時の法人税と消費税
事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を買い手に売却する手法です。この場合、売り手企業には、事業の売却によって得た利益(譲渡益)に対して法人税が課されます。
譲渡益は、売却価格から譲渡対象となる資産の簿価を差し引いて計算されます。また、事業譲渡では、土地を除く有形・無形固定資産(のれん代など)、棚卸資産が消費税の課税対象です。
売り手企業は、買い手から消費税を預かり、国に納税する義務があります。なお、インボイス制度導入後は、買い手が仕入税額控除を受けるために、売り手に適格請求書(インボイス)の発行を求めるのが一般的です。課税売上高1,000万円以下の免税事業者であっても、インボイスを発行するためには課税事業者になる必要があり、結果として消費税の納税義務が発生する場合が多いため注意が必要です。
③ 不動産売却に伴う税金
M&Aのプロセスにおいて、会社が所有する不動産を売却するケースもあります。この場合、不動産の売却益に対して法人税が課されるのは他の資産と同様です。
加えて、不動産の所有権移転登記を行う際には、買い手側が「登録免許税」と「不動産取得税」を負担するのが一般的ですが、契約内容によっては売り手が負担する場合もあります。
特に注意すべきは、売却する不動産の所有期間です。法人は所有期間による税率変動はありませんが、個人は5年超かどうかで税率が大きく変わるため、売却時期の検討が重要です。
④ 組織再編(合併・分割・株式交換など)における税務
合併や会社分割、株式交換といった組織再編スキームを用いる場合、税務の取り扱いはより複雑になります。これらのスキームが税制上の「適格要件」を満たす「適格組織再編」に該当する場合、資産の移転は簿価で行われ、譲渡損益の認識が繰り延べられるため、原則として課税は発生しません。
これにより、売り手側は多額の税負担をせずに事業の再編や売却を行うことが可能になります。しかし、適格要件を満たさない「非適格組織再編」と判断された場合は、資産や株式の移転は時価で行われ、含み益に対して法人税や所得税が課されることになります。
適格要件は、当事者間の支配関係や事業継続性など、厳格に定められているため、専門家と慎重に検討する必要があります。

M&Aでかかる税金・税務の詳細と計算方法|買い手向け
M&Aの買い手側においても、選択するスキームに応じて様々な税務上の考慮事項が存在します。ここでは、株式取得、事業譲渡、不動産取得、そして株式交換といった代表的なケースにおける買い手側の税務について解説します。
① 株式取得時の税務と非課税条件
買い手が株式を取得して会社を子会社化する場合、その株式の取得自体には原則として税金はかかりません。消費税の対象外であり、不動産取得税なども発生しないためです。
ただし、買い手が非上場株式を個人から取得する場合、取引価額の妥当性に税務上の問題が生じることがあります。時価より大幅に低い価額で取得した場合、その差額が贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります。
② 事業譲渡での資産取得税負担
事業譲渡において、買い手は売り手に対して資産の対価を支払います。この際、譲渡対象資産に課税資産(建物、機械、のれんなど)が含まれている場合、買い手はその対価に含まれる消費税を支払う必要があります。
支払った消費税は、課税売上の消費税から控除(仕入税額控除)できますが、一時的にキャッシュアウトフローが発生します。
また、事業譲渡によって取得した「のれん(営業権)」は、税務上5年間で均等に償却することができ、償却費を損金として計上することで法人税の負担を軽減する効果があります。これは、事業譲渡を買い手側が選択する大きなメリットの一つです。
③ 不動産取得時の税金
M&Aに伴い不動産を取得した場合、買い手には「不動産取得税」と「登録免許税」が課されます。不動産取得税は、不動産の取得という事実に対して一度だけ課される地方税で、税額は固定資産税評価額に一定の税率を乗じて計算されます。
登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行う際に課される国税です。こちらも固定資産税評価額を基準に税額が決定されます。
これらの税金は、M&Aの取引金額そのものではなく、公的な評価額に基づいて計算される点が特徴です。不動産の評価額を事前に把握し、納税資金を準備しておくことが重要です。
④ 株式交換や移転時の買収税務
株式交換や株式移転は、買い手が自社の株式を交付することで、対象会社を完全子会社化する組織再編スキームです。これらの手法が税制適格要件を満たす場合、売り手株主の株式譲渡益に対する課税が繰り延べられるというメリットがあります。
買い手側にとっては、多額の買収資金を準備することなくM&Aを実行できるという利点があります。
ただし、税務上の取り扱いは非常に複雑であり、適格要件を満たすための設計には高度な専門知識が求められます。支配関係の継続や事業関連性などの要件を一つでも満たさない場合、売り手側に多額の税金が発生するリスクがあるため、専門家と綿密に計画を進めることが不可欠です。

M&Aの税金対策・節税ポイント|売り手向け
M&Aにおける売り手側の税負担は、事前の対策によって大きく軽減できる可能性があります。ここでは、課税所得を圧縮したり、特例を活用したりするための具体的な節税ポイントを紹介します。
節税方法①:役員退職金で課税所得を減らす
オーナー経営者が会社を売却する際、株式の譲渡対価の一部を「役員退職金」として受け取る方法があります。株式譲渡所得の税率は約20%ですが、退職所得は分離課税で退職所得控除も適用されるため、税負担を大きく減らせる可能性があります。
例えば、勤続20年超の場合、控除額は「800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)」で、所得税を大きく減らせます。
ただし、高すぎる退職金は税務署から否認される恐れがあるため、在任期間や功績に見合った金額設定が必要です。
節税方法②:仲介手数料などの譲渡費用を漏れなく計上する
株式譲渡を成功させるためにM&A仲介会社や税理士、弁護士に支払った手数料や報酬は、「譲渡費用」として売却価格から差し引くことができます。
これにより課税譲渡所得が減り、所得税や住民税の負担が軽減されます。これらの費用を証明するための契約書や領収書は、必ず保管しておくようにしましょう。
節税方法③:株式取得費加算特例を活用する
この特例は、相続で取得した株式を一定期間内に譲渡すると、相続税の一部を取得費に加算できます。
取得費が増えることで、課税対象となる譲渡所得が減少し、結果として所得税や住民税の負担が軽減されます。
この特例の適用を受けるためには、相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に株式を譲渡する必要があります。事業承継のタイミングでM&Aを検討している場合には、非常に有効な節税策となり得ます。
節税方法④:繰越欠損金を活用する
繰越欠損金とは、過去の事業年度で生じた赤字(欠損金)のうち、翌年度以降に繰り越すことが認められている金額のことです。売り手企業に繰越欠損金がある場合、株式譲渡ではなく事業譲渡を選ぶと節税できる場合があります。
事業譲渡によって生じた売却益は、この繰越欠損金と相殺することが可能です。
課税所得が減り、その年度の法人税負担を軽減できます。ただし、繰越欠損金の利用には期限があるため、M&Aの検討段階でその残高と利用可能性を確認しておくことが重要です。
節税方法⑤:組織再編スキームで税率を調整
法人株主が子会社株式を売却する場合、その譲渡益には法人税(実効税率約30%)が課されます。一方で、個人株主の株式譲渡益にかかる税率は約20%です。
この税率差を利用し、会社分割で子会社株式を個人株主に移し、その後売却することで全体の税負担を減らせる場合があります。
ただし、このような組織再編スキームは、税務上の合理性がないと判断された場合に否認されるリスク(租税回避行為とみなされるリスク)も伴います。実行にあたっては、税務の専門家と慎重に検討を重ねる必要があります。
節税方法⑥:暦年贈与を活用して株式を移転する
オーナー経営者が将来のM&Aや事業承継を見据えている場合、早い段階から後継者や親族へ暦年贈与(年間110万円まで非課税)で株式を少しずつ移す方法も有効です。
これにより、オーナー経営者個人の手元に残る株式が減るため、M&A時に一度に発生する譲渡所得を分散させることができます。
また、相続税対策としても有効ですが、計画的な実行が必要であり、M&Aの直前に行うと否認されるリスクもあるため、長期的な視点で専門家と相談しながら進めることが重要です。

M&Aの税金対策・節税ポイント|買い手向け
買い手側も、M&Aのスキームや会計処理を工夫することで、税負担を軽減し、投資効果を高めることが可能です。
ここでは、買い手にとって有効な節税ポイントを解説します。
節税方法①:のれんや営業権を償却して節税
事業譲渡によってM&Aを行った場合、買収価格が対象事業の純資産価額を上回る部分の金額は「のれん(営業権)」として資産計上されます。
こののれんは、税務上5年間にわたって均等に償却することが認められており、毎期の償却費を損金として費用計上できます。
損金が増えることで課税所得が減り、法人税の節税につながります。これは株式譲渡にはない事業譲渡特有のメリットで、買い手が選ぶ理由の一つです。
節税方法②:支払利息を損金に算入する
M&Aの買収資金を金融機関からの借入金で調達した場合、その支払利息は原則として損金に算入することができます。
これにより課税所得が減り、法人税負担を軽くできます。
ただし、過大な借入によってM&Aを行うLBO(レバレッジド・バイアウト)のようなケースでは、支払利息の損金算入が一部制限される「過少資本税制」や「過大支払利息税制」といった規制の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
節税方法③:買収費用を損金として計上する
M&Aのプロセスでは、デューデリジェンス(買収監査)の費用や、仲介会社への手数料、弁護士や会計士へのアドバイザリー費用など、様々な追加費用が発生します。
これらの費用のうち、M&Aが最終的に成立しなかった場合に支出した費用は、その事業年度の損金として計上することが可能です。
一方、M&Aが成立した場合、株式取得にかかる付随費用は株式の取得価額に算入され、資産として計上されるため、すぐに損金計上はできません。
節税方法④:再編スキームで課税繰延を活用
買い手側が、現金の代わりに自社の株式を対価としてM&Aを行う株式交換や株式移転といった組織再編スキームを活用する場合、売り手株主の税負担を繰り延べることができます。
これにより、売り手株主の合意を得やすくなり、交渉をスムーズに進められるというメリットがあります。
また、買い手にとっても、手元資金を温存したまま大型の買収を実行できるため、財務戦略の柔軟性が高まります。適格要件を満たすための緻密な設計が成功の鍵となります。
節税方法⑤:繰越欠損金を引き継いで活用する
買収対象の会社に繰越欠損金がある場合、その活用は買い手にとって大きな節税メリットになります。税制適格要件を満たす合併や、一定の要件を満たす株式取得を行った場合、被買収企業が持つ繰越欠損金を買収後の自社の所得と相殺し、法人税負担を軽減できます。
ただし、繰越欠損金の引き継ぎには厳しい制限(支配関係の発生から5年以内の特定事由など)が設けられています。
繰越欠損金の利用を前提にせず、専門家と適用要件を慎重に確認することが重要です。
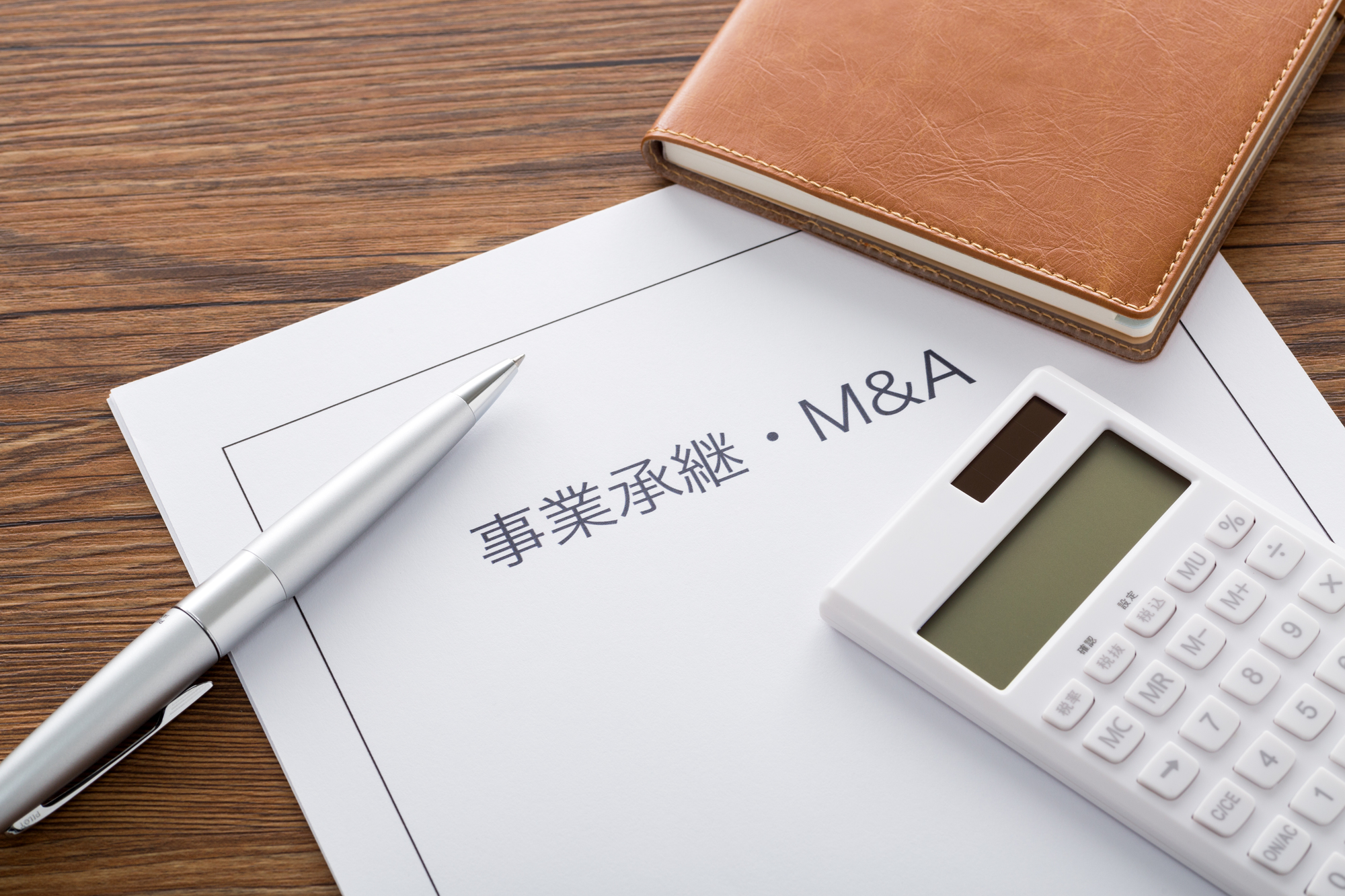


M&Aの税金対策における注意点

M&Aにおける節税策は有効ですが、行き過ぎた対策は税務署から否認されるリスクを伴います。ここでは、税務対策を講じるに際して注意すべき5つのポイントを解説します。
注意点①:節税目的のM&Aは否認リスク
M&Aのスキームが、事業上の合理的な理由ではなく、単に税負担を軽減することのみを目的として行われた場合、税務署に否認される可能性が高く、最大の税務調査リスクとされています。
「同族会社の行為計算の否認規定」などの規定に基づくものです。
M&Aを実行する際は、なぜそのスキームを選択したのか、事業戦略上の合理的な理由を明確に説明できるようにしておくことが重要です。
注意点②:過大な職務対価は損金不算入の恐れ
経営陣に対して支払われる役員退職金や職務対価が、同業他社の水準などと比較して著しく高額であると判断された場合、過大部分の金額は損金として認められません(損金不算入)。
損金不算入となるか否かの基準は、売り手企業側で法人税が課され、受け取った個人側でも給与所得(または一時所得)として課税関係が発生するため、結果として税負担が非常に重くなる可能性があります。
退職金の金額設定は、社会通念上の範囲内で行う必要があります。
注意点③:非適格分割で重課税の可能性
会社分割や合併などの組織再編において、課税の繰延べが認められる「適格要件」を満たすことは非常に重要です。
もし、適格要件を満たすと判断して進めていたものが、税務調査で要件を満たしていない「非適格」であると指摘された場合、想定外の多額課税が発生する可能性があります。
特に、非適格分割による譲渡損益が生じて法人税が課されると、企業のキャッシュフローに深刻な影響を及ぼしかねません。組織再編スキームの採用は、専門家と慎重に検討することが不可欠です。
注意点④:特例適用に要件確認が必要
M&Aで活用できる税制上の特例や優遇措置には、それぞれ詳細かつ厳格な適用要件が定められています。
例えば、株式交付制度や事業再編に伴う特例など、複雑な要件をすべて満たす必要があります。
一見すると適用できそうに見える特例も、特例の適用条件に合致しなければ、日常的に適用できることの多い制度ではなく、必ず税理士に相談し、全要件を満たしているかを確認することが不可欠です。
注意点⑤:税務調査対策は事前準備が重要
M&Aは取引金額が大きく注目を集めやすいため、税務調査の対象となりやすい取引です。
万が一調査を受けた場合に備えて、M&Aの検討段階から、意思決定のプロセスや交渉の記録、会議資料、契約書などを整理・保存しておくことが重要です。事前の準備が、税務リスクの最小化につながります。
税金トラブルや税務調査対応が必要となるケース
M&A後、税金に関するトラブルや税務調査の対象となりやすいのは、主に「取引価額の妥当性」と「組織再編の合理性」が問われるケースです。
例えば、同族間での株式売買が時価より大幅に低い価格で行われた場合、その差額が贈与とみなされ、贈与税の課される可能性があります。
また、買収価格に含まれる「のれん」の金額が過大と判断されれば、償却費の一部が否認される可能性があります。さらに、節税だけを目的とした複雑な組織再編スキームは、租税回避行為として否認されるリスクがあります。これらのトラブルを避けるためには、取引の各段階で、その価額やスキームを選んだ理由を、客観的資料で説明できるよう準備しておくことが重要です。
税金の前に経営者・担当者が最初に押さえるべきこと
]
M&Aを成功に導くためには、税務や法務といった専門知識はもちろん重要ですが、それ以前に「自社にとって最適な相手を見つけること」が全ての始まりです。
自社の強みや文化を正しく理解してくれる買い手、または成長戦略に合う売り手はどこにいるのか。
こうした情報を効率的に集め、最適な相手を見つける第一歩として、国内最大級のM&Aプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」の活用は非常に有効です。TRANBIでは、全国の幅広い業種・規模の企業が登録しており、匿名での交渉から始められるため、自社の情報を守りながら、多くの選択肢の中から最適なパートナー候補を探すことができます。まずはTRANBIに登録し、どのような企業がM&Aを検討しているのか、情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。


M&Aの税金に関するよくある質問と注意点

売却価格によって納税額はどう変わる?
納税額は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた「利益(所得)」に対して課税されるため、売却価格が高いほど利益が増え、納税額も比例して増えます。
ただし、個人の株式譲渡のように税率が一定(約20%)の場合と、法人のように利益が他の所得と合算されて超過累進税率が適用される場合とでは、計算構造が異なります。
買い手側が見落としがちな税務リスクとは?
買い手が見落としがちなリスクとして、「繰越欠損金の引継ぎ制限」と「偶発債務の存在」が挙げられます。買収対象企業に多額の繰越欠損金があっても、要件を満たさなければ引き継ぎできません。
また、デューデリジェンスで発見できなかった未払残業代や訴訟リスクなどの偶発債務が、買収後に発覚し、想定外の負担となるケースも少なくありません。
節税を意識したM&Aでの落とし穴は?
節税を過度に意識するあまり、事業の実態や戦略に合わない不自然なスキームを組んでしまうことが最大の落とし穴です。 税務上の利点だけを狙った取引は、税務署に「租税回避行為」とみなされ、否認される可能性が高まります。あくまで事業目的が主であり、節税は副次的な効果と捉えるべきです。
スキームで節税効果はどれだけ変わる?
スキームによって節税効果は劇的に変わる可能性があります。例えば、オーナー社長が会社を売却する際、単純な株式譲渡ではなく、役員退職金を併用することで、適用される税率と控除額が大きく変わり、数千万円単位で納税額が変わることもあります。
また、適格組織再編を活用すれば、本来発生するはずの数億円の税金が繰り延べられるケースもあります。
事業形態別(個人/合同会社/株式会社)で税負担はどう違う?
個人事業主が事業譲渡を行う場合、譲渡益は事業所得または譲渡所得として総合課税の対象となり、所得が増えるほど高い税率(最大55%)が適用されます。
合同会社の社員が持分を譲渡する場合は、個人の株主と同様に約20%の申告分離課税となります。株式会社の法人株主が株式を売却した場合は、法人税(約30%)の対象となります。このように、事業形態によって適用税率は大きく異なります。
節税目的でのM&Aはリスクが高い?
はい、リスクは高いです。M&Aの目的が「節税」そのものであると税務署に判断された場合、行為計算否認規定などに基づき、その税務上の効果が取り消される可能性があります。
M&Aはあくまで事業の成長や承継といった合理的な目的のために行うべきであり、その結果として税負担が軽くなる、という順序で考えることが重要です。
税制改正の情報を正しく得るには?
税制改正に関する最も正確な情報は、国税庁のウェブサイトや、毎年発行される「税制改正大綱」で確認できます。
しかし、内容は非常に専門的で難しいため、顧問税理士などから自社に関係する改正点を分かりやすく解説してもらうのが確実で効率的です。
まとめ:M&Aにおける税金対策の総括と実務アクション
M&Aにおける税金は、その種類の多さと制度の複雑さから、多くの経営者にとって難しいテーマです。しかし、本記事で解説したように、用いるスキームや売り手・買い手といった立場によって、誰にどのような税金が課されるのかという基本構造を理解することが、対策の第一歩となります。特に、株式譲渡と事業譲渡の違い、そして売り手が個人か法人かによる課税関係の違いは、必ず押さえるべき重要なポイントです。
さらに、M&A税務は、毎年の税制改正によって変化し続けるため、常に最新の情報をキャッチアップし、活用できる優遇措置を見逃さない姿勢が求められます。役員退職金の活用やのれんの償却といった古典的な節税策から、組織再編税制を活用した高度なスキームまで、選択肢は多岐にわたります。
最も重要なことは、これらの税金対策を単独で判断・実行しないことです。節税を意識するあまり事業の実態からかけ離れたスキームを選択すれば、税務調査で否認されるという本末転倒な結果を招きかねません。M&Aの成功とは、税務リスクを最小限に抑え、事業価値を最大化することです。そのためには、信頼できる税理士やM&Aアドバイザーに早期の段階から相談し、自社の状況に即した最適なアクションプランを共に描いていくことが、何よりも確実な道筋となるでしょう。







