
売り手にとってM&Aとは?メリット・デメリットと注意点を徹底解説!
後継者の不在や会社の将来性への不安等の解決にM&Aは有効な手段となりえます。M&Aのメリット・デメリット、成功させるためのポイント、具体的な手続きの流れや費用まで、網羅的に解説します。
- 02 M&Aの売り手の売却先企業の選定ポイント
- 希望条件に合う売却価格
- 自社の目的に合ったM&Aスキーム
- 従業員の雇用維持と処遇改善の可能性
- 企業文化・経営理念の親和性
- 事業の継続と成長につながるシナジー
- 買い手企業の財務基盤と信頼性
- M&A後の経営方針と売り手経営者の関与
- 03 売り手にとってのM&Aのメリット
- メリット①:創業者利益を現金化できる
- メリット②:後継者不在でも事業承継可能
- メリット③:成長余地のある企業に引き継げる
- メリット④:負債やリスクの軽減が図れる
- メリット⑤:従業員の雇用を守りやすい
- 04 売り手にとってのM&Aのデメリット・リスク
- デメリット① 希望条件で売却できない
- デメリット② 従業員の離職リスクがある
- デメリット③ 機密情報が漏れる可能性
- デメリット④ 買い手との交渉が難航する
- デメリット⑤ 企業文化の違いで混乱する
- 06 売り手がM&Aを行う際の注意点
- 注意点①:情報漏洩に最大限の注意を払う
- 注意点②:企業価値を正しく伝える準備する
- 注意点③:複数の買い手を比較検討する
- 注意点④:手数料や税負担を事前に確認する
- 注意点⑤:M&Aの目的と軸を見失わない
「後継者が見つからない」「会社の将来性に漠然とした不安がある」など、事業の未来に悩みを抱えていませんか。
こうした課題を解決する有効な選択肢の一つがM&Aです。
本記事では、M&Aを検討する売り手の皆様が知っておくべき、M&Aのメリット・デメリット、成功させるためのポイント、具体的な手続きの流れや費用まで、網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、M&Aに関する不安や疑問が解消され、ご自身の会社にとって最善の決断を下すための知識が身につくでしょう。
後悔のない未来を選択するために、まずはM&Aの全体像を正しく理解することから始めましょう。


売り手にとってのM&Aは?近年増加傾向の理由

近年、M&Aは特別なものではなく、多くの企業にとって現実的な経営戦略の一つとして認識されるようになりました。
特に中小企業において、売り手としてM&Aを選択するケースが増加しています。
その背景には、後継者問題の深刻化やM&Aに対するイメージの変化、そして国による支援体制の拡充があります。
本章では、売り手側のM&Aが増加している3つの主要な理由について詳しく解説します。
後継者不在による事業承継の手段増加
多くの中小企業が後継者不足という深刻な課題に直面しています。経営者の高齢化が進む一方で、親族や社内に適当な後継者が見つからないケースは少なくありません。
このような状況で、廃業ではなく、M&Aで第三者に事業を引き継ぐ選択肢が注目されています。これにより、経営者は会社と従業員の未来を守りつつ、事業の継続を図ることが可能になります。
M&Aに対するイメージ改善と理解促進
かつてM&Aは「身売り」や「乗っ取り」といったネガティブなイメージで語られることがありました。
しかし、近年ではその認識が大きく変わり、企業の成長戦略や事業承継の有効な手段として広く認知されるようになっています。
メディアで友好的なM&Aの成功事例が報じられる機会が増えたことや、M&Aに関する情報発信が活発になったことで、経営者の間での理解が深まったことが大きな要因です。このポジティブなイメージが、M&Aを検討する心理的ハードルを下げています。
中小企業向け支援体制の拡充による実行容易化
国や地方自治体も、中小企業の事業承継を重要な政策課題と位置づけ、M&Aを推進するための支援体制を強化しています。
各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターでは、専門家による秘密厳守の無料相談やマッチング支援を受けられます。
また、M&A仲介会社やプラットフォームサービスも多様化し、以前よりも負担が少なく、M&Aの専門家のサポートを受けられる環境が整っています。
こうした支援体制の拡充が、中小企業にとってM&Aをより身近で実行しやすい選択肢にしています。



M&Aの売り手の売却先企業の選定ポイント

M&Aを成功させるためには、自社にとって最適な買い手企業を見つけることが極めて重要です。
売却価格は重要ですが、それだけで判断すると、従業員の雇用や事業の将来に予期せぬ問題が生じる可能性があります。
ここでは、売り手の視点から、後悔しない売却先企業を選定するための7つの重要なポイントを解説します。
これらのポイントを総合的に評価し、慎重に相手を見極めましょう。
希望条件に合う売却価格
まず、自社が希望する売却価格を満たしているかは、重要な選定ポイントです。
企業の価値を正当に評価し、納得のいく価格を提示してくれる買い手候補を探しましょう。
自社の目的に合ったM&Aスキーム
M&Aの手法(スキーム)も重要です。
株式譲渡か事業譲渡かによって、税負担や手続きが大きく異なります。
自社の状況や目的に最も適したスキームを提案してくれるかどうかも、買い手選定の重要な判断材料となります。
従業員の雇用維持と処遇改善の可能性
長年会社を支えてくれた従業員の雇用を守ることは、多くの経営者にとって最優先事項の一つでしょう。
M&A後も原則として従業員の雇用を維持し、労働条件を維持または改善してくれる買い手であるかは、必ず確認すべきです。
トップ面談で、従業員の処遇に関する考え方や具体的な計画を質問し、誠実な回答が得られるかを見極めることが重要です。
従業員が安心して働き続けられる環境を整えている企業を選びましょう。
企業文化・経営理念の親和性
企業文化や経営理念が大きく異なると、従業員に摩擦や混乱が生じ、大量離職につながる恐れがあります。
自社が大切にしてきた価値観や文化を尊重し、理解を示してくれる買い手を選ぶことが、円滑な統合の鍵となります。
これまでの事業で重視してきた価値や社風を伝え、相手企業との文化や理念に親和性があるか確認しましょう。
互いの文化を尊重し合える関係性が理想です。
事業の継続と成長につながるシナジー
M&Aの目的は、単なる事業の売却ではありません。
自社の事業が買い手のリソースやネットワークと組み合わさることで、さらなる成長を遂げられるかどうかも重要な視点です。
これは「シナジー効果」と呼ばれます。買い手の持つ販売網、技術力、ブランド力などが自社の事業にどのようなプラスの効果をもたらすのかを具体的に検討しましょう。
事業の将来的な発展が見込める相手こそ、理想的なパートナーと言えます。
買い手企業の財務基盤と信頼性
M&Aの取引を確実に完了させるためには、買い手企業の財務的な安定性が不可欠です。
たとえ良い条件を提示されても、資金調達がうまくいかず、最終的に契約が破談になるリスクも考慮しなければなりません。
買い手企業の財務状況や過去の実績を調査し、信頼できる相手かどうかを慎重に判断する必要があります。
M&A仲介会社などの専門家に相談し、客観的な視点で評価することが求められます。
M&A後の経営方針と売り手経営者の関与
M&Aが成立した後、事業がどのような方針で運営されるのか、そして売り手である経営者自身がどのように関与を求められるのかも、事前に確認しておくべき重要なポイントです。
一定期間引継ぎのために経営に関与する必要があるのか、完全に退くのか。
M&A後のご自身のキャリアプランとも照らし合わせ、双方にとって納得のいく形を模索することが大切です。



売り手にとってのM&Aのメリット

M&Aは売り手にとって、会社売却以上に多くのメリットをもたらします。
後継者問題の解決から創業者利益の確保、従業員の雇用の安定まで、その利点は多岐にわたります。
この章では、売り手の視点から見たM&Aの5つの主要なメリットについて、それぞれ具体的に解説していきます。
メリット①:創業者利益を現金化できる
経営者にとって、会社は長年の努力の結晶であり、その価値は個人の資産と密接に結びついています。
M&Aによって自社の株式や事業を売却することで、これまで築き上げてきた会社の価値を現金として受け取ることができます。
これは「創業者利益の確定」と呼ばれます。
これにより得た資金は、引退後の生活資金や、新たな事業への挑戦、あるいは個人の資産運用など、様々な目的に活用することが可能になります。
メリット②:後継者不在でも事業承継可能
後継者が見つからないために、優良な事業でありながら廃業せざるを得ないケースは後を絶ちません。
M&Aは、こうした「後継者不在問題」を解決する極めて有効な手段です。
親族や社内に後継者がいなくても、意欲と能力のある第三者企業に引き継げます。
これにより、長年培ってきた技術やノウハウ、取引先との関係などを次世代につなぐことが可能になります。
メリット③:成長余地のある企業に引き継げる
自社単独では難しかった大規模な投資や販路拡大も、資金力やネットワークを持つ大手企業の傘下に入ることで実現可能になる場合があります。M&Aは、事業の成長を加速させるための起爆剤となり得ます。
自社の事業や技術を高く評価し、さらなる成長のために投資を惜しまない買い手企業に引き継ぐことができれば、事業は新たなステージへと飛躍できるでしょう。
これは、経営者にとって大きな喜びとなります。
メリット④:負債やリスクの軽減が図れる
会社の経営には、常に様々なリスクが伴います。
特に中小企業の経営者は、会社の借入金に対して個人保証を行っているケースが多く、事業が傾いた場合には個人資産を失うリスクを抱えています。
M&Aによって会社を売却する際、買い手や金融機関との交渉・合意が必要ですが、経営者個人の保証を解除できる可能性があります。
経営の負担や将来の不安から解放され、安心して引退後の生活を送れます。
メリット⑤:従業員の雇用を守りやすい
後継者が見つからずに廃業を選択した場合、従業員は職を失うことになります。これは経営者にとって、非常に心苦しい決断です。
M&Aであれば、従業員の雇用を維持したまま事業を引き継いでもらうことが可能です。
多くの場合、買い手企業は既存の従業員のスキルや経験を高く評価し、雇用を継続します。
ただし、M&A後の配置や労働条件については、買い手と事前に確認・合意しておくことが、円滑な引継ぎの鍵となります。



売り手にとってのM&Aのデメリット・リスク

M&Aは多くのメリットがある一方で、売り手にとって注意すべきデメリットやリスクも存在します。
ここでは、M&Aを進める上で売り手が直面しうる5つの代表的なデメリット・リスクについて解説します。
これらのリスクを事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵です。
デメリット① 希望条件で売却できない
M&Aを検討し始めても、必ずしも自社が希望する価格や条件で売却できるとは限りません。
自社の価値評価が想定より低かったり、魅力的な買い手が見つからなかったりするケースもあります。
業績悪化時や業界の先行き不透明な場合は、買い手探しが難航する可能性があります。
M&Aを成功させるには、適切なタイミングを見極め、企業価値を高める努力を日頃から行っておくことが重要です。
デメリット② 従業員の離職リスクがある
M&Aによって経営者が変わることは、従業員にとって大きな環境の変化であり、不安を感じる人も少なくありません。
新しい経営方針や文化に馴染めず、モチベーションが低下し離職するリスクがあります。
特に、M&Aのプロセスや今後の処遇について十分な説明がない場合、従業員の不信感は増大します。
従業員の不安を払拭し、円滑な統合を図るためには、買い手企業と連携し、丁寧なコミュニケーションを心がけることが不可欠です。
デメリット③ 機密情報が漏れる可能性
M&Aの交渉過程では、買い手候補に対して、自社の財務状況や技術情報、顧客リストといった機密情報を開示する必要があります。
この際、秘密保持契約(NDA)を締結しますが、情報漏洩のリスクを完全にゼロにすることは困難です。
万が一、交渉が破談になった後に情報が漏洩すれば、事業に深刻なダメージを与える可能性があります。
信頼できる相手を慎重に選び、情報開示の範囲を交渉の進捗に応じて段階的に管理することが重要です。
デメリット④ 買い手との交渉が難航する
M&Aの交渉は、売却価格や従業員の処遇、経営の引継ぎ方法など、多岐にわたる項目について双方の利害を調整するプロセスです。
お互いの希望条件が大きく異なれば、交渉が長引き、精神的に負担が大きくなることもあります。
特に、法務や財務に関する専門的な知識が必要となる場面も多く、売り手側だけで交渉を進めるのは困難です。
M&Aの専門家である仲介会社やアドバイザーのサポートを受けながら、冷静に交渉を進めることが重要です。
デメリット⑤ 企業文化の違いで混乱する
M&Aが成立し、いざ統合(PMI:Post Merger Integration)が始まると、企業文化の違いが大きな壁として立ちはだかることがあります。
仕事の進め方や意思決定のプロセス、価値観の違いから、現場で混乱や対立が生じるケースは少なくありません。
文化的摩擦は、生産性低下や従業員離職につながる恐れがあります。
買い手選定の段階から、企業文化の親和性を重視するとともに、M&A後も双方の文化を尊重し、時間をかけて融合させていく努力が必要です。


売り手から見たM&Aの種類と特徴

M&Aにはさまざまな手法(スキーム)があります。
どのスキームを選択するかによって、手続きの複雑さ、税金の負担、会社への影響などが大きく異なります。売り手としては、それぞれの特徴を理解し、自社の目的や状況に適した方法を選ぶことが重要です。
ここでは、中小企業のM&Aでよく用いられる代表的な7つのスキームについて、その特徴とメリット
株式譲渡
株式譲渡は、売り手の株主が保有する株式を買い手に売却し、経営権を移転させる方法です。手続きが比較的シンプルで、中小企業のM&Aにおいて最も多く利用されています。- メリット: 手続きが簡便で、会社を丸ごと引き継ぐため、事業への影響が少ない点が挙げられます。許認可も原則そのまま引き継がれますが、業種によっては届出や認可が必要です。
- デメリット: 売り手企業が抱える負債や不要な資産もすべて引き継がれるため、買い手側がデューデリジェンス(買収監査)を慎重に行う必要があります。また、株主が分散している場合は、全株主から同意を得る手間がかかります。
株式取得(新株引受)
株式取得(新株引受)は、買い手が売り手の新株を引き受けて経営権を取得する方法です。第三者割当増資とも呼ばれます。
- メリット: 売り手企業は、売却の対価として得た資金を会社の運転資金や設備投資に充てることができるため、事業の成長や財務体質の改善につながります。
- デメリット: 既存株主の持株比率が低下するため、株主総会での特別決議など、複雑な手続きが必要になる場合があります。また、買い手が経営権を完全に取得するまでには時間がかかることがあります。
事業譲渡
事業譲渡は、会社の経営権ではなく、事業の一部または全部を売買する方法です。売り手は特定の事業だけを売却し、会社自体は手元に残すことができます。
- メリット: 売りたい事業だけを選んで売却できるため、不採算事業を切り離し、主力事業に集中するといった選択が可能です。買い手にとっても、不要な負債を引き継ぐリスクがないという利点があります。
- デメリット: 関連する資産や負債、契約、従業員を個別に移転する必要があり、手続きが煩雑になります。メ従業員の転籍には個別の同意が必要となり、事業に必要な許認可は原則として買い手が再取得する必要があります。
合併
合併とは、複数の会社が契約によって一つの会社に統合される手法です。一方の会社がもう一方の会社を吸収する「吸収合併」と、新しく設立した会社にすべての会社が統合される「新設合併」があります。
- メリット: 複数の会社が一つになることで、スケールメリットやシナジー効果を追求しやすく、事業基盤の強化につながります。
- デメリット: 権利義務を包括的に承継するため、手続きが複雑で時間もかかります。また、異なる組織文化を持つ従業員同士の融合(PMI)が難しく、現場の混乱を招く可能性があります。
会社分割
会社分割は、会社が営む事業の一部または全部を分割し、別の会社に承継させる手法です。既存の会社に承継させる「吸収分割」と、新しく設立した会社に承継させる「新設分割」があります。
- メリット: 事業譲渡と同様に、特定の事業を切り出して承継させることができます。労働契約承継法に基づく所定の手続き(労働者への事前説明など)を経ることで、分割対象事業に主として従事する従業員の雇用契約は、個別の同意なく承継されます。
- デメリット: 権手続きが複雑であり、株主や債権者を保護するための手続きが必要となります。税務上の取り扱いも複雑なため、専門家の助言が不可欠です。
株式交換
株式交換は、売り手企業がその発行済み株式のすべてを買い手企業に取得させ、その対価として買い手企業の株式や現金を受け取る手法です。これにより、売り手企業は買い手企業の完全子会社となります。
- メリット: 買い手企業は、買収資金として自社の株式を活用できるため、多額の現金を準備する必要がありません。また、売り手企業の法人格は維持され、独立性を保ちやすい特徴があります。
- デメリット: 買い手企業の株価が下落すると、売り手側が受け取る価値も減少するリスクがあります。また、株主総会の特別決議が必要など、手続きは複雑です。
株式移転
株式移転は、一つまたは複数の会社が、その発行済み株式のすべてを新しく設立する会社(親会社)に取得させる手法です。既存の会社は、新設された親会社の完全子会社となります。主に、共同持株会社を設立する際に用いられます。
- メリット: 複数の企業がグループとして統合する際に、それぞれの独立性を保ちながら経営の効率化を図ることができます。
- デメリット: 株式交換と同様に手続きが複雑であり、時間とコストがかかります。中小企業のM&Aでは利用例が少ない方法です。



売り手がM&Aを行う際の注意点

M&Aは、売り手企業の未来を左右する重要な経営判断です。
成功すれば多くのメリットを享受できますが、進め方を誤ると、思わぬトラブルに発展し、後悔する結果になりかねません。
ここでは、売り手がM&Aを円滑に進め、最良の成果を得るために、特に注意すべき5つのポイントを解説します。
これらの注意点を常に念頭に置き、慎重にプロセスを進めましょう。
注意点①:情報漏洩に最大限の注意を払う
M&Aを検討しているという情報が、正式発表前に社内外へ情報が漏れるのは避けるべきです。
従業員の動揺や離職、取引先・金融機関との関係悪化を招く恐れがあります。
M&A仲介会社などの専門家と秘密保持契約を締結することはもちろん、社内でも情報を共有する範囲を経営陣など最小限にとどめることが重要です。交渉相手とのやり取りも、細心の注意を払って行いましょう。
注意点②:企業価値を正しく伝える準備する
自社の価値を買い手候補に正しく、そして魅力的に伝える準備が不可欠です。自社の強みや技術、将来的な収益性を客観的データで説明できなければ、高い評価は得られません。
事業計画書や企業概要書(インフォメーション・メモランダム)といった資料を、専門家のアドバイスを受けながら丁寧に作成しましょう。
自社の魅力を最大限にアピールすることが、より良い条件での売却につながります。
注意点③:複数の買い手を比較検討する
最初に声をかけてくれた一社とだけ交渉を進めるのは、得策ではありません。
より良い条件を引き出し、自社にとって最適なパートナーを見つけるためには、複数の買い手候補を比較検討することが非常に重要です。
複数候補と交渉すれば競争が生まれ、売却価格や条件が有利になる可能性が高まります。
また、様々な企業の考え方やビジョンに触れることで、自社の将来にとって本当に良い相手は誰かを見極めることができます。
注意点④:手数料や税負担を事前に確認する
M&Aには、仲介会社に支払う手数料や、弁護士・税理士への報酬など、様々な費用が発生します。また、株式や事業を売却して得た利益(譲渡所得)には、税金が課せられます。
これらのコストを事前に把握しておかないと、「手元に残る現金が想定よりずっと少なかった」という事態になりかねません。契約前に、手数料の税計算を専門家に確認し、手取り額を試算しておくことが重要です。
注意点⑤:M&Aの目的と軸を見失わない
M&Aの交渉は長期にわたることが多く、複雑な論点が次々と出てきます。
その過程で、当初の目的を見失い、目先の金額など、些細な条件に固執してしまうことがあります。
「なぜM&Aをするのか」「何を最も大切にするのか」という原点を忘れないようにしましょう。
従業員の雇用なのか、事業の成長なのか、創業者利益の確保なのか。自社の軸を明確にしておくことが、交渉の場で適切な判断を下すための羅針盤となります。



売り手側のM&Aの方法と流れ

M&Aは、思い立ってすぐに成立するものではありません。
専門家への相談から始まり、買い手探し、交渉、契約締結に至るまで、計画的に進める必要があります。
ここでは、売り手側の一般的なM&A方法と、7つのステップを解説します。
全体像を知ることで、各段階の行動が明確になり、手続きをスムーズに進められます。
手順①M&Aの検討と相談先の選定
まず、自社の経営課題を解決するために、M&Aが本当に最適な選択肢なのかを慎重に検討します。
その上で、M&Aを進めることを決断したら、信頼できる相談先を見つけることが最初のステップです。
相談先には、M&A仲介会社や金融機関、事業承継・引継ぎ支援センターなどがありますが、近年ではM&Aプラットフォームの活用も一般的です。
国内最大級のM&Aプラットフォーム「TRANBI」には、多様な業種・規模の買い手候補が数千社登録されています。
匿名で案件を登録し、買い手から直接アプローチを受けられるため、初期の候補探しに有効です。
手順②企業価値の評価と資料準備
次に、自社の企業価値がどのくらいになるのかを客観的に評価します。
これは「バリュエーション」と呼ばれ、売却価格の目安を把握し、交渉の基準とするために非常に重要です。
同時に、買い手候補に自社の魅力を伝えるための資料を準備します。
会社の基本情報や事業内容、財務状況などをまとめた企業概要書(ノンネームシート、インフォメーション・メモランダム)」を作成します。

手順③買い手候補の探索と打診
準備が整ったら、いよいよ買い手候補を探します。
M&A仲介会社やプラットフォームを利用して、自社の事業とシナジーが見込める企業や、自社の希望条件に合う企業をリストアップします。
最初は社名を伏せたノンネームシートで打診し、興味を示した候補企業との間で秘密保持契約(NDA)を締結した上で、より詳細な企業概要書を開示し、具体的な検討を促します。

手順④トップ面談と基本合意の締結
条件や親和性の高い企業を選び、経営者同士で面談(トップ面談)を行います。
ここでは、経営理念やビジョン、M&A後の事業方針を確認し、信頼関係を築くことが目的です。
交渉の結果、双方が大筋で合意に至れば、「基本合意書(LOI)」を締結します。
これには、現時点での売却価格やスケジュールなどが盛り込まれますが、価格など主要条件は法的拘束力がありませんが、独占交渉権や秘密保持義務には法的拘束力を持たせるのが一般的です。

手順⑤デューデリジェンスへの対応
基本合意を締結すると、買い手側による詳細な調査「デューデリジェンス(DD)」が実施されます。
これは、売り手企業の財務状況や法務上のリスク、事業の実態などを精査し、買収の最終判断を下すためのプロセスです。
売り手は、買い手の求める資料を迅速に提出し、質問には誠実に回答する必要があります。この対応が不十分だと、買い手の不信感を招き、交渉が決裂する原因にもなりかねません。

手順⑥最終交渉と最終契約の締結
デューデリジェンスの結果、大きな問題がなければ、最終的な条件交渉に入ります。
デューデリジェンスで新たなリスクが見つかれば、売却価格を見直す場合もあります。
双方がすべての条件に合意したら、法的な拘束力を持つ「最終契約書(DA)」を締結します。
実務では、株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書(SPA)」、事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書(APA)」など、スキームに応じた名称の契約書が用いられます。
契約書の内容は非常に専門的であるため、弁護士などの専門家によるリーガルチェックが不可欠です。

手順⑦クロージング
最終契約書に定められた条件(クロージング条件)がすべて満たされた後、株式の譲渡と売買代金の決済が行われます。
これをもって、M&Aのすべての手続きが完了し、経営権が正式に買い手に移転します。
この一連のプロセスを「クロージング」と呼びます。契約内容によっては、クロージング後も売り手が一定期間引継ぎ業務を行う場合があります。




M&Aで売り手にかかる費用・税金
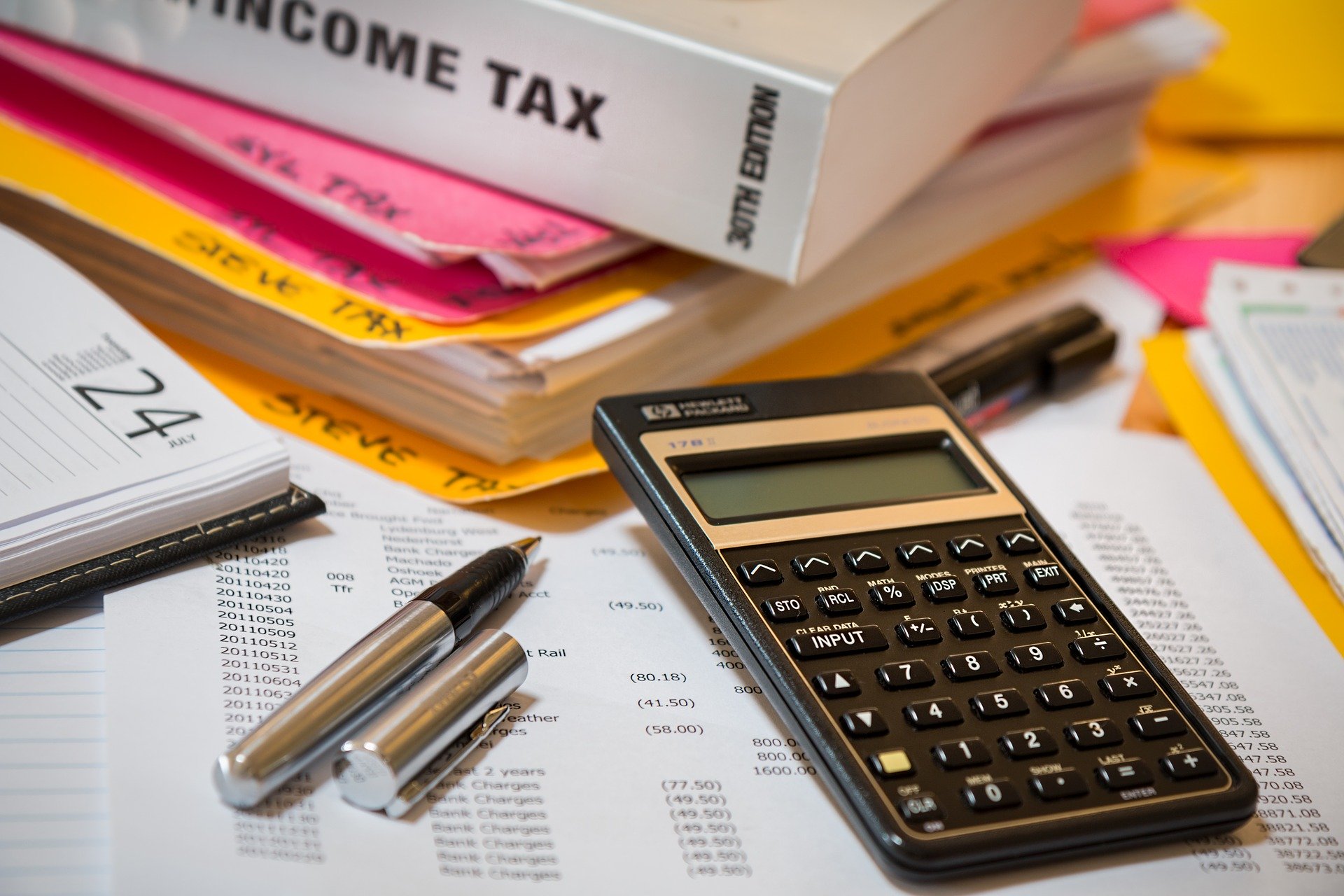
M&Aを成功させるためには、そのプロセスで発生する費用や、売却益にかかる税金について正しく理解しておくことが不可欠です。
事前に資金計画を立てないと、想定外の出費に慌てたり、手元資金が予想より減る可能性があります。
この章では、M&Aで売り手側に発生する費用の種類と相場、そして税金について解説します。
M&Aにかかる費用の種類と相場
M&Aを進めるにあたり、売り手は主にM&A仲介会社などの専門家に支払う手数料が必要となります。
手数料の体系は支援機関ごとに大きく異なり、近年ではM&A支援機関登録制度において手数料の公表が求められています。
一般的な「レーマン方式」(取引金額に応じた料率計算)でも、料率や最低報酬額、中間金の有無などは異なります。
契約前には複数の支援機関の開示情報を比較検討し、料金体系を必ず確認しましょう。
M&Aで売り手にかかる税金
M&Aによって利益(譲渡所得)が生じた場合、売り手には税金が課せられます。
課される税金の種類は、売り手が個人か法人か、またM&Aのスキームによって異なるため、注意が必要です。
- 株式譲渡の場合: 個人の場合、株式譲渡益に対して所得税15.315%と住民税5%が課され、合計20.315%の申告分離課税が適用されます。売り手が法人の場合は、他の所得と合算され、法人税等の対象となります。
- 事業譲渡の場合: 売り手である会社に、譲渡益に対して法人税等が課せられます。また、譲渡する資産(土地などの非課税資産を除く)の内容によっては、消費税の課税対象となるため、買い手から消費税を預かり、納税する必要があります。
税負担を減らすには、適切な節税策を検討することが重要です。
例えば、役員退職金として受け取ることで税制上の優遇措置である「退職所得控除」を活用する方法があります。
どのような対策が可能か、税理士などの専門家にあらかじめ相談し、最適なタックスプランニングを行うことが賢明です。



M&Aの売り手に関するよくある質問
M&Aは多くの経営者にとって初めての経験であり、様々な疑問や不安がつきものです。
ここでは、売り手の立場にある経営者から特によく寄せられる4つの質問について、簡潔にお答えします。
M&Aにはどれくらいの期間がかかる?
M&Aの期間は、企業の規模や業種、交渉の状況によって大きく異なりますが、一般的には半年から1年以上かかるケースが多いです。
相談先の選定から始まり、買い手候補探し、交渉、デューデリジェンス、契約締結と、多くのステップを踏む必要があります。
スムーズに進めるためには、早めに準備を開始することが重要です。
会社の価値はどう決まる?
会社の価値(企業価値)の算定には、様々な方法があります。
代表的なものに、会社の純資産に着目する「コストアプローチ」、類似する上場企業の株価などを参考にする「マーケットアプローチ」、将来の収益性を予測して価値を算出する「インカムアプローチ」などがあります。実際には、これらの方法を複数組み合わせて、最終的な売却価格は買い手との交渉によって決定されます。
従業員にはいつ告知する?
従業員への告知タイミングは、M&Aで最も慎重な判断が必要な事項の一つです。
情報が早期に漏れると、従業員の間に動揺が広がり、事業に支障をきたす恐れがあります。
情報漏洩を防ぐため、多くは最終契約後またはクロージング直後に告知します。
ただし、事業譲渡などで従業員の個別の同意が必要な場合は、より早い段階での説明が求められることもあります。
秘密は守られるのか不安がある場合は?
M&Aの情報管理は非常に重要です。
M&A仲介会社や交渉相手とは、必ず秘密保持契約(NDA)を締結します。
これにより、法的な拘束力をもって情報の目的外使用や漏洩を防ぎます。
信頼できる専門家や相手を選ぶことが大前提ですが、NDAを締結しても漏洩リスクは残るため、交渉進捗に応じて情報開示を段階的に管理することが有効です。


まとめ|M&A売り手として後悔しない選択をしよう!
本記事では、M&Aを検討する売り手の視点から、そのメリット・デメリット、売却先の選定ポイント、具体的な流れや費用、注意点に至るまで、網羅的に解説しました。
M&Aは、後継者不在や事業の将来性といった経営課題を解決し、会社と従業員、そして経営者自身の未来を拓くための強力な選択肢です。
しかし、そのプロセスは複雑で、多くの重要な判断を伴います。
成功の鍵は、M&Aの目的を明確にし、信頼できる専門家のサポートを得ながら、自社にとって最適なパートナーを慎重に見極めることです。
情報収集を欠かさず各ステップを丁寧に進めれば、後悔のない最良の決断ができます。
この記事が、あなたの会社にとって明るい未来を切り拓く一助となれば幸いです。








