
事業譲渡とは何か?売り手側のメリット・デメリットや注意点を紹介
会社の事業を売却するときに利用する『事業譲渡』とは、何なのでしょうか。行う目的や意味を解説します。会社の譲渡と何が異なるのか、事業譲渡特有のメリット・デメリットも知っておきましょう。事業譲渡の流れや、実際の事例も紹介します。



事業譲渡とは?

会社の事業を他者に譲る『事業譲渡』には、どんな意味があるのでしょうか。他の譲渡方法との違いや、主な種類を知っておきましょう。
事業譲渡を行う意味
事業譲渡は、会社の事業を他社に売却することを指します。
事業全体だけでなく、一部のみを売却する場合も含まれます。
売り手の会社に支払われる対価は現金です。
似たようなものに『株式譲渡』や『会社分割』があります。事業譲渡は、それぞれの事業に関わる資産・負債を他社へ譲る仕組みです。会社のオーナーを変更する株式譲渡、事業を包括的に他社へ渡す会社分割とは法的な観点で異なります。
具体的には、事業に関係する部署・従業員・オフィスなどの資産・負債を特定化し、売却する仕組みです。部署だけを売却して、従業員を残すこともできます。
具体的には、事業に関係する部署・従業員・オフィスなどの資産・負債を特定化し、売却する仕組みです。部署のみを売却して、従業員を残す選択も可能ですこともできます。
契約手続きを簡単にしたい場合、株式譲渡の方が適しています。
事業譲渡には引き継げない契約もあり、取引先との契約は買い手が別途承認を得る必要があります。
事業譲渡の種類
事業譲渡は、「全部譲渡」(事業全てを売却)と「一部譲渡」(一部のみを売却)の2種類に分けられます。
本業を残し、その他の事業のみを売却したい場合は一部譲渡を選択します。
会社の取り扱う全ての事業を売却したい場合は全部譲渡を選択しますが、株式譲渡やM&Aで会社ごと売却する方法もあるでしょう。
どの方法が最適かは、専門家に相談して判断することが望ましいでしょう。
事業譲渡は消費税がかかるなど、他の売却方法よりもコストがかかるケースもあります。


事業譲渡と株式譲渡・会社分割の違い
M&Aの手法には事業譲渡の他に「株式譲渡」や「会社分割」があり、それぞれ目的や法的な手続き、税務上の扱いなどが大きく異なります。
どの手法が最適かは、会社の状況やM&Aの目的によって変わるため、以下の比較表で各々の違いを正しく理解しておくことが重要です。
| 比較項目 | 事業譲渡 | 株式譲渡 | 会社分割 |
|---|---|---|---|
| 譲渡対象 | 事業に関する資産・負債 (個別に選別) |
会社の株式 (経営権) |
事業に関する権利義務 (包括的) |
| 法人格の継続 | 売り手・買い手ともに継続 | 株主は変わるが会社は継続 | 売り手・買い手ともに継続 (新設分割も) |
| 手続き | 煩雑 (資産・負債・契約の個別移転) |
比較的簡便 (株主名簿の書き換えが中心) |
煩雑 (債権者保護手続きなどが必要な場合も) |
| 債務の承継 | 原則、引き継がない (契約で個別に合意) |
会社に紐づく全ての債務(簿外債務含む)を引き継ぐ | 包括的に引き継ぐ |
| 従業員の雇用 | 個別の再契約が必要 | 原則、そのまま引き継がれる | 原則、そのまま引き継がれる |
| 許認可 | 買い手が再取得する必要がある | 原則、そのまま引き継がれる | 事業による (再取得が必要な場合も) |
| 主な税金 | 【売り手】 ・法人税 ・消費税 【買い手】 ・消費税 ・不動産取得税など |
【売り手】 ・所得税(個人の場合) ・法人税(法人の場合) 【買い手】 税負担なし |
適格要件を満たせば課税されない場合がある |


売り手側のメリット・デメリット

事業だけを切り離して売却できる事業譲渡には、メリットとデメリットがあります。売却前に把握しておきましょう。売り手側から見たメリット・デメリットを紹介します。
メリット
事業譲渡の魅力は、事業の一部を切り離して譲渡できることです。社員は会社に残して工場だけ売却したいなど、一部の資産を手放したいときに向いています。
会社を丸ごと売却するのとは異なり、法人格が残るのも特徴です。会社名は残して、必要ない事業だけ売却できます。会社を全て売却してしまうと、次の事業を始めるときに新会社の設立が必要です。
手間をかけずに事業を切り替えたい場合は、事業譲渡が向いているでしょう。売却によって、現金資産が手に入るのもメリットです。譲渡の方法によっては株の移動で現金が手に入らない場合もありますが、事業譲渡なら会社の資金が増えます。
デメリット
事業譲渡を行う場合、手続きがややこしくなります。例えば従業員を他社に引き継ぐ場合、再契約が必要です。取引先との契約の引継ぎの同意や再契約も必要で、個別の手続きが増えてしまいます。全てを丸ごと引き継ぐ買収と異なり、手間がかかるものと考えておきましょう。
買い手は事業だけを引き継ぐため、何らかの債務があるときは売り手側に返済の義務があります。債務を引き取ってもらうこともできますが、買い手が了承する場合に限ります。
赤字事業を売却する場合、債務ごと引き取ってもらえる手法の方が売り手にはメリットが大きいでしょう。
買い手との契約によっては、売り手は譲渡した事業と同系列の事業を新規開業しないよう求められることがあります。新しく事業を始める場合には、契約内容も確認しておきましょう。

買い手側のメリット・デメリット

事業譲渡の買い手側には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?それぞれ主なものを紹介します。デメリットが大きい場合には、事業譲渡以外の買収方法を検討しましょう。
メリット
買い手は、事業を譲渡したいと考えている企業の中から条件に合う企業を探せます。事業単位で引き継げるため、必要な事業のみピックアップできるのも利点です。
会社の負債の引き継ぎや、買収後のトラブルが起きにくいのもメリットといえるでしょう。負債を引き取る契約をしない限り、買い手にかかる金銭的な負担は少ないはずです。
これから社内で新規事業を立ち上げようと考えている場合も、事業譲渡を受けるのが向いています。他社から事業を買い取ると、必要な設備やノウハウを効率的に手に入れられるでしょう。
節税効果もメリットの一つです。事業譲渡で節税に生かせるのは『のれん』と呼ばれる買取価格と企業価値設定の差額で、5年間損金として計上できます。
デメリット
事業譲渡は現金による支払いが必要です。
実際にお金が動くため、投資した資金の回収が見込めるのかも考えておかなければなりません。企業価値として換算される『のれん代』も、正確に把握しておきましょう。
従業員や取引先との関係も承継したい場合は、手続きが複雑です。個別の契約の引継ぎの確認や再契約が必要なので注意しましょう。事業譲渡への不安がある場合、雇用や取引を拒否されるケースもあります。
譲渡を確定する前に、どこまで引き継ぎが可能なのか話し合いを進めておくとスムーズです。

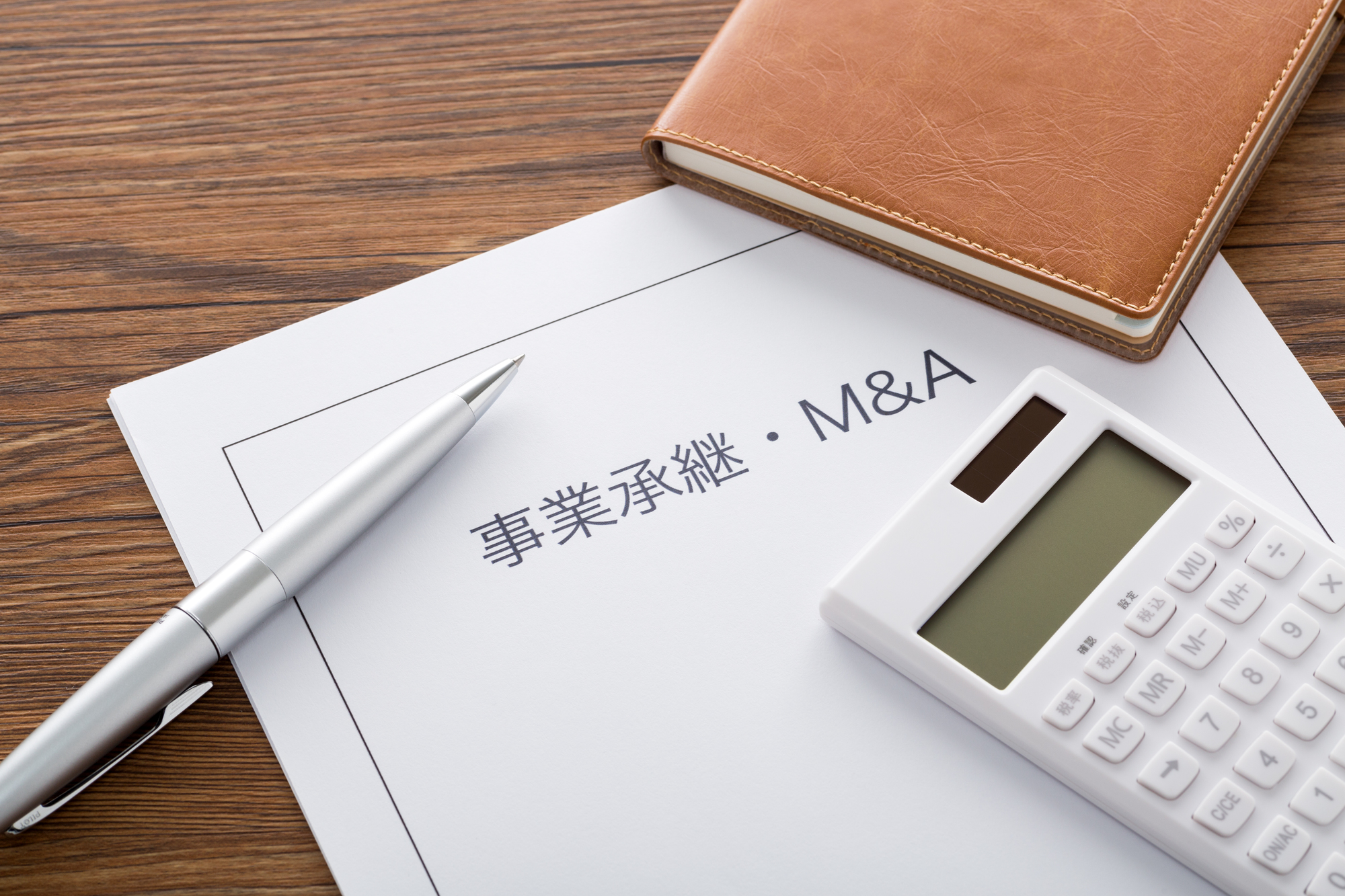
事業譲渡が特に有効な3つのケース
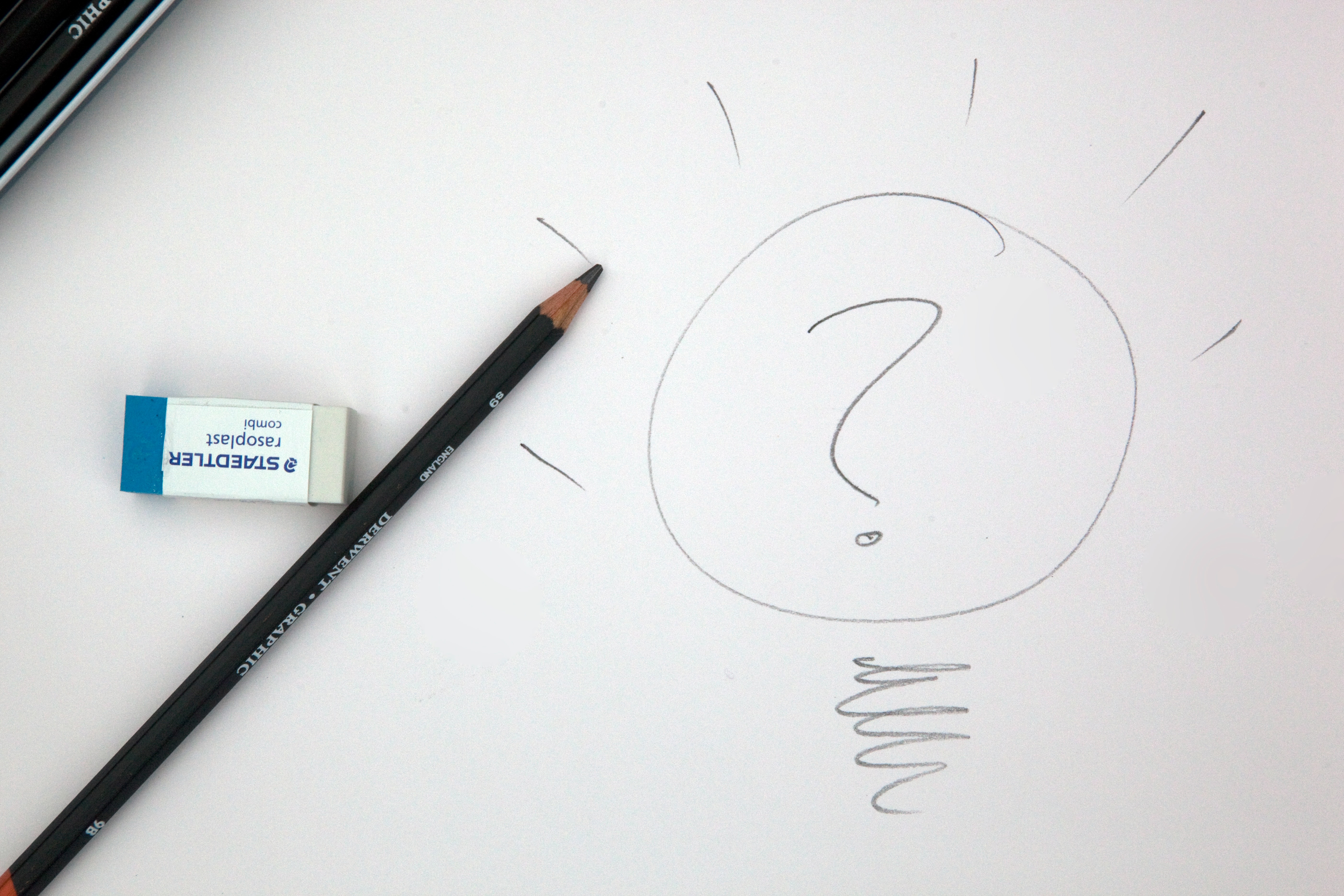
事業譲渡は、特定の目的を持つ企業にとって非常に有効な選択肢となります。
ここでは、事業譲渡が特に効果を発揮する代表的な3つのケースについて解説します。
不採算事業のみを切り離したい場合
複数の事業を展開している中で、特定の事業だけが赤字で経営全体の重荷となっているケースがあります。
このような場合、事業譲渡を活用して不採算事業だけを売却すれば、経営をスリム化できます。
会社全体を売却する必要はなく、主力事業や成長事業を残したまま経営資源を再配分できます。
その結果、企業全体の収益性改善を目指すことが可能です。
会社の経営権は手元に残したい場合
後継者不在で事業承継を考えていても、創業した会社は手放したくないという経営者も少なくありません。
事業譲渡であれば、特定の事業を売却して現金化しつつも、会社の法人格(経営権)は引き続き維持できます。
その結果、会社名を残したり、他の事業を続けたり、売却資金で新規事業を始めることもできます。
買い手側が簿外債務のリスクを避けたい場合
買い手にとって、M&Aにおける大きなリスクの一つが、貸借対照表に記載されていない「簿外債務」や「偶発債務」です。 株式譲渡では会社を丸ごと引き継ぐため、こうした隠れた債務も承継してしまいます。
一方、事業譲渡なら契約で承継する資産や負債の範囲を明確に定められます。
そのため、買い手は不要な債務を引き継ぐリスクを限定でき、安心して事業を譲り受けることが可能です。



手続きの流れ

事業譲渡を完了するまでには、複数の手続きがあります。
一般的なM&Aの手法と大きく変わりませんが、株主の了承や許認可の取得など、事業譲渡ならではの手続きが必要です。
計画の立案・交渉先の決定
売り手は、経営資源や経営状況、現在の課題を分析し、どの事業を譲渡するか計画を立てるのが最初のステップです。
M&Aの専門家に相談しながら、『自社の強み』と『問題点』を明確にします。事業譲渡によって手放すことで利益が生まれるのか、価値はどのくらいなのかを客観的に把握しましょう。
自社の強みや価値を正確に把握できていないと 場合、市場相場よりも低い金額で譲渡してしまう恐れがあります。
買い手も、事業譲渡を行う旨をM&Aのアドバイザーなどに相談した上で、自社の状況を精査します。『事業買収の目的』『買収したい事業』『買収でもたらされるメリット』などを細かく分析することが重要です。
事業譲渡の交渉先を探す方法としては、『M&Aのマッチングサイト』『仲介会社』『事業承継・引継ぎ支援センター』などが挙げられます。
交渉・基本合意契約の締結
譲渡先の候補が決まれば、交渉に進みます。条件・金額など、双方が納得できるよう経営陣同士で話し合いを進めましょう。
話し合いや条件確認の結果、事業譲渡を進める場合は基本合意契約を結びます。買い手側が納得し、事業を引き受ける意思があることを示す契約です。
基本合意契約は譲渡確定を意味しません。
ただし、買い手側が交渉の独占権を持つ契約を結んだ場合は、同時期に複数の企業と譲渡の交渉はできません。
デューデリジェンス
企業価値を把握するために行う調査は『デューデリジェンス』と呼ばれます。買い手側が、本当に事業を引き受けるか判断するための材料です。
売り手側の事業に問題がないかを精査します。問題なく経営が続けられているか、トラブルなどはないか確認する作業です。企業価値の把握がしっかりできていないと、買取価格の設定間違いや買収後のトラブルにもつながります。
デューデリジェンスは、専門家と買い手企業の担当者が行うものです。確認漏れがないよう、しっかり監査を進めましょう。問題がないと判断されれば事業譲渡の手続きが本格化します。
事業譲渡契約の締結・各書類の提出
事業譲渡・引受の意思が双方確定した後は、事業譲渡契約を結びます。この段階で、基本的には譲渡が確定する仕組みです。
必要に応じて書面の提出も済ませます。企業の規模によっては、公正取引委員会への書類提出や臨時報告書の作成が必要です。
公正取引委員会への書類提出は、買い手側の企業規模によって義務が変わります。国内売上高200億円以上の企業の場合、その他の条件も満たすときは忘れずに手続きを進めましょう。
株主総会特別決議
事業譲渡が確定した後は、株主総会を開きます。事業譲渡には、株主の承認が必要です。否決されると事業譲渡ができなくなるため、あらかじめ株主の意向を確認しておくとスムーズに進みます。
確実に譲渡を進めたいときは、株主の整理や意向確認をしておきましょう。株主の整理は、会社側が株式を買い取るなどの方法で交渉できます。
株主総会で承認を得るには、出席者の3分の2以上の賛成が必要です。
売り手側は全部譲渡・一部譲渡どちらの場合も株主総会の開催が必要ですが、買い手側は事業の全てを引き受けるときに株主総会での決議が求められます。
監督官庁の許認可・名義変更手続き
事業譲渡の後は、買い手側がスムーズに事業を引き継げるよう手続きを行います。資産が譲渡されたときは、名義変更が必要です。登記されているものに関しては、変更の手続きを済ませておきましょう。
許認可が必要な事業の場合は、買い手側が監督官庁に認可を申請し、 事前に許認可を取得しておく必要があります。
建設業界や公共サービスなど、認可が必要な事業を引き受ける場合は認可が取れるか否かは重要なポイントでしょう。手続きを忘れていると、事業を引き継いだものの運営ができない事態も考えられます。





事業譲渡金額の算出方法

事業譲渡金額は、最終的には売り手と買い手の交渉で決まります。
その基盤となる客観的な事業価値を評価するために、専門的な「企業価値評価(バリュエーション)」の手法が用いられます。
代表的なアプローチとして以下の3つがあり、対象事業の特性に応じて単独または複数の方法を組み合わせて価値を算出します。
1. コストアプローチ(純資産価額法)
譲渡対象となる事業に紐づく資産から負債を差し引いた「純資産」を基準に事業価値を評価する方法です。
貸借対照表を基に算出するため客観性が高く、譲渡価格の最低ラインを把握する目的でよく用いられます。
- 簿価純資産法:帳簿上の数値をそのまま用いて算出します。簡便ですが、資産の時価が反映されないという欠点があります。
- 時価純資産法:土地や有価証券など、帳簿価額と時価が乖離している資産を時価に評価し直して算出します。より実態に近い価値を把握できます。
2. マーケットアプローチ(市場比較法)
評価対象の事業と類似する上場企業や、過去のM&A事例などを比較対象として価値を算出する方法です。市場の客観的な評価を反映できるメリットがあります。
- 類似会社比較法(マルチプル法):事業内容が似ている上場企業の株価が、利益や純資産の何倍で評価されているか(マルチプル)を算出し、評価対象事業の財務数値に当てはめて価値を計算します。
- 類似取引比較法: 過去に行われた類似のM&A事例における取引価格を参考に価値を算出します。
3. インカムアプローチ(収益還元法)
評価対象の事業が将来生み出すと期待される収益やキャッシュフローを基準に価値を算出する方法です。事業の将来性を評価に反映できる点が最大の特徴です。
- DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法:将来のフリーキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り引いて合計することで事業価値を算出します。M&Aの実務で最も広く利用される手法の一つですが、将来予測の精度が結果に大きく影響します




事業譲渡で発生する税金
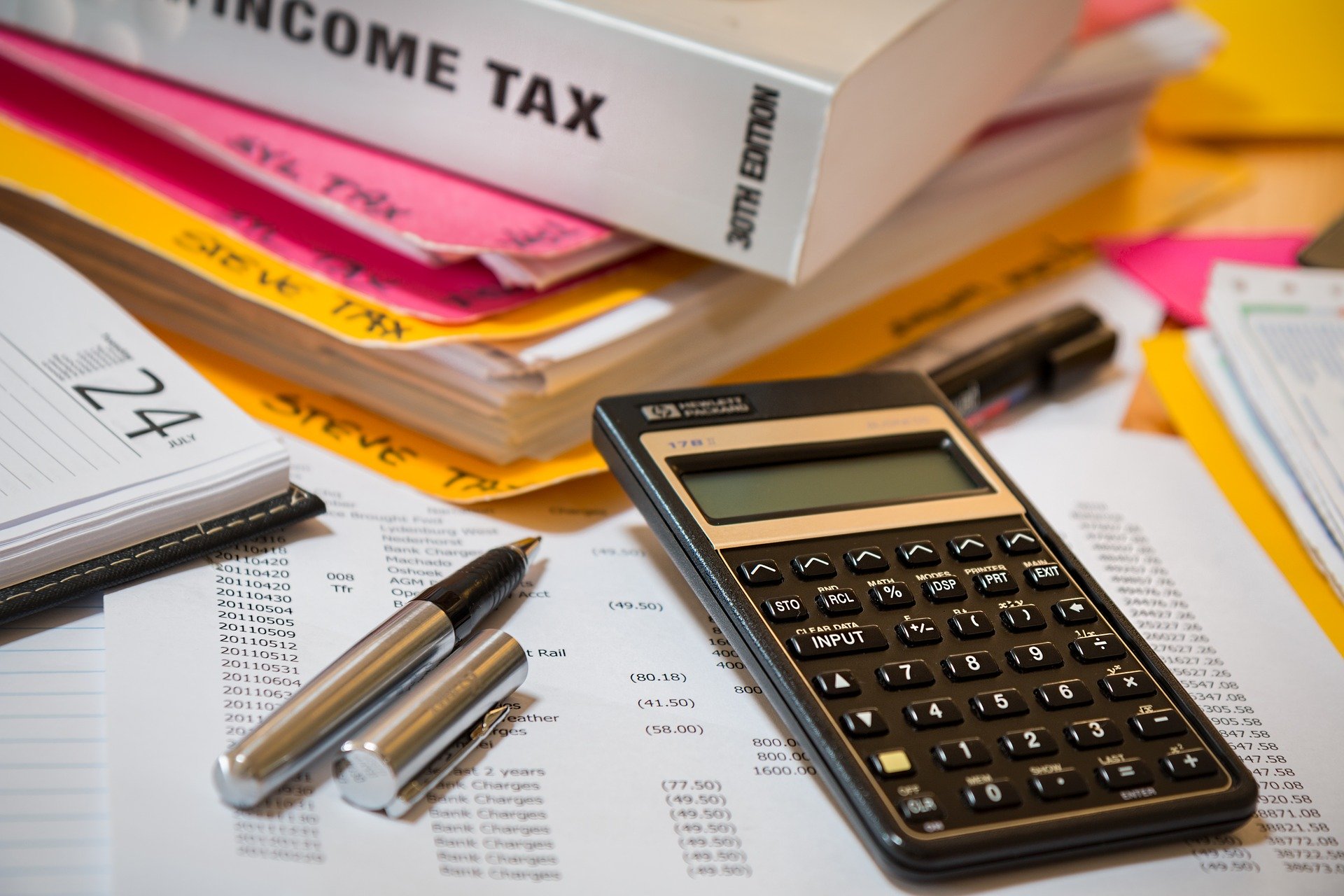
事業譲渡を行う際には、売り手・買い手双方に税金が発生します。
特に株式譲渡とは税務上の取り扱いが大きく異なるため、事前に専門家へ相談し、正確な納税額を把握しておくことが不可欠です。
売り手側の税金
売り手企業には、主に「法人税」と「消費税」が課されます。
- 法人税: 事業譲渡によって得た利益(譲渡益)に対して課税されます。譲渡益は「譲渡価格 − 譲渡資産の簿価」で計算され、他の事業で得た利益と合算された上で、法人税率が適用されます。もし他の事業が赤字であれば、譲渡益と相殺して納税額を抑えることも可能です。
- 消費税: 譲渡資産のうち、「課税資産」に対して消費税が課されます。売り手は、買い手から譲渡代金と共に消費税を預かり、国に納付する義務があります。
- 課税資産の例: 建物、機械設備、車両、のれん(営業権)、商標権など
- 非課税資産の例: 土地、有価証券、売掛金などの債権
買い手側の税金
買い手企業には、主に「消費税」「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」などが課されます。
- 消費税: 売り手と同様、課税資産の取得に対して発生します。支払った消費税は、自社の消費税申告の際に「仕入税額控除」の対象となり、自社の売上にかかる消費税額から差し引くことができるため、実質的な負担にはならないケースが多いです。
- 不動産取得税: 譲渡対象に土地や建物といった不動産が含まれる場合に、その取得に対して課税されます。
- 登録免許税:不動産の所有権移転登記など、登記手続きが必要な場合に発生します。
- 印紙税: 事業譲渡契約書を作成する際に、契約書に記載された金額に応じて収入印紙を貼付する形で納税します。



事業譲渡の際の会計処理
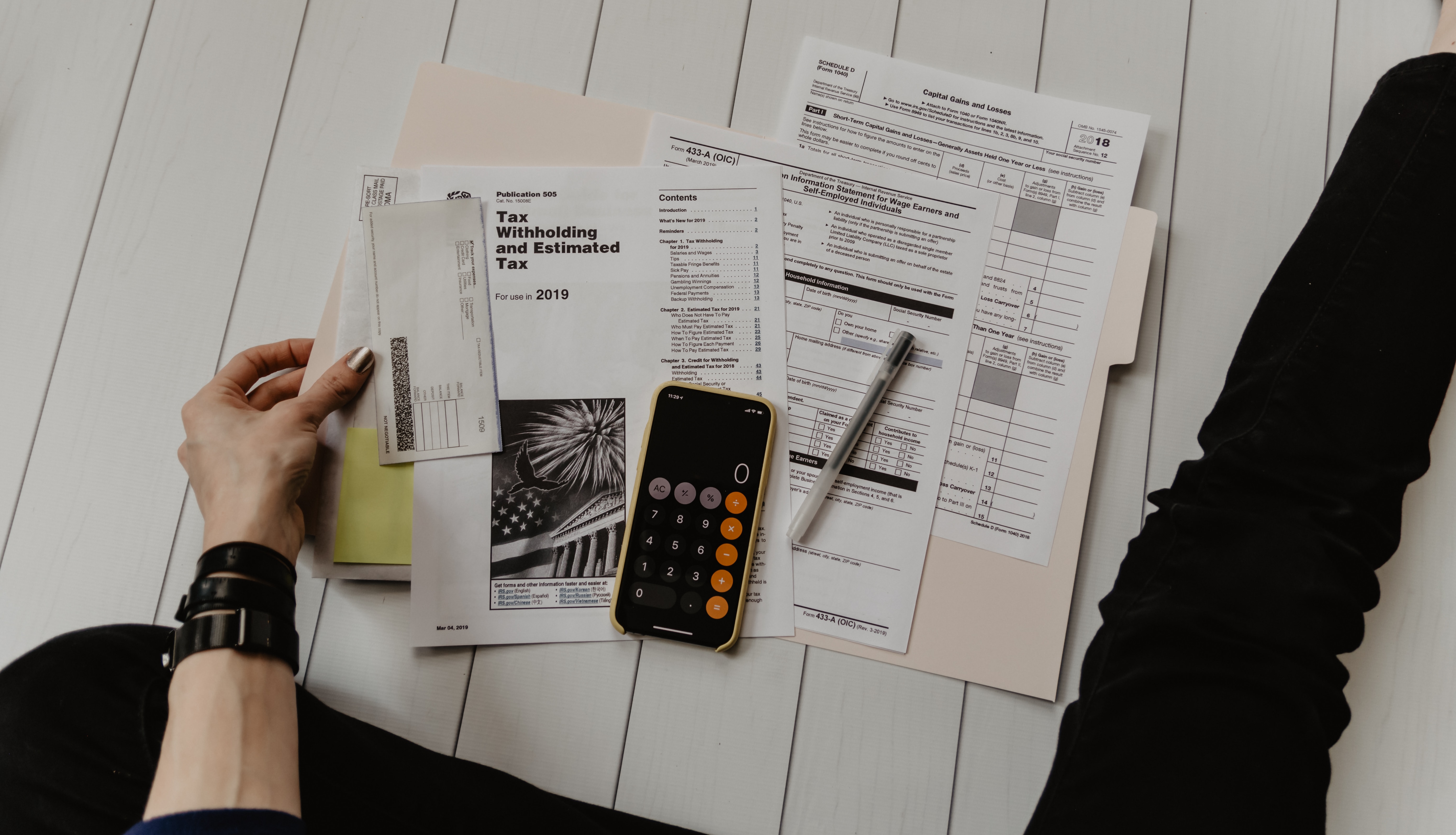
事業譲渡では、売り手・買い手それぞれで会計処理が必要となります。資産や負債の移転を会計帳簿に正しく反映させるため、適切な勘定科目を用いて仕訳を行います。
売り手側の会計処理
売り手側は、譲渡する資産と負債を帳簿から消去し、受け取った対価との差額を「事業譲渡益」または「事業譲渡損」として特別損益に計上します。
【仕訳例】 譲渡対価5,000万円で、諸資産(簿価3,500万円)と諸負債(簿価1,000万円)を譲渡した場合の仕訳例です。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 現金預金 | 5,000万円 | |
| 諸負債 | 1,000万円 | |
| 諸資産 | 3,500万円 | |
| 事業譲渡益 | 2,500万円 |
買い手側の会計処理
買い手側は、譲り受けた資産と負債を時価で自社の貸借対照表に計上します。支払った対価が、受け入れた資産と負債の差額(時価純資産額)を上回る場合、その差額を「のれん」として資産に計上します。
【仕訳例】 譲渡対価5,000万円で、諸資産(時価3,500万円)と諸負債(時価1,000万円)を譲り受けた場合の仕訳は以下のようになります。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 諸資産 | 3,500万円 | |
| のれん | 2,500万円 | |
| 現金預金 | 1,000万円 |

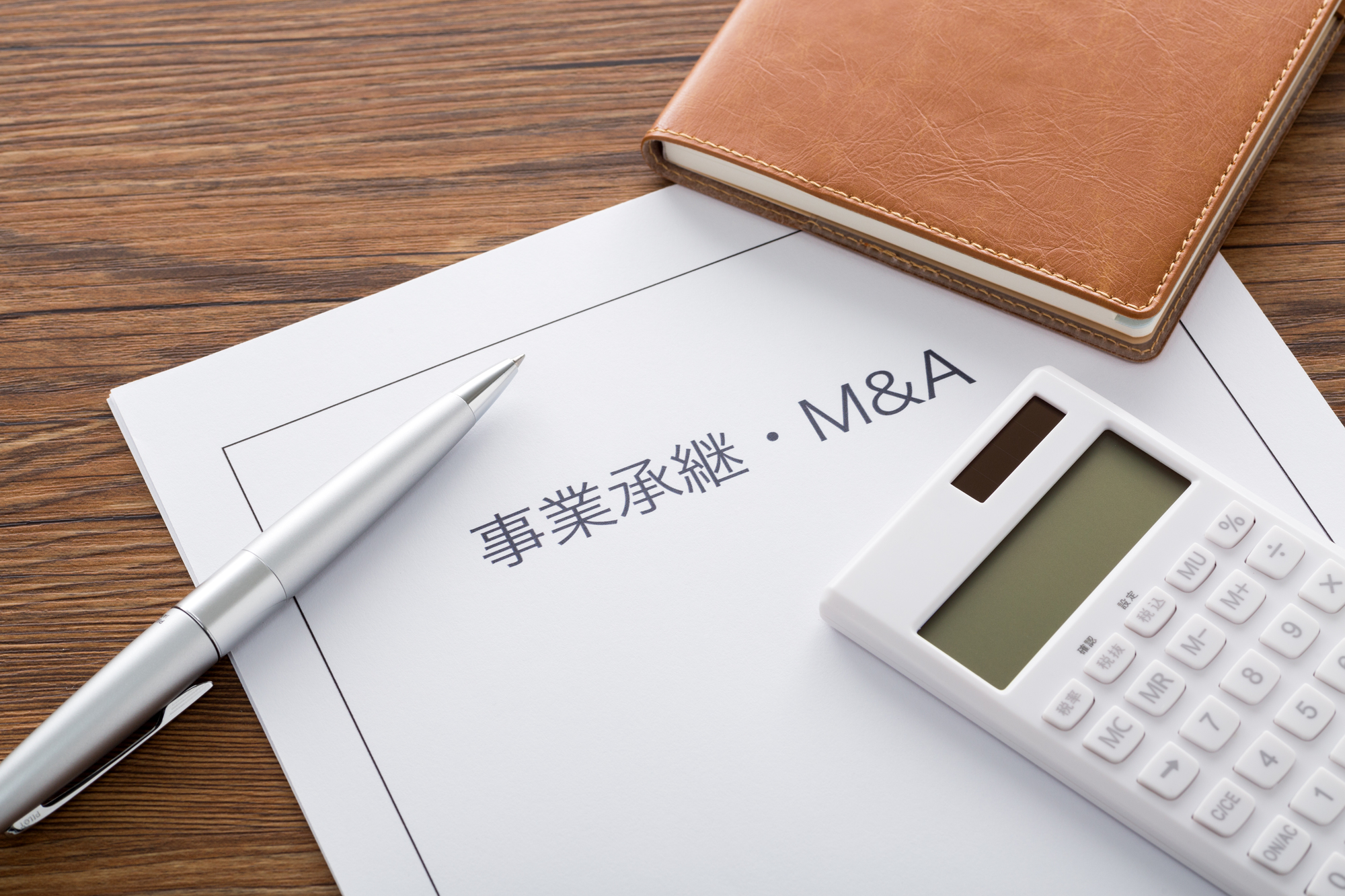
事業譲渡を成功させるためのポイント

事業譲渡は、ノンコア事業の整理や後継者問題の解決に役立つ経営戦略の一つです。ただし、そのプロセスは複雑で多くの時間と労力を要します。
ここでは、事業譲渡を成功に導くための重要なポイントを解説します。
ポイント1:専門家(M&Aアドバイザー)への早期相談
事業譲渡の検討を始めたら、できるだけ早い段階でM&Aアドバイザーなどの専門家に相談することが成功の鍵を握ります。
M&Aには法務・税務・会計など幅広い知識が必要であり、自社だけで全てを進めるのは困難です。
専門家は、客観的な視点から自社の企業価値を評価し、最適な譲渡スキームの提案、譲渡先の選定、交渉のサポートまで、一連のプロセスを支援してくれます。
早期に相談することで、自社の現状を正確に把握し、十分な準備期間を確保できるため、より有利な条件での譲渡や、理想的な譲渡先とのマッチングの可能性が高まります。情報収集の一環としてでも、まずは専門家の意見を聞いてみることが重要です。
ポイント2:譲渡目的と希望条件を明確にする
「なぜ事業を譲渡するのか」という目的を明確にすることは、交渉の軸となり、譲渡後のミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。
例えば、「主力事業に経営資源を集中させたい」「後継者不在のため、従業員の雇用を守りたい」「創業者利益を確保したい」など、目的によって優先すべき条件は変わってきます。
譲渡目的を明確にした後は、希望条件を整理します。譲渡価格のほか、従業員の雇用維持、取引先との関係継続、譲渡後の経営への関与度などについて、譲れない条件と譲歩できる条件を分けてリスト化しましょう。
これにより、交渉の場で迅速かつ的確な意思決定が可能になります。
ポイント3:企業価値を正しく評価し、アピール材料を準備する
譲渡価格の交渉を有利に進めるためには、自社の事業価値を客観的かつ正しく評価することが不可欠です。
企業価値評価には、純資産を基準にする方法や、将来の収益性を基に算出する方法(DCF法など)など、様々なアプローチがあります。
専門家による評価を参考に、自社の価値を理論的に説明できるように準備しましょう。
同時に、財務諸表には表れない自社の強み(アピール材料)を整理することも重要です。
例えば、独自の技術や特許、高い市場シェア、優秀な人材、強固な顧客基盤、ブランドイメージなどが挙げられます。
これらの無形資産が、買い手企業にとってどのようなシナジー(相乗効果)を生むのかを具体的に提示することで、評価額以上の価値を認めさせ、より良い条件を引き出すことが可能になります。
ポイント4:適切な情報開示と誠実な交渉
事業譲渡の交渉過程では、買い手企業から事業に関する詳細な情報の開示を求められます(デューデリジェンス)。
この際、自社にとって不都合な情報(例えば、偶発債務や訴訟リスクなど)があったとしても、決して隠してはいけません。
ネガティブな情報も誠実に開示し、対策や見通しを説明することが、信頼構築には不可欠です。
もし後から隠していた事実が発覚すれば、交渉が破談になるだけでなく、損害賠償問題に発展するリスクもあります。
「Win-Win」の関係を目指し、常に誠実な姿勢で交渉に臨むことが、最終的な成功につながります。
ポイント5:従業員や取引先への丁寧な説明とフォロー
事業譲渡は、従業員や取引先に大きな影響を与える可能性があります。
特に、従業員は雇用の維持や労働条件の変更などに対して不安を抱くため、情報開示のタイミングや方法には細心の注意が必要です。
契約締結後は速やかに従業員説明会を開き、譲渡の背景や目的、今後の処遇を経営者自身の言葉で丁寧に説明することが必要です。
従業員の動揺を最小限に抑え、モチベーションを維持するためにも、譲渡後も継続的なコミュニケーションと精神的なフォローを心がけましょう。
また、主要な取引先に対しても、契約締結後に速やかに報告し、今後の取引関係に支障がないことを説明して安心させることが、事業の円滑な引き継ぎに不可欠です。
ポイント6:M&Aプラットフォームを有効活用する
近年、インターネット上で売り手と買い手を直接つなぐM&Aプラットフォームの活用が広がっています。
M&A仲介会社に依頼するのと並行して、あるいは新たな選択肢として、こうしたプラットフォームを有効活用することも検討しましょう。
国内最大級のM&Aプラットフォームである「TRANBI(トランビ)」では、売り手は無料で自社の事業を匿名で登録し、全国の幅広い買い手候補に直接アプローチすることが可能です。
仲介会社を介さずに交渉できるため、スピーディーなマッチングが可能です。
また、異業種の企業から思わぬ提案を受けられることもあります。
情報収集の段階から積極的に活用することで、より多くの選択肢の中から自社にとって最適なパートナーを見つけられる可能性が高まります。




知っておくべき留意点とは

事業譲渡を行う場合、気をつけたいポイントがあります。従業員を引き継いで雇用するときは、個別の契約手続きを忘れないようにしましょう。また株式譲渡ではかからない消費税も発生します。
従業員の取り扱い
事業譲渡を行う場合、気をつけたいポイントがあります。
,span>従業員を引き継ぐ場合は、個別の契約手続きを忘れないようにしましょう。
また株式譲渡ではかからない消費税も発生します。
売り手側は従業員を残し、て自社の別部署に配置転換することも可能です。
事業を手放すとき、事業を譲り受けるときは、従業員の扱いについても話し合っておきましょう。
消費税の取り扱い
事業譲渡では、会社が保有する資産に対して消費税が発生します。株式には消費税がかからないため、消費税分のコストをかけたくないときは株式譲渡が向いているでしょう。
売り手側が現金を受け取る場合、消費税10%分を計上して納める必要があります。
実際の利益は買取価格から消費税を差し引いた金額になる点に注意が必要です。
なお、事業譲渡をしても全てに税金がかかるわけではありません。消費税法で、『課税資産』として判断されるものに消費税が課されます。


事業譲渡の成功例

(出典) pexels.com
事業譲渡は実際にはどのように行われているのでしょうか?有名な事例を紹介します。売り手側には資金が提供され、買い手側は自社にとってメリットのある事業が手に入るのが特徴です。
帝人ファーマ
帝人ファーマは2021年に、『武田薬品工業』より糖尿病治療薬を販売する事業を引き継ぎました。買取価格は1330億円です。
販売される糖尿病治療薬は、『ネシーナ』『リオベル』『イニシンク』『ザファテック』の4種類です。
武田薬品工業では、長期的な成長を目指し特定の医薬品開発・販売に注力しています。糖尿病治療薬は同社のビジネス戦略のカテゴリから外れていたため、事業譲渡が決まった形です。
帝人ファーマは循環器疾患や代謝関連の医薬品への投資を考えており、双方のニーズが一致しました。
シャープ
シャープは、音響機器を扱う老舗メーカー『オンキヨー』より、『ホームAV事業』を引き継いでいます。買取価格は約33億円です。VOXX社と合同で『オンキヨーテクノロジー社』を設立し、生産と販売を担当しています。
新会社にも『オンキヨー』の名称が残り、ブランド名が引き継がれているのが特徴です。
売り手側にも大きなメリットが生まれました。オンキヨーグループの業績悪化により、一部事業を売却し経営を立て直すのが目的です。2019年には別の会社への譲渡を模索していましたが、条件面で折り合いがつかず一時的に譲渡計画が停止していました。
シャープとVOXX社への譲渡は2021年5月26日に決まり、9月8日には譲渡手続きが完了しています。
TRANBIでの事業譲渡の成功事例
TRANBIは、M&Aの各段階においてさまざまな形で活用され、多くの成約に貢献しています。
以下では4つの事例におけるTRANBIの活用方法をまとめます。
建設業界の新卒採用サイト譲渡事例(売り手:D社)
D社の社長は、当初は買い手として参加したTRANBIのセミナーでTRANBI社長の高橋と出会いました。
悩んでいた事業について相談したところ、売却登録を勧められ、その場でTRANBIに登録しました。
登録後は、有料サービス「ピックアップ案件」を利用し、多くの候補者からの申し込みを得ました。
最終的に30件以上の申し込みがあり、1年以上かけて、熱意ある買い手を選定し、数十万円で事業譲渡に成功しました。
※D社の成約インタビュー
「1,000万円をかけて作り上げた事業を数十万円で譲渡した理由 ~お金よりも相手の夢を応援したい~」
認可外保育園譲渡事例(売り手:Kさん)
コロナ禍で経営難に陥っていたKさんは、他の支援機関では買い手が見つからず、「東京都事業承継・引継ぎ支援センター」からTRANBIを紹介されて登録しました。
TRANBIの活用にあたっては、案件情報をできる限り正直に入力し、買い手が事業を想像しやすいように工夫しました。また、申し込みがあった際には、できる限り翌日までに返信することを心がけました。
多忙な中でも効率的に対応できるよう、「売り手様向けM&Aガイド」に掲載されている返信用テンプレートを活用し、円滑なやり取りを実現しました。
また、ヘルプや他の成功事例を参考に、自分の案件が買い手に届きやすいよう工夫し、お知らせメールもオンにして情報収集を続けました。
その結果、目標の4倍である20件の申し込みがあり、不動産オーナーの承諾も得られた唯一の相手である学校法人へ、273万円での事業譲渡を成し遂げました。
※Kさんの成約インタビュー
「断られても諦めない!不可能と思われた認可外保育園を譲渡できた女性の強い信念」
家事代行事業買収事例(買い手:株式会社D・S社長)
複数のM&A経験を持つD社のS社長は、以前から家事代行事業に関心があり、TRANBIに掲載されていた15年実績のある案件(譲渡希望価格8,000万円)に注目しました。
S社長は、親交のあるM&Aアドバイザーに連絡を入れ、TRANBIの案件に関する交渉を託しました。
4社のコンペとなりましたが、M&Aアドバイザーとの連携やS社長の経営者としての実績、人柄や信頼性が決め手となり、4,500万円での買収に成功しました。
※S社長の成約インタビュー
「家事代行事業を4500万円でM&A!買い手として譲れない『3つの条件』とは」
エステサロン買収事例(買い手:M&A仲介会社A社)
M&A仲介会社A社は、新規でのエステサロン開業を検討していた際、TRANBIで理想的な案件を発見し、すぐに交渉に入りました。
デューデリジェンスで高額回数券販売による「隠れ債務」が判明しましたが、改善可能と判断し、最終的に譲渡金額0円での買収をしました。
A社は、新規立ち上げに比べ、M&Aがコストと時間を大幅に削減できたと強調しています。
※A社の成約インタビュー
「前払いビジネスの買収は要注意!事業譲渡で見落としがちな”隠れ債務”とは?」
事業譲渡に関するよくある質問

Q. 個人事業主でも事業譲渡はできますか?
A. はい、可能です。法人だけでなく、個人事業主も事業譲渡を行うことができます。譲渡する対象は、店舗や設備といった有形資産だけでなく、顧客リスト、取引先との関係、技術やノウハウ、ブランドイメージといった無形資産も含まれます。手続きの進め方は法人の場合とほぼ同様です。
Q. 従業員の雇用契約はどうなりますか?転籍を拒否された場合は?
A. 事業譲渡の場合、従業員の雇用契約は自動的には引き継がれません。買い手企業が従業員の雇用を継続するためには、従業員ごとに同意を得て、新しい雇用契約を結ぶ必要があります。 もし従業員が転籍を拒否した場合、その従業員は元の会社(売り手企業)に残留することになります。売り手企業は、その従業員の新たな配属先を検討するなどの対応が必要です。
Q. 会社の負債や借入金も引き継がれますか?
A. 事業譲渡の大きな特徴は、譲渡する資産や負債を契約によって個別に選択できる点です。したがって、負債や借入金は自動的に引き継がれません。どの資産を譲渡し、どの負債を引き継ぐかは、売り手と買い手の間の交渉と契約内容によって決まります。
Q. 譲渡価格はどのように決まりますか?相場はありますか?
A. 最終的な譲渡価格は、当事者間の交渉によって決定されます。その交渉のベースとなるのが企業価値評価です。一般的には、譲渡対象となる資産の時価(時価純資産)に、ブランド力や技術力といった無形の価値(のれん代・営業権)を上乗せして算出されます。
のれん代は明確な相場があるわけではなく、業界の動向、事業の将来性、買い手とのシナジー効果などによって大きく変動します。
Q. 秘密は守られますか?従業員や取引先にいつ伝えるべき?
A. はい、秘密は厳守されます。M&Aの交渉を始める際には、まず秘密保持契約(NDA)を締結するのが一般的です。
これにより、検討段階の情報が外部に漏れることを防ぎます。 従業員や取引先へは、最終契約締結後に公表するのが一般的です。早すぎる公表は、従業員の不安や取引先の混乱を招く可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
Q. 事業譲渡にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 規模や内容によりますが、一般的には半年~1年ほどかかるケースが多いです。
専門家への相談から始まり、譲渡先の選定、トップ面談、基本合意、デューデリジェンス(買収監査)、最終契約の締結、そして事業の引き継ぎまで、多くのステップを踏むため、ある程度の期間が必要となります。
まとめ
事業譲渡は、会社が営む『事業』を他社に売却する方法です。
一つの事業を売却したい場合や、物資と人材を資産と切り離したい場合にも活用できます。
手続きが複雑になるため、簡易な方法を模索しているときは『株式譲渡』を利用するケースが多いでしょう。
他の譲渡方法とはメリット・デメリットが異なるため、手続きの流れを確認しておくのが大切です。







