
M&Aが従業員に与える影響と最適な対応策|説明タイミング・退職リスクを徹底解説
M&Aで従業員は不安になりがち。雇用承継の基礎、説明のタイミング、待遇や異動の影響、反対への向き合い方、PMIの勘所まで“人”に効く実務をまとめました。M&Aで従業員は不安になりがち。雇用承継の基礎、説明のタイミング、待遇や異動の影響、反対への向き合い方、PMIの勘所まで“人”に効く実務をまとめました。


M&Aの実施が決まった際、「従業員にどう説明すれば不安や反発を避けられるか」「優秀な人材の離職を防ぐにはどうすればよいか」と悩む経営者や担当者も多いでしょう。M&Aの成功は、統合後の事業を支える従業員の理解と協力にかかっています。
本記事では、M&Aが従業員の雇用や待遇にどのような影響を及ぼすのかを、法的な基本ルールとともに分かりやすく解説します。
また、従業員にとってのメリット・デメリットや、説明のタイミング・内容についても具体的なステップで解説します。
Mこの記事を最後までお読みいただくことで、M&Aにおける従業員対応の要点を深く理解し、不安を最小限に抑え、円滑な組織統合を実現するための具体的な道筋を描けるようになるでしょう。
M&A後の従業員扱いの基本ルール

M&A実施時の従業員の雇用契約の扱いは、採用するM&Aのスキーム(手法)によって異なります。
ここでは、代表的なM&Aスキームごとの違いと、どのような手法であっても共通する法的なルールや企業の義務について、基礎から分かりやすく解説します。
M&Aスキームで異なる雇用契約の承継
M&Aの手法によって、従業員の雇用契約が買い手企業に引き継がれるプロセスは異なります。
特に「株式譲渡」と「事業譲渡」では、従業員の同意の要否など手続きが大きく異なるため、その違いを正確に理解しておくことが重要です。
株式譲渡は、会社のオーナー(株主)が変わるだけで、会社(法人格)そのものは存続します。
そのため、雇用主は変わらず、従業員の雇用契約は原則としてそのままの条件で継続されます。
一方、事業譲渡は、会社の事業の一部または全部を切り出して売買する手法です。
この場合、従業員の雇用契約を買い手企業へ承継させるには、一人ひとりから個別に同意を得る必要があります。
本人の同意なく自動的に転籍させることはできません。もし従業員が転籍に同意しない場合、原則として売り手企業との雇用関係が継続されます。

労働法による従業員の保護と企業の義務
M&Aの形態に関わらず、日本の労働法では従業員の権利が手厚く保護されており、企業は様々な義務を負うことになります。経営判断を優先して法的義務を軽視すると、深刻な労使トラブルに発展するおそれがあります。
まず、労働契約法では、企業が客観的に合理的な理由なく、社会通念上相当と認められない限り、一方的に従業員を解雇することを禁じています。M&Aを理由にした安易な解雇は、不当解雇と判断される可能性が高いです。
また、給与の引き下げなど、従業員にとって不利益な労働条件の変更を行う際には、原則として一人ひとりから個別の同意を得る必要があります。
企業には、従業員が安全に働ける環境を整える「安全配慮義務」や、M&Aの背景や目的を誠実に説明する「説明責任」も求められます。
参考 : 厚生労働省 ー 人を雇うときのルール


M&Aが従業員にもたらす主なメリット

M&Aは環境の変化に不安を感じる一方で、キャリアや待遇面でのメリットも期待できます。
ここでは、雇用の継続からキャリアアップ、労働条件の改善といった、従業員が享受できる具体的な利点について、より詳しく解説します。
① 雇用が継続され安定した働き方が維持できる
特に後継者不足や経営不振がM&Aの理由である場合、従業員にとって最大のメリットは雇用の継続です。
M&Aによって経営基盤が安定した企業の傘下に入ることで、倒産や事業縮小による失業のリスクから解放されます。
雇用契約がそのまま引き継がれることで、従業員は安心して働き続けることができ、安定した生活基盤の上で将来設計を立てやすくなります。
② 待遇や福利厚生が改善される可能性がある
買い手企業が、売り手企業よりも規模の大きい企業である場合、給与や賞与といった金銭的な待遇が向上するケースは少なくありません。
また、退職金制度や確定拠出年金、住宅手当、育児・介護支援制度など、より充実した福利厚生制度が適用されることも期待できます。
労働環境が改善されれば、従業員のエンゲージメントや仕事への満足度向上に直結するでしょう。
③ キャリアアップや昇進の機会が広がる
事業規模の拡大や新規事業への進出は、従業員に新たなキャリアの可能性を提示します。
新たな部署や事業領域に挑戦することで、多様なスキルや専門性を磨けるでしょう。
また、グループ内公募制度などを活用して、より責任のあるポジションに就くなど、成果次第で昇進の機会も増え、従業員の成長意欲を力強く後押しします。
④ 大企業グループの信用力を得られる
大手企業のグループの一員となることで、企業の社会的信用力は大きく向上します。
これにより、大規模なプロジェクトに参画できたり、金融機関からの融資が受けやすくなったりと、事業展開の幅が広がります。従業員も、安定したブランドの下で働く誇りと安心感を得られ、仕事への意欲が高まります。
⑤ 教育や研修制度の充実が期待できる
大手企業は、人材育成のための体系的な教育・研修プログラムを備えていることが多く、M&Aによって従業員がこれらを利用できる可能性が広がります。
階層別研修やスキルアップ研修、資格取得支援制度などが整っていれば、従業員は自身の能力を計画的に伸ばし、市場価値を高めることができるでしょう。
M&Aが従業員にもたらす主なデメリット・影響
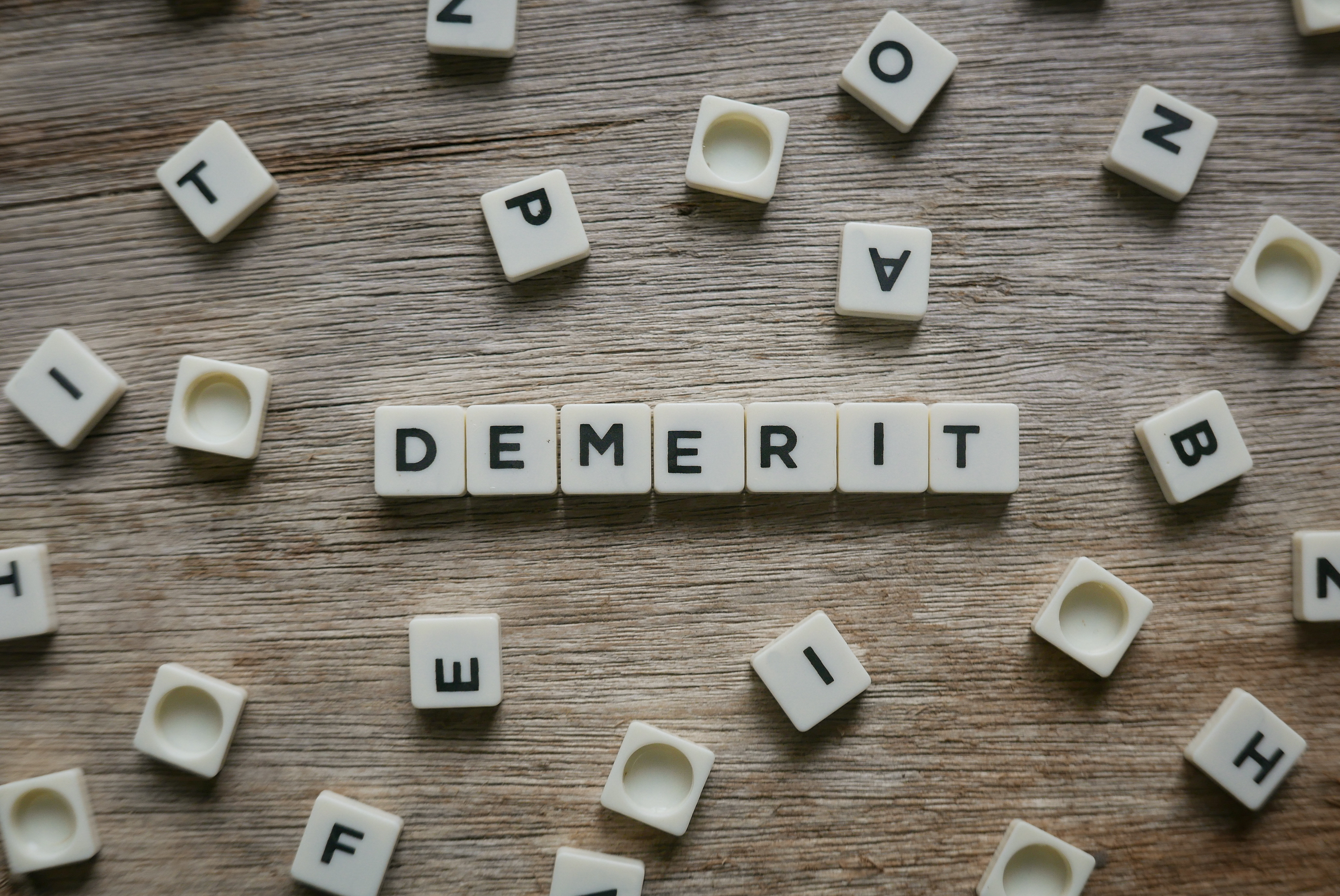
M&Aは多くのメリットがありますが、一方で従業員に変化や負担を与える側面もあります。
ここでは、勤務地や待遇の変更、企業文化の違いによるストレスなど、従業員が直面しうるデメリットや具体的な影響について、事前に把握しておくべき点を解説します。
① 勤務地や配属先が変更される可能性がある
M&Aに伴う組織再編や、本社機能・工場の統廃合により、従業員の勤務地や所属部署が変更されることがあります。
場合によっては、本人の意に沿わない転居を伴う異動もあり得ます。
通勤時間の増加や単身赴任、慣れない土地での生活は、本人や家族にも大きな負担となる可能性があります。
② 待遇や評価制度が変わることがある
M&A後は、多くの場合、買い手企業の給与体系や人事評価制度に統一されていきます。
これにより、昇給ルールや賞与基準が変わり、従来高く評価されていた従業員が、新基準では同様の評価を得られない可能性があります。
年功序列から成果主義へ移行するなど、制度変更が結果的に待遇の悪化につながる可能性もあります。
③ 企業文化の違いでストレスを感じる
企業には長い年月をかけて形成された独自の社風や価値観、仕事の進め方があります。
M&Aで異なる企業文化が融合する過程では、従業員が強い戸惑いやストレスを感じることは少なくありません。
例えば、意思決定のスピード感の違い、会議の進め方、コミュニケーションの取り方など、これまで「当たり前」だったことが通用しなくなることで、人間関係の軋轢や業務上の混乱が生じる可能性があります。
④ 転籍や退職を求められる場合がある
事業譲渡において、買い手企業への転籍に同意できない場合や、M&A後の人員整理を目的として、希望退職者の募集や退職の打診が行われる場合もあります。
本人の意思は尊重されますが、環境変化やキャリアプラン不一致を理由に退職を選ぶ従業員が出る可能性もあります。
⑤ 将来への不安から離職が増えることがある
労働条件や職場環境の変化、新しい経営方針に対する漠然とした不安から、M&Aをきっかけに転職を考える従業員が出てくることは避けられません。
特に、企業の将来を担うべき優秀な人材や、顧客との強い信頼関係を築いているベテラン社員が流出してしまうと、企業の競争力そのものが大きく低下してしまいます。情報不足は従業員の不信感や憶測を呼び、組織全体の士気を下げる要因となります。

従業員に対するM&Aの開示方法と説明タイミング

M&Aを成功に導くためには、従業員の不安を最小限に抑え、前向きな協力を得ることが不可欠です。
そのためには、適切なタイミングで、誠意ある説明を行うことが極めて重要になります。
ここでは、従業員への情報開示の最適な時期と、その際に伝えるべき内容、そして説明の重要性について解説します。
開示タイミングは基本合意後から最終契約前
従業員への情報開示は、情報漏洩のリスクと従業員の不安とのバランスを考慮し、一般的には、M&Aの基本合意(LOI)後から最終契約前に説明するのが望ましいとされています。
この段階であれば、M&Aの実現可能性が高まり、従業員に説明できる具体的な情報も固まってきているためです。
基本合意後に準備を進め、経営層や管理職へ個別に説明した後、全体説明会を行う段階的な進め方が一般的です。
従業員に対する説明の重要性・意義
従業員への説明は単なる情報共有ではなく、不安を和らげ安心感を与えるための重要なコミュニケーションです。
企業の真摯な姿勢を示すことで、従業員からの信頼と納得感を得ることができ、これが優秀な人材の離職を防ぐ最大の対策となります。
また、従業員がM&Aを自分事として捉え、協力体制を築くことは、M&A後の円滑な統合(PMI)に欠かせません。
説明会・個別面談で伝えるべき事項
従業員説明会やその後の個別面談では、従業員が最も知りたいであろう今後の処遇に関する具体的な情報を、誠実かつ透明性を持って伝えることが重要です。
具体的には、「雇用契約がどうなるか」「給与や退職金、福利厚生といった待遇の変更点」「勤務場所や配属先の見通し」「今後の業務内容や役割の変化」といった点を明確に説明する必要があります。また、M&Aの目的や背景、新しい経営方針、今後の大まかなスケジュール、そして従業員の相談窓口といったサポート体制についても丁寧に伝えることで、従業員の不安を払拭し、前向きな協力を引き出すことができます。

M&Aに反対する従業員への対応

M&Aを進める中では、変化への不安や経営陣への不信感から、従業員が反対するケースもあります。
しかし、法的に従業員の権利は保護されており、反対を理由とした解雇は認められません。
ここでは、従業員がM&Aに反対する真の理由を理解し、適切に対処するための方法を解説します。
従業員がM&Aに反対する主な理由
従業員がM&Aに反対する背景には、複合的な不安や懸念が存在します。
最も根源的な理由は、「雇用は維持されるのか」「給与や待遇が悪化するのではないか」といった自身の処遇に対する直接的な不安です。
加えて、新しい経営方針への不信感や、慣れ親しんだ文化・人間関係が失われることへの不安、将来のキャリアが見えにくくなる懸念などもあります。
こうした不安は、情報共有が不足しているとさらに強まります。
従業員は簡単に解雇することはできない
日本の労働契約法では、労働者は手厚く保護されており、企業が「M&Aに反対したから」という理由で一方的に従業員を解雇することは、不当解雇として無効と判断される可能性が高いです。
仮に、事業の重複などを理由に人員整理が必要になったとしても、いわゆる「整理解雇」が有効と認められるには、「①人員削減の必要性」「②回避努力」「③人選の合理性」「④手続きの妥当性」という4つの要件を全てを満たす必要があります。この条件を満たすのは難しく、企業には慎重な対応が求められます。
従業員の意見のヒアリングと適切な対処方法
M&Aに反対する従業員に対しては、まずその意見を否定せず、反対の理由や不安を丁寧に聞き取ることが第一歩です。
一方的な説得ではなく、面談などを通して真摯に対話し、心情を理解する姿勢が大切です。
その上で、誤解があればそれを解き、現時点で伝えられる範囲の情報を誠実に共有し、共に新しい未来を考える姿勢を示すことが、信頼回復と円滑な統合の鍵となります。


まとめ
M&Aを真の成功に導くためには、財務や法務だけでなく、最も重要な資産である「人」、つまり従業員の存在が欠かせません。
従業員一人ひとりが抱える将来への不安や懸念に真摯に向き合い、適切な情報提供と誠実な対話を通じて、揺るぎない信頼関係を構築することが、経営者にとって最も重要な責務と言えます。
M&Aのプロセスにおいては、法的な義務を遵守することはもちろん、従業員のこれまでの貢献に敬意を払い、一人ひとりのキャリアや人生に配慮する姿勢が強く求められます。
周到な準備、丁寧な説明、統合後のフォローアップを徹底することで、優秀な人材の離職を防ぎ、両社の強みを生かした組織づくりが可能になるでしょう。






