
個人で後継者のいない会社を買う方法と注意点|メリット・デメリット・探し方を徹底解説
個人で後継者不在の会社を買う方法を徹底解説。スモールM&Aの探し方・相場と資金調達、買収の流れ、DD・契約〜PMI、注意点と失敗回避を事例とQ&Aで網羅。
- 05 後継者のいない会社を個人で買う際に失敗しないポイント
- ポイント①:財務状況を正確に把握する
- ポイント②:事業運営後のサポート体制確保
- ポイント③:譲渡契約・条件内容の明確化
- ポイント④:買収後の事業計画・経営ビジョンを明確に
- 06 個人が後継者のいない会社を買う流れと必要準備
- STEP1:買収目的と事業の方向性整理
- STEP2:買収候補企業の選定と情報収集
- STEP3:財務・法務デューデリジェンス
- STEP4:資金計画・予算設定
- STEP5:交渉・契約・引き継ぎ
- 08 TRANBIを活用して個人が後継者のいない企業を買収した事例
- 事例①:会社員との二足の草鞋!300万円でキックボクシングジムのオーナーに
- 事例②:ベテラン会社員が「経営者の思い」を引き継いだ、印刷代行サービスの事業承継
- 事例③:「将来の夢への第一歩」20代女性が110万円で挑戦したレンタルスペース経営


「後継者がいない会社を買収して事業を伸ばしたい」と思っても、具体的な方法やリスクが分からず踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
基礎知識と十分な準備があれば、個人でも会社を買収して経営者として成功することは可能です。
本記事では、後継者のいない会社を個人が買うことのメリット・デメリットから、会社の探し方、具体的な買収の流れ、そして失敗を回避するための重要なポイントまで、専門的な内容もかみ砕きながら網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、M&Aのプロセス全体に対する解像度が格段に上がり、自信を持って第一歩を踏み出せるようになるでしょう。
個人が後継者のいない会社を買うことはできる?

結論から言うと、一定の資金力や経営に関する知識、そして何より事業への情熱があれば、個人でも後継者のいない会社を買収し、その経営を引き継ぐことは可能です。
現在、日本の中小企業は経営者の高齢化と深刻な後継者不足という大きな課題に直面しています。
優れた技術や安定した顧客基盤を持ちながらも、担い手がいないために廃業を選択せざるを得ない企業が後を絶ちません。
このような状況を背景に、親族や社内の従業員ではなく、第三者が事業を引き継ぐ「第三者承継」を目的とした個人によるM&A(スモールM&A)の市場が、国による後押しもあり急速に拡大しています。
買収対象は、引退を考える中小企業が中心で、「株式譲渡」や「事業譲渡」といった方法で経営権を取得します。
個人の買い手にとっては、ゼロから事業を立ち上げるよりもリスクを抑えて経営者になれる、またとないチャンスが広がっているのです。


後継者のいない会社を個人が買うメリット

後継者のいない会社を個人が買うことには、買い手・売り手の双方に大きなメリットがあります。
これは単なる売買にとどまらず、双方の未来をより良くする戦略的な手段となります。
ここでは、それぞれの立場から見た具体的なメリットを、より深く掘り下げて解説します。
買い手のメリット
買い手にとって、後継者のいない会社を買うことには多くのメリットがあります。
特に、ゼロから起業する場合と比較すると、時間、コスト、リスクの各面で大きなアドバンテージを得ることができます。
開業コストとリスクの抑制
最大のメリットは、ゼロから起業する場合の時間的・金銭的コストと、それに伴う不確実性というリスクを大幅に抑制できる点です。
すでに事業基盤が整っているため、失敗のリスクを抑えながら経営者としてのキャリアをスタートできます。
既存の経営資源の活用
従業員のノウハウ、安定した顧客基盤、必要な設備や一部の許認可をそのまま引き継ぐことができます。
これにより、創業期に最も困難とされる「最初の実績作り」を省略できるのです。
準備期間の短縮と信用の承継
会社の登記やオフィス契約といった煩雑な手続きが不要なだけでなく、金融機関との取引実績や取引口座など、法人としての信用基盤を活用できる
場合があります。
ただし、経営者交代時には金融機関による再審査や条件見直しが行われることが一般的であり、必ずしも融資条件がそのまま維持されるわけではありません。
それでも、新規創業と比べれば、一定の信用履歴を持つ法人としてスタートできる点は大きな利点です。
社会貢献性の高さ
後継者不在で困る企業を引き継ぎ、技術や文化を次世代へ残すことには大きな社会的意義があります。
事業を通じて地域経済に貢献できる点は、経営者としての大きなやりがいにつながるでしょう。
売り手のメリット
会社を売却する側の経営者にとっても、廃業ではなくM&Aを選択することには、金銭的なメリットだけでなく、精神的な満足感にもつながる多くの利点があります。
廃業の回避と雇用の維持
最も大きなメリットは、廃業という寂しい選択を避け、長年築いてきた会社や従業員の雇用を守ることができる点です。
長年築き上げてきたものを失うことなく、未来へ託すことができます。
創業者利益の獲得
廃業には多額のコストと手間がかかりますが、M&Aであれば、土地や設備といった有形資産はもちろん、ブランド価値や技術力といった目に見えない無形の資産も含めて事業全体を現金化し、引退後の生活資金
事業の成長・発展の可能性
買い手の持つ新しい視点や経営力、資金力が加わることで、自社がこれまで成し得なかった新たな成長や発展を遂げる可能性も生まれます。
買収後も事業が成長していく姿を見届けることができるのは、大きな喜びとなるでしょう。



後継者のいない会社を個人が買うデメリット・注意点

多くのメリットがある一方で、個人が後継者のいない会社を買う際には、特有のデメリットや慎重に進めるべき点も存在します。
買収後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、双方の視点からリスクを理解し、事前に対策を講じることが重要です。
ここでは、見落としがちな潜在的リスクや注意点を具体的に解説します。
買い手のデメリット・注意点
買い手は、M&Aの華やかな側面だけでなく、その裏に潜むリスクにも目を向ける必要があります。
特に、人やお金に関する問題は、買収後の経営を大きく左右します。
従業員や取引先との関係再構築
特に小規模な会社では、前経営者の個人的な人柄やリーダーシップに惹かれていた従業員や取引先も少なくありません。
経営者が変わることで、彼らとの信頼関係を一から築き直す必要があり、これには大きな労力と繊細なコミュニケーションが求められます。
簿外債務などの潜在的リスク
財務諸表に載らない簿外債務や将来の訴訟リスクを抱えている場合もあります。
事前のデューデリジェンス(企業調査)を徹底し、見えない負債のリスクを洗い出すことが、最大のリスクヘッジとなります。
企業文化のミスマッチ
長年かけて培われた独自の企業文化や暗黙のルールが、新しい経営者の価値観と合わない場合があります。
文化の違いはモチベーション低下や離職を招く恐れがあるため、買収前に組織風土を把握しておくことが重要です。
売り手のデメリット・注意点
売り手にとっても、M&Aは必ずしも理想通りに進むとは限りません。希望と現実の差を埋めるための準備と心構えが必要です。
希望条件での売却が困難な可能性
自社が長年かけて築いた価値と、買い手が客観的に評価する価値との間には、しばしば乖離が生じます。
これにより交渉が長引いたり、想定より低い価格での譲渡を余儀なくされることがあります。
買い手が見つからないリスク
自社の事業内容や財務状況によっては、理想的な買い手がなかなか見つからず、売却のタイミングを逃してしまうケースも少なくありません。
M&A市場における自社の客観的な立ち位置を理解しておくことが重要です。
企業文化や労働条件の変化への懸念
買収後に従業員の労働条件が悪化したり、大切にしてきた企業理念や文化が失われたりするのではないかという懸念は尽きないでしょう。
信頼できる買い手を見極め、雇用維持など譲れない条件を契約書に明記することが重要です。


後継者がいない会社の相場や価値の決まり方
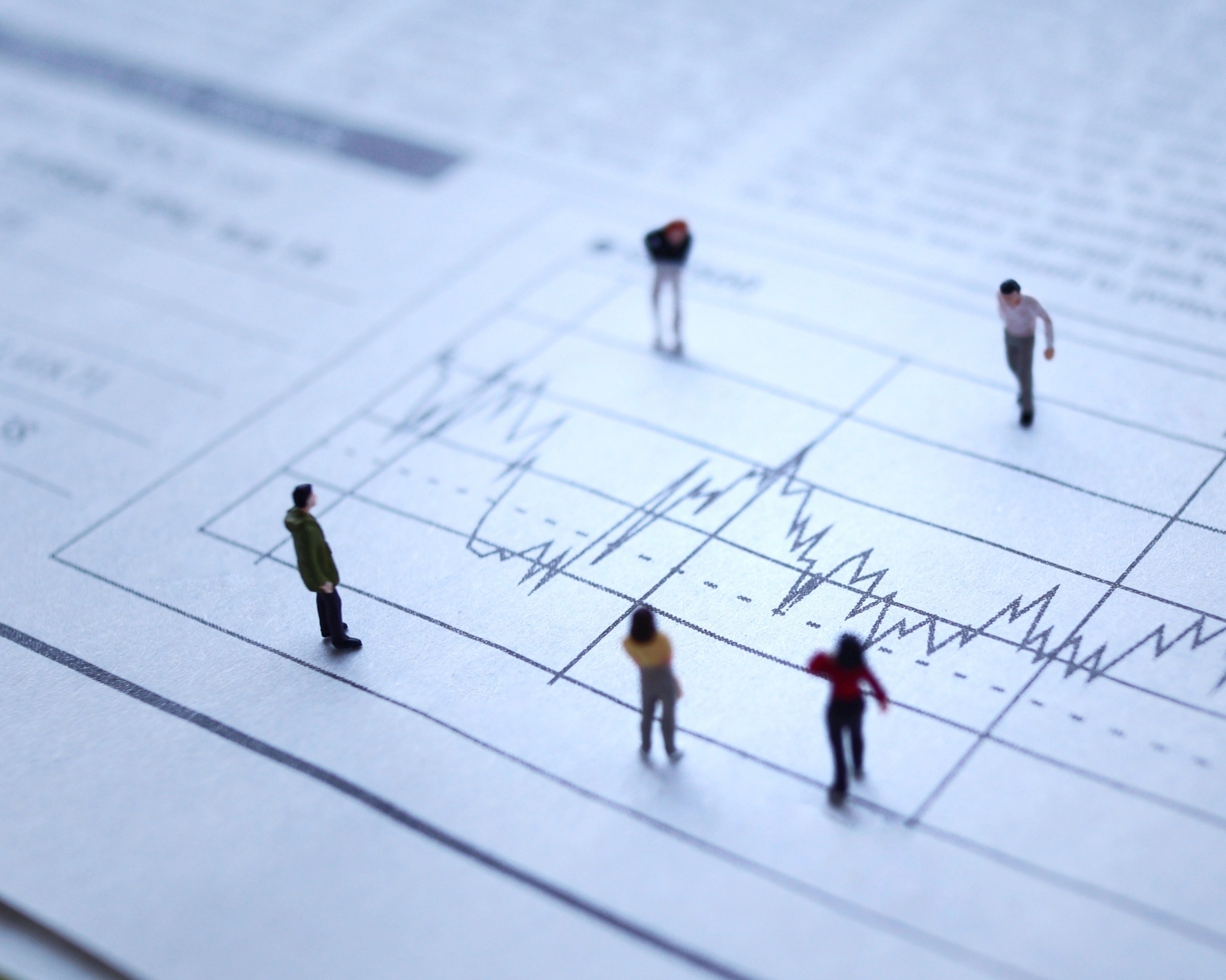
後継者不在の会社を検討する際、多くの人が最初に気にするのは「買収価格の相場」です。
しかし、上場株式のように明確な市場価格はなく、各社ごとに企業価値評価(バリュエーション)を行って算出します。企業価値評価には様々な手法がありますが、代表的なものに以下の3つがあります。
- 時価純資産法
資産から負債を差し引いた純資産額を基準に評価する方法です。客観的ですが、将来性は反映しづらい特徴があります。客観的で分かりやすい反面、将来の収益性が反映されにくいという特徴があります。 - DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法:
将来のキャッシュフローを予測し、割引率を用いて現在価値に換算する手法です。成長性を反映できますが、前提の精度が結果を左右します。成長性や収益性を反映できますが、予測の精度が価値を大きく左右します。 - 類似会社比較法
同業上場企業の株価指標(PERやEV/EBITDAなど)を参考に、相対的に価値を算出します。市場の評価を反映できるメリットがあります。
実務では複数の評価手法を併用し、資産・収益・業界動向・ブランド力などを総合的に考慮して最終的な価格を決めます。



後継者のいない会社を個人で買う際に失敗しないポイント

個人による会社買収は、大きな可能性を秘めている一方で、情報不足や準備不足から失敗に終わるケースも少なくありません。
成功確率を飛躍的に高めるためには、いくつかの重要なポイントを確実に押さえておく必要があります。
ここでは、買収を成功に導くために不可欠な4つのポイントを、より具体的に解説します。
ポイント①:財務状況を正確に把握する
失敗を避けるための絶対的な第一歩は、対象企業の財務状況を徹底的に調査し、その実態を正確に把握することです。
決算書の数値だけでなく、日々の資金繰りやキャッシュフローも確認することが重要です。
帳簿に載らない簿外債務や、将来発生しうる訴訟リスクなどがないかを確認する「デューデリジェンス(買収監査・企業調査)」は、時間と費用をかけても省略せず行いましょう。
さらに、数字だけでなく、キーパーソンとなる従業員へのヒアリングを通じて組織の風土を理解したり、ビジネスモデルの強み・弱みを分析したりといった定性的な情報も深く知ることが、買収後のスムーズな経営統合、すなわちPMI(Post Merger Integration)の成功につながります。
ポイント②:事業運営後のサポート体制確保
特に異業種からの参入や、初めて経営者になる場合は、買収後の事業運営で必ず壁にぶつかります。
そのため、前経営者と引き継ぎ期間や顧問契約の内容を事前に決め、業務内容や取引先との関係性を時間をかけてしっかりと学ぶことが重要です。
また、いつでも客観的なアドバイスを求められる専門家や支援機関との関係を構築しておくことも、精神的な支えとなります。
中小企業診断士・商工会議所・事業引継ぎ支援センターなど、公的支援機関を積極的に活用し、孤独な判断に陥らない体制を整えておきましょう。
ポイント③:譲渡契約・条件内容の明確化
売り手との間で合意した内容は、どんな小さな事項でも、必ず書面で残すことがトラブル防止の基本です。
特に、譲渡対象となる資産の範囲、従業員の雇用条件、競業避止義務(売り手が一定期間、同種の事業を行わないこと)、そして表明保証(開示した情報が真実かつ正確であることの保証)など、重要な条件は契約書に具体的に明記しましょう。
口約束は絶対に避け、隠れた債務が発覚した場合の補償に関する取り決めなども、弁護士などの専門家によるリーガルチェックを受け、法的に有効な形で契約を締結することが不可欠です。
ポイント④:買収後の事業計画・経営ビジョンを明確に
買収はゴールではなく、新たな経営のスタートラインです。
買収後にどのような事業を展開し、会社をどのように成長させていきたいのか、明確な事業計画と経営ビジョンを持つことが成功の大前提となります。
具体的な数値目標や、買収後100日間の行動計画(100日プラン)などを策定し、それを既存の従業員や取引先と丁寧に共有することで、新しい経営体制への理解と協力を得やすくなります。
明確なビジョンは、変化に対する従業員の不安を希望に変え、組織に一体感を生み出す原動力となるでしょう。



個人が後継者のいない会社を買う流れと必要準備

個人が後継者のいない会社を買収するプロセスは、いくつかの明確なステップに分かれています。
それぞれの段階で適切な準備と的確な判断を行うことが、M&Aプロジェクト全体を成功に導きます。
ここでは、検討開始から引き継ぎ完了までの一連の流れを5つのステップに分けて、具体的に解説します。
STEP1:買収目的と事業の方向性整理
まず初めに、「なぜ自分は会社を買収するのか」「どのような事業を通じて社会に貢献したいのか」という根源的な目的を明確にします。
自身の経験やスキル、情熱を最大限に活かせる業界はどこか、どの程度の規模の事業を想定しているかなど、自己分析を通じて基本的な方針を固めましょう。
同時に、興味のある業界の市場動向や競合状況を調べ、事業の方向性を具体化していきます。
この軸がブレてしまうと、後の候補企業選定で判断が迷走し、時間を浪費する原因となります。
STEP2:買収候補企業の選定と情報収集
事業の方向性が固まったら、次に買収候補となる企業を探すフェーズに入ります。
近年では、オンラインのM&Aマッチングプラットフォームが充実しており、個人でも多くの案件情報を効率的に収集できます。
その他、全国に設置されている事業引継ぎ支援センターや、M&A仲介会社に相談するのも有効な手段です。
有望な候補が見つかったら、秘密保持契約(NDA)を締結した上で、詳細情報を開示してもらいます。複数の案件を比較検討し、自身の目的と戦略に最も合致する候補を絞り込んでいきましょう。
STEP3:財務・法務デューデリジェンス
有望な候補企業と基本合意を結んだ後、デューデリジェンス(DD:買収監査)を実施します。
これは、買収対象企業の価値やリスクを専門家の視点から精査する、買収プロセスにおける最重要工程です。
財務DD(財務状況の調査)や法務DD(法的リスクの調査)に加え、事業DD(ビジネスモデルや市場競争力の調査)も行います。
財務諸表の分析だけでなく、実際に現地を訪れてオペレーションを確認したり、経営者や従業員にヒアリングを行ったりすることも重要です。
公認会計士や弁護士といった専門家の力を借りて、徹底的に調査を行いましょう。
STEP4:資金計画・予算設定
デューデリジェンスと並行して、買収に必要な資金計画を具体化させます。
必要な資金は、会社そのものの購入費用(譲渡価格)だけではありません。
買収後の事業運営に必要な運転資金や、不測の事態に備えるための予備費も十分に考慮に入れる必要があります。
自己資金で不足する場合は、日本政策金融公庫の事業承継・集約・活性化支援資金などの公的融資や、民間金融機関からの融資を活用します。
STEP5:交渉・契約・引き継ぎ
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な譲渡条件について売り手と交渉を行います。
価格はもちろん、従業員の雇用維持や引き継ぎ期間、前経営者の処遇など、細部にわたる条件を詰め、双方が合意に達したら、最終契約を締結します。
契約締結後は、いよいよ経営の引き継ぎ期間です。前経営者から業務や取引関係を丁寧に引き継ぎ、従業員や顧客の不安を払拭しながら、スムーズな経営移行を目指します。





後継者がいない会社を個人が探す方法

後継者のいない会社を買収したくても、「どのように探せばいいのか」と迷う人も多いでしょう。
幸い、近年は個人でも効率的に案件を探せるプラットフォームやサービスが非常に充実しています。
ここでは、探し方の全体像を最初に示し、M&Aマッチング・仲介・公的機関の3分類で整理しました。
主なサービスの紹介と特徴・比較
後継者のいない会社を探す主な方法として、以下の3つの選択肢が挙げられます。
- M&Aマッチングプラットフォーム
オンライン上で売り手と買い手が直接情報を検索し、コンタクトを取れるサービスです。匿名交渉が可能で手数料が安い反面、交渉は自己責任となります。 - M&A仲介会社
専門アドバイザーが案件探しから契約まで一貫支援してくれます。安心感はありますが手数料が発生します。 - 事業引継ぎ支援センター
国の公的機関で、全国に窓口があり無料相談可能。中立的立場で地域案件に強いのが特徴で、最初の相談窓口として有用です。
おすすめのM&Aマッチングプラットフォーム
後継者を探す方法は多岐にわたりますが、中でも個人が利用しやすいのがオンラインのM&Aマッチングプラットフォームです。
その代表格として「TRANBI(トランビ)」が挙げられます。
TRANBIは、国内最大級の事業承継・M&Aプラットフォームであり、数多くの案件が登録されています。
利用者が多く、個人でも挑戦しやすい数百万単位の小規模な案件から、数億円規模の案件まで幅広く探せるのが特徴です。
売り手と買い手が直接交渉できるシステムになっており、仲介会社を介さずにスピーディーに話を進めることも可能です。また、必要に応じて専門家紹介やサポートも利用できます。
後継者のいない会社を探す第一歩として、まずはTRANBIなどに会員登録して公開案件の傾向・相場観を把握し、希望条件を言語化することを推奨します。


TRANBIを活用して個人が後継者のいない企業を買収した事例

事例①:会社員との二足の草鞋!300万円でキックボクシングジムのオーナーに
上場企業で経営企画に携わるA氏は、議員秘書時代に後継者不足による廃業を目の当たりにした経験から、事業承継に強い関心を抱いていました。 会社員を続けながら経営者としての視点も養いたいと考え、「リーズナブルで効率的に事業を引き継げる」個人M&Aの可能性に注目します。
A氏は2年ほどTRANBIを閲覧し、「従業員を引き継げて、ある程度自走しているスモールな店舗ビジネス」という明確な軸で案件を探し続けました。 そして、自身の群馬県への転勤というプライベートな変化と、同県内のキックボクシングジムの売却案件という、またとないタイミングの巡り合わせが訪れます。その結果、転勤先と案件の所在地が一致し、意思決定がしやすい条件がそろいました。 売り手である元K-1選手が「次の事業に専念したい」という純粋な動機であることを面談で確認し、迅速かつ誠実な対応で信頼関係を構築。 競争率の高い案件でしたが、見事に独占交渉権を獲得し、300万円での事業譲渡を成功させました。
現在、A氏は「会社員としての経営視点と、店舗オーナーとしてのお客様目線を体得することは、いいシナジーを生む」と実感しています。 本業と両立できる事業を、タイミングを逃さずに見つけることの重要性を示すこの事例。TRANBIの豊富な案件数と情報量が、こうした幸運なマッチングを可能にしています。

事例②:ベテラン会社員が「経営者の思い」を引き継いだ、印刷代行サービスの事業承継
物流企業で28年間キャリアを積んだB氏は、サラリーマンとして一区切りついたことを機に、自身の新たな挑戦の場を模索していました。 単に事業を買うのではなく、「経営者の思いを引き継ぐ」ことをテーマに、自身の営業経験が活かせる事業承継案件を探していました。
出張の合間にTRANBIで案件を探すのが日課だったB氏は、気になる案件を見つけては「自分が経営者ならどうするか」とシミュレーションを重ねていました。 そんな中、高齢の経営者が後継者不足に悩み、学生顧客との温かい関係性を誰かに託したいと願う印刷代行業者の案件を発見します。
「跡を継いでもらいたいと思うからには、今の経営者の思いがある」。 そう考えていたB氏にとって、まさに理想の案件でした。
店舗を訪問し、経営者の人柄や学生たちに愛される光景を目の当たりにしたことで、彼の買収意思は100%固まりました。 競合候補もいる中、迅速な資金繰りと熱意で交渉を進め、最初の面談からわずか半月で成約。
これは、無形資産(顧客関係・地域性・経営者の思い)も評価軸として重要である点を示す事例です。 経営者の「思い」という無形の資産に共感し、それを引き継ぐ覚悟を持つことで、売り手・買い手双方にとって最高のM&Aが実現します。

事例③:「将来の夢への第一歩」20代女性が110万円で挑戦したレンタルスペース経営
コンサルタントとして働く20代のC氏は、将来海外でゲストハウスを運営するという大きな夢を持っていました。 その夢への第一歩として、まずはリスクを抑えながら事業運営のノウハウを学べるスモールM&Aに挑戦することを決意します。
彼女が活用したのは、国内最大級のM&AプラットフォームTRANBI。
副業でも運営しやすいレンタルスペース事業に絞り、TRANBIで豊富な案件を比較検討しました。
最終的に選んだのは、自宅から自転車で駆け付けられる距離にあった神楽坂の案件。 収支が赤字状態だと判明しても、「どうすればビジネスを伸ばせるか考えるのがとても好きなんです。逆に楽しみだなと思いました」と、その挑戦を前向きに捉えました。
交渉の決め手は、彼女の熱意でした。 競合がいる中で、ゲストハウス運営という将来の夢と、その足がかりにしたいという「覚悟」を率直に伝えたことで、売り手の心を動かし、信頼を勝ち取ります。
この事例は、M&Aが独立や起業への有効なステップとなり得ることを教えてくれます。
「泳げるようになりたいなら、まずプールに飛び込む」という彼女の言葉通り、TRANBIは、未来への情熱を持つ挑戦者が第一歩を踏み出すための最適な舞台を提供します。



個人による後継者のいない企業の買収に関するよくある質問

個人での会社買収を検討する中で、多くの方が同じような疑問や不安を抱きます。
ここでは、特によく寄せられる質問とその回答を、より実践的なアドバイスを交えてQ&A形式でまとめました。
ぜひ参考にしてください。
個人での買収は本当に可能?必要な資格や条件は?
はい、個人での買収は十分に可能で、国家資格も不要です。
目安として自己資金+不足分は公的融資で補う計画を用意し、初年度の運転資金3〜6か月分を確保します。
買収資金は自己資金のほか、日本政策金融公庫などの公的融資を積極的に活用することも可能です。経営能力については、必ずしも同業種の経験が必要なわけではなく、前職で培ったマネジメント経験やマーケティングスキルなど、自身の強みをどのように活かせるかが問われます。
どんな業種・会社規模なら個人向けか?
個人向けとしては、オーナーの力量が事業の成長に直結しやすい、比較的小規模な事業が適していると言えます。具体的には、地域ニーズが安定し、人の交代で品質が維持しやすい小規模サービス業(学習塾・フィットネス・理美容・修理業等)や小規模製造・小売が適しています。
重要なのは、流行り廃りの激しいビジネスではなく、地域に根差した安定的なニーズがある事業を選ぶことです。
買収金額で言えば、数百万~数千万円程度の「スモールM&A」と呼ばれる規模の案件が中心となります。
事前準備で一番重要なチェックポイントは?
最も重要なのは、徹底した「デューデリジェンス(企業調査)」に尽きます。
財務状況はもちろん、事業の将来性、従業員や取引先との関係、法的なリスクなど、あらゆる側面から対象企業を深く、客観的に理解することが失敗を避ける最大のポイントです。
特に、財務諸表の数字の裏にある実態、例えば特定の取引先に売上を依存していないか、キーパーソンが退職するリスクはないかなど、ビジネスの根幹に関わるリスクを見抜くことが重要になります。
売り手とトラブルになりやすい条件は?
従業員の処遇(特に雇用維持と給与)、譲渡後の役員の残留、そして譲渡価格の3点が、最もトラブルになりやすいポイントです。
特に、長年連れ添った従業員の将来を案じる売り手は多く、彼らの雇用条件を維持することは非常に重要な交渉事項となります。
また、譲渡価格の算定根拠について双方の認識が異となると、交渉が感情的になり、難航する原因となります。
契約前に細部までしっかり話し合い、曖昧な点を残さずに全てを書面で合意することが不可欠です。
万一失敗した場合のリスク回避策は?
最も有効なリスク回避策は、交渉の初期段階で「撤退ライン(価格上限、必要粗利、主要人材の継続、解約条項の有無等)」を明確に決めておくことです。デューデリジェンスの過程で、事前に想定していなかった重大なリスク(例えば多額の簿外債務など)が発見された場合には、それまでにかけた時間や労力が惜しくても、勇気を持って交渉を中止する決断が必要です。
また、買収資金をすべて自己資金で賄うのではなく、融資を適切に活用することで、万一事業がうまくいかなかった場合に個人の資産がすべて失われるリスクを限定的にすることも、賢明なリスク管理の一環と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、個人が後継者のいない会社を買収する方法について、メリット・デメリットから具体的な流れ、成功のポイントまでを、一歩踏み込んで網羅的に解説しました。 後継者不足が社会問題となる現代において、個人による事業承継M&Aは、買い手にとってはリスクを抑えて経営者になるまたとないチャンスであり、売り手にとっては大切に育てた事業と従業員の未来を守るための有効な手段です。
成功の鍵は、デューデリジェンスをはじめとする徹底した事前準備と、買収後の未来を描く明確な経営ビジョンにあります。
そして、この複雑なプロセスを独力で進めるのではなく、M&A仲介会社や事業引継ぎ支援センターは相談中心で、地域によりマッチング機能の範囲が異なります。民間サイトと併用すると効率的です。
本記事で得た知識を羅針盤に、ぜひ貴社の成長戦略の一つとして、後継者のいない会社の買収という選択肢を真剣に検討してみてはいかがでしょうか。







