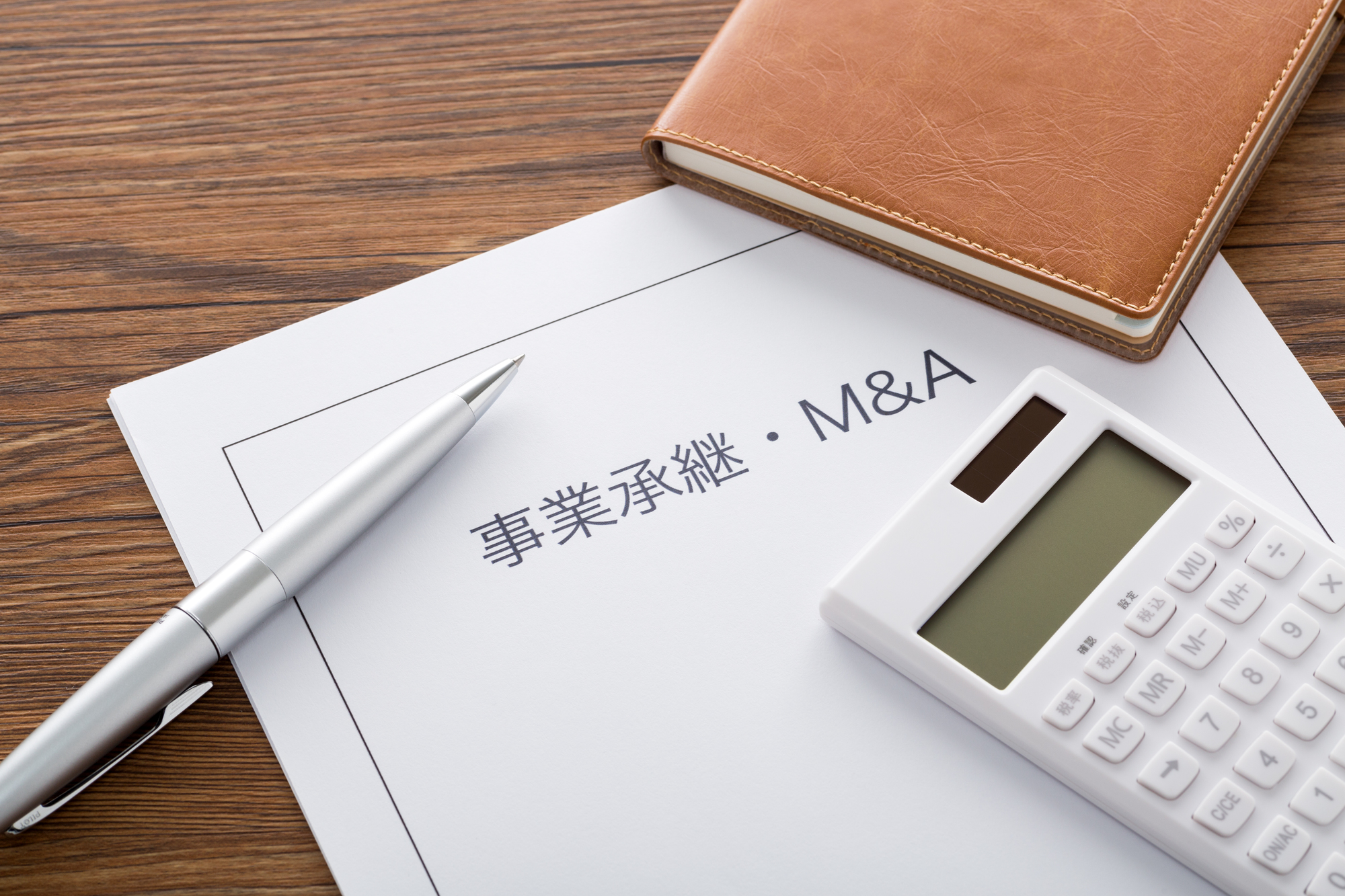社会福祉法人のM&A完全ガイド|スキーム・相場・事例・注意点まで徹底解説
株式譲渡不可の社会福祉法人で、どう再編を進める?許認可・評議員会/理事会決議、周知同意、DD/PMI、コンプライアンスまで実務視点で詳説。
- 04 厚生労働省|社会福祉法人「合併・事業譲渡マニュアル」の要点まとめ
- ① 合併と事業譲渡の基本的な手続き
- ② 行政庁への申請と承認の流れ
- ③ 職員と利用者への周知と同意手続き
- ④ 財務状況と資産引継ぎの確認事項
- ⑤ 不正な経営権譲渡防止と法令遵守
- 05 社会福祉法人M&Aの流れと手続き
- STEP1:事前準備・現状分析
- STEP2:相手法人・買い手候補の選定
- STEP3:デューデリジェンス・条件交渉
- STEP4:契約・承認・行政手続き
- STEP5:移行・引継ぎ・事後報告
- 07 社会福祉法人M&Aのメリット
- メリット①:経営基盤の安定化・継続性の確保
- メリット②:後継者問題の早期解決
- メリット③:資源・人材・ノハウのシナジー
- メリット④:財務・資金調達面の強化
- メリット⑤:サービス提供地域の拡大


社会福祉法人の後継者問題や事業の継続性に頭を悩ませ、M&Aを検討しているものの、一般企業との違いや特有の法規制が多く、どこに手をつければよいか分からないとお困りではありませんか。
社会福祉法人のM&Aは非営利性のため法的な制約が多く、株式会社のように株式譲渡によって経営権を移転させることはできません。そのため、主に「事業譲渡」というスキームが用いられるのが実情です。
本記事では、社会福祉法人M&Aの仕組みや、代表的なスキーム、厚生労働省のマニュアルに沿った手続きの流れ、費用相場、成功事例までを網羅的に解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、複雑な社会福祉法人のM&Aに関する知識が整理され、経営基盤の安定化や事業承継に向けた具体的な次の一手を打つための道筋が見えるはずです。
まずは、社会福祉法人M&Aの全体像を掴むために、本記事の内容をご確認ください。
社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉法に基づき設立された非営利の民間法人で、社会福祉事業の実施を目的としています。
その事業内容は、介護、障がい者支援、保育など、特に公共性が高く、地域社会にとって不可欠なサービスが中心となります。設立には所轄庁の認可が必要で、理事会や評議員会の設置が義務付けられています。そのため、運営は行政の厳格な監督下に置かれます。
また、非営利法人であるため、事業で得た利益を配当することはできず、法人の資産は本来の社会福祉事業に再投資されることが原則です。
社会福祉法人のM&Aとは ― 仕組みと背景
社会福祉法人におけるM&Aは、一般的な株式会社のM&Aとは根本的に異なります。
株式会社では株式譲渡で経営権を移転できますが、社会福祉法人では法人の所有権を売買することは法律で禁じられています。
しかし、近年の急速な高齢化やそれに伴う人材不足、後継者問題などを背景に、事業の継続性を確保する手段としてM&Aの手法を活用する法人が増えています。具体的には、株式譲渡ではなく「事業譲渡」という形で、事業の一部または全部を他の法人へ引き継ぐケースが主流です。
非営利性を保ちながら経営基盤を安定させる、現実的な選択肢となっています。
社会福祉法人M&Aの主要スキーム

社会福祉法人のM&Aでは、株式会社のように株式を譲渡する方法は使えないため、限られた手法の中から最適なスキームを選択する必要があります。
ここでは、代表的な3つのスキームについて、その概要と特徴を解説します。
事業譲渡スキーム
事業譲渡は、法人が運営する事業の一部または全部を、他の社会福祉法人などに譲渡する方法を指します。
法人の資産を直接売買できないため、このスキームが主流です。手続きを進める上では、譲渡する事業に関する許認可の継承や、利用者・職員への説明と同意が不可欠であり、関係省庁との綿密な調整が求められます。また、実質的な経営権の移転に伴い、理事長の交代や役員体制の変更が行われることも少なくありません。
合併・吸収スキーム
合併・吸収スキームは、複数の社会福祉法人が一つの法人格に統合される手法です。
吸収合併(既存法人が他方を吸収)や新設合併(新法人を設立して統合)といった方法があります。
このスキームのメリットは、法人格を一本化することで、経営資源の集約や運営の効率化を抜本的に図れる点にあります。
一方で、異なる理念や文化を持つ組織をまとめる過程は複雑で、職員の処遇や事業方針の調整には慎重な対応が必要です。
また、合併には所轄庁の認可が必須であり、手続きも煩雑になる傾向があります。


厚生労働省|社会福祉法人「合併・事業譲渡マニュアル」の要点まとめ

厚生労働省は、社会福祉法人のM&Aを円滑に進めるための指針として 「社会福祉法人の合併・事業譲渡等マニュアル」を公開しています。
このマニュアルは、手続きの透明性確保と法令遵守を目的としており、実務を進める上での重要な指針です。
① 合併と事業譲渡の基本的な手続き
マニュアルでは、まず社会福祉法に基づく合併・事業譲渡の法的根拠が明示されています。
その上で、合併契約書や事業譲渡契約書など、主要書類の作成手順や記載事項が具体的に示されています。
また、これらの契約を有効にするために必須となる、理事会および評議員会での議決手続きについても、招集方法や決議要件まで、確認すべき手順を記載しています。
② 行政庁への申請と承認の流れ
社会福祉法人のM&Aは、所轄庁の承認なしに進めることはできません。マニュアルでは、申請前に所轄庁へ事前相談を行うことの重要性を強調しています。
申請に必要な書類一覧や提出方法についても詳しく説明されており、承認までにかかる標準的な期間や、行政が審査する際の基準を事前に把握することができます。提出書類に不備があった場合の対応や、追加資料の準備方法も記載されており、円滑な許認可取得を支援します。
③ 職員と利用者への周知と同意手続き
M&Aは、職員やサービスの利用者に大きな影響を与える可能性があります。そのため、マニュアルでは、法人再編の目的や今後の運営方針を、関係者へ丁寧に説明することの重要性を示しています。
説明会の開催や通知文書の配布など、具体的な周知方法と適切な時期が示されています。
特に、利用者との契約を引き継ぐ際には、個別の同意取得と、その記録を適切に保存する方法を確立することが不可欠です。
④ 財務状況と資産引継ぎの確認事項
適正なM&Aのためには、対象となる法人の財務状況を正確に把握することが大前提です。
マニュアルでは、資産や負債、国や自治体からの補助金の状況などを精査し、一覧化することを求めています。
引継ぎに伴う税務や会計上の処理についても確認が必要です。客観的な評価を行うため、弁護士や会計士といった第三者の専門家によるデューデリジェンス(資産査定)の実施が推奨されています。
⑤ 不正な経営権譲渡防止と法令遵守
社会福祉法人の非営利性を守るため、不正な経営権の譲渡は厳しく禁じられています。
特に、理事長職や経営権を金銭で売買する行為は、法律違反にあたります。
マニュアルでは、こうした事態を防ぐため、内部統制や監査体制の強化策を具体的に整理し、法令やガイドラインに基づいたコンプライアンス体制を確立することの重要性を強調しています。
社会福祉法人M&Aの流れと手続き

社会福祉法人のM&Aは、一般企業のM&Aとは異なる特有の手続きが求められます。
ここでは、事前準備から引継ぎ完了までの一連の流れを5つのステップに分けて解説します。
STEP1:事前準備・現状分析
最初のステップは、自法人の現状を正確に把握し、M&Aの目的を明確にすることです。
財務状況、事業内容、組織体制(ガバナンス)を客観的に分析し、課題を洗い出します。
その上で、なぜM&Aが必要なのか、後継者問題の解決、経営基盤の強化など、目的を理事会や評議員会で共有し、内部での意思決定を行います。
この段階で、社会福祉法人特有の開示情報や調査すべきポイントを整理しておくことが重要です。
STEP2:相手法人・買い手候補の選定
次に、M&Aのパートナーとなる相手法人や買い手候補を探します。
買い手としては、事業規模の拡大を目指す他の社会福祉法人、介護・福祉分野へ参入したい民間企業などが想定されます。
候補先を探す方法としては、業界内のネットワークを活用するほか、専門のM&A仲介会社に依頼するのが一般的です。
仲介会社を選ぶ際は、社会福祉法人のM&A実績が豊富かどうかを確認することが成功の鍵となります。
STEP3:デューデリジェンス・条件交渉
候補先が見つかったら、本格的な交渉とデューデリジェンス(買収監査)に移ります。
デューデリジェンスでは、買い手側が売り手側の財務や法務、事業内容を詳細に調査し、リスクがないかを確認します。
特に社会福祉法人の場合、事業に必要な許認可が適切に取得・維持されているか、行政からの補助金の扱いはどうなっているか、といった点が重要な調査ポイントになります。この調査結果を踏まえ、譲渡価格や職員の処遇といった具体的な条件交渉が行われます。
STEP4:契約・承認・行政手続き
双方の条件が合意に達したら、事業譲渡契約書などの正式な契約を締結します。
契約締結後、売り手・買い手双方の法人で、理事会および評議員会の承認を得る必要があります。
この内部手続きと並行して、管轄する行政機関(都道府県や市町村など)へ許認可を申請します。
社会福祉法人のM&Aでは、行政手続きが最も重要で時間を要するため、専門家と連携し慎重に進める必要があります。
STEP5:移行・引継ぎ・事後報告
行政からの認可が無事に下りたら、最終段階である引継ぎ作業に入ります。
職員や利用者に対して、改めてM&Aの実行を正式に報告し、スムーズな業務の引継ぎ計画を実行します。また、不動産や預金口座などの資産名義の変更手続きも必要です。
すべての引継ぎ完了後、行政に事業完了を報告し、一連の手続きが終了します。
移行後も、運営体制が適切に機能しているか、定期的な監査や評価が必要です。



社会福祉法人M&Aの相場と費用|対価・手数料の全体像

社会福祉法人のM&Aを検討する際、譲渡対価や仲介手数料などの費用は無視できない重要なポイントです。
ここでは、費用の考え方や相場の全体像について解説します。
M&A対価の考え方と相場
社会福祉法人のM&Aにおける対価は、株式会社のように単純な企業価値評価で決まるわけではありません。
非営利法人であるため、法人解散時には所轄庁の認可を得て、他の社会福祉法人や公益法人に資産を帰属させるのが一般的です。そのため、純資産自体が譲渡対価になるわけではありません。
事業譲渡の場合、施設の収益性や利用者の数、専門人材の有無などが価格に反映され、適切な事業価値の見極めが必要となります。
仲介手数料・コストの目安
M&Aを進める際には、専門家である仲介会社への手数料が発生します。
手数料体系は会社により異なりますが、一般的に「着手金」と「成功報酬」で構成されます。
着手金は、M&Aの相手探しなどを正式に依頼する際に支払う費用で、数十万円から数百万円が目安です。
成功報酬は、M&Aが成約した際に支払うもので、取引価格に応じて一定の料率で計算される「レーマン方式」と呼ばれる報酬計算基準が広く採用されています。
このほか、弁護士や会計士への費用も別途必要になる場合があります。
役員・経営層への報酬・インセンティブ
社会福祉法人のM&Aにおいて、理事長や役員が退任時に、対価として直接金銭を受け取ることは原則禁止されています。
これは、法人の私物化を防ぎ、非営利性を担保するための重要なルールです。
ただし、退任する理事長などに対して、功労金として適正な範囲の退職金を支払うことは可能です。
金額は役員退職慰労金規程などに基づき、社会通念上妥当な範囲で決定する必要があります。不当に高額な報酬は行政から指摘を受けるおそれがあるため注意が必要です。


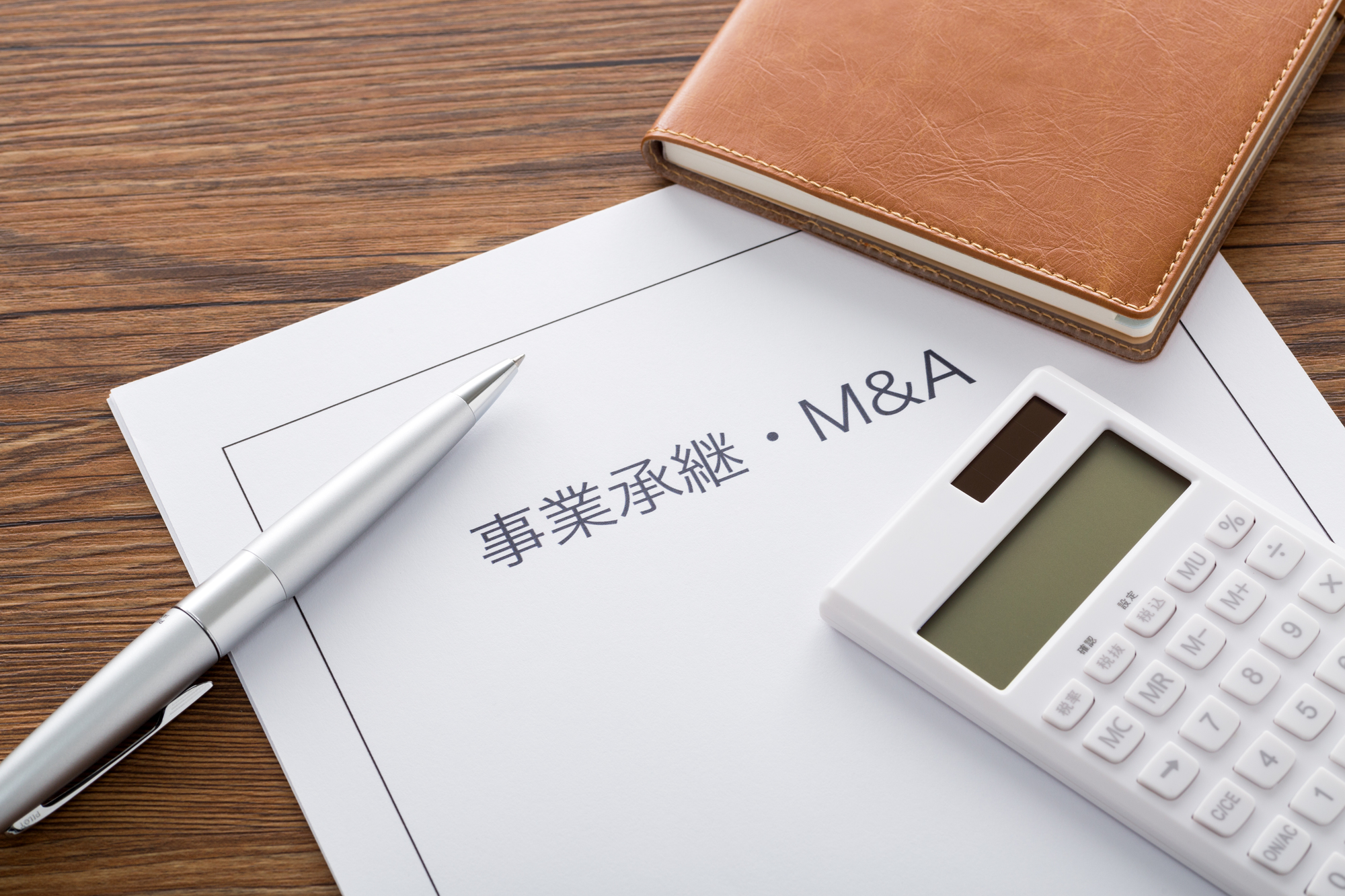
社会福祉法人M&Aのメリット

社会福祉法人がM&Aを活用することで、多くの経営課題を解決し、持続可能な運営体制を築くことが可能になります。
ここでは、M&Aがもたらす5つの主要なメリットを解説します。
メリット①:経営基盤の安定化・継続性の確保
M&Aによって規模の大きな法人や経営基盤の安定した企業の傘下に入ることで、財務状況が強化され、長期的に安定した経営が実現できます。
これにより、地域に不可欠な介護・福祉サービスを継続して提供でき、利用者の安心に繋がります。
また、経営が安定することで、職員の雇用を守り、安心して働ける環境を維持できるという大きなメリットもあります。
メリット②:後継者問題の早期解決
多くの社会福祉法人、特に創業者である理事長が高齢化している法人にとって、後継者の不在は事業継続を脅かす深刻な問題です。
M&Aは、この後継者問題を解決する有効な手段の一つです。
信頼できる第三者に法人を引き継ぐことで、経営者は安心して引退でき、事業や理念を次世代へ引き継ぐことができます。
メリット③:資源・人材・ノハウのシナジー
他法人との統合により、互いの強みを活かした相乗効果(シナジー)が期待できます。
例えば、大手法人が持つ先進的な運営ノウハウやICTシステムを導入することで、業務効率が飛躍的に向上することがあります。
また、人材交流を通じて専門知識やスキルを共有し、提供するサービスの質を高めることも可能です。これにより、利用者満足度の向上や、職員の専門性強化に繋がります。
メリット④:財務・資金調達面の強化
単独の法人では困難だった大規模な設備投資や新規事業への挑戦も、M&Aによって可能になる場合があります。
経営基盤の強い法人と連携することで、金融機関からの信用が高まり、資金調達が容易になります。
これにより、施設の改修や最新設備の導入などが進めやすくなり、より質の高いサービスを提供するための環境を整備できます。
メリット⑤:サービス提供地域の拡大
複数の法人が一つになることで、より広範な地域に対してサービスを提供できるようになります。
それぞれの法人が持っていた拠点を連携させることで、地域を越えたサービスのネットワークを構築することが可能です。
これは、利用者には選択肢の拡大という利点を、法人には事業規模の拡大と地域貢献の強化をもたらします。



社会福祉法人M&Aの動向
介護・福祉業界は、「2025年問題」や「2040年問題」(生産年齢人口の急減)を控え、介護・福祉業界は大きな転換期を迎えています。
社会保障需要の増大と担い手不足という構造的課題を背景に、事業の存続と成長を目指すM&Aによる業界再編が加速しています。
特に、以下のような課題を直接的な解決策として、M&Aを検討する法人が増加傾向にあります。
- 深刻化する人材不足と採用競争の激化
M&Aにより、相手法人の人材を確保し、採用活動を効率化する狙いがあります。 - 物価・光熱費高騰による収益圧迫
スケールメリットを活かし、食材や消耗品の共同購入によるコスト削減を図ります。 - DX化やICT導入の遅れ
資金力やノウハウを持つ大手法人と連携し、見守りセンサーや記録システムなどの介護テック導入を進めます。 - 頻繁な制度改正への対応力強化
複雑化する介護保険制度の改定などに対し、組織的に対応できる体制を構築します。
買い手側も多様化しており、同業の社会福祉法人による規模拡大だけでなく、不動産業やIT企業など異業種からの参入も増えています。こうした動向の中、M&A市場では、施設の規模だけでなく、専門性の高い介護サービス(看取り、リハビリ等)やDX化の進捗度、地域でのブランド力といった専門性や地域ブランドなど「付加価値」を持つ法人が、より高く評価される傾向にあります。

社会福祉法人M&Aのデメリット・注意点

社会福祉法人のM&Aは多くのメリットがある一方、特有の難しさやリスクも伴います。
ここでは、特に注意すべき5つのポイントを解説します。
① 行政手続きや許認可承継の複雑化
社会福祉法人の事業は、行政の許認可を前提として運営されています。
M&Aを行う際には、これらの許認可を滞りなく買い手へ承継させる手続きが必要となり、これが非常に複雑で時間を要します。
所轄庁への事前相談から始まり、多数の申請書類を準備する必要があります。
また、国や自治体からの補助金や介護報酬の承継についても、各条件を丁寧に確認する必要があります。
手続きの遅延は事業運営に直接影響するため、慎重な対応が求められるのです。
② 職員や利用者への説明・同意の負担
&Aは、職員や利用者の生活に直結する重要なイベントです。
そのため、関係者への丁寧な説明と理解を得るプロセスが不可欠となります。
なぜM&Aが必要なのか、今後の運営方針はどうなるのか、といった点を透明性をもって説明し、不安を軽減する説明が必要です。
特に、職員の雇用継続や労働条件の調整は、労務トラブルを防ぐためにも、慎重な対応が欠かせません。地域住民や関係機関への理解促進も、円滑な事業継続のためには欠かせません。
③ 理事会や評議員会での承認調整の難航
M&Aを実行するには、理事会および評議員会での承認決議が法的に必須となります。
しかし、この内部での合意形成が難航するケースも少なくありません。
理事や評議員の間で、M&Aの必要性や相手選定をめぐって意見が対立し、議論が長期化する場合があります。
また、決議手続きの進め方に法的な不備があると、決議手続きに不備があると、後に無効と判断されるおそれもあるため、法令遵守に基づく適正な議事運営が必要です。
④ 非営利性や地域貢献理念の薄れ
社会福祉法人の根幹には、利益追求を目的としない「非営利性」と「地域社会への貢献」という理念があります。
M&A、特に営利企業が買い手となる場合、こうした理念が損なわれる懸念が生じる場合があります。
運営の効率化を追求するあまり、サービスの質が低下したり、採算の取れない地域サービスから撤退した場合、地域福祉からの信頼を失うおそれがあります。
M&A後も、法人が本来持つべき理念や運営方針の一貫性をいかに維持するかが大きな課題となります。
⑤ 統合後の運営方針や文化の不一致
M&Aが成立しても、統合プロセス(PMI)が適切に進まなければ、期待した効果は得られません。
特に、異なる経営理念や組織文化を持つ法人が一つになる際には、様々なコンフリクトが発生しがちです。
業務の進め方や人事制度の違いにより、現場の混乱や職員間の対立が生じることがあります。
こうした組織風土の違いを乗り越え、新しい一つの組織として融合するには、トップの明確なリーダーシップと、継続的で丁寧なコミュニケーションが重要です。


社会福祉法人M&Aを成功させるためのポイント

社会福祉法人のM&Aは複雑ですが、ポイントを押さえることで成功の確率を大きく高めることができます。
ここでは、成功に不可欠な3つの要素を解説します。
ポイント①:信頼できる専門家・仲介会社の選び方
社会福祉法人のM&Aは、特有の法規制や行政手続きが多く、高度な専門知識が求められます。そのため、自法人だけで進めるのは非常に困難です。成功の鍵は、信頼できる専門家や仲介会社の選定にあります。
M&A仲介会社やコンサルタント、弁護士などを選ぶ際には、必ず社会福祉法人のM&Aに関する実績や専門知識が豊富かどうかを確認しましょう。複数の専門家から話を聞き、法人の理念や状況を最も理解してくれるパートナーを見つけることが重要です。
ポイント②:透明な情報開示とガバナンス強化
M&Aのプロセスにおいては、買い手候補に対して自法人の情報を正確かつ誠実に開示することが、信頼関係の基礎となります。デューデリジェンスの際には、財務状況や潜在的なリスクを含め、透明性の高い情報開示を行うことが重要です。
同時に、M&Aという重要な意思決定を行うにあたり、理事会や評議員会が適切に機能しているか、ガバナンス体制を再点検することも重要です。内外への説明責任を果たし、手続きの透明性を確保することで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
ポイント③:行政との適切な連携
社会福祉法人のM&Aは、所轄庁からの許認可なくしては成立しません。そのため、行政との良好な関係構築と、継続的な連携が重要です。
計画の初期段階から所轄庁の担当部署へ相談を持ちかけ、M&Aの目的や計画の概要を説明し、指導や助言を仰ぐ姿勢が求められます。手続き上の論点や想定リスクを事前に共有することで、申請プロセスを円滑に進め、認可取得までの期間短縮にもつながります。



社会福祉法人M&Aに関するよくある質問

社会福祉法人のM&Aを検討する中で、多くの経営者が抱く共通の疑問があります。
ここでは、特によくある3つの質問にお答えします。
Q1:社会福祉法人の売買は禁止か?
はい、社会福祉法人そのものを株式会社のように売買することは、法令で禁止されています。これは、社会福祉法人が利益の配当を目的としない非営利法人であり、特定の個人の所有物ではないためです。
ただし、法人の売買はできなくとも、法人が運営する事業を、他の法人へ譲渡することは可能です。
本記事で解説してきたように、事業譲渡というスキームを用いることで、実質的に経営を承継させることが認められています。
Q2:社会福祉法人M&Aで理事長交代だけでも経営権移転は可能?
形式的に理事長を交代させるだけでは、実質的な経営権が移転したとは見なされない可能性があります。社会福祉法人の運営は、理事長個人ではなく、理事会や評議員会によって意思決定される仕組みのためです。
仮に、金銭の授受により特定の人物を理事長に据え、法人を事実上支配する行為は、違法な名義貸しや経営権の売買とみなされるおそれが高いです。経営権の移転は、事業譲渡などの正規の手続きに則って、透明性をもって行う必要があります。
Q3:行政・厚労省の許認可やガイドラインは?
社会福祉法人のM&Aに関する手続きは、厚生労働省が公表する「社会福祉法人の合併・事業譲渡等マニュアル」が基本的な指針となります。このマニュアルには、必要な行政手続きのフローや提出書類、留意点などが詳細に記載されています。
具体的な許認可の申請先は、法人が拠点を置く都道府県や市町村などの所轄庁となります。M&Aを検討する際は、マニュアルを確認のうえ、早期に所轄庁の担当部署へ事前相談を行うことが、円滑な手続きの鍵となります。
参考 : 社会福祉法人の合併・事業譲渡等マニュアル
まとめ
本記事では、社会福祉法人のM&Aについて、その基本的な仕組みから具体的なスキーム、手続きの流れ、費用、そして成功のためのポイントまでを網羅的に解説しました。社会福祉法人のM&Aは、非営利法人特有の法制度により、株式会社のM&Aとは大きく異なります。
特に、法人そのものの売買はできず、「事業譲渡」が主なスキームとなる点や、所轄庁の許認可が必須である点は、必ず押さえておくべき重要なポイントです。
後継者問題や経営基盤の強化といった課題に直面する経営者やM&A担当者にとって、M&Aは事業を未来へ繋ぐための有効な選択肢です。
しかし、そのプロセスは複雑であり、多くの注意点を伴います。
本記事で解説した最新の動向や実務ノウハウが、皆様の適切な経営判断の一助となれば幸いです。成功のためには、専門家と連携し、透明性を確保しながら慎重に進めることが最も重要です。