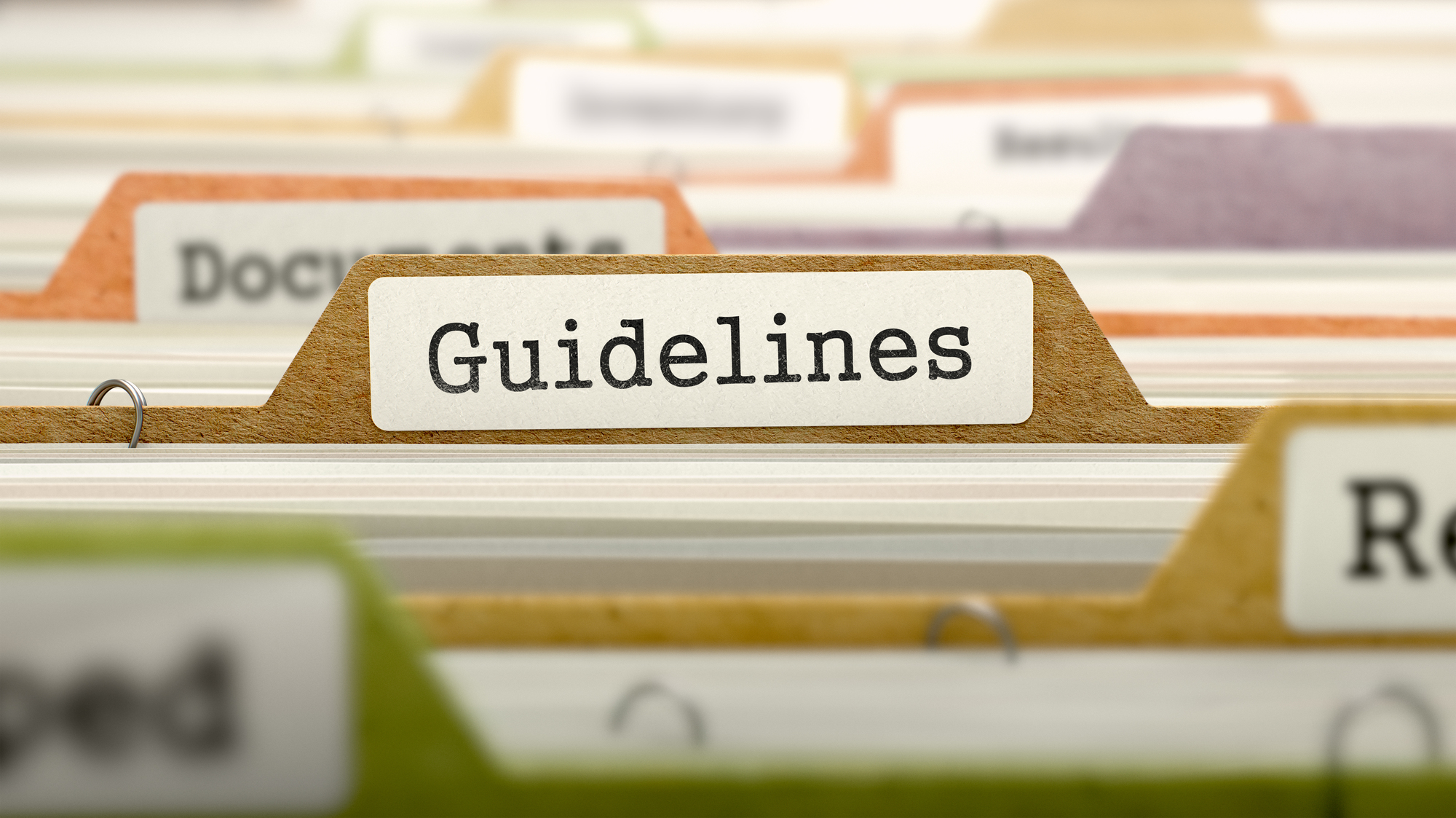チェンジオブコントロール条項がある場合のリスク。確認方法は?
チェンジオブコントロール条項は、契約当事者に実質的な支配権の変更があった際に、それを契約解除事由にできることを定めたルールです。M&Aを実行する上でのリスクや、売り手と買い手がそれぞれ注意しなければならない点について解説します。


チェンジオブコントロール条項とは

商取引の契約書には『チェンジオブコントロール条項(Change of Control)』と呼ばれる条項が付される場合があります。COC条項は、誰がどのような目的で設定するのでしょうか?
資本拘束条項のこと
チェンジオブコントロール条項(COC)は、重要な商取引で用いられる『資本拘束条項』です。契約当事者のどちらか一方に『経営権の変更』が生じた場合、もう片方の当事者はそれを契約解除事由にできるというものです。
経営権の変更が生じるケースとしては、M&Aや代理店契約、ライセンス契約などが挙げられます。
M&Aで企業を買収する側としては、売り手企業とその取引先との契約内にCOC条項がないか確認しておく必要があります。条項が存在した場合、M&Aで経営権が移転した後に取引先との契約が解除される恐れがあるためです。
チェンジオブコントロール条項の役割
商取引の契約書にCOC条項を設ける理由としては、以下が挙げられます。
- 機密情報や技術の流出を防ぐ
- 敵対的買収を防ぐ
M&AでA社の経営権がB社に移った場合、A社の取引先であるC社の機密情報や技術がB社に流出してしまう恐れがあります。B社とC社が競合であった場合、C社は不利益を被ってしまうかもしれません。
COC条項があれば、取引先は経営権の移行を理由に契約解除ができるため、自社の技術や情報が競合に流れる事態を未然に防げます。
また、他者からの『敵対的買収』を防ぐ目的もあります。敵対的買収とは、経営陣の同意なしに株の買い占めを行い、会社の経営を支配する行為です。
COC条項があると、経営権を支配しても取引先から契約を解除されてしまうため、買収を仕掛ける側にとっては買収の魅力が低下してしまうのです。


取引先に知らせずにM&Aはできる?

取引先との契約書にCOC条項が盛り込まれている場合、取引先に知らせることなく会社や事業を売却することはできません。条項には『通知の義務』が記載されており、通知をせずにM&Aを強行すれば、ルール違反とみなされます。
通知が必要
取引先への通知は法律で義務付けられているわけではありませんが、COC条項が盛り込まれている場合は、通知が必要です。
会社の経営権が変更になれば、取引先や関係者は『今後も取引は続くのか?』と将来について不安を抱くでしょう。
『取引先を引き継げるか否か』は、買い手にとってM&Aの成否を決める重要なポイントとなります。しかし、契約前に取引先に通知することは売り手にとってM&A情報の拡散となり、リスクを伴います。そのため、取引先が重要なM&Aのポイントとなる場合には、契約後クロージングまでのM&Aの成立条件として、「重要な大口取引先からの取引継続意志の確認」などを盛り込みなどして対応することが実務対応といえます。
通知義務に関する条項例
COC条項には『通知義務に関する条項』が定められており、契約当事者は条項の内容に基づいて通知を行わなければなりません。事前の通知が必要なのか、M&A実行後でもよいのかは、条項の内容によって異なります。
一般的に以下のような記載があるので、自社の契約書を確認しましょう。
- 事前に甲に対してその旨を書面で通知し、甲は何らの催告を要せず、本契約を解除できる
- 保有する株主の変動があるときは、事前または事後に甲に対してその旨を書面で通知しなければならない

M&Aにおけるリスクになる?

COC条項の最大のリスクは『重要な取引先を失ってしまうこと』です。契約解除によって、取引先が一つ、二つと失われていけば、企業価値の毀損へとつながります。買い手にとってはM&Aを行う意味が失われてしまうでしょう。
重要な取引先と契約を継続できない可能性
COC条項は敵対的買収からの防衛策となる一方で、これまで関係を築いてきた重要な取引先を失ってしまう可能性がある点に注意が必要です。
M&Aを実行した途端に取引先から契約を解除され、新たな経営者は今後の事業が立ち行かなくなってしまうかもしれません。
とりわけ、取引先が重要な仕入れ先であった場合、原材料を調達できず、商品そのものを作れなくなってしまう恐れもあります。COC条項のある取引先が1社でもあれば、経営の屋台骨が揺らぎかねないのです。
契約解除に関する条項例
契約解除が付されている条項例は以下の通りです。解除権のみの場合もあれば、通知義務と解除権がセットになっている場合もあります。
- 甲は、丙が乙の唯一の株主でなくなったときは、本契約を解除できる。
- 乙は、合併・株式交換・株式移転があった場合、または乙の全議決権の1/2を超える議決権を保有する株主の変動がある場合に、事前にその旨を書面で通知しなければならない。甲は催告を要せず、本契約の解除が可能である。
契約を解除するかどうかは取引先が判断します。取引先と買収する企業の関係性によっても、結果は変わってくるでしょう。

チェンジオブコントロール条項の確認方法

COC条項の内容は、M&Aの成否や譲渡価格の算定に大きな影響を与えます。COC条項の記載の有無は、いつどのように確認すればよいのでしょうか?条項が発覚するのはデューデリジェンスの段階が多いですが、できるだけ早い段階で見つけるのが理想です。
法務デュー・デリジェンスを行う
M&Aでは、最終契約書を締結する前に、デュー・デリジェンス(買収調査監査・DD)を行います。M&A実行後に、売り手の粉飾決算や簿外債務などが発覚する可能性があるため、買収監査によってリスクや問題点などを事前に洗い出す必要があるのです。
デュー・デリジェンスの種類は、財務・法務・人事・IT・事業と多岐にわたります。『法務DD』では、法務の専門家が個々の契約書を細かく確認し、COC条項の有無・内容・経営への影響などを精査します。
売り手としては、DDの時点でM&Aが破綻になるのは避けたいものです。M&Aの計画を立てる段階で、COC条項の有無を把握しておきましょう。DDによってCOC条項の存在が発覚し、売却が頓挫するケースもあります。
弁護士からの助言を受ける
買い手は最終契約を締結する前に、法的リスクをできるだけ細かく洗い出す必要があります。COC条項に関する法的リスクのチェックや対応については、弁護士にサポートを依頼しましょう。
法務DDでは、法務に詳しい弁護士が調査監査を担当するのが一般的ですが、DDだけに限らず、M&Aの交渉をスタートさせる初期段階から信頼できる弁護士を見つけておくと、COC条項を含むさまざまな法的リスクをより早く抽出できるでしょう。


チェンジオブコントロール条項がある場合

COC条項がある場合は、クロージングまでに何らかの対応をする必要があります。M&Aの最終契約締結日からクロージング日までは1カ月ほどの期間を設けるのが通常で、この間に売り手は取引先に通知をしたり、取引継続の承認を得たりします。
取引先に契約継続の承認を得るよう求める
COC条項があっても、必ずしもM&Aの妨げになるとは限りません。買い手は売り手に対して『取引先との交渉』を求めましょう。実務的には通知や交渉によって、契約継続が認められるケースがほとんどです。以下のような対応を得られれば問題は起こらないでしょう。
- 取引継続に関する同意書を作成してもらう
売り手としても、COC条項が原因で交渉が決裂するのは本意ではないため、取引先と積極的に交渉をしてくれる可能性は高いでしょう。
売り手が交渉をする際は、『買い手が信頼できる企業であること』や『これまで通りの取引があること』をしっかりと伝えるのがポイントです。
クロージングの前提条件を定める
『クロージングの前提条件』とは、M&Aを実行(クロージング)するために必要な条件を指します。前提条件を定めた場合、『条件が充足されない限りはM&Aを実行しない』という選択が可能です。
例えば、売り手に対するクロージングの前提条件には、『クロージング日までにCOC条項がある取引先企業から取引継続の同意をもらうこと』『対応ができなかった場合はM&Aを実行しない(延期する)』といった内容を盛り込みます。


まとめ
チェンジオブコントロール条項は、経営権が移動した際のルールを定めたものです。M&Aにより取引先との契約の解除事由が生じるため、できるだけ早い段階でCOC条項の有無や内容を把握しておくことが求められます。
COC条項が付された契約があれば、売り手は取引実行日までに、取引先から取引継続の承諾を得るように努めましょう。COC条項を含む法的リスクの対応に関しては、信頼できる弁護士やM&Aの専門家に相談して進めるのが理想です。