
事業譲渡×ファンド活用のメリットとは?PE・VC・承継ファンドを徹底解説
事業譲渡でファンド活用を検討する経営者向けに、PEファンド・VC・事業承継ファンドの違いとメリットを徹底解説。成長戦略、承継問題、資金調達の観点から最適なパートナー選びや活用ポイントが理解できる実践的ガイドです。


挑戦する企業に広がる“成長の新ルート”──ファンド活用が企業の未来をどのように拓いていくのか
近年、日本企業を取り巻くビジネス環境は大きく変化しており、業界構造、テクノロジー、働き方、価値観といったあらゆる側面でこれまで以上のスピードで変革が進んでいます。
このような環境の中で注目されているのが、PEファンド、ベンチャーキャピタル、事業承継ファンドなどの外部パートナーとの連携です。
ファンドはもはや「株を買う存在」というよりも、企業の可能性を広げ、成長を後押しするパートナーとして活用されるケースが増えています。
なぜ今、ファンドと組む企業が増えているのか

近年、ファンドと協業する企業が急増しています。
その背景には、企業を取り巻く環境が劇的に変化していることが挙げられます。
特に中小〜中堅企業や成長企業にとって、内部リソースだけで課題を解決することが難しくなっているという現実があります。
かつての日本企業は、社内の経験や人材だけで事業成長を続けることが一般的でした。
しかし現在は、市場変化のスピードがそれを上回るほど速くなっています。
新規参入企業は次々と現れ、テクノロジーは年単位ではなく月単位で進歩し、顧客の価値観も絶え間なく変化しています。
こうした変化に対し、企業は今まで以上に柔軟で迅速な対応が求められるようになりました。
それに伴い、以下のような構造的な課題が顕在化しています。
- 現場で必要なスキルや役割が多様化し、採用と育成の難度が上昇
- 企業規模が大きくなるほど、管理や意思決定に関わる経営負荷が増大
- 市場が広がる一方で、競争が激しくなり投資の先行が必要
- 海外展開や新規事業など、未経験領域の課題に社内だけで挑む敷居が上昇
- デジタル化や業務効率化など、専門性を要するテーマが増加
つまり、内部リソースだけで成長を維持することが、構造的に難しくなってきているのです。
その結果、多くの企業が「外部のプロフェッショナル」と協業することに価値を見出すようになっています。ファンドは資金提供者であると同時に、経営人材や業界ネットワークを提供し、経営管理や戦略策定の仕組みづくりにも深く関わります。単なる出資者ではなく、企業の成長を共に設計するパートナーとしての機能が求められ、実際に多くの成功事例が生まれているのです。
さらに近年は、企業の側も「外部の力を借りることは当たり前」という認識に変わりつつあります。
以前は「自前主義」が強かった企業であっても、「必要なところには外部の専門性を取り入れるほうが、結果として成長が加速する」という価値観が浸透してきています。
こうした潮流が重なったことで、ファンドとの連携は特殊な選択肢ではなく、成長企業が自然に選ぶ次のステップとして一般化しつつあるのです。

成長ステージごとの最適なパートナー

企業が成長していく過程は、決して一本の直線ではありません。
初期の混沌としたフェーズから、組織が形を持ちはじめるフェーズ、さらに規模拡大に向けて最適化が求められるフェーズ——。各段階で直面する課題や必要なリソースは大きく異なります。
そのため、ファンドとの協業においても「どのステージにいるのか」が非常に重要な判断軸となります。
同じ「成長を目指す企業」であっても、
- 何に悩んでいるのか
- どの部分がネックになっているのか
- どの方向へ進みたいのか
によって最適なパートナーは大きく変わります。
① ベンチャーキャピタル(VC)
まだ形が固まらない段階の企業を支え、“挑戦を市場で輝かせる存在”
事業の初期は、ビジョンやアイデアは豊かであっても、資金、仲間、実績、仕組みなど、多くのものが足りません。
VCが最も力を発揮するのは、このような成長初期のステージです。
このフェーズでは、企業の中心にあるのは「これから何をつくるか」「どんな未来を目指すか」といった、極めて創造的な問いです。
VCは次のような支援によって、その未完成の可能性を未来へ押し出します。
- 市場の可能性を見立てる
- プロダクトづくりの方向性を整える
- 事業モデルの磨き込み
- チームづくりや採用の支援
- 将来の資金調達やIPO戦略の伴走
- 業界ネットワークへの接続
VCが入ることで、まだ小さな芽だった事業が、社会の大きな流れと接続し、成長の速度が一気に上がることも珍しくありません。
初期の不確実性が大きい段階ほど、挑戦の熱量を理解してくれるプレーヤーが必要になり、その役割を担うのがまさにVCです。
② PEファンド(バイアウトファンド)
一定の規模に達した企業が、次の成長カーブを描くための加速装置
企業が一定の規模に成長すると、新しい課題が姿を見せはじめます。
売上が数十億〜百億規模になると、課題は仕組み化に集約されていきます。
- 組織が大きくなり意思決定が複雑になる
- 管理体制が追いつかなくなる
- 若手経営層が不足する
- さらなる成長のための打ち手が見えづらくなる
これらの課題は、優れたビジネスモデルや高い受注力があっても「仕組みの限界」によって成長が鈍化してしまうタイミングです。
PEファンドは、まさにこのフェーズにおいて既存事業の強化と新たな成長ステージへの引き上げに圧倒的な強みを持ちます。
- 経営管理の再構築
- KPIの整備
- デジタル化や効率化の推進
- 営業戦略の再設計
- 次世代リーダーの登用・採用
- 海外展開や新領域への投資
- M&Aによる非連続な成長の実現
企業の価値を「仕組み」と「戦略」で引き上げる力があるため、既存事業に手応えがありつつも停滞感のある企業との相性が非常に高いと言えます。
③ 事業承継ファンド
次の担い手不足という課題に対して、事業の未来を守り続ける支援者
多くの企業が直面する課題に「後継者不在」があります。これは規模に関係なく、地域・業界を問わず全国的に広がっている構造問題です。
事業承継ファンドは、経営者が引退した後も企業が存続し、さらに成長し続けるための土台づくりに寄り添います。
- 経営管理の仕組み化
- 経営人材の派遣
- 組織文化の尊重と改善
- 地域とのネットワーク強化
- 承継後の成長戦略の策定
- 雇用維持と社員教育
単なる事業の引き継ぎではなく、企業の命をつなぐという意味合いが強いのが特徴です。
特に、創業者色が強く、属人的に回ってきた企業ほど、承継ファンドの関与によって組織としての持続可能性が高まるケースが多くなっています。
企業のステージが変われば、必要な支援も変わります。
成長初期には挑戦を加速させる支援が必要であり、成長途上では仕組みを整え、安定成長へつなぐ支援が必要になります。
承継時には未来へ事業をつなぐための支援が不可欠になります。
このように、企業の成長ステージによって最適なファンドは変化します。
だからこそ、「いま企業がどのフェーズにいるのか」「どんな未来を描こうとしているのか」を明確にすることで、より良いパートナー選びができるようになります。


経営の選択肢を広げる仕組み/LBO・MBO

企業が外部パートナーと連携する場面でよく登場する「LBO」や「MBO」。
これらは専門的な金融スキームとして語られることが多く、やや難しい印象を持たれがちですが、本質的には企業が未来への一歩を踏み出すための方法として非常に有効な仕組みです。
LBOもMBOも、企業の規模や課題、目指す方向性によって柔軟に活用できるため、
事業承継や独立、組織づくり、成長加速などさまざまな場面で機能します。
ここでは、それぞれの仕組みが企業にもたらす価値や、どのような場面で力を発揮するのかを深く見ていきます。
LBO(レバレッジド・バイアウト)
──“未来のキャッシュフロー”を力に変えて、成長を実現する金融技術
LBOの最大の特徴は、企業自身が将来生み出すキャッシュフロー(利益・返済原資)を活用して、大きな成長機会に踏み出せることにあります。
これは、企業にとって次のような価値をもたらします。
資金不足で諦めていた成長投資が可能になる
通常、企業が大きな投資を行う際には、手元資金や新株発行だけでは資金が足りないケースも多くあります。
しかしLBOでは、企業が持つ未来の収益力を金融機関が評価し、融資を組み合わせることで 必要な資金を一気に準備できるというメリットがあります。
- 事業承継のための買収資金
- MBOによる独立
- 成長市場への参入
- 工場や設備の大型投資
- カーブアウト案件の買収
こうした大規模な意思決定が、資金制約でストップすることが減ります。
既存事業の価値を活かした成長戦略が描ける
LBOは、事業のキャッシュフローをベースにするため、「安定収益があるが、成長のきっかけをつかめていない企業」 との相性が非常に良いです。
たとえば、堅実に利益を出しているものの、成長投資のタイミングが掴めない企業がLBOを活用すると、投資余力が一気に広がり、新しい市場への挑戦がしやすくなります。
レバレッジがあるからこそ、経営にスピードが生まれる
レバレッジとは「てこの原理」です。
自らの資本だけでは難しい挑戦も、他の資本を味方につけることで実行できるようになります。
その結果、企業は大胆な打ち手を出せるようになり、経営の選択肢が広がり、機会を逃さないスピード感が生まれます。
LBOは、成長を加速させるための金融テクノロジーとして非常に有効です。
MBO(マネジメント・バイアウト)
──経営陣が主体となり、“理想の経営”を実現するための独立手段
MBOは、経営陣自身が企業や事業を買い取り、より大きな裁量と責任を持って経営を行う仕組みです。
MBOが選ばれる背景には、次のようなニーズがあります。
よりスピーディで柔軟な経営判断を可能にしたい
親会社の方針に縛られて自由な経営が行えないケースや、現場の声を活かした意思決定がしたい場合、MBOによる独立が選択肢になります。
独立後は、経営陣の判断で事業を進めることができるため、スピード感のある経営が可能になります。
事業の価値をさらに引き出すための独立
特に大企業の中で眠っている埋もれた事業において、「小さな市場だが、独立すれば大きな価値を出せる」というケースは少なくありません。
MBOは、こうした事業を本来あるべき姿で成長させられる仕組みとして機能します。
継承したい事業を、経営陣主体で守りながら成長させたい
後継者不在の企業において、内部の経営陣が承継し、ファンドとともに会社を次のステージへ導くケースも増えています。
この場合のMBOは企業文化を守りつつ、成長への道を開くスタイルとして活用されます。
LBOとMBOの共通項は「企業が自ら未来を選び取れるようになること」
どちらの手法にも共通するのは、企業が目指す未来を、自ら選べるようになる という点です。
- 資金不足で諦めていた成長投資が可能になる
- 経営の自由度が高まり、スピードが出る
- 承継問題に対して、持続的な解決策が生まれる
- 事業の可能性を最大限に引き出せる
- 外部パートナーと協力しやすくなる
つまりLBOとMBOは、企業が「次の一歩」を踏み出すための非常に強力なツールとして存在しています。
今の延長線では見えなかった選択肢が開けるため、多くの企業にとって未来の可能性を広げる重要な選択肢となりつつあります。



資金の提供だけではない、ファンドとの協業の価値

ファンドとの協業が注目されている理由として、まず思い浮かぶのは「資金の提供」という側面かもしれません。
しかし実際には、企業がファンドと組む価値の大半は、資金以外の目に見えない支援にあると言われています。
企業が成長するためには、当然ながら資金が必要です。しかし本当に企業を強くするものは、資金そのものではなく、戦略・人材・知見・仕組み・ネットワーク といった「経営の質」をつくる要素です。
ファンドは、この経営の質を高める観点から、多面的に企業を支援します。
ここでは、その価値をもう少し深く掘り下げていきます。
①経営判断がスピードアップする
企業規模が大きくなるにつれて、意思決定にはより多くのステークホルダーが関与するようになり、判断が遅くなることが珍しくありません。
しかしファンドが入ると、意思決定のフローが整理され、「最も価値を生む判断」を軸にした高速な経営が可能になります。
- どの投資が最も長期的な価値を生むのか
- どの事業に集中すべきか
- どこにリソースを振り分けるべきか
こうした問いに対して、ファンドは経験に裏打ちされた視点を持ち込むため、より合理的でスピーディな判断ができるようになります。
②経営体制が厚くなる(経営の孤独が減る)
多くの経営者が感じているのが、「最終判断を自分一人で背負わなければならない」という負荷です。
ファンドが入ることで、次のような心強い変化が生まれます。
- 経営陣に経験豊富なプロフェッショナルが参加する
- 重要な意思決定を議論する相手が増える
- KPIや戦略の妥当性を多角的にチェックできる
- 経営企画・管理の専門家が伴走する
結果として、経営陣の層が厚くなり、孤独な経営からチームで戦う経営に進化します。
③人材採用・組織づくりが強化される
成長企業にとって最大の課題は、「採用したいときに、必要な人材がいない」ことです。
ファンドは多くの企業を見てきているため、足りていない役割はどこか、どのような人材を採用すべきか、どのような報酬設計が適切か、組織図はどう構築すべきか、といった組織づくりの設計にも深く関わります。
さらに、ファンドのネットワークを活用することで、通常の採用ルートでは出会えないハイクラス人材とつながることも可能になります。
④新規事業や事業開発の成功確率が高まる
新しい挑戦は、成功確率が高くありません。
しかしファンドは、他社の成功・失敗事例を大量に蓄積しているため、企業が避けるべきリスクや攻めるべきポイントを明確にできます。
- 新規事業の市場選定
- 最適な成長戦略の策定
- 業界とのシナジー分析
- 共同事業のパートナー選び
こうした場面でファンドの知見が活きることで、新しい取り組みが成功する確率が大きく高まります。
⑤外部ネットワークが広がり、チャンスが増える
ファンドは多くの企業・金融機関・業界団体とつながっているため、企業にとっては新しい出会いのハブになります。
- 提携先の紹介
- 大手企業との協業
- 海外パートナーとの接続
- 次のM&A候補の発掘
- 成長市場における情報収集
ファンドと組むことで、企業単体では届かなかった領域に挑戦するきっかけが生まれます。
⑥企業のブランド力・信頼性が向上する
ファンドが投資を行う企業には、一定の審査と評価プロセスが存在します。
そのため、ファンドとの提携は次のような効果をもたらします。
- 取引先からの信頼性が高まる
- 銀行からの信用が上がり、融資がスムーズになる
- 採用市場でのブランドが向上する
結果として、企業が成長していくための外部からの協力が得やすくなるのです。
ファンドとの協業は、企業が強くなるための総合支援です。
ファンドが提供する価値は、お金だけではありません。
むしろ、資金以上に価値の高い経営の質の向上が最大の特徴です。
- 経営判断のスピード
- 組織づくり
- 人材戦略
- 新規事業
- ネットワーク
- 信頼性の向上
これらが掛け算されることで、企業は 「単独では到達できなかったステージ」へと進んでいくことができます。



ファンド活用は、企業が未来の選択肢を増やすための手段

企業が成長し続けるためには、環境の変化にあわせて選択肢を増やし続けることが重要になります。
市場、顧客、テクノロジー、人材、競争環境。どれも常に変わり続けている中で、「今の延長線だけでは未来を描けない」という企業が増えています。
こうした状況の中で、ファンドの存在は企業に新しい選択肢と可能性を提供する装置として機能しています。
ファンドを活用することは、企業が「成長曲線を自ら選び取る」ための柔軟な方法の1つであり、次のステージへ踏み出すきっかけになります。
ここでは、その未来の選択肢を広げるという観点からファンド活用の価値を深く見ていきます。
①自社だけでは持ち得なかった成長ルートが開ける
企業の成長は、社内リソースだけに依存するとどうしても限界があります。
人材不足や時間の制約、資金調達の難しさなどが壁となり、やりたいことがあっても着手できないケースは少なくありません。
ファンドと組むことで、次のような新しい成長のルートが見えてきます。
- M&Aによる事業拡大
- 海外展開という新しい市場への挑戦
- 大型設備投資による生産能力の増加
- 新規事業・第二創業の立ち上げ
- 組織体制の強化とスケーリング
- 経営管理・財務基盤の高度化
これらは、多くの企業にとって「興味はあるが、踏み出すには勇気が必要」という領域です。
ファンドとの連携は、こうした領域を踏み出せる領域へ変えていく力を持っています。
②企業が成長の主導権を持てるようになる
ファンド活用というと、「外部に頼る」「経営が乗っ取られる」という誤解が残っている場合もあります。
しかし現在のファンドは、企業が主体的に未来を選択するためのサポーターとして機能します。
- 経営者の意志を尊重する
- 長期的なビジョンに共感して投資を行う
- 組織文化や地域性を丁寧に理解する
- 経営者と同じ方向を見て伴走する
つまり、ファンドは企業の未来を「代わりに決める」のではなく、企業が「選び取れるように支える」役割を持ちます。
これにより、企業は自分たちの意思で、未来の経営をデザインできるという状態に近づきます。
③持続的な成長と未来への投資がしやすくなる
成長が止まる企業の多くは、未来の投資よりも今の維持に注力せざるを得なくなります。
- 優先順位をつけるのが難しくなる
- リソースが分散してしまう
- 攻めより守りに経営が偏る
- 経営者の視野が短期化する
こうした状態は、長期的には企業の競争力を弱めてしまいます。
ファンドを活用することで、未来への投資に使える資源と余裕が増え、次のような“攻めの経営”が可能になります。
- 中長期の成長戦略に集中できる
- 必要な投資を一気に進められる
- 経営の視野が広がる
- 持続的な価値創出に意識が向く
攻めるための土台が整うことで、企業は 「将来の市場」に向けた動きを早い段階で仕込むことができます。
④承継・独立・再編など“経営の岐路”で選択肢が広がる
特に中小〜中堅企業においては、「会社の未来をどうするか」という岐路が必ず訪れます。
- 後継者不在
- 親会社からの独立
- グループ再編
- MBOによる事業移管
- 第二創業の開始
ファンドは、こうした転換点において非常に柔軟な選択肢を提供できます。
たとえば
- 内部承継を実現するためのMBO支援
- 創業者の想いを尊重した承継ファンドの活用
- 親会社からの独立(スピンアウト)支援
- グループ再編のための資本調整
- 事業の磨き上げを前提としたバイアウト
このように、企業の第二の人生をどうデザインするかという場面でもファンドは幅広い役割を果たします。
⑤企業が「未来の選択肢を持ち続けられる状態」をつくる
ファンド活用が提供する価値は単なる資金調達ではなく、企業が未来に向けて歩み続けるための柔軟性と選択肢です。
- 成長の道筋が増える
- 経営判断の幅が広がる
- 組織が強くなる
- 承継の選択肢が増える
- 外部との協業がしやすくなる
- 新規事業やM&Aのチャンスが広がる
これらはすべて、企業が「未来のどのルートを選ぶか」を自ら決められる状態につながっています。
企業にとって最も大切なのは、未来の選択肢を持ち続けることです。
ファンドの活用は、そのための強力な道具であり、企業が次のステージへ踏み出すための手段としてますます価値を高めています。


よくある質問
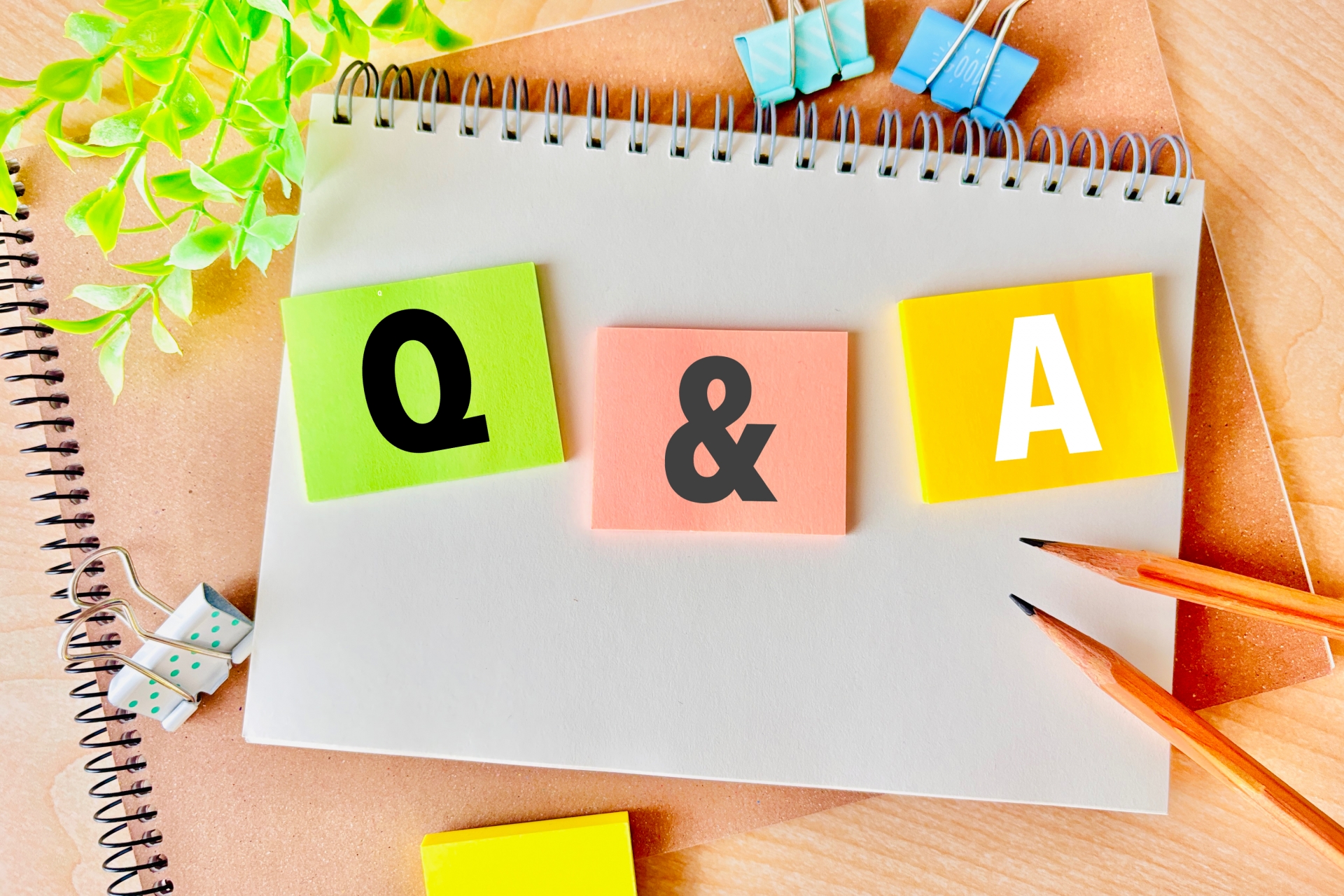
Q1. ファンドと組むメリットは何ですか?資金以外の価値はありますか?
A. はい、近年のファンド活用は“資金以外の価値”が非常に大きいです。
- 経営管理の強化
- 組織づくりや採用支援
- 新規事業やM&Aの実行力
- 営業・マーケティング改善
- 経営者の意思決定を支えるプロ人材の参画
など、経営の質を高める「第二の経営チーム」として機能するのが最大のメリットです。
Q2. 事業譲渡と株式譲渡のどちらがよいのか?
A. 企業の状況・目的・税務・リスク構造によって最適解が変わります。
- 事業譲渡:必要な事業だけ切り離せる・買い手がリスクを選べる
- 株式譲渡:手続きが早い・一体での承継がスムーズ
PEファンドや承継ファンドはどちらにも対応可能なため、企業にとって最適なストラクチャーを一緒に設計するケースが一般的です。
Q3. ファンドは「ハゲタカ」ではありませんか?
A. 現代のファンドは、企業価値の向上を第一に考える成長パートナーです。
経営者の意志を尊重し、
- 組織の強化
- 事業の成長
- 雇用維持
- 承継後の安定運営
などにコミットするファンドが増えています。
今は「企業の未来を一緒に作る存在」としての役割が主流です。
Q4. どのタイミングでファンドに相談すべきですか?
A. 課題が明確になる前の早期相談が理想です。
- 成長が鈍化してきた
- 新規事業を本格化したい
- 後継者問題が気になり始めた
- 数年後のEXITを見据えたい
こうした兆しの段階で相談すると、より良い戦略設計ができます。
Q5. カーブアウト(事業部門の独立)にもファンドは使えますか?
A. 非常に相性が良いです。
PEファンドは
- 経営管理の立ち上げ
- IT・人事の独立
- 新会社のKPI設計
- 市場戦略の再構築
など、大企業の切り出し案件を多く手掛けています。
カーブアウト成功の鍵である独立初期の伴走が得意領域です。
Q6.ファンドとの協業にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 案件によって異なりますが、一般的には3〜6カ月程度が目安です。
- 事業承継:3〜4ヶ月
- バイアウト:4〜6ヶ月
- カーブアウト:6ヶ月〜1年程度(分離作業のため)
早い段階で資料を整えておくとスムーズに進みます。
まとめ
VC・PE・事業承継ファンドなどのファンドも企業の成長を多面的に支える存在として進化しています。
- 初期の挑戦を後押しするVC
- 成熟企業を次のステージへ導くPE
- 大切な事業を未来へつなぐ承継ファンド
企業がどのステージにあっても、ファンドは成長のチャンスを広げる仲間になり得ます。
ファンド活用とは、企業が未来の可能性を最大化するための選択肢を手にすることです。







