
合同会社のM&Aは難しい?売却から税金対策まで徹底解説!
合同会社のM&Aには株式会社とは異なる注意点がありますが、正しい知識と手順を理解すれば成功は可能です。合同会社のM&Aについて網羅的に解説します。
合同会社のM&Aを検討しているものの、「株式会社と何が違うのか」「手続きが複雑で難しそう」といった不安や疑問を抱えていませんか?
合同会社のM&Aには株式会社とは異なる注意点がありますが、正しい知識と手順を理解すれば成功は可能です。
本記事では、合同会社のM&Aが難しいとされる理由から、具体的な手法(スキーム)、手続きの流れ、税金対策、そして成功のポイントまで、網羅的に解説します。
最後まで読むことで、合同会社M&Aへの不安が解消され、自社に最適な選択の道筋が見えてくるはずです。
まずはM&Aの全体像を掴み、成功に向けた第一歩を踏み出しましょう。


合同会社と株式会社のM&Aの違い

合同会社のM&Aを理解するためには、まず株式会社との違いを把握することが重要です。
ここでは、合同会社特有のM&Aの意味や特徴、そしてM&Aで用いられる代表的な手法について解説します。
合同会社におけるM&Aの意味と特徴
合同会社は、株式会社と異なり、所有と経営が一致しているのが特徴です。ここで言う「社員」とは、一般的な従業員(労働者)のことではなく、会社に出資したオーナー(経営者)を指します。
この社員が会社の経営権を持ち、原則として社員全員の同意がなければ重要な意思決定ができません。
そのため、M&Aにおいても、株式会社の株式譲渡のように単に株式を売買するだけでは経営権は移らず、社員全員の同意が重要です。
M&Aでよく用いられる手法
合同会社のM&Aでは、主に「持分譲渡」「事業譲渡」「合併」といった手法が用いられます。
持分譲渡は、社員が持つ「持分」を譲渡することで、会社の経営権を移転させる手法です。
事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を売却する手法で、特定の事業だけを切り離したい場合に有効です。
合併は、複数の会社を一つの法人格に統合する手法で、吸収合併が一般的です。
手法の選択は目的や当事者の状況によって異なり、手続きや税務上の扱いも変わるため慎重な検討が必要です。


合同会社のM&Aが難しい理由

合同会社のM&Aは、株式会社に比べて「難しい」と言われることがあります。
その背景には、合同会社特有の組織構造や法的な制約が関係しています。
ここでは、M&Aを困難にする5つの具体的な理由を掘り下げて解説します。
理由①:持分・事業譲渡には社員の同意が必要
合同会社が持分譲渡や事業譲渡を行うには、原則として「総社員の同意」が必要です。
株式会社は株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上)で可能ですが、合同会社は一人でも反対すると進められません。
特に社員数が多い場合、全員の同意を取り付けることは大きなハードルとなります。
理由②:経営支配を得るには全社員の同意が必要
買い手側にとって、会社の経営権を完全に掌握するためには、全社員から持分を譲り受ける必要があります。
一部の社員が持分を保有すると、経営の自由度は制限されます。
この点が、買い手にとって合同会社のM&Aを躊躇させる一因となっています。
理由③:合同会社は買い手にとって魅力が乏しい
合同会社は株式会社より社会的信用度や知名度が低く見なされる傾向があります。
また、株式市場への上場もできないため、買い手にとって投資の出口戦略が描きにくいというデメリットがあります。
これらの要因から、M&Aの対象として魅力が乏しいと判断され、買い手が見つかりにくい傾向があります。
理由④:情報が非公開でリスクが把握しにくい
合同会社には、株式会社のような決算公告の義務がありません。
そのため、財務や経営状態の情報が公開されず、買い手はデューデリジェンス(買収監査)まで詳細なリスクを把握できません。
情報の非対称性が、M&A交渉の障壁となるケースは少なくないのです。
理由⑤:株式会社への組織変更にも手間と同意が必要
M&Aをスムーズに進めるために、合同会社から株式会社へ組織変更する選択肢もあります。
しかし、この組織変更自体にも総社員の同意が必要であり、さらに債権者保護手続きなど、時間とコストがかかります。
M&Aの手段として組織変更を選択する場合でも、同意形成の手間からは逃れられません。


合同会社のM&Aにおけるスキーム別の手続きと流れ

合同会社のM&Aを成功させるには、各スキーム(手法)の手続きと流れを正確に理解することが不可欠です。
持分譲渡、事業譲渡、吸収合併、会社分割、そして株式会社化後の株式譲渡、それぞれの具体的な手順や必要書類について詳しく解説します。
持分譲渡
持分譲渡は、合同会社の社員がその地位(持分)を第三者に譲渡する手法です。
まず譲渡人(売り手)と譲受人(買い手)が持分譲渡契約を結びます。
その後、他の社員全員の同意を得る必要があり、定款に別段な定めがなければ、総社員の同意書を作成します。
同意が得られたら、定款の変更(社員名の変更)と法務局での変更登記申請を行います。
必要書類は、持分譲渡契約書、総社員の同意書、定款、変更登記申請書などが挙げられます。
社員が持分を譲渡すると経営権を失いますが、雇用契約を結んでいれは従業員として会社に残れます。
事業譲渡
事業譲渡は、会社の一部の事業または全部の事業を譲渡する手法です。
譲渡対象の範囲(資産、負債、契約、従業員など)を決め、取締役会等で承認を得ます。
その後、買い手企業との間で事業譲渡契約を締結し、原則として総社員の同意を得ます。
契約書には、譲渡対象資産・負債の明細、譲渡価格、従業員の処遇などを詳細に記載することが重要です。
また、個別の資産や契約ごとに移転手続きが必要となり、不動産があれば所有権移転登記、従業員の転籍には個別の同意が求められます。
吸収合併
吸収合併は、一方の会社が他方を吸収し、全権利義務を引き継ぐ手法です。
まず、合併当事会社間で吸収合併契約を締結します。その後、合同会社側では原則として総社員の同意が、株式会社側では株主総会の特別決議が、それぞれ必要となります。
その後、官報公告や催告による債権者保護手続きを1ヶ月以上行います。
手続きが完了したら、効力発生日から2週間以内に、存続会社と消滅会社が共同で法務局に登記申請を行います。
吸収合併契約書、総社員の同意書、債権者保護手続き関係書類、登記申請書など、多くの書類準備が必要です。
会社分割
会社分割は、会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の会社に承継させる手法です。
新設分割(新たに会社を設立して承継させる)と吸収分割(既存の会社に承継させる)があります。
手続きは合併と類似しており、分割計画書または分割契約書の作成、総社員の同意、債権者保護手続き、登記申請という流れで進みます。
切り出す事業の範囲を明確にした分割計画書(契約書)の作成が重要となります。
株式会社化後の株式譲渡
M&Aを円滑化するため、合同会社から株式会社へ組織変更した後に株式譲渡を行う方法もあります。
まず、組織変更計画を作成し、総社員の同意を得て、債権者保護手続きを行います。
その後、法務局で合同会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に申請します。
株式会社化後、株主(元社員)が株式を買い手に譲渡すればM&Aが完了します。
手続きが煩雑ですが、株式会社形態で売却できるため買い手に魅力があります。



合同会社で事業譲渡によるM&Aをするメリット・デメリット

数あるM&Aスキームの中でも、合同会社において事業譲渡は有力な選択肢の一つです。
ここでは、事業譲渡を選択した場合のメリットとデメリットを整理し、どのようなケースで有効な手法となるのかを解説します。
メリット
- 社員全員の同意が不要な場合がある
定款で別段の定めを設ければ、総社員の同意ではなく特定の要件(例:業務執行社員過半数の同意)で事業譲渡が可能です。 - 売却する事業を選べる
会社全体ではなく、特定の事業や資産のみを切り出して売却できるため、売り手はコア事業を手元に残しつつ、不採算事業を整理することが可能です。 - 雇用契約の引継ぎが明確
合併や会社分割とは異なり、事業譲渡では従業員の雇用契約は自動的に引き継がれません。従業員を買い手企業へ移籍(転籍)させるには、一人ひとりの個別の同意が必要になります。これにより、誰が移籍するのかが明確になり、トラブル防止と計画的に雇用を維持することにつながります。 - 不要な負債を避けられる
買い手は、必要な資産や事業だけを選んで買収できるため、簿外債務や偶発債務といった予期せぬリスクを引き継ぐ可能性を低減できます。 - 買い手の選択肢が広がる
会社全体ではなく事業単位での買収となるため、買い手は比較的小規模な投資で済みます。これにより、買い手候補の幅が広がる可能性があります。
デメリット
- 手続きが煩雑になる
譲渡対象となる資産、負債、契約などを個別に移転させる手続きが必要なため、持分譲渡に比べて手間と時間がかかります。許認可の再取得が必要な場合もあります。 - 税負担が重くなる可能性がある
事業譲渡によって得た利益には法人税が課されます。また、譲渡対象に課税資産があれば消費税もかかるため、税務面の検討が必要です。 - 取引先との契約を再度結ぶ必要がある
事業に関する契約関係は自動的には引き継がれないため、取引先や顧客との契約を買い手企業が結び直す必要があります。


合同会社のM&Aのポイント
合同会社のM&Aを成功に導くためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
円滑なM&Aを実現するための具体的な要点を解説します。
合同会社のM&Aに詳しい専門家や仲介会社を選ぶ
合同会社の&Aは法務・税務の専門知識が不可欠で、専門家の協力が成功の鍵となります。
顧問税理士や弁護士はもちろん、M&Aの経験が豊富なアドバイザーや専門の仲介会社に相談することが重要です。
無料診断・マッチングサービスの活用
近年、オンラインで企業価値を簡易的に査定できるサービスや、売り手と買い手を繋ぐM&Aプラットフォームが増えています。
合同会社は情報が非公開で買い手が見つかりにくいという課題がありますが、こうしたプラットフォームを活用することで、全国の潜在的な買い手候補にアプローチできます。
国内最大級の事業承継・M&Aプラットフォームである「TRANBI(トランビ)」では、売り手が匿名で自社情報を登録し、興味を持った買い手と直接交渉できます。
特に、買い手が見つかりにくい合同会社にとって、多くの潜在的な買い手候補に効率的にアプローチできる有効な手段と言えるでしょう。
M&A後の統合(PMI)・運営体制構築
M&Aは契約が完了すれば終わりではありません。
実際は、その後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)がM&Aの成否を分けます。
特に、従業員の処遇や企業文化の融合、業務システムや経理プロセスの統合、そして新しい運営体制の構築などを計画的に進めることが重要です。
売り手と買い手が協力し、スムーズな引継ぎを実現するための計画を事前に策定しておく必要があります。



合同会社M&Aにかかる税金・税務上の注意点
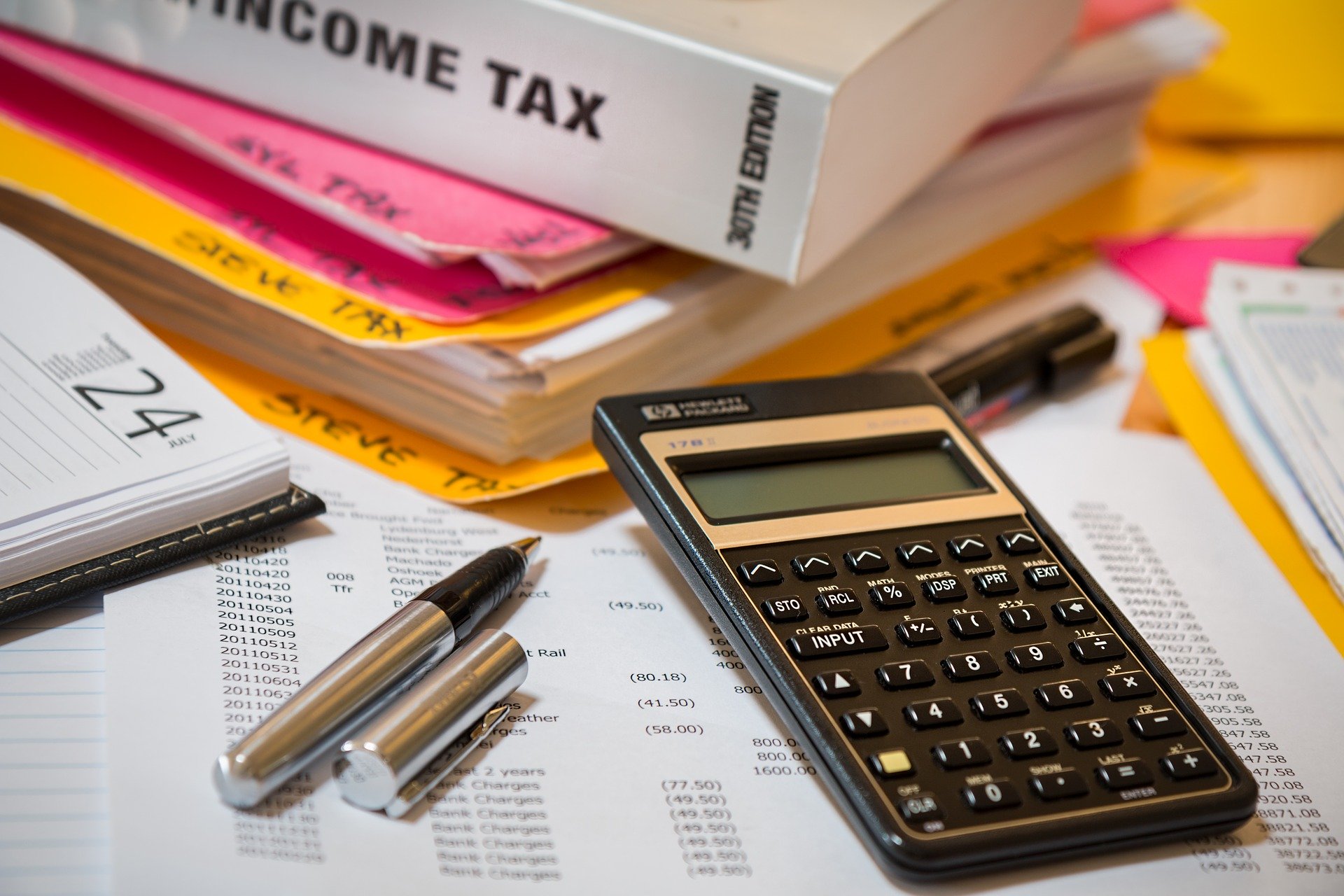
M&Aを実行する際には、税金の問題を避けて通ることはできません。
選択するスキームによって課される税金の種類や税率が大きく異なるため、事前の税務プランニングが極めて重要です。
ここでは、合同会社のM&Aで特に注意すべき税金について解説します。
持分譲渡時の譲渡所得課税
社員(個人)が持分を譲渡して利益(譲渡所得)を得た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いた額に対し、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計で20.315%が課税されます。
法人が持分を譲渡した場合は、他の所得と合算して法人税が課されます。
事業譲渡による法人税の発生
事業譲渡によって会社が利益を得た場合、その譲渡益に対して法人税が課されます。
譲渡益は、譲渡価額から資産簿価を差し引いて算出します。
税額が大きくなる可能性があるため、事前にシミュレーションが必要です。
消費税課税対象となる取引
事業譲渡においては、譲渡対象となる資産に消費税の課税対象となるものが含まれている場合、消費税が課されます。
例えば、建物や機械設備、営業権(のれん)などが該当します。
土地や有価証券は非課税です。
買い手側は消費税を支払う必要がありますが、原則として仕入税額控除の対象となります。
みなし配当による所得税負担
会社が社員から自己の持分を買い取る場合、、社員が受け取る対価は「①資本の払戻し部分(出資元本)」と「②利益の分配部分」に分けられます。
このうち②の利益の分配部分が、税法上「配当とみなされる」ため、「みなし配当」と呼ばれます。
通常の持分譲渡益(譲渡所得)が約20%の分離課税であるのに対し、みなし配当は給与など他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象となり、税率がより高くなる可能性があるため、注意が必要です。
税務デューデリジェンスの重要性
買い手にとって、対象会社の過去の税務申告が適正に行われているかを確認する「税務デューデリジェンス」は非常に重要です。
過去の申告漏れや税務リスクがM&A後に発覚すれば、買い手が予期せぬ税負担を負うことになりかねません。
売り手側も、事前に税務リスクを洗い出しておくことで、交渉をスムーズに進めることができます。




合同会社の売却価格の評価方法

M&Aにおいて、売却価格(企業価値)の算定は最も重要なプロセスの一つです。
客観的かつ合理的な方法で企業価値を評価し、交渉に臨むことが、双方にとって納得のいく取引の実現に繋がります。
ここでは、代表的な評価方法と価格交渉のポイントを解説します。
企業価値の算出方法
企業価値の評価方法には様々なアプローチがありますが、主に以下の3つが用いられます。
- DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)
会社が将来生み出すフリーキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法。将来の収益性を重視する評価方法です - 純資産法
会社の貸借対照表上の純資産を基準に評価する方法。客観性が高いですが、将来の収益性が反映されにくい側面があります。 - 取類似業種比準法
上場同業他社の株価や財務指標を基に相対評価する方法。市場評価を反映できる一方、適用可能な類似企業がない場合は難しいです。 合同会社の場合、情報が非公開であるため、特に純資産法や、事業計画の実現可能性を慎重に評価した上でのDCF法が重視される傾向にあります。
価格交渉時のポイント
売却価格は、算出された企業価値評価額を参考にしつつ、最終的には当事者間の交渉によって決定されます。
売り手は、自社の強みや将来性、無形資産(技術、ノウハウ、顧客基盤など)を具体的にアピールすることが重要です。
買い手は、デューデリジェンスで発見されたリスクや、シナジー効果の度合いを価格に反映させようとします。
また、価格だけでなく、従業員の雇用維持や役員の処遇、譲渡後の引継ぎ期間といった条件面も交渉の重要な要素となります。



合同会社のM&Aでよくある質問
最後に、合同会社のM&Aに関して、経営者や担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
合同会社のM&Aの売却価格の相場はどの程度か?
売却価格の相場は、業種、事業規模、収益性、将来性などによって大きく変動するため、一概に「いくら」と言うことはできません。
一般的には、時価純資産に営業利益の数年分(2〜5年程度)を加えた金額が一つの目安とされますが、あくまで簡易的な計算です。
正確な価値を知るためには、M&Aの専門家に企業価値評価を依頼することをお勧めします。
合同会社のM&A後の税務負担は?
税務負担は、売り手と買い手、そして選択するスキームによって異なります。
売り手側では、持分譲渡なら譲渡所得税、事業譲渡なら法人税が主に発生します。
買い手側では、事業譲渡において課税資産に対する消費税の支払い義務が生じます。
納税のタイミングは、個人の場合は確定申告時、法人の場合は事業年度終了後となりますので、資金繰りにも注意が必要です。
無償での持分譲渡は可能か?
親族間などで持分を無償や低額で譲渡することは可能ですが、税務上は時価取引とみなされ、受け取った側に贈与税が課される場合があります。
また、譲渡した側にも「みなし譲渡所得課税」が適用される可能性があるため、無償譲渡を検討する際は、必ず税理士などの専門家に相談してください。
まとめ
本記事では、合同会社のM&Aが難しいとされる理由から、具体的な手法、税金、成功のポイントまでを包括的に解説しました。
合同会社のM&Aは、株式会社とは異なり「総社員の同意」が原則となるなど、特有のハードルが存在します。
しかし、持分譲渡や事業譲渡といったスキームごとの手続きを正しく理解し、計画的に進めることで、円滑な事業承継や事業の成長を実現することが可能です。
成功の鍵は、早期の段階から弁護士や税理士、M&Aアドバイザーといった専門家の支援を受けることです。
特に、税務リスクの把握や適正な企業価値評価、法的に有効な契約書の作成は、専門家なしでは非常に困難です。
M&Aプラットフォームなどを活用して情報収集を進めつつ、信頼できるパートナーを見つけ、自社にとって最適なM&Aの実現を目指してください。






