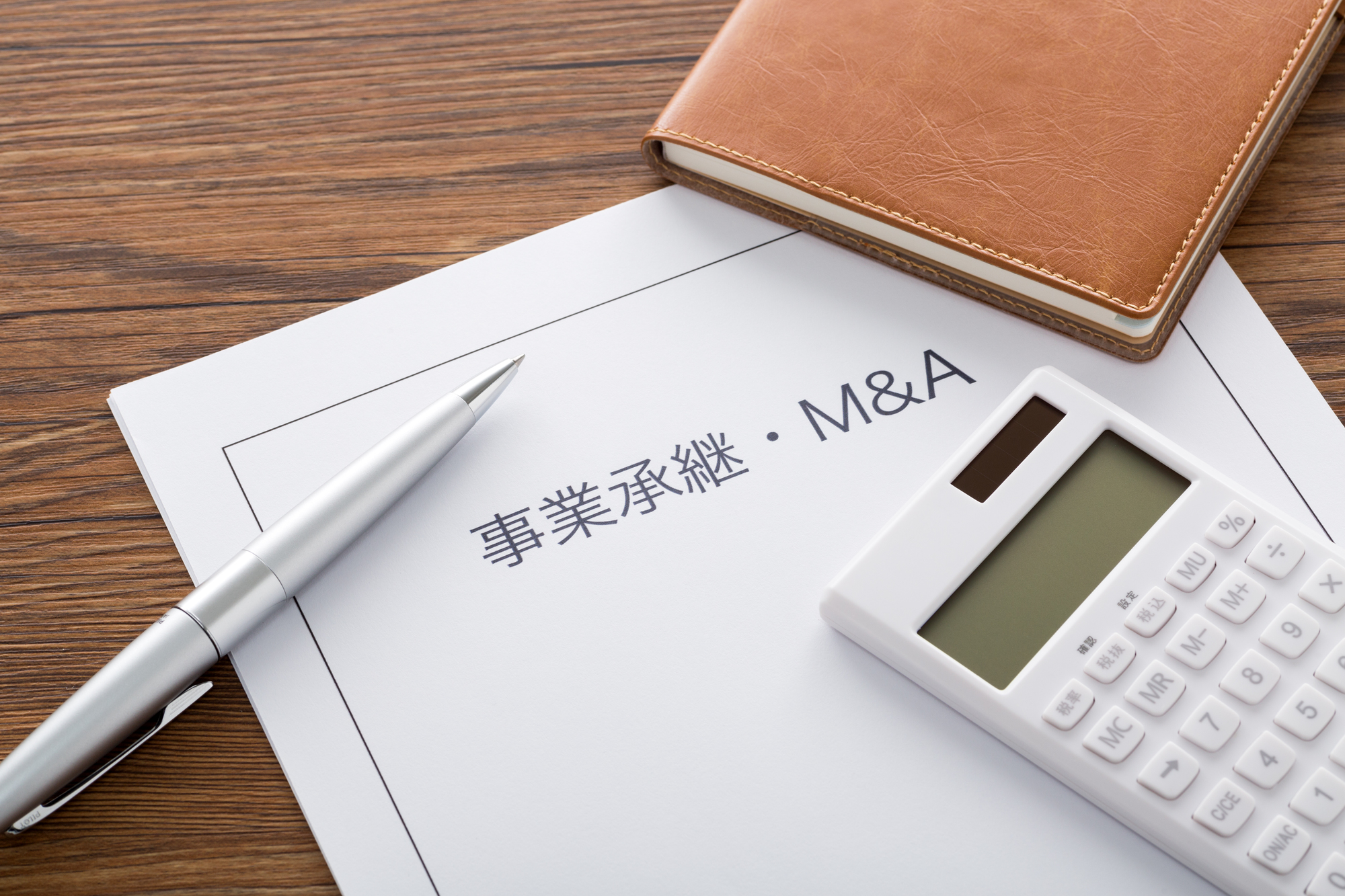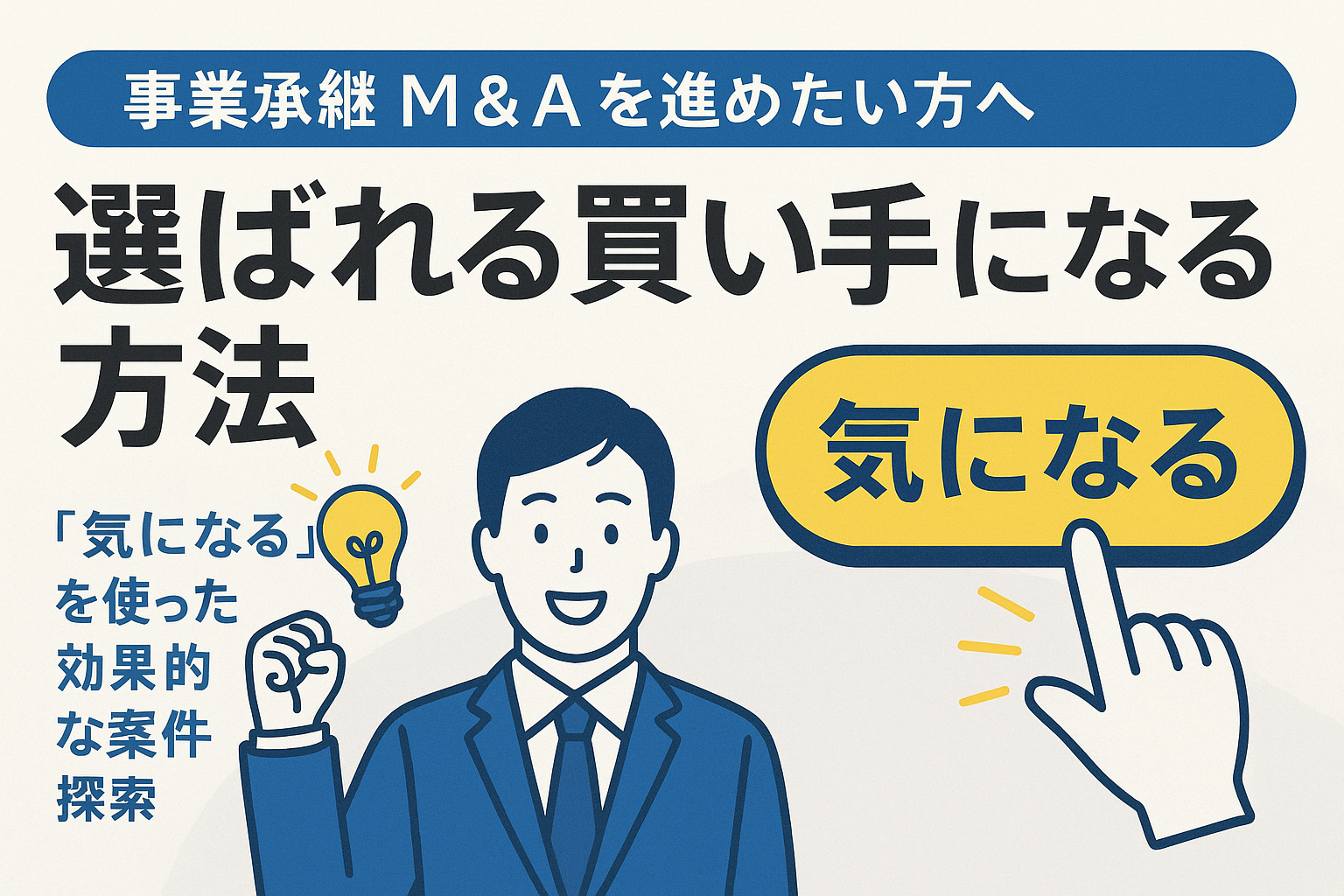事業承継税制はデメリットだらけ?適用外になった場合はどうなる?
事業承継税制を活用すると、事業承継時の相続税・贈与税が猶予・免除されます。メリットが大きい一方で、途中で適用外となった場合は、猶予納税額の一括納付も考えられます。制度を利用する前に、デメリットやリスクを把握しておきましょう。
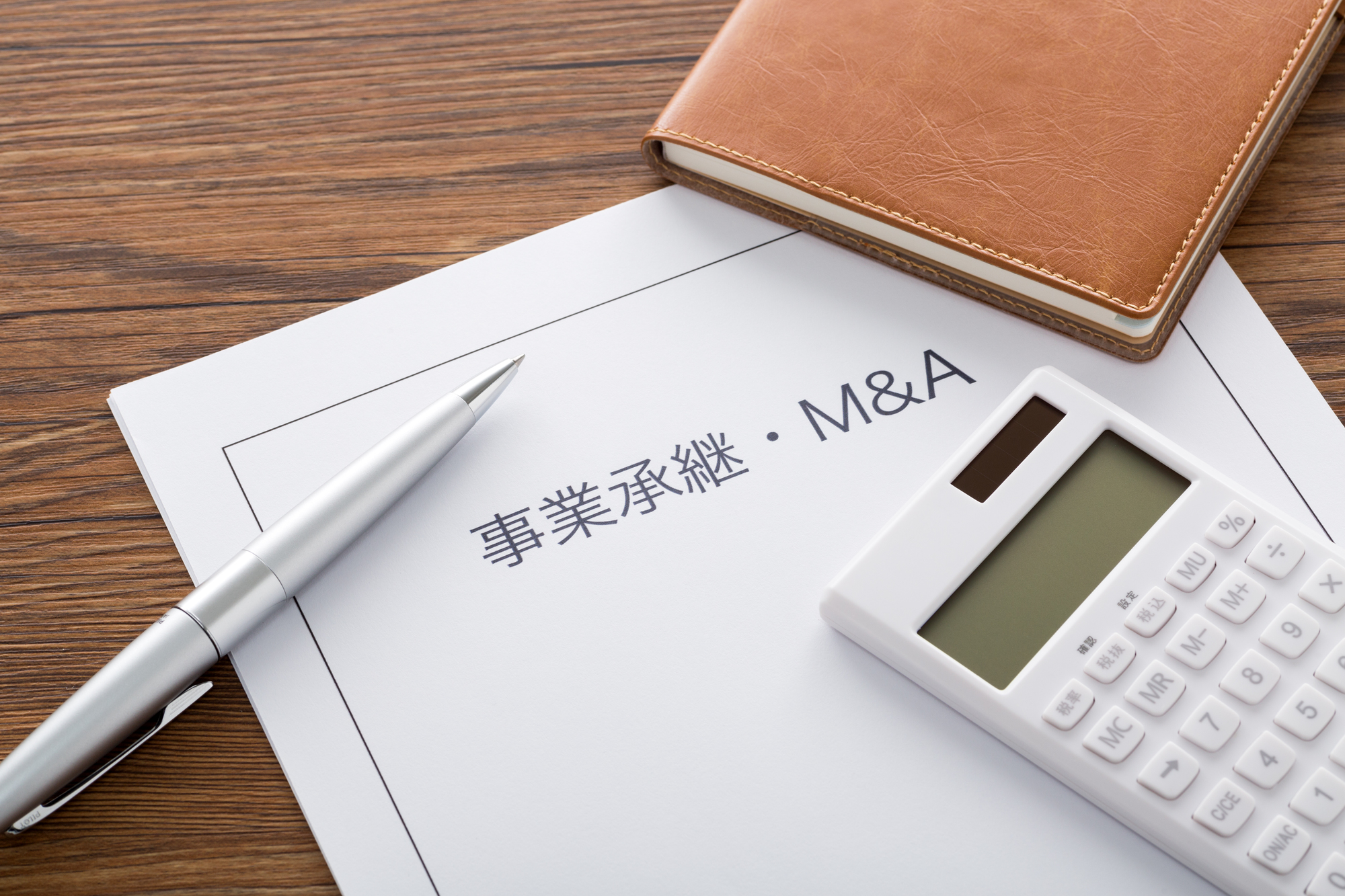

法人版事業承継税制の仕組み

先代経営者から事業を引き継ぐ場合、後継者には贈与税や相続税が課されます。『事業承継税制』は、本来支払うべき税金を猶予する制度で、中小企業の『経営承継円滑化法』に基づいています。
事業承継税制には個人版と法人版がありますが、ここでは会社の株式を対象とする『法人版事業承継税制』について解説を進めます。
非上場会社の事業承継をスムーズにする制度
法人版事業承継税制は、非上場会社の株式を贈与や相続で取得した場合において、贈与税・相続税を『猶予』または『免除』する制度です。
制度ができた背景には、事業承継に関する税金負担が大きく、黒字廃業を選択する中小企業が増えていることが挙げられます。
非上場企業の株式には売買できるマーケットがありません。株式を受け継いでも現金化ができず、後継者は納税のための資金確保に奔走するのが現実です。税金問題で事業承継が進まなければ、業績が好調な企業でも廃業を選択せざるを得ないでしょう。
2025年までに70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人で、うち約半数は後継者が未定です。現状を放置すれば廃業が急増し、約22兆円のGDPと累計約650万人の雇用が消失すると推測されています。
事業承継問題を解決するために制定されたのが、『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)』で、法人版事業承継税制はその中の制度の一つです。
参考:中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題 P.1|中小企業庁
特例措置が設けられ、利用者は増加
2018年の税制改革により、事業承継税制に『10年間限定の特例措置(2018年1月1日から2027年12月31日まで)』が追加され、要件が大幅に緩和されました。
東京商工会議所によると、改正以降の申請件数は右肩上がりで、2021年3月31日時点で累計申請数が9000件に迫っています。
現在、法人版事業承継税制には『一般措置』と『特例措置』の二つが存在します。特例を受けるには『5年以内の特例承継計画』の提出が必要ですが、承認後は以下の条件が適用されます。
| 特例措置 | 一般措置 | |
| 対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大2/3まで |
| 納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |
| 承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
| 雇用確保要件 | 弾力化(要件を満たさなかった場合、その理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し確認を受ける必要あり) | 承継後5年間、平均8割の雇用維持が必要 |
| 事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 | あり(譲渡対価金額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除) | なし |
| 相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与 |
参考:中小企業の円滑な事業承継の実現に向けた意見概要 P.8|東京商工会議所
参考:事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)について|中小企業庁



事業承継税制が使いにくいとされる理由

要件の緩和以来、利用者は増加傾向にあるものの、『使いにくい』『難しい』として、申請をためらう経営者は多いようです。事業承継税制が普及しない背景には何があるのでしょうか?
すぐに免除ではなく、あくまで納税猶予
『事業承継税制を利用すると相続税・贈与税が全額免除される』と思っている人も多いようですが、あくまでも納税猶予です。『猶予』とは、実行のタイミングを延ばすことであって、非課税や免除とは意味が異なります。
後継者(2代目)が経営を続けている間は納税が猶予され、次の後継者(3代目)に事業承継をしてはじめて、猶予税額が免除される仕組みです。『すぐに免除されるわけではない』という点が、使いにくいとされる理由の一つでしょう。
なお、納税の猶予には一定の要件があり、要件を満たせなくなった場合は『猶予の打ち切り』になります。
細かい要件があり、複雑なイメージがある
事業承継税制を受けるには、いくつもの要件をクリアしなければなりません。手続きの煩雑さも、制度の積極的な利用を妨げる要因になっているようです。
事業承継税制では、会社・先代経営者・後継者のそれぞれに適用要件があります。例えば、これは中小企業に適用される制度のため、承継法上の中小企業者の条件を満たさなければなりません。
後継者には、『後継者と同族関係者で50%を超える議決権を保有していること』『承継者が1人の場合、同族内で筆頭株主となること』などの、細かい要件があります。
取り消しになると一括納税の可能性がある
納税が猶予されるのは、一定の要件を満たしている場合です。『納税猶予の取消事由』に該当すると、猶予税額を一括納税しなければならない可能性があります。
例えば、認定取消事由(相続)には、『会社が解散した場合』や『(相続人が)認定承継会社の代表者を退任した場合』などが挙げられます。
納税猶予の期限までの日数に応じた『利子税』も支払わなければならないため、負担はさらに大きくなります。途中で納税するリスクを考えると、制度活用を躊躇する経営者も少なくないようです。
利子税は年3.6%ですが、『利子税特例基準割合』に応じて、年ごとに変動します。詳細は国税庁のHPで確認しましょう。
参考:No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予|国税庁
頼れる専門家を見つけにくくコストもかかる
事業承継税制は手続きが煩雑で条文の規定も細かいことから、税理士や会計士などの専門家に手続きを依頼するのが一般的です。
しかし、専門家にはそれぞれに得意分野があるため、担当者が制度の仕組みや手続きの流れを正確に把握しているとは限らないのが実情です。制度の恩恵を受けたいと思っても、頼れる専門家がなかなか見つからず、断念する経営者も珍しくありません。
また、引き受けてくれる専門家が見つかったとしても、手続きには多くのコストがかかります。計画書や届出書など、書面の作成費用だけでもかなりの額になるでしょう。



贈与税の納税猶予で注意すること

株式贈与は自己が保有する株式を他人へ譲渡する手段の一つで、株式を受け取った人(後継者)は価額に応じた贈与税を納めるのが基本です。贈与税の納税猶予を受けた場合に注意すべき点を確認しましょう。
後継者は3年以上役員を務める必要がある
贈与で納税猶予を受ける場合、後継者は贈与日までに『引き続き3年以上』にわたり、役員の地位を有している必要があります。
例えば、先代経営者の息子が1年間役員を務めた後、数年間会社を離れ、再び役員の地位に就いて2年間が経過したとしましょう。
役員を務めた期間が合計3年であったとしても、『引き続き3年以上』という要件に合致しないため、制度の適用外です。事業承継を考えている経営者は、計画的に後継者を育てる必要があるでしょう。
先代経営者が死亡後、株式は相続税の対象に
贈与者である先代経営者が死亡した場合、猶予されていた贈与税は『免除』となります。
しかし、特例によって得た株式は先代経営者の死亡により、『相続による取得』または『遺贈による取得』に変わるため、今度は『相続税』の対象となる点に注意が必要です。
この際、事業承継税制で『相続税の納税猶予』への切り替え手続きを行うと、『相続税の納税猶予及び免除の特例』が適用されます。切り替えの申請期間は相続開始の日から8カ月以内です。期間内に忘れずに手続きを行いましょう。
相続時精算課税制度を使用する場合
贈与税の計算には、『暦年課税』と『相続時精算課税』があり、いずれかを選択できます。
- 暦年課税:1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される累進課税(最高税率55%)
- 相続時精算課税:贈与時には『特別控除額及び一定の税率』にて贈与税を支払い、相続時には『相続税額(贈与財産+その他の相続財産)』の中から既に支払った贈与税額を精算する方法
相続時精算課税は、贈与後に株価が上昇しても税額に影響はありません。累計贈与額2500万円までは贈与税がかからず、超過分には一律20%の贈与税が課税されます。
株価の値上がりが見込まれるのであれば、相続時精算課税を選択した方が税額を抑えることができる可能性が高いでしょう。
しかし、一度選択すると、贈与者からの贈与は全て相続時精算課税となります。贈与時の株価に課税されるため、業績不振が続いた場合は不利になるでしょう。

相続税の納税猶予で注意すること

『相続』とは、先代経営者が死亡した際に財産を特定の後継者が引き継ぐことを指します。事業承継税制を活用すれば、相続税が猶予されますが、いくつかの注意点があります。
M&Aをすると相続税の免除が打ち切りに
2代目の相続税の納税猶予は、3代目への株式承継時に免除となりますが、後継者になる3代目がまだ幼い場合、相続税免除までの猶予期間はかなり長くなります。
もし3代目に承継せず、M&Aで第三者に株式譲渡した場合、相続税の猶予は打ち切りとなり、猶予されていた相続税と利子税を支払わなければなりません。
なお、猶予適用5年以内では株式の一部譲渡でも打ち切りとなりますが、5年経過後は売却分のみの打ち切りです。
遺留分や他の相続人の相続税に配慮が必要
事業承継税制の適用にあたり、『遺留分』や『後継者以外の相続人の相続税』について配慮する必要があります。
遺留分とは、被相続人の近親者(兄弟姉妹以外)の遺産取得分です。法律上最低限保証されている相続分であるため、特定の後継者に全額を贈与する遺言をしても、相続人による『遺留分減殺請求権』によって取り戻されてしまいます。
遺留分対策として、先代経営者は遺留分を満たすだけの相続財産を確保しておかなければなりません。後継者には自社株、近親者には役員退職金を渡すという手もあります。
また、相続税の税率は『被相続者の総財産』によって決まるため、財産に株が含まれる場合、税率が高くなる恐れがあります。
後継者は事業承継税制で納税が猶予されますが、ほかの相続人は多額の相続税を支払う事態になるでしょう。相続人の納税資金の確保も考えておくべきといえます。




特例事業承継税制も必要な手続きが多い?

事業承継税制には、『一般』と『特例』の二つの枠組みがあります。特例には期限があり、決められた期間までに数多くの書類を提出しなければなりません。手続きの流れを確認しましょう。
特例承継計画の提出、認定申請
特例事業承継税制の大まかな流れは以下の通りです。
- 特例承継計画の作成と提出
- 株式の贈与・相続
- 都道府県知事への認定申請(特例承継計画を添付)
- 税務署への申告
まずは、5年間の事業計画を記した『特例承継計画』の作成を行います。『認定経営革新等支援機関(税理士・商工会・商工会議所)』に所見を記載してもらった上で、2023年3月31日までに都道府県知事に提出しましょう。
相続・贈与の開始後は、贈与税・相続税の申告期限までに、認定申請と税務署への申告を済ませます。
- 贈与税の申告期限:贈与年の翌年の2月1日~3月15日
- 相続税の申告期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内
贈与税の場合、『贈与年の10月15日~翌年1月15日』に認定申請を行います。相続税の場合は『相続の開始⽇の翌⽇から8カ月以内』に申請を済ませましょう。
税務署への申告時は、贈与税・相続税の申告書と『認定書の写し』が必要です。
定期的に継続届出書の提出が必要
贈与税・相続税の申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間を『(特例)経営(贈与)承継期間』と呼びます。
この期間中は毎年、『継続届出書』の提出が必要です。5年を経過した後も、3年ごとに提出を続けなければなりません。
提出時は、『特例認定(贈与・相続)承継会社に関する明細書』や『会社の株主名簿の写し』などの書類の添付が必要です。
継続届出書や添付書類を提出しなかった場合、提出期限の翌日から2カ月を経過する日までに、猶予納税額と利子税を納付することになります。くれぐれも漏れがないように注意しましょう。
担保の提供も必要
相続税・贈与税の申告期限までに、納付税額(利子税を含む)に相当する担保を提供する必要があります。担保と認められる財産は以下の通りです。
- 納税猶予の対象となる非上場株式の全て(非上場株式または持分会社の持分)
- 不動産
- 国債・地方債
- 税務署長が確実と認める有価証券
- 税務署長が確実と認める保証人の保証
非上場株式の全てが提供された場合は、その価値が納税猶予税額に満たない場合でも、税額に相当する担保が提供されたものとみなされます(みなす充足)。
提出書類は、担保の種類によって異なりますが、共通書類として『担保提供書』『担保目録』『速やかに担保関係書類の提出を行う旨の確約書』を提出します。
参考:(問9) 担保提供に関する書類等はいつまでに提出しなければならないのでしょうか。|国税庁

事業承継税制を使うべきケースは?

手続きが多い上、途中で猶予打ち切りになるリスクがあるものの、事業承継税制を積極的に使った方がよい場合もあります。代表的な二つのケースを例に挙げましょう。
自社株対策をしておらず間に合わない場合
自社株対策の一つとして、『後継者に少しずつ株を贈与していくこと』が挙げられます。贈与税の課税方法は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産合計額に応じて課税する『暦年課税制度』が基本です。
110万円を超える部分に贈与税が課されるルールのため、非課税枠を利用して毎年コツコツと贈与をしていけば、将来の相続税の負担を大きく減らせるでしょう。
一方で、自社株対策を行っておらず、贈与や相続時に多額の納付税が発生するようであれば、多少手続きに手間がかかっても事業承継税制を活用するのが賢明といえます。
自社株の評価額が高い場合
安定した利益が出ている企業などは、毎年株価が上がっていきます。評価額が高い場合、贈与や相続の際に高額な税金が発生するため、通常は株式評価額が低いタイミングを狙って贈与するのが一般的です。
非上場企業の株は換金性がなく、評価額が高い時点で贈与や相続が行われると、後継者は納税資金の確保に苦労することになるでしょう。
事業承継税制を活用すれば、事業承継時の税負担を抑えられますが、同時に猶予が取り消された際のリスクについても考えておく必要があります。
まとめ
事業承継税制を活用すれば、事業承継時に発生する贈与税や相続税の負担から解放されます。税制改革以降は要件が大幅に緩和され、これまで制度の対象外だった人も、特例の恩恵を受けることが可能となりました。
ただし、単純に『全額免除される』『後継者にただで譲れる』と思ってしまうと、大きな問題を抱え込む恐れがあります。制度のリスクやデメリットをよく理解した上で活用を検討しましょう。