
スタートアップM&A完全ガイド|売り手・買い手双方の戦略と実務
スタートアップのM&Aは、買い手にとっては革新的な技術や人材を獲得し事業を加速させる手段であり、売り手にとっては事業成長を加速させ、創業者利益を確定させるための有効な戦略です。スタートアップのM&Aの基本から2024年の最新動向、具体的なスキーム、成功・失敗事例、売り手・買い手双方の視点に立った実務プロセス、さらには経済産業省の支援策まで、網羅的に解説します。
- 08 スタートアップのM&Aの流れ
- STEP1:戦略策定・ターゲット選定
- STEP2:企業価値評価・デューデリジェンス
- STEP3:基本合意(LOI)・価格交渉
- STEP4:契約締結・クロージング
- STEP5:PMIと統合後の経営
- 09 スタートアップのM&Aに関する会計・税務・法務の主要ポイント
- ストックオプションと資本政策の整理
- 繰越欠損金と税務上の留意点
- 株式評価と課税関係の把握
- 知的財産権とライセンス契約の精査
- 最終契約書の法務・税務レビュー
- 11 スタートアップのM&Aにおける仲介会社・アドバイザーの選び方
- 選び方①:スタートアップのM&Aの実績が豊富
- 選び方②:業界知識とネットワークを持つ
- 選び方③:手数料体系が明確で納得できる
- 選び方④:契約内容と責任範囲が明確
- 選び方⑤:コミュニケーションが丁寧で迅速


自社の成長戦略としてM&Aを検討している買い手企業様、そして事業の更なる飛躍やイグジットを目指す売り手企業(スタートアップ)の経営者様。M&Aの進め方や成功のポイントがわからず、行動に移せずにいませんか?
スタートアップのM&Aは、買い手にとっては革新的な技術や人材を獲得し事業を加速させる手段であり、売り手にとっては事業成長を加速させ、創業者利益を確定させるための有効な戦略です。
この記事では、スタートアップのM&Aの基本から2024年の最新動向、具体的なスキーム、成功・失敗事例、売り手・買い手双方の視点に立った実務プロセス、さらには経済産業省の支援策まで、網羅的に解説します。
本記事を読み終える頃には、M&Aを成功に導くための具体的な知識が身につき、自社の戦略を描くための新たな一手が見つかるはずです。
まずはこの記事で、スタートアップのM&Aの全体像を掴み、未来に向けて第一歩を踏み出しましょう。
スタートアップのM&Aとは

スタートアップのM&Aとは、設立から数年の若い企業(スタートアップ)が関わる企業の合併・買収(M&A)のことです。
買い手企業は、スタートアップの持つ革新的な技術やサービス、優秀な人材を獲得することで、新規事業の創出や既存事業の強化といったオープンイノベーションを加速させることを目指します。
一方、売り手であるスタートアップにとっては、大手企業の傘下に入ることで、資金力や販路などの経営資源を活用し、事業成長を大きく加速できます。
近年、日本では大企業によるオープンイノベーションの必要性の高まりや、国による支援策の拡充を背景に、スタートアップM&Aは増加傾向にあります。
これは、買い手にとっては成長戦略の重要な選択肢として、売り手にとってはIPO以外の有力なイグジット手段として、その重要性を増していることを示しています。

M&Aを検討する理由とタイミング
M&Aは、売り手と買い手の成長戦略が一致したときに成立します。それぞれの立場から、M&Aを目指す理由と最適なタイミングは異なります。
売り手(スタートアップ)がM&Aを目指す理由とタイミング
スタートアップがM&Aを目指す最大の理由は、事業の成長を飛躍的に加速させられる点にあります。
買い手企業の持つ豊富な経営資源(資金、販路、人材など)を活用することで、自社単独では時間のかかるスケールアップを短期間で実現可能です。
また、M&Aは創業者や投資家にとって、IPOと並ぶ有力な資金回収手段でもあります。
M&Aを実行するタイミングは、プロダクトやサービスが市場に受け入れられ、さらなる成長のために外部リソースが必要となった段階が一般的です。
買い手企業がM&Aを目指す理由とタイミング
買い手企業がM&Aを目指す主な理由は、事業開発のスピードアップと、自社にないリソースの獲得です。
ゼロから新規事業を立ち上げるよりも、既に市場で実績のあるスタートアップを買収する方が、迅速かつ確実に事業を軌道に乗せられます。
また、革新的な技術やノウハウ、優秀なエンジニアや経営チームをまとめて獲得できる点も大きな魅力です。
M&Aを検討するタイミングとしては、既存事業の成長が鈍化し始めたときや、新たな市場へ迅速に参入したいときなどが挙げられます。

スタートアップのM&Aのメリット
スタートアップのM&Aは、買い手と売り手の双方に大きなメリットをもたらす可能性があります。
双方の立場からメリットを理解することで、効果的なM&A戦略を立てられます。
買い手側のメリット
- 事業の成長が加速する:大企業の経営資源(資金、販路、ブランド力)を活用し、事業を急成長させられます。
- 個人保証の責任から解放:創業者が負っていた借入金の個人保証や担保を解消できます。
- 従業員の雇用が守られる:大企業の傘下に入ることで、従業員の雇用安定や待遇改善が期待できます。
- 取引先との関係を維持:信用力の高い企業のグループに入ることで、既存の取引先との関係を維持・強化できます。
- 高い売却益を得られる: 創業者や株主は、保有株式を売却し大きな利益を得られます。
- 次の事業に投資できる:売却で得た資金を元手に、新規事業に挑戦できます。
- 後継者問題を解消できる:経営者の高齢化などによる後継者不在の問題を解決できます。


スタートアップのM&Aのデメリット・リスク
多くのメリットがある一方で、スタートアップM&Aにはデメリットやリスクもあります。
こうした問題を事前に把握し、対策を取ることがM&Aの成功には欠かせません。
買い手のデメリット
- 統合に時間と手間がかかる:異なる文化を持つ組織の統合(PMI)には、想定以上の時間とコストがかかることがあります。
- シナジー効果が得られない:事前の見込みが甘く、期待したほどの相乗効果が発揮されないリスクがあります。
- 人材が流出する可能性あり:買収後に主要な役員や技術者が退職し、企業の競争力が下がる恐れがあります。
- のれんの減損リスクがある: 買収額が純資産を上回る部分(のれん)は、将来減損処理が必要になる場合があります。
- 隠れた債務が見つかる恐れ: 適正評価手続き(デューデリジェンス)で見抜けなかった簿外債務や偶発債務が、買収後に発覚する場合があります。
- 買収コストが高額になりやすい: 競争が激しい分野では、買収額が高騰し、投資回収が難しくなることがあります。
- 文化や価値観が合わない場合がある: 企業文化やビジョンの違いで、組織内に対立が生じることがあります。

売り手のデメリット
- 希望条件で売却できない可能性がある:買い手が見つからなかったり、希望する条件での売却が困難だったりする場合があります。
- 統合作業に時間がかかる:買収後の統合プロセスに多大な労力を要し、本来の事業に集中できない恐れがあります。
- 取引先に不安を与える恐れがある:経営権の変更で、取引先が取引の継続に不安を感じる可能性があります。
- 社員の士気が下がる恐れがある:処遇の変化や将来への不安から、従業員のモチベーションが低下することがあります。
- 顧客が離れる可能性がある:サービス変更などを理由に、既存顧客が離れるリスクがあります。
- 経営の主導権を失う場合もある:買い手企業の意向で、創業者が望む経営ができなくなる可能性があります。
- 秘密情報が外部に漏れることも:交渉中に、自社の技術や顧客情報などの機密情報が漏洩するリスクがあります。
-
事例1:PayPalによるPaidyの買収(2021年)
- 概要:米決済大手PayPalが日本のBNPL(Buy Now, Pay Later)スタートアップであるPaidyを約3,000億円で買収。日本のフィンテック業界で過去最大級のM&Aとして注目されました。
- 参考URL: https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-09-08/QZ3CA3DWLU6A01
-
事例2:Hugging FaceなどによるSakana AIへの出資(2024年)
- 概要:シリコンバレーの有力VCであるNew Enterprise Associates(NEA)、Khosla Ventures、Lux Capital、Translink Capital、500 Global、さらにNVIDIAが日本の生成AIスタートアップであるSakana AIに出資。日本企業からの出資と合わせてシリーズAで約100~200億円、累計で約300億円の調達に成功しました。日本の高度なAI技術を持つスタートアップに対する、海外投資家の高い関心を示す事例です。
- 参考URL: https://sakana.ai/series-a-jp/
-
具体例:ZOZOによるyutoriの買収(2020年)
- 概要:ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営するZOZOが、Z世代から人気を集めるD2Cアパレルブランドを展開するスタートアップ「yutori」を子会社化しました。ZOZOは、yutoriの持つ若者向けのブランド創造力やSNSマーケティングのノウハウを取り込むことで、新たな顧客層の開拓を目指しました。
- 参考URL: https://www.wwdjapan.com/articles/1105081
-
具体例:塩野義製薬によるQpex Biopharmaの買収(2023年)
- 概要:塩野義製薬が、薬剤耐性(AMR)菌に対する新規抗菌薬の開発を手がける米国のバイオ医薬品企業Qpex Biopharma Inc.を買収。自社だけでは困難な革新的な医薬品の開発パイプラインを獲得し、AMR問題への貢献を目指す戦略的な買収です。
- 参考URL: https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2023/6/20230626.html
-
具体例:カーライル・グループによるUzabaseの買収(2022年)
- 概要:米大手投資ファンドのカーライル・グループが、経済情報プラットフォーム「SPEEDA」やソーシャル経済メディア「NewsPicks」を運営する株式会社ユーザベースのTOB(株式公開買付け)を実施し、非公開化しました。ファンドの支援のもとで、短期的な業績にとらわれず、中長期的な視点での事業成長を目指すことが目的です
- 参考URL: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0983I0Z01C22A1000000/
- 【買い手の視点】なぜM&Aを行うのか」という目的を明確化し、自社の経営戦略に合致するスタートアップをリストアップします。市場での位置づけや技術の将来性、企業文化の適合度などを分析し、ターゲット企業を選定します。
- 【売り手の視点】自社の強みや将来性を客観的に評価し、どのような企業と組めば事業を最大化できるかを検討します。自社の条件を整理し、M&Aアドバイザーと相談して買い手候補を探します。
- 【買い手の視点】ターゲット企業の価値を算定する「企業価値評価(バリュエーション)」を行い、同時に財務・法務・ビジネスモデルなどを詳細に調査する「デューデリジェンス(DD)」を実施して、潜在リスクを洗い出します。
- 【売り手の視点】買い手から要求される資料を迅速かつ正確に提出し、デューデリジェンスに協力します。自社の企業価値を正当に評価してもらうため、事業計画の合理性や技術の優位性を明確に説明する準備が必要です。
- 【買い手の視点】 デューデリジェンスの結果を踏まえ、買収価格や譲渡条件などについて交渉を行います。独占交渉権を確保し、主要な合意事項をまとめた「基本合意書(LOI)」を締結します。
- 【売り手の視点】買い手からの提案を慎重に検討し、希望条件とのすり合わせを行います。従業員の処遇や事業の継続性など、価格以外の条件も丁寧に協議することが重要です。
- 【双方の視点】基本合意の内容に基づき、弁護士などの専門家を交えて最終的な契約条件を詰め、株式譲渡契約書(SPA)などの契約書類を作成します。双方が署名・捺印し、株式の譲渡や対価の支払いといったクロージング手続きを経て、M&Aが完了します。
- 【買い手の視点】M&Aの成否を分ける最も重要なフェーズです。買収後の統合プロセスである「PMI(Post Merger Integration)」を計画的かつ迅速に実行し、期待したシナジー効果を早期に実現することを目指します。
- 【売り手の視点】買い手企業と協力し、円滑な統合に貢献します。経営陣や従業員が新しい環境に適応し、能力を発揮できるよう、積極的にコミュニケーションを取り企業文化の融合を支えます。
-
① 中小M&Aガイドライン
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline.html -
② オープンイノベーション促進税制の概要と申請手続き
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html -
③ スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針(公正取引委員会+経産省)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/startup.html -
④ スタートアップ支援策一覧(経産省)
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startup/index.html

2024年のスタートアップM&A市場動向と統計データ

2024年のスタートアップM&A市場は、引き続き活況です。
大企業によるオープンイノベーションの推進や、事業承継問題の解決策としてのM&A活用が市場を牽引しており、こうした動向を理解することは、効果的な経営戦略に欠かせません。
ここでは、最新の統計データに基づき、市場の現状と今後の見通しを解説します。
M&A件数・金額の推移
日本のM&A市場は、近年活発な動きを見せています。
M&Aアドバイザリー大手のレコフの調査によると、日本企業が関わったM&A件数および金額は以下の通りです。
| 年 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2021年 | 4,280件 | 約16.5兆円 |
| 2022年 | 4,304件 | 約11.4兆円 |
| 2023年 | 4,015件 | 約17.9兆円 |
| 2024年 | 4,700件 | 約19.6兆円 |
出典:株式会社レコフ「日本のM&A市場の動向」各年版より当社作成
URL: https://www.recof.co.jp/
2023年は一時的に件数が前年を下回りましたが、2024年に入り再び回復基調で、2025年上期の件数も2,509件で、前年同期比+7.1%です。
これは、世界的な金融環境の安定や、日本企業の成長意欲の高まりが背景にあります。特にスタートアップを対象としたオープンイノベーション目的のM&Aは、大手企業を中心に引き続き活発です。IT・AI、ヘルスケア、SaaSなどの成長分野のM&Aが市場をけん引しており、今後もデジタルトランスフォーメーション(DX)やGX(グリーン・トランスフォーメーション)の流れを受け、関連分野でのM&Aはさらに活発化すると予測されます。
市場拡大・活性化の背景
スタートアップM&A市場が活性化している背景には、複数の要因があります。
買い手側の要因としては、大企業が自社単独での研究開発に限界を感じ、外部の技術やアイデアを取り込むオープンイノベーションを加速させています。
一方、売り手側の要因としては、ベンチャーキャピタル(VC)が出資した資金の償還期限(投資ファンドの満期)が迫り、投資回収の手段としてM&Aを選択するケースも増えています。
さらに、経済産業省が主導するオープンイノベーション促進税制などの政策的な後押しも、市場拡大に大きく寄与しています。
グローバル市場との比較
日本のスタートアップM&A市場は拡大しているものの、米国や中国といったグローバル市場と比較すると、まだ規模は小さい状況です。
米国では、GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)に代表される巨大IT企業が、次世代の技術を獲得するために巨額の資金でスタートアップを積極的に買収しています。
しかし、近年は海外の投資家やグローバル企業が、日本の質の高い技術やユニークなビジネスモデルを持つスタートアップに注目し始めており、実際に大型のクロスボーダーM&Aも生まれています。象徴的な事例は、以下のようなものが挙げられます。
グローバル市場との比較
日本のスタートアップM&A市場は拡大しているものの、米国や中国といったグローバル市場と比較すると、まだ規模は小さい状況です。
米国では、GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)に代表される巨大IT企業が、次世代の技術を獲得するために巨額の資金でスタートアップを積極的に買収しています。
しかし、近年は海外の投資家やグローバル企業が、日本の質の高い技術やユニークなビジネスモデルを持つスタートアップに注目し始めており、実際に大型のクロスボーダーM&Aも生まれています。象徴的な事例は、以下のようなものが挙げられます。
今後は、クロスボーダーM&A(国境を越えたM&A)も増加し、日本の市場は今後さらにグローバルな競争環境に置かれるでしょう。


主要なスタートアップのM&A事例
スタートアップのM&Aの成功確率を高めるためには、過去の事例から学ぶことが非常に重要です。
ここでは、近年の主要なM&A事例を3つのタイプに分けて紹介し、その背景とポイントを解説します。
事例1:IT・AI分野の大型M&A
近年、最も活発なのがIT・AI分野のM&Aです。大手IT企業(買い手)が、自社のサービス強化や新規事業創出を目的として、独自のAI技術や優秀なエンジニアを抱えるスタートアップ(売り手)を買収するケースが相次いでいます。成功の鍵は、買収後の技術統合(PMI)を円滑に進め、売り手側の技術者が能力を発揮できる環境を整えることです。
事例2:ヘルスケア・製造業のイノベーション型M&A
ヘルスケアや製造業といった伝統的な産業でも、M&Aによるイノベーション創出の動きが活発化しています。これらのM&Aは、買い手にとっては既存事業の枠組みを超えた新たな価値創造を、売り手にとっては研究開発の加速と安定した事業基盤の獲得を可能にします。
事例3:MBO(経営陣による買収)/ TOB(株式公開買付け)
近年、上場しているスタートアップが、投資ファンドの支援を受けてMBO(経営陣による買収)を行ったり、TOB(株式公開買付け)によって非公開化したりするケースが増えています。これは、短期的な株価や業績に左右されず、中長期視点で経営改革や事業投資を進めることが目的です。


スタートアップのM&Aで用いられるスキーム
スタートアップのM&Aでは、目的や状況に応じて複数の手法(スキーム)が使われます。
それぞれのスキームには特徴があり、税務や法務上の手続きも異なるため、自社の目的に最も合った手法を選択することが重要です。
ここでは、代表的な6つのスキームについて、その概要と違いを表形式で分かりやすく解説します。
| スキーム | 概要と他の手法との違い |
|---|---|
| 株式譲渡 | 会社の支配権(株式)を現金で売買する最も基本的な手法。会社はそのまま存続し、株主だけが変わります。 |
| 株式交換 | 買収の対価として現金の代わりに買い手企業の株式を交付し、売り手企業を完全子会社化する手法。売り手企業の株主は、買い手企業の株主になります。 |
| 株式移転 | 新しく設立した会社を完全親会社とし、既存の会社(売り手)がその完全子会社となる手法。複数の企業を統合してホールディングス体制を築く際などに用いられます。 |
| 合併 | 複数の会社を法的に一つの会社に統合する手法。少なくとも一つの会社は消滅します。株式譲渡などとは異なり、会社そのものが一つになります。 |
| 事業譲渡 | 会社全体ではなく、特定事業(資産、人材、契約など)を選んで個別に売買する手法。買い手は必要な事業だけを取得でき、不要な負債を引き継ぐリスクを避けやすいのが特徴です。 |
| 会社分割 | 事業譲渡と似ていますが、特定の事業に関する権利義務を包括的に別会社へ承継させる手法。事業譲渡のように取引先などから個別の同意を得る必要がない点が大きな違いです。 |





スタートアップのM&Aの流れ
スタートアップのM&Aは、体系化されたプロセスに沿って計画的に進める必要があります。
戦略策定から交渉、契約締結、そして買収後の統合(PMI)まで、各ステップにおける売り手・買い手双方の視点を理解することが成功の鍵です。
STEP1:戦略策定・ターゲット選定
STEP2:企業価値評価・デューデリジェンス
STEP3:基本合意(LOI)・価格交渉
STEP4:契約締結・クロージング
STEP5:PMIと統合後の経営






スタートアップのM&Aに関する会計・税務・法務の主要ポイント
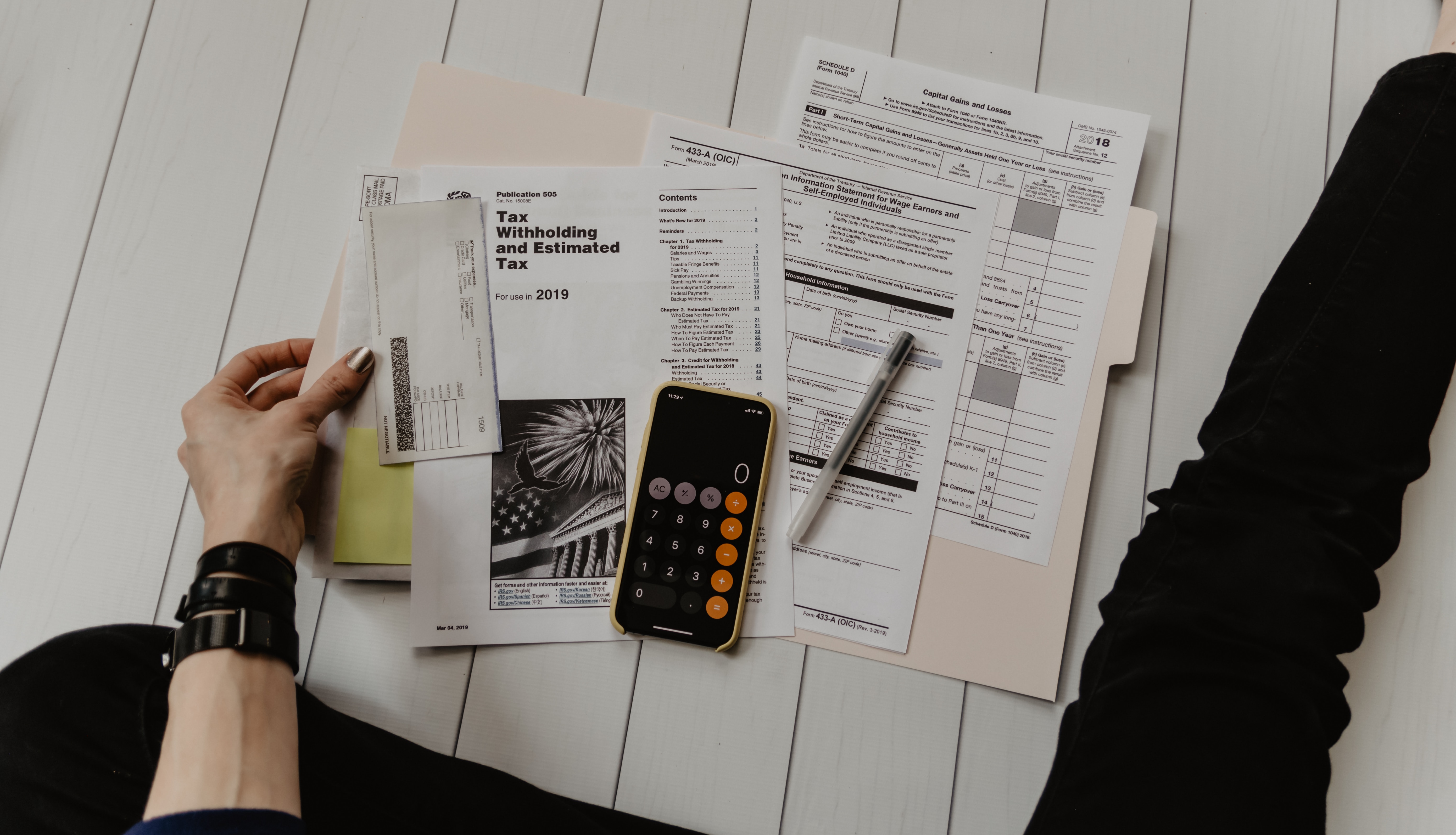
スタートアップのM&Aを円滑に進めるには、会計・税務・法務の知識が欠かせません。
これらの論点は売り手・買い手双方に影響するため、両者が正しく理解し、専門家を交えて慎重に対応する必要があります。
ストックオプションと資本政策の整理
スタートアップは、従業員のインセンティブとしてストックオプションを発行しているケースが多くあります。
M&Aの際には、これらのストックオプションをどのように扱うか(引き継ぐ、消滅させるなど)を事前に整理し、契約に明記する必要があります。
行使価格や発行済株式数への影響を正確に把握し、適切な資本政策を立てることが重要です。
繰越欠損金と税務上の留意点
赤字経営のスタートアップも多いですが、その累積赤字(繰越欠損金)は、将来の黒字と相殺して法人税負担を軽減できる貴重な税務上の資産です。
しかし、M&Aのスキームによっては、この繰越欠損金の引継ぎが制限される場合があります。
合併や会社分割を行う際には、欠損金の引継ぎ要件を専門家と共に確認することが重要です。
株式評価と課税関係の把握
M&Aにおける株式の取引価格は、当事者間の合意で決まります。
しかし、税務上は客観的な時価で評価する必要があり、時価と取引価格が大きく乖離している場合、株主に対して予期せぬ贈与税などが課されるリスクがあります。
特に株主間で株式を売買する際には、適切な株式評価を行い、税務リスクを正確に把握しておく必要があります。
知的財産権とライセンス契約の精査
スタートアップの価値の源泉は、特許や商標、ソフトウェアなどの知的財産権(IP)であることが少なくありません。
M&Aに際しては、これらの権利が法的に有効か、他社の権利を侵害していないか、重要なライセンス契約にM&Aを制限する条項(チェンジオブコントロール条項)がないか確認することが重要です。
最終契約書の法務・税務レビュー
最終契約書(株式譲渡契約書など)は、M&Aのすべての条件を法的に確定させる最も重要な書類です。
特に、売り手企業が表明した内容が事実と異なっていた場合の「表明保証条項」や、それによって生じた損害を補償する「補償条項」は、リスクを管理する上で中心的な役割を果たします。
弁護士や税理士による徹底的なレビューを受け、法務・税務上のリスクを最小限に抑えることが不可欠です。


経済産業省・政府によるスタートアップのM&A支援とガイドライン
日本政府および経済産業省は、オープンイノベーションを促進し、スタートアップエコシステムを活性化させるため、M&Aに関する様々な支援策やガイドラインを整備しています。
これらの制度は、売り手・買い手双方が円滑な取引を進める上で非常に有用であり、税制優遇を受けられる可能性もあります。
以下に、主要な支援策と関連資料のリンクをまとめましたので、ぜひご活用ください。
スタートアップのM&Aにおける仲介会社・アドバイザーの選び方

スタートアップのM&Aは専門性が高く、成功させるためには売り手・買い手双方にとって信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)は、豊富な知識と経験でM&Aの全プロセスをサポートしてくれます。
ただし、質には差があるため慎重に選ぶ必要があります。ここでは、良いパートナーを見つけるための5つの選び方を解説します。
選び方①:スタートアップのM&Aの実績が豊富
M&Aと一言で言っても、事業承継型M&AとスタートアップのM&Aでは、評価方法や交渉のポイントが大きく異なります。
スタートアップのM&Aに関する専門知識と豊富な支援実績を持つ会社を選ぶことが重要です。
過去の取引件数や成功事例を確認し、自社に近い案件の経験があるかを見極めることが重要です。
選び方②:業界知識とネットワークを持つ
自社の属する業界に精通しているかどうかも重要な選定基準です。
業界の動向や特有のビジネス慣行を深く理解しているアドバイザーであれば、より的確な企業価値評価やシナジー効果の高い相手候補の紹介が期待できます。
幅広いネットワークを持ち、自社だけではアプローチできないような有力な候補先を提案してくれるかどうかも見極めましょう。
選び方③:手数料体系が明確で納得できる
M&A仲介の手数料体系は、会社によって様々です。
一般的には、取引金額に応じて算出される「レーマン方式」による成功報酬が中心ですが、着手金や中間報酬が必要な場合もあります。
契約前に手数料の算出方法や支払い時期の説明を受け、その内容が明確で納得できることを確認します。
選び方④:契約内容と責任範囲が明確
アドバイザーと締結する業務委託契約書の内容は、隅々まで確認することが重要です。
特に秘密保持義務の範囲、独占交渉権の有無、契約解除条件は、後のトラブル防止に重要です。
アドバイザーの責任範囲と提供されるサービス内容が明確に記載されているかを確認し、不明な点は事前に解消しておきましょう。
選び方⑤:コミュニケーションが丁寧で迅速
M&Aのプロセスは長期間にわたることが多く、担当者との相性やコミュニケーションの質は非常に重要です。
質問に対するレスポンスが迅速か、専門的な内容を分かりやすく説明してくれるか、さらに、自社の立場に立ち親身に相談に乗ってくれるか、といった点を見極めましょう。
信頼関係を築けるパートナーを選ぶことが、M&A成功の鍵となります。



M&Aプラットフォームという新たな選択肢
近年、M&Aの進め方に新たな選択肢が登場しています。
それが、オンラインで売り手と買い手を直接マッチングさせる「M&Aプラットフォーム」です。
従来の仲介会社を介する方法に比べ、手数料を安く抑えられる点や、地域や業種を問わず、幅広い相手先候補をスピーディーに探せる点が大きな魅力です。
特に、コストを抑えて効率的にM&Aを進めたいスタートアップにとって有効な手段です。
ただし、交渉や手続きを自社主導で進める必要があるため、ある程度の知識は必要となります。
仲介会社とプラットフォーム、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。


スタートアップのM&Aに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、スタートアップのM&Aに関して、経営者や担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. スタートアップのM&Aの相場・評価の目安は?
A1.スタートアップの企業価値評価に決まった相場はありませんが、類似企業のM&A事例や、将来の収益性を予測するDCF法などが用いられます。
IT業界では「売上高の数倍〜十数倍」、SaaSビジネスでは「ARR(年間経常収益)の数倍」といった指標が参考にされることもありますが、技術の独自性や市場の成長性によって大きく変動します。
Q2. PMIや人材流出リスクを防ぐには?
A2. PMI(買収後の統合プロセス)を成功させ、人材流出を防ぐには、交渉段階から統合後のビジョンを共有し、従業員の不安を解消することが重要です。
特に、キーパーソンとなる役員やエンジニアに対しては、魅力的な処遇や権限移譲を提示し、モチベーションを維持する施策(リテンションプラン)を講じることが効果的です。
Q3. M&A後ののれん償却や税務処理のポイントは?
A3. M&Aにおいて、買収価格が対象企業の純資産額を超える場合、その差額は「のれん」として会計上、資産計上されます。
日本の会計基準では、この「のれん」を20年以内の期間で均等に償却する必要があり、販売管理費として計上されるため、営業利益を減らす要因となります。
税務上の取り扱いも複雑なため、必ず会計士や税理士に相談してください。
Q4. スタートアップのM&AとIPO・バイアウトとの違いは?
A4. IPO(新規株式公開)は、証券取引所に上場し、広く一般投資家から資金を調達する方法です。
一方、M&Aは特定の企業に経営権を譲渡する方法です。
バイアウトはM&Aの一種で、主に投資ファンドが企業の株式を買い取り、経営改善を行った後に売却して利益を得る手法を指します。
それぞれメリット・デメリットが異なるため、自社の成長戦略に合った出口戦略を選ぶことが重要です。
Q5. M&Aに失敗した場合の主なリスクは?
A5. M&Aが失敗に終わった場合、期待した効果が得られないだけでなく、複数のリスクが表面化します。
具体的には、買収した事業が不振に陥り「のれんの減損」を迫られる会計上のリスク、主要な経営陣や従業員が退職してしまう「人材流出リスク」、そして、統合がうまくいかずに組織が混乱する「経営上のリスク」などが挙げられます。
まとめ
本記事では、スタートアップのM&Aを、売り手と買い手双方の視点から網羅的に解説しました。
買い手にとってM&Aは、革新的な技術や人材を獲得し、事業を飛躍させるための強力なエンジンです。
一方、売り手にとってM&Aは、事業成長を加速させ、創業者利益を最大化するための重要な戦略的選択肢となります。
M&Aを成功させるためには、売り手・買い手双方が自社の戦略に基づいた明確な目的を持ち、適切なパートナーを選び、そして何よりも買収後の丁寧な統合プロセス(PMI)を協力して進めることが不可欠です。
この記事が、皆様の未来を切り拓く一助となれば幸いです。







