
会計事務所・税理士事務所のM&A|メリット・相場・事例から手続きまで徹底解説
後継者不足や成長戦略に効く会計事務所M&A。価格算定の目安、実務フロー、仲介/プラットフォーム選び、リーク対策や人材流出防止の勘所を具体的に解説。
- 08 M&A・事業承継の流れ・手順
- STEP1:M&Aの検討・準備
- STEP2:専門家への相談
- STEP3:譲渡先の選定(マッチング)
- STEP4:トップ面談・基本合意の締結
- STEP5:デューデリジェンス(買収監査)の実施
- STEP6:最終契約の締結とクロージング
- STEP7:PMI(経営統合プロセス)
- 10 会計事務所・税理士事務所M&Aの仲介会社・支援機関の選び方
- 信頼できるパートナー選びの重要性
- 仲介会社・支援機関を選ぶ際の比較ポイント
- おすすめのM&A仲介会社・支援サービス
- 自社の規模とニーズで選ぶべきパートナーは変わる
- 幅広いネットワークと実績を誇る「大手M&A仲介会社」
- 業界特有の事情に精通した「専門特化型ブティック」
- コストを抑えて相手を探せる「M&Aマッチングプラットフォーム」
- 中立的な立場で相談できる「公的支援機関」


「後継者が見つからず、事務所の将来に不安を感じる」「事業をさらに拡大したいが、何から始めれば良いかわからない」といった、会計事務所の経営者の方が抱える特有の悩みは、決して少なくありません。
そのような課題を解決する有効な手段の一つが、M&A(企業の合併・買収)です。本記事では、会計事務所や税理士事務所のM&Aについて、その背景やメリット・デメリットから、価格相場の考え方、具体的な成功事例、そしてM&Aを成功に導くための手続きの流れまで、わかりやすく丁寧に解説します。
この記事を読むことで、M&Aに関する疑問や不安が解消され、自社の状況に合った次の一歩を踏み出すための知識を得られるでしょう。
ぜひ、事務所の輝かしい未来を切り拓くための羅針盤としてご活用ください。
会計事務所・税理士事務所とは

会計事務所や税理士事務所は、企業や個人に会計や税務の専門サービスを提供する事業所です。これらは企業の健全な経済活動を根幹から支える、社会的に非常に重要な役割を担っています。
両者は混同されがちですが、厳密には違いがあります。税理士事務所は、税理士資格を持つ所長が運営し、税務代理・税務書類の作成・税務相談といった法律で定められた「税理士の独占業務」を担います。
一方、会計事務所は、記帳代行や経営コンサルティングを主業務とすることが多く、税理士が在籍していない場合もあります。
いずれの事務所も、クライアントの成長を支えるパートナーとして、質の高いサービスを提供しています。

会計事務所・税理士事務所のM&Aと事業承継の基礎知識
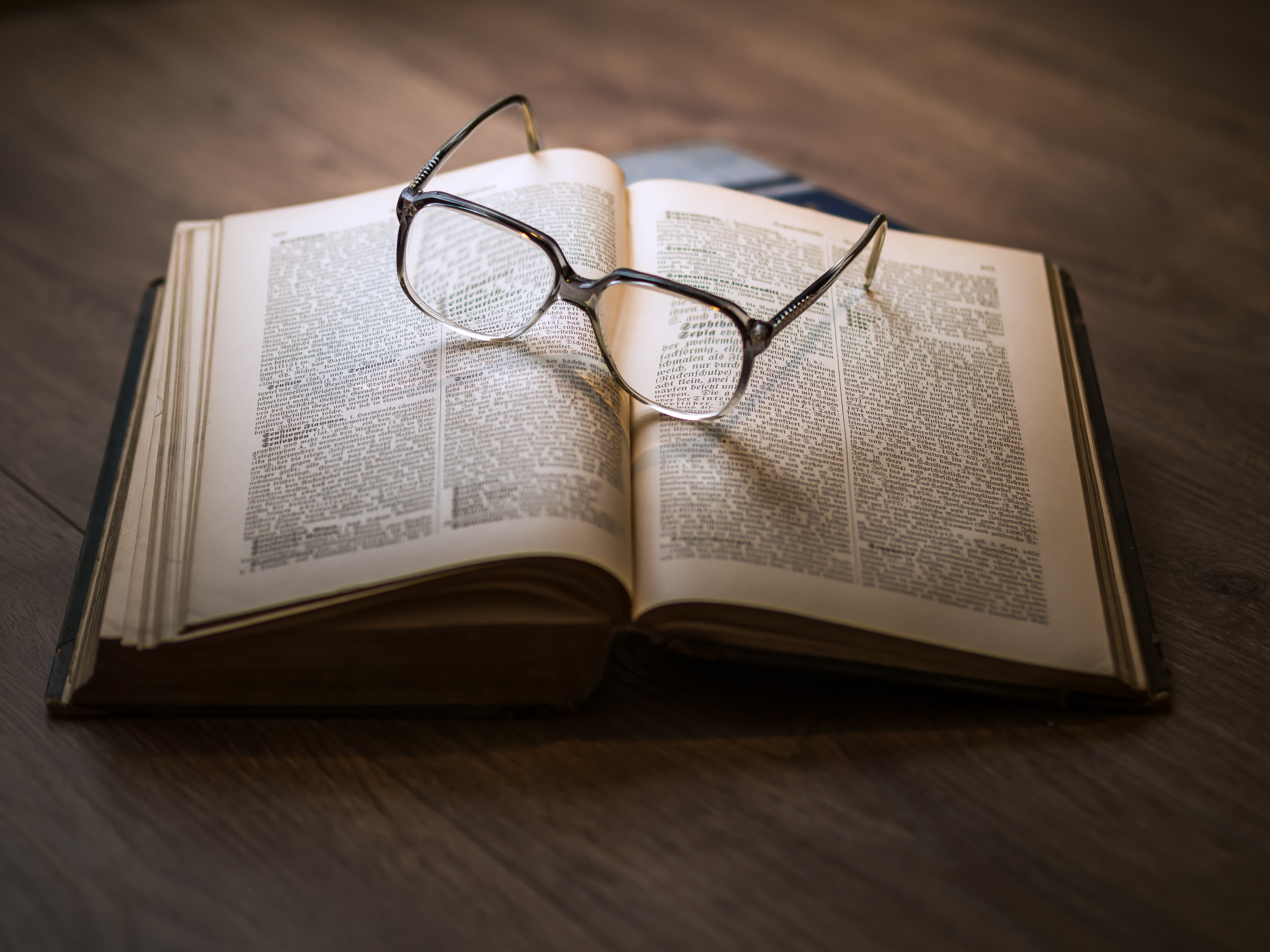
会計事務所や税理士事務所の業界においても、M&Aは事業の存続と成長のための重要な経営戦略と位置づけられています。
ここでは、業界特有のM&Aの動向や、事業承継との関係性について基本的な知識を解説します。
会計事務所業界におけるM&Aの現状
M&Aとは、事務所の経営権を第三者に譲渡・移転することを指します。
近年、会計事務所の業界でM&Aが活発化している最大の背景は、経営者の高齢化と深刻な後継者不足です。親族や所内に適任者が見つからず、事業の継続に悩む事務所が第三者への譲渡(M&A)を選択するケースが急増しています。
さらに、人材確保の難しさや顧客ニーズの多様化に対応するため、規模拡大や専門性強化を目的としたM&Aも増えています。
事業承継とM&Aの違い
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐこと全般を指す言葉です。承継先によって「親族内承継」「従業員承継」「第三者承継(M&A)」の3つに大別されます。
つまり、M&Aは事業承継を実現するための有力な手法の一つです。かつては親族内承継が主流でしたが、近年は後継者不在の事務所が増加したことで、第三者である企業や個人に事業を引き継ぐM&Aの重要性が高まっています。
M&Aは、信頼できる相手に事業を託すことで、廃業を避け、雇用と顧客サービスを守れる有効な手段です。
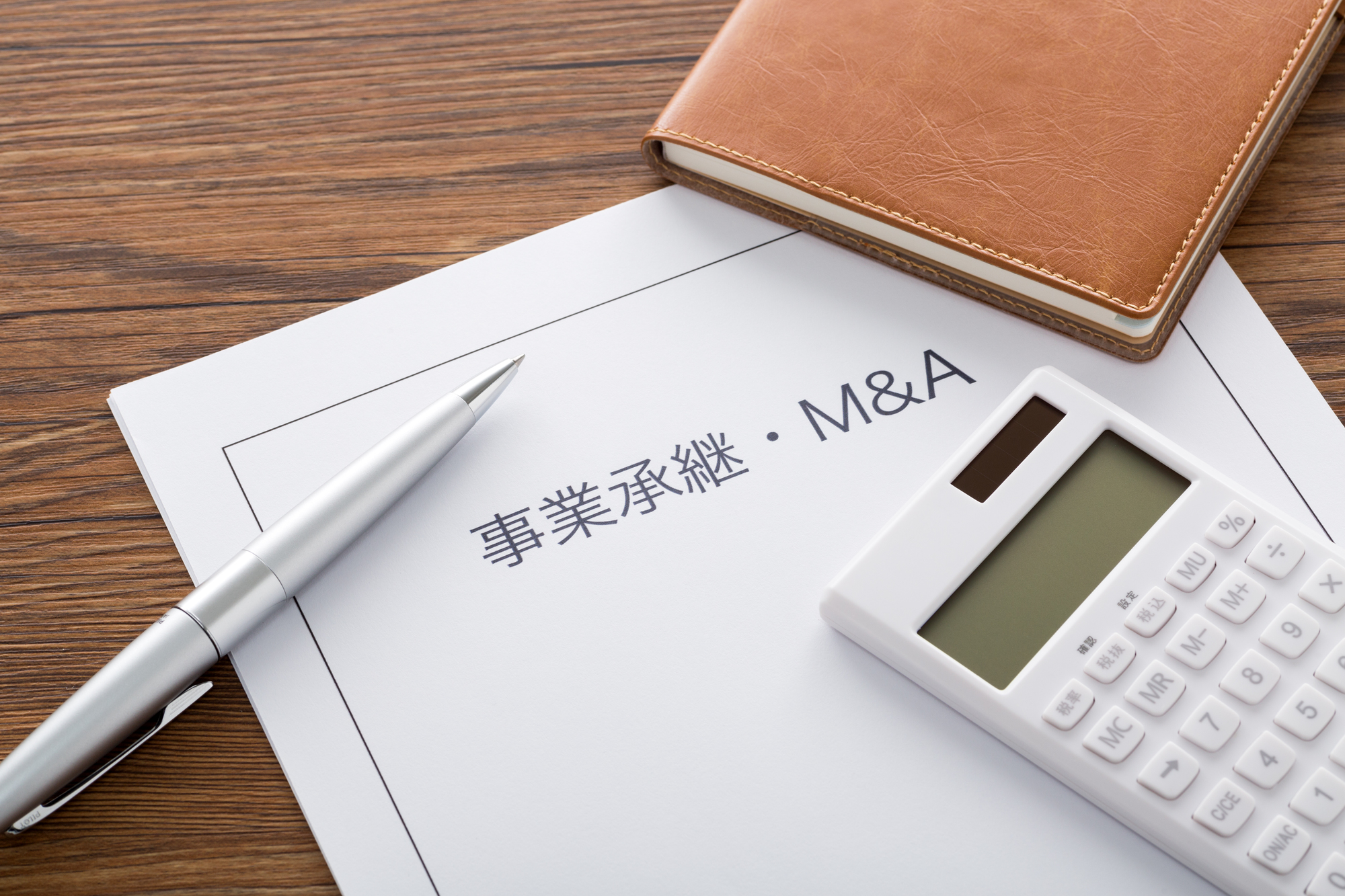

会計事務所・税理士事務所M&Aの市場動向

近年、業界再編の動きが活発化しています。
背景には、経営者の高齢化に伴う後継者不足という構造的な問題があり、多くの中小規模事務所がM&Aを解決策として選択しています。
一方で、大手・中堅の事務所は事業規模の拡大、対応エリアの拡充、専門分野の強化を目的にM&Aを積極的に活用しています。国際税務やDX支援、事業承継支援などの専門性を持つ事務所は需要が高く、今後も市場をけん引すると見込まれます。
会計事務所・税理士事務所におけるM&Aのメリット

買い手側のメリット
買い手にとって、M&Aは事業成長を大きく加速させる有効な手段です。
- 優良な顧客基盤の獲得
売り手が長年かけて築いた顧客基盤と顧問契約を一括で引き継げるため、安定した収益源を短期間で確保できます。 - 専門人材の確保
採用・育成が困難な、経験豊富な税理士や専門知識を持つスタッフをまとめて確保できます。 - 事業エリア・専門分野の拡大
自社だけでは進出が難しかった地域への展開や、新たな専門分野のサービス提供を迅速に開始できます。 - 競争力と信用の向上
事務所の規模が拡大することで、ブランド力が向上し、社会的な信用や競争優位性を高めることができます。
売り手側のメリット
売り手である経営者にとって、M&Aは長年の経営課題を解決し、穏やかな引退を実現するための最適なソリューションとなり得ます。
- 後継者問題の解決
親族や所内に後継者がいないという、最も深刻な問題を円滑に解決できます。 - 事業と雇用の継続
廃業を避け、信頼できる相手に事業を託すことで、従業員の雇用と大切なクライアントへのサービス提供を守ることができます。 - 創業者利益の獲得
事業譲渡によって売却益を確保できるため、引退後の豊かな生活設計が可能になります。 - 経営責任からの解放
日々のプレッシャーから解放され、事務所が継続する安心感を得られることは大きなメリットです。



会計事務所・税理士事務所におけるM&Aのデメリット

買い手側のデメリット
買い手側が直面する最大の課題は、M&A後の統合プロセス(PMI)の難しさです。
- 組織文化の衝突
長年培われた事務所の文化や価値観、業務の進め方が大きく異なる場合、従業員間に軋轢が生じ、組織全体の生産性が低下するリスクがあります。 - 顧客・人材の離反
経営者の交代に対するクライアントの不安から顧問契約が解除されたり、キーパーソンとなる人材が退職してしまったりする可能性があります。 - 偶発債務のリスク
調査で見落とされた簿外債務や未払い残業代を引き継ぐ可能性があります。
売り手側のデメリット
売り手側にとっては、必ずしも自身の希望通りの条件で売却できるとは限らない点がデメリットとして挙げられます。
- 希望条件との乖離
事務所の規模や収益性によっては、買い手が見つかりにくかったり、想定よりも低い譲渡価格を提示されたりする可能性があります。 - 情報漏洩のリスク
M&Aの交渉情報が漏れると、従業員や顧客に不安を与え、組織が混乱するおそれがあります。 - 経営からの完全な離脱
M&Aが成立すれば、大切に育ててきた事業の経営権を完全に手放すことになります。経営への関与ができなくなることに、一抹の寂しさを感じる経営者も少なくありません。



会計事務所・税理士事務所M&Aの相場と価格算出方法

会計事務所のM&Aでは、売却価格の相場が大きな関心事です。価格は企業価値評価の手法を用い、客観的な根拠に基づいて算出します。
M&Aの価格(相場)を決める要素
M&Aの価格は単一の計算式では決まらず、複数の要素を総合評価して決定されます。
主な評価要素は、顧問料の安定性、顧客基盤の質と量、スタッフの経験と専門性、独自ノウハウ、ブランド、地域の市場性です。最終的な価格はこれらを踏まえて交渉により決まります。
代表的な価格算出方法(バリュエーション)
企業価値評価は、以下の3つの方法を状況に応じて組み合わせて行います。
- マーケットアプローチ
「年間顧問報酬×0.8〜1.5倍」といった指標が参考にされることがあります。ただし目安に過ぎず、解約リスク、顧客層の安定性、付加価値、地域性などによって変動するため、個別事情の精査が必要です。 - インカムアプローチ
営業利益の3〜7倍を目安に算出します。所長依存度や有資格者構成、将来収益性によって倍率が変動します。7倍は例外的なケースです。 - コストアプローチ
事務所が保有する純資産を基に評価します。
実務では複数手法を併用し、算出結果を基に譲渡価格を交渉します。



会計事務所・税理士事務所M&Aのスキーム

会計事務所のM&Aで用いられる手法(スキーム)にはいくつかの種類があり、法人の形態やM&Aの目的に応じて最適なものを選択することが重要です。
株式譲渡
株式譲渡は、株主が株式を売却して経営権を移転する方法です。
株式会社形態の会計事務所などで用いられる、最も一般的なスキームです。手続きが簡単で、雇用や顧客契約をそのまま承継できる点がメリットです。
税理士法人では株式が存在しないため株式譲渡は行えません。社員の持分譲渡や加入・退社により経営権を移転します。
事業譲渡
事業譲渡は、特定の事業や資産を選んで売買する方法です。
個人事務所の場合や、法人の一部事業のみを切り出して譲渡したい場合に適しています。譲渡する資産や契約を個別に選定できるため柔軟性が高い反面、手続きが煩雑になる傾向があります。
合併
合併は、複数の法人を一つに統合する方法です。
組織を完全に一体化させることで、強力なシナジー効果が期待できますが、手続きが非常に複雑で時間もかかるため、他のスキームに比べて選択されるケースは限定的です。



M&A・事業承継の流れ・手順

会計事務所のM&Aや事業承継は、半年〜1年以上かかるのが一般的です。成功のためには、各ステップを慎重かつ計画的に進める必要があります。
STEP1:M&Aの検討・準備
まず、自社の財務状況や強み・弱み、後継者の有無などを客観的に分析し、M&Aの目的(後継者問題の解決、事業拡大など)を明確にします。
この段階で、譲渡価格や従業員の処遇など、譲れない条件を整理しておくことが重要です。

STEP2:専門家への相談
M&Aには専門知識が不可欠なため、信頼できるM&A仲介会社やアドバイザーに相談します。
秘密保持契約を締結した上で、自社の希望を伝え、本格的な準備を開始します。

STEP3:譲渡先の選定(マッチング)
仲介会社が、希望条件に合致する候補先を匿名で選定します。
関心を示した候補先企業と、お互いの名称を明かさない形で企業の概要書(ノンネームシート)を交換し、交渉を進める相手を絞り込みます。


STEP4:トップ面談・基本合意の締結
経営者同士で面談し、理念や将来像を共有します。
双方の意思が一致したら、価格やスケジュールなどの条件を定めた基本合意書を締結します。


STEP5:デューデリジェンス(買収監査)の実施
基本合意後、買い手側が売り手側の財務・税務・法務・労務などの状況を詳細に調査します。
これをデューデリジェンス(買収監査)と呼び、事前に開示されていないリスクがないかを確認する重要なプロセスです。

STEP6:最終契約の締結とクロージング
調査結果を踏まえて最終条件を交渉し、合意に達したら最終契約を締結します。
その後、株式や事業の引き渡し、対価の決済を行い、M&Aの法的手続きが完了します(クロージング)。


STEP7:PMI(経営統合プロセス)
契約締結はゴールではなく、文化や業務を統合し、シナジーを高めるPMIが重要です。



会計事務所・税理士事務所M&Aのポイント・注意点

会計事務所のM&Aを成功に導くためには、いくつか重要なポイントと注意点が存在します。
これらを事前に理解し、対策を講じておくことが不可欠です。
成功確率を高めるためのポイント
まず、M&Aの目的を明確にし、一貫した方針で交渉に臨むことが重要です。
また、自社の強みや魅力を客観的に評価し、適正な企業価値を算出しておくことも欠かせません。
そして最も重要なのが、従業員やクライアントの離反を防ぐことです。
M&A後のビジョンを丁寧に説明し、不安を取り除くためのコミュニケーションを尽くす必要があります。信頼できるM&Aの専門家をパートナーに選ぶことも、成功の確率を大きく高める要因となります。
M&Aプロセスにおける注意点
M&Aのプロセスでは、情報管理を徹底しなければなりません。
交渉に関する情報が外部に漏洩すると、従業員や取引先に動揺が広がり、事業価値を損なう原因となります。
また、焦って相手を決めないことが大切です。複数の候補先と面談し、経営理念や文化が合う、心から信頼できる相手かどうかを慎重に見極めることが大切です。契約条件は専門家の助言を受けつつ細部まで確認し、将来のトラブルを防ぎます。


会計事務所・税理士事務所M&Aの仲介会社・支援機関の選び方

M&Aを円滑に進めるには、信頼できる仲介会社の選定が重要です。自社に最適なパートナーを見つけるための要点を解説します。
信頼できるパートナー選びの重要性
M&Aは法務・税務・会計などの専門知識が必要で、交渉力も求められます。
知識や経験の不足は、不利な条件での契約や、思わぬトラブルにつながりかねません。
実績のある仲介会社は、幅広いネットワークで最適な相手を見つけ、専門知識をもとに交渉を進めます。
M&Aの成否は、パートナー選びにかかっていると言っても過言ではありません。
仲介会社・支援機関を選ぶ際の比較ポイント
仲介会社を選ぶ際は、次の点を比較検討します。
- 実績と専門性
会計・税理士業界のM&A実績があり、業界事情に精通しているか。 - 料金体系
着手金・中間金・成功報酬などの発生タイミングと料率が明確か。 - サポート体制
相談から契約、PMIまで一貫して対応できるか。 - 担当者との相性
親身に対応し、信頼関係を築けるか。
おすすめのM&A仲介会社・支援サービス
M&Aの成功は、自社に最適なパートナーを見つけられるかどうかに大きく左右されます。
M&A支援サービスは特徴や得意分野が異なるため、規模・目的・予算に応じて慎重に選ぶ必要があります。
ここでは、代表的な相談先の種類と、それぞれのメリット・デメリットを具体的に解説します。
自社の規模とニーズで選ぶべきパートナーは変わる
M&Aの相談先は、大きく分けて「大手M&A仲介会社」「専門特化型ブティック」「M&Aマッチングプラットフォーム」「公的支援機関」の4つに分類できます。
例えば、比較的大規模で複雑な案件であれば実績豊富な大手仲介会社が適しているかもしれませんし、業界特有の慣習を深く理解してほしい場合は専門特化型が心強いでしょう。
各サービスの特徴を理解し、自社に最も合う支援タイプを選びましょう。
幅広いネットワークと実績を誇る「大手M&A仲介会社」
大手M&A仲介会社は、全国対応のネットワークと多業種の豊富な実績が強みです。多数の買い手候補の中から、最も条件の良い相手先を探せる可能性が高いでしょう。法務・税務などの専門家も社内に抱え、ワンストップで包括的なサポートを受けられる点も魅力です。
- こんな事務所におすすめ
比較的大規模な事務所、複雑なスキームが想定される案件、全国から幅広く候補先を探したい場合。 - 代表的な企業
「M&Aキャピタルパートナーズ」「日本M&Aセンター」など。
業界特有の事情に精通した「専門特化型ブティック」
会計事務所や税理士事務所といった特定の業界に特化しているため、業界ならではの価値評価や慣習、特有のリスクを深く理解した上でアドバイスを受けられます。担当者との距離が近く、個別事情に応じた柔軟なサポートを受けられます。
- おすすめの事務所
専門知識を重視し、担当者と密に進めたい事務所。 - 代表企業
M&A総合会計事務所 など。
コストを抑えて相手を探せる「M&Aマッチングプラットフォーム」
オンライン上で、売り手と買い手が直接コミュニケーションを取り、マッチングを進めるサービスです。
仲介を挟まないため、手数料を大きく抑えられる点が利点です。近年、登録者数が急増しており、思わぬ相手と出会えるチャンスも増えています。
- こんな事務所におすすめ
比較的小規模な案件、M&Aの費用をできるだけ抑えたい、ある程度の知識があり主体的に交渉を進めたい場合。 - 代表的なプラットフォーム
国内最大級の登録者数を誇る「TRANBI(トランビ)」など。
中立的な立場で相談できる「公的支援機関」
国が各都道府県に設置している「事業承継・引継ぎ支援センター」なども、M&Aに関する相談ができる窓口です。公的機関のため、中立的な立場から無料で相談できる点が特徴です。ただし、仲介会社のように手厚い実務サポートを行うわけではないため、M&Aを検討し始めた段階での情報収集や、セカンドオピニオンを求める場として活用するのが良いでしょう。
- こんな事務所におすすめ
M&Aを検討し始めたばかりで何から手をつければ良いか分からない、まずは中立的な意見を聞いてみたい場合。



会計事務所M&Aに関するよくある質問(Q&A)

M&Aを検討するにあたり、多くの経営者様が抱える疑問や不安にお答えします。
Q1. 小さな個人事務所でも、M&Aは可能なのでしょうか?
はい、もちろん可能です。
むしろ、地域に根ざした優良な顧客基盤を持つ小規模事務所は、買い手にとって非常に魅力的です。後継者問題は事務所の規模に関わらず発生するため、M&Aのニーズは常に存在します。重要なのは規模の大小ではなく、自社の強み(顧客層の安定性、特定の専門性など)を正しく評価し、アピールすることです。
Q2. M&Aを考え始めるべき、タイミングやきっかけはありますか?
経営者様が60代に差し掛かり、引退を意識し始めたタイミングで、かつ親族や所内に適当な後継者が見当たらない場合が最も一般的なきっかけです。
その他にも、「自身の健康への不安」や「単独での事業拡大に限界を感じた」といった理由で検討を始める方もいらっしゃいます。
円滑なM&Aには1年以上の期間を要することも多いため、引退を希望する時期から逆算して、3〜5年ほど前から準備を始めるのが理想的です。
Q3. 事務所の売却価格は、どのようにして決まるのですか?
一つの決まった計算式があるわけではなく、複数の評価方法を組み合わせて総合的に算出されます。
一般的には、「年間顧問報酬の0.8〜1.5倍」や「営業利益(役員報酬等を調整後)の3〜7倍」に、純資産額を加味して算定されるケースが多いです。
ただし、これはあくまで目安であり、顧客の質や従業員の勤続年数、将来性などが加味され、最終的には当事者間の交渉によって決定されます。
Q4. 少しでも高く売却するために、事前に準備できることはありますか?
はい、いくつかポイントがあります。
まず、誰が見ても業務内容が分かるように業務マニュアルを整備し、「所長がいなくても事務所が回る」状態を作ることが重要です。
また、顧問契約書を整理・締結し直し、安定した収益基盤を明確にすることも価値向上に繋がります。
日頃から利益率の改善や、特定の顧客への売上依存度を下げるといった経営努力も、評価を高める上で有効です。
Q5. 従業員や顧問先に、M&Aの話はいつ伝えるべきですか?
これはM&Aにおいて最も慎重さを要する問題の一つです。
最適なタイミングはM&Aのスキームによって大きく異なります。
情報漏洩防止のため、最終契約後に告知するケースが多いものの、一概には言えません。
特に「事業譲渡」スキームを用いる場合、従業員の雇用契約や顧客との取引契約は個別に承継手続きが必要となり、事前に同意を得なければなりません。事前説明を怠ると従業員や顧客の離反を招き、M&Aが破談するおそれがあります。どのスキームを選択するにせよ、専門家のアドバイスのもと、買い手と十分に協議し、発表のタイミングや伝え方を慎重に計画することが不可欠です。
Q6. M&A後、従業員の雇用や待遇は守られるのでしょうか?
友好的なM&Aの大半は、従業員の雇用を維持することが譲渡の前提条件となります。
買い手側も、経験豊富なスタッフは事業にとって貴重な財産だと考えているため、基本的に雇用は継続されます。
待遇についても、現状維持か、より良い条件が提示されることがほとんどです。ただし、万全を期すため、従業員の雇用維持については最終契約書に明記することが極めて重要です。
Q7. 売却後、所長はすぐに引退できるのでしょうか?
ケースバイケースですが、多くの場合は円滑な引き継ぎのために、一定期間(例:1年〜3年程度)、会長や顧問といった形で会社に残り、買い手企業をサポートすることが求められます。
特に、顧客との関係性が所長個人に依存している場合は、この引き継ぎ期間がM&Aの成否を分ける重要な要素となります。役割や報酬、期間といった条件は、交渉の段階で明確に定めておく必要があります。
まとめ
本記事では、会計事務所および税理士事務所のM&Aについて、その基礎知識からメリット・デメリット、価格相場、具体的な手続き、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。
後継者不足や競争激化といった課題を抱える多くの事務所にとって、M&Aは事業の存続と成長を実現するための極めて有効な戦略です。
成功の鍵は、M&Aの目的を明確にし、信頼できる専門家のサポートを受けながら、計画的に手続きを進めることにあります。
まずは自社の現状を正確に把握し、M&Aがどのような未来をもたらす可能性があるのかを検討することから始めてみてはいかがでしょうか。本記事が、次の一歩を踏み出す参考になれば幸いです。






