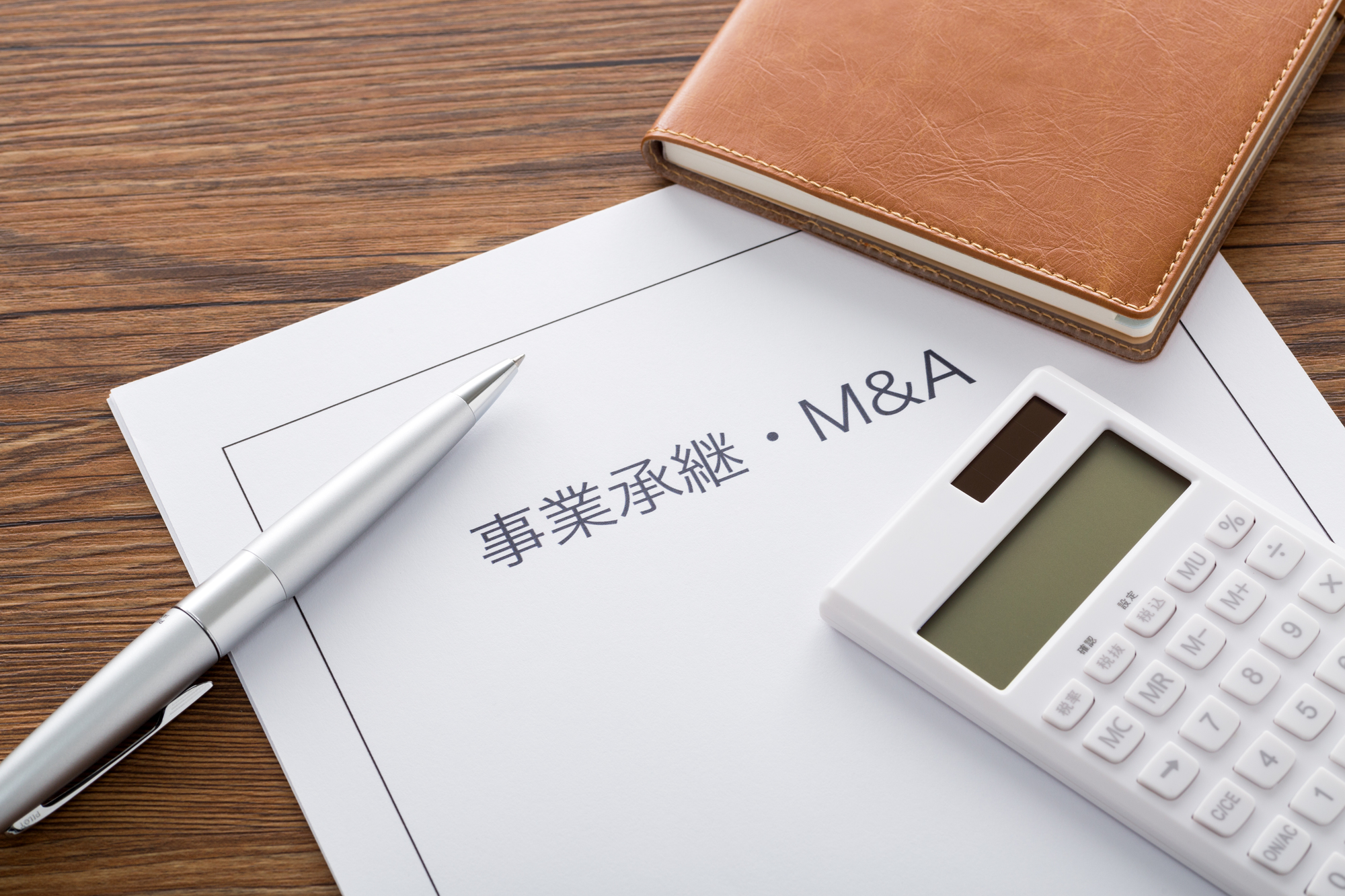製造業のM&A|メリット・事例・動向を徹底解説【2025年最新】
製造業×M&Aの実務ガイド。メリデメ、流れ、仲介/プラットフォーム選び、現場で効くチェックポイントを凝縮。まずは不安の見える化から。
- 05 M&A・事業承継の流れ・手順
- STEP1:事前準備と専門家への相談
- STEP2:相手先の選定と交渉開始
- STEP3:基本合意書の締結
- STEP4:デューデリジェンス(企業調査)
- STEP5:最終契約・クロージング
- STEP6:統合・PMI(経営統合プロセス)
- 08 M&Aプラットフォームを活用した製造業のM&A
- M&Aプラットフォームとは
- M&Aプラットフォームのメリット
- 代表的なM&Aプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」
- 製造業における活用ポイントと注意点
- 09 TRANBIを活用した製造業M&Aの成功事例
- 【事例1】若き2代目経営者が仕掛ける「攻め」のM&A。町工場を「カッコいい製造業」へ
- 【事例2】70歳で後継者探しに数年…TRANBIで出会えた「苦労がわかる創業者」
- 【事例3】84歳の創業者が見つけた「事業をさらに伸ばしてくれる」後継者


「後継者が見つからない」「事業の将来性に不安を感じる」という製造業の経営者も少なくありません。
国内市場の縮小や競争激化の中で、M&Aは事業承継と成長を実現する有効な手段です。
この記事では、製造業のM&Aにおけるメリット・デメリットから、2025年の最新動向、具体的な成功事例、そしてM&Aを成功に導くための手順や注意点までを網羅的に解説します。
本記事を最後までお読みいただくことで、M&Aに関する漠然とした不安が解消され、貴社の未来を切り拓くための具体的な一歩を踏み出すための知識が身につくはずです。
製造業とは

製造業は、原材料を加工して製品を生産する、日本のGDPの約2割を占める主要産業です。
本章では、その市場規模の現状と、多くの企業が直面している深刻な経営課題について詳しく解説します。
製造業の市場規模と推移
日本の製造業は、長年にわたり国内総生産(GDP)の約2割を維持する、文字通り国の屋台骨となる産業です。
特に自動車産業や、そのサプライチェーンを形成する電子部品・デバイス、生産用機械といった分野が市場の中核を担い、世界市場で高い競争力を誇ってきました。
安定した国内需要と、高品質な製品の海外輸出が収益の両輪となっていましたが、その構造は変化の時を迎えています。
国内では少子化による人口減少、海外では新興国の台頭により競争が激化しています。
この厳しい環境変化に対応するため、多くの企業が事業構造の変革を迫られています。
製造業の経営課題
現在の製造業は、複合的で深刻な経営課題に直面しており、これらの課題が、M&Aを検討する主な要因です。
第一に、後継者不足と技術継承の課題があります。
経営者の高齢化が進む一方で、親族や社内に適当な後継者が見つからないケースが急増しています。これにより、長年培ってきた独自の技術やノウハウが失われるリスクが高まっています。
第二に、コスト上昇による収益悪化です。
世界的なインフレーションによる原材料費やエネルギー価格の高騰、さらには人件費の上昇が利益を圧迫しています。価格転嫁が難しい中小企業にとっては、特に深刻な問題です。
第三に、設備投資やデジタル化への対応の遅れです。
カーボンニュートラルやDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応が急務ですが、老朽化した設備の更新や新しい技術への投資には多額の資金が必要です。資金力に乏しい企業は、競争から取り残される危機に瀕しています。


製造業M&Aの背景と動向

製造業においてM&Aが活発化している背景には、事業承継と成長戦略という二つの大きな動機があります。
これらの動向は、今後ますます加速すると見られています。
事業承継型M&Aの増加
最も大きな要因は、経営者の高齢化と後継者不足です。
中小企業庁の調査では、休廃業・解散企業の経営者年齢は60代以上が8割を超えています。
出典:中小企業庁『2025年版 中小企業白書』
M&Aは、事業と技術、雇用を第三者に引き継ぎ、廃業を避ける重要な手段です。
成長戦略型M&Aの加速
国内市場が成熟・縮小する中で、企業が持続的に成長するためには、新たな付加価値の創出が不可欠です。
同業他社との統合による「スケールメリットの追求」、異業種企業との連携による「事業の多角化」、そして先進技術を持つスタートアップ企業の買収による「技術革新のスピードアップ」など、M&Aは企業の成長戦略を実現する強力なツールとして活用されています。
2025年以降は、EV、AI、カーボンニュートラル関連技術などを目的としたM&Aが増えると見込まれます。



製造業M&Aのメリット

M&Aは、事業を譲渡する売り手と譲り受ける買い手の双方に大きなメリットをもたらします。
本章では、それぞれの立場から得られる具体的な利点について、より深く掘り下げて解説します。
譲渡側(売り手)のメリット
- 後継者問題の解決と事業の存続
最大のメリットは、後継者不在による廃業を防げることです。M&Aによって信頼できる第三者に事業を引き継ぐことで、技術やブランド、雇用や取引先との関係を維持し、事業を次世代へ引き継ぐことができます。 - 創業者利益の獲得と個人保証の解除
オーナー経営者は、株式譲渡により会社の価値を現金化できます。これは、引退後の生活資金となるだけでなく、金融機関との交渉を経て、会社の借入金に対する個人保証や担保提供を解消できる可能性があり、経営者の精神的・経済的な負担を大きく軽減します。 - 企業のさらなる成長
資金力や販売網を持つ企業の傘下に入ることで、自社単独では不可能だった大規模な設備投資や研究開発、海外展開などが可能になります。自社事業がより大きなステージで成長する姿を見届けられます。 - 従業員の活躍の場の拡大
大手企業のグループに入ることで、従業員はキャリアアップの機会や充実した福利厚生を得られる可能性があります。これも経営者にとっては大きな安心材料となります。
譲受け側(買い手)のメリット
- 事業拡大のスピードアップ
最大のメリットは時間を短縮できることです。ゼロから工場を建設し、人材を育成し、販路を開拓するには膨大な時間とコストがかかります。
M&Aを活用すれば、すでに確立された事業基盤(人材、技術、設備、販路、顧客)を一度に獲得でき、事業拡大を圧倒的なスピードで実現できます。 - 新規事業や市場への参入
自社とは異なる技術や製品を持つ企業を買収することで、リスクを抑えながら新たな事業分野へ効率的に参入できます。また、特定の地域に強みを持つ企業を譲り受けることで、地理的な事業エリアの拡大も可能になります。 - 人材・技術・ノウハウの獲得
製造業の競争力の源泉は、熟練技術者や開発人材、特許や独自ノウハウなどが競争力の源泉です。M&Aは、これらの経営資源をまとめて獲得できる極めて有効な手段であり、自社の技術力や開発力を飛躍的に向上させることができます。 - サプライチェーンの強化
原材料の供給元や製品の販売先となる企業をM&Aによってグループ内に取り込む「垂直統合」により、サプライチェーン全体の効率化と安定化を図ることができます。これにより、コスト削減や安定供給の実現が期待されます。


製造業M&Aのデメリット
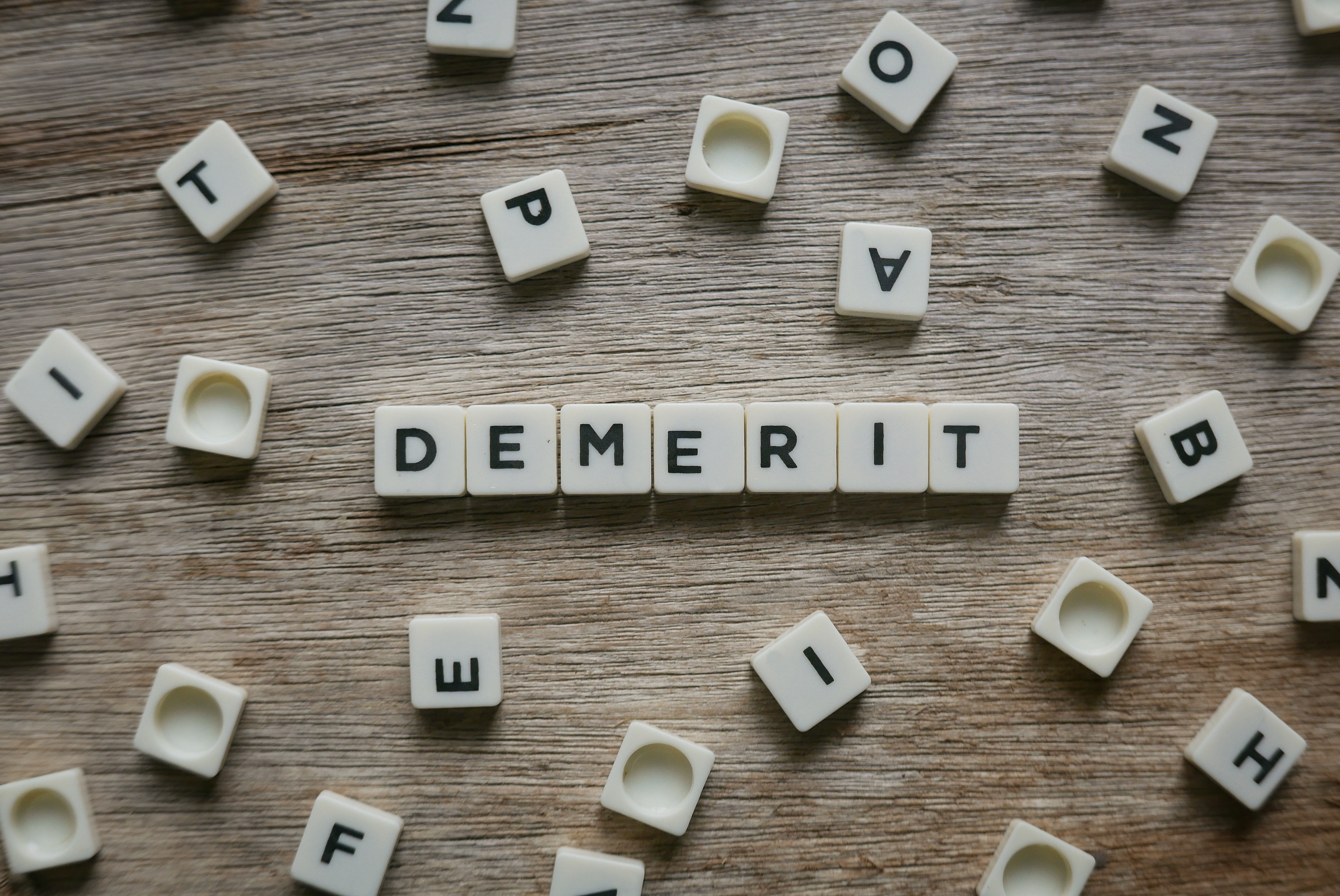
M&Aは多くの利点がある一方、無視できないデメリットやリスクも伴います。
本章では、売り手と買い手それぞれの立場で直面しうる主な課題と、その対策の重要性について解説します。
譲渡側(売り手)のデメリット
- 希望条件に合う相手が見つからない可能性
理想的な買い手がすぐに見つかるとは限りません。事業価値や文化を理解する相手を探すには時間がかかります。交渉が長期化したり、最終的に不成立に終わったりする可能性も十分にあります。 - 情報漏洩のリスク
M&A情報が漏洩すると、離職や取引停止など深刻な影響を招くおそれがあります。そのため、徹底した情報管理が不可欠です。 - 経営権の喪失と従業員の処遇
M&Aが成立すれば、会社の経営権は買い手に移ります。これにより、創業者としての経営の自由度は失われます。
また、統合後の新しい経営方針や人事制度、企業文化の変革に従業員が馴染めず、優秀な人材が離職してしまうリスクも考慮しなければなりません。
譲受け側(買い手)のデメリット
- 想定したシナジー効果が得られないリスク
M&Aの成否を分ける最大の要因です。両社の強みを組み合わせることで生まれるはずの相乗効果(シナジー)が、企業文化の衝突、業務プロセスの非効率、従業員の反発などによって発揮されないケースは少なくありません。 - 簿外債務や偶発債務を引き継ぐリスク
事前のデューデリジェンス(企業調査)が不十分な場合、貸借対照表に記載されていない未払いの残業代や退職金、訴訟リスク、環境汚染の浄化費用といった「隠れた負債」を引き継いでしまう危険性があります。これは買収後の経営に深刻な影響を与えます。 - 人材の流出とモチベーションの低下
M&Aは従業員にとって大きな環境変化であり、不安や不満から主要な技術者や営業担当者といったキーパーソンが離職してしまうリスクがあります。残った従業員のモチベーションが低下し、組織全体の生産性が落ち込むことも大きなデメリットです。 - M&A後の統合プロセスの困難さ
買収後の統合プロセス(PMI)は、M&Aの成否を左右する最も重要なフェーズです。しかし、経営・人事・情報システムの統合には時間とコストがかかり、計画通りに進まない場合もあります。


M&A・事業承継の流れ・手順

M&Aは一般的に半年から1年以上を要する、複雑なプロセスです。
本章では、準備段階から経営統合までの標準的な流れを6ステップで解説します。
STEP1:事前準備と専門家への相談
M&Aの成功は、最初のステップである事前準備にかかっていると言っても過言ではありません。
まず、M&Aの目的(後継者問題の解決、事業成長、創業者利益の確保など)を明確に定義します。
次に、財務状況や強み・弱み、技術、人材などを客観的に分析し、企業価値を把握します。
この段階で、M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)などの専門家に相談し、客観的な助言を受けることが重要です。

STEP2:相手先の選定と交渉開始
専門家と連携し、希望条件に合う相手候補を探索します。
候補が見つかったら、社名を伏せた匿名概要書を提示し、相手の関心度を確認します。
相手が関心を示したら、秘密保持契約を締結のうえ、詳細情報をまとめた資料を開示します。
この資料を基に、相手企業はM&Aを本格的に検討し、交渉がスタートします。



STEP3:基本合意書の締結
経営トップの面談などを通じて、M&Aに対する基本的な方向性や条件を協議します。
そして、譲渡価格の概算やスケジュールで大筋合意に至った段階で、基本合意書(LOI)を締結します。
基本合意書は、価格など主要条件に法的拘束力がないのが一般的ですが、独占交渉や秘密保持など一部条項には拘束力を持たせるのが通常です。これにより、買い手は安心して次のステップであるデューデリジェンスに進めます。


STEP4:デューデリジェンス(企業調査)
デューデリジェンスは、買い手が売り手の価値やリスクを精査するための詳細調査です。
公認会計士や弁護士、税理士などが、財務・税務・法務・事業・人事・ITなど多面的に実態を調査します。
製造業では、工場不動産の法規制、設備の資産価値や老朽化、知的財産、環境汚染リスクが重要項目です。
重大な問題が見つかれば、価格の減額や交渉決裂につながる場合があります。


STEP5:最終契約・クロージング
デューデリジェンス結果を踏まえ、最終価格やその他の条件を交渉します。
双方が合意に至れば、「最終契約書(DA)」を締結します。この契約書は法的な拘束力を持ち、M&Aの取引内容を確定させるものです。
契約締結後は、条件充足を確認し、株式や事業資産の引渡しと代金決済を実行します。
これらが完了すれば、取引は成立し、クロージングとなります。


STEP6:統合・PMI(経営統合プロセス)
クロージングはゴールではなく、新たなスタートです。
PMI(Post Merger Integration)は、M&Aのシナジー効果を最大化し、成功に導くための最も重要なプロセスです。
具体的には、経営理念・ビジョンの共有、業務や情報システムの統合、人事制度や評価の整合を計画的に実行します。
PMIを丁寧に行うことで、不安を解消し、一体感のある組織を構築でき、M&Aの真の成功に繋がります。


製造業M&Aにおける注意点
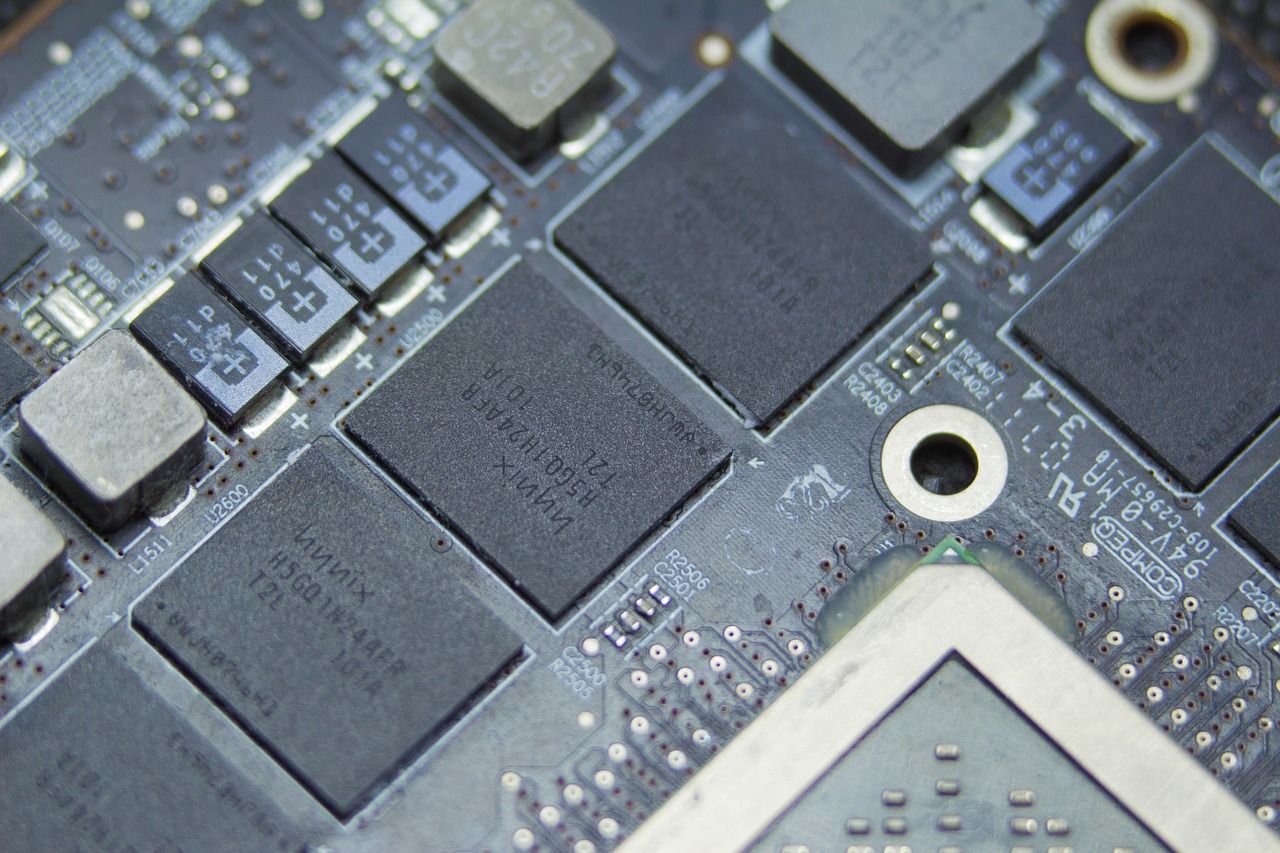
製造業のM&Aには、業界特有の注意点が存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることが、M&Aを成功に導く上で不可欠です。
技術・ノウハウの流出リスク管理
製造業の価値の源泉は、独自の技術や製造ノウハウ、特許などの知的財産にあります。
M&Aの交渉過程でこれらの機密情報を開示するため、情報漏洩のリスク管理は最重要課題です。
秘密保持契約(NDA)を締結し、開示範囲や時期を慎重に設計して段階的に提供することが求められます。
従業員(特に技術者)の離職防止
M&Aは、従業員にとって大きな環境変化となり、将来への不安から優秀な人材が離職してしまうリスクがあります。特に、熟練技術者や開発担当者の流出は、事業価値を大きく損なうおそれがあります。
経営者は、M&Aの目的や統合後のビジョンを丁寧に説明し、不安を払拭することが重要です。
また、キーパーソンとなる人材に対しては、一定期間の雇用継続を契約条件に盛り込むキーマン条項などの対策も有効です。
デューデリジェンスにおける特有のリスク
製造業のデューデリジェンスでは、財務や法務といった一般的な項目に加え、特有のリスクにも注意が必要です。
例えば、土壌汚染やアスベストなどの環境問題、設備老朽化による将来の修繕費、サプライチェーン上のリスクを徹底的に調査する必要があります。
これらを見逃すと、買収後に想定外の費用が発生し、投資対効果を大きく悪化する可能性があります。


製造業M&Aの仲介会社・支援機関の選び方

M&Aは高度な専門知識を要するため、信頼できるパートナー選びが成功を大きく左右します。
自社に最適な仲介会社や支援機関を選ぶためには、いくつかの重要な視点があります。
製造業M&Aに強い実績を持つ仲介会社を選ぶ
パートナー選定で最も重要なのは、製造業のM&A成約実績です。製造業は業種が多岐にわたり、それぞれに特有のビジネスモデルや技術、商慣習が存在します。
同業種や類似規模の実績が多い会社は、的確な評価と最適なマッチングが期待できます。
過去実績を具体的に確認し、自社に最も合うパートナーを選定しましょう。
業界知識と専門家ネットワークの有無を確認する
製造業のM&Aでは、技術の将来性や特許の価値を正しく評価したり、複雑なサプライチェーンを理解したりといった、高度な専門知識が求められます。担当アドバイザーが、こうした業界特有の知見を持つかどうかは、交渉を有利に進める重要な差になります。
また、デューデリジェンスなどで必要となる弁護士、公認会計士、税理士といった外部の専門家との強力なネットワークを有しているかも重要な選定基準です。各分野の専門家と連携し、多角的に支援できる体制があるかを確認しましょう。
手数料体系とサポート体制の透明性を重視する
M&Aには多額の費用が発生するため、手数料体系の明確さと透明性は絶対に欠かせません。
契約前に、着手金や中間金の有無、成功報酬の計算方法(一般的には「レーマン方式」と呼ばれる、取引金額に応じて料率が変動する体系が用いられます)について、詳細な説明を求めましょう。
また、どこまでの業務をサポートしてくれるのか、その範囲を明確にすることも重要です。相手探しから交渉、契約、PMIまで一貫支援できる体制があるかが、安心してM&Aを進めるための鍵となります。


M&Aプラットフォームを活用した製造業のM&A

近年、M&A仲介会社やFAといった従来の支援サービスに加え、インターネット上でM&Aのマッチングを行う「M&Aプラットフォーム」の活用が急速に広がっています。これは、中小企業のM&Aをよりオープンかつ効率的なものにする新しい選択肢です。
M&Aプラットフォームとは
M&Aプラットフォームは、事業を譲渡したい企業と譲り受けたい企業が、オンライン上で直接情報を探し、コミュニケーションをとることができるマッチングサービスです。売り手は情報を登録し、買い手は戦略に合う企業を探して直接アプローチできます。
M&Aプラットフォームのメリット
M&Aプラットフォームを活用する最大のメリットは、コストを抑えやすい点にあります。
一般的に仲介会社に比べて手数料が安い傾向があり、小規模案件では大きな利点になります。
また、幅広い相手探しが可能であることも魅力です。
地域や業種を問わず多数の案件から相手を探せるため、思いがけない優良なパートナーに出会える可能性があります。
代表的なM&Aプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」
「TRANBI」は、国内最大級の登録案件数を誇る代表的なM&Aプラットフォームの一つです。
売り手は無料で情報を登録でき、幅広い買い手から直接オファーを受けられる可能性があります。
最大の特徴は、売り手と買い手が直接交渉でき、スピーディーにマッチングできる点です。>br> 製造業においても、自社のニッチな技術や特定の設備を評価してくれる買い手を、全国から効率的に探すための有効なツールとなり得ます。
製造業における活用ポイントと注意点
高い技術力を持つニッチな製造業企業にとって、M&Aプラットフォームは有効な手段となり得ます。
自社の技術を求めている企業を全国から探したり、自社のサプライチェーンを強化できる部品メーカーを探したりといった活用が可能です。
ただし、プラットフォームの利用には注意点もあります。
交渉や手続きの多くを自社で進める必要があるため、M&Aに関する一定の知識が求められます。
また、企業価値評価やデューデリジェンスなど専門的プロセスは、別途専門家へ依頼する必要が生じる場合もあります。


TRANBIを活用した製造業M&Aの成功事例

M&Aはもはや大企業だけのものではありません。
後継者問題の解決や、事業のさらなる成長を目指す多くの中小企業にとって、M&Aは未来を切り拓くための強力な選択肢となっています。
ここでは、国内最大級のM&Aプラットフォーム「TRANBI」を活用し、実際にM&Aを成功させた製造業の経営者の皆様の事例をご紹介します。
それぞれの事例から、自社の未来を考えるヒントを見つけてください。
【事例1】若き2代目経営者が仕掛ける「攻め」のM&A。町工場を「カッコいい製造業」へ
事業の多角化によって、経営基盤をさらに安定させたいとお考えではありませんか。
A社のA社長は、自社の成長戦略としてM&Aを積極的に活用しています。
元々は溶接加工業を営むA社の2代目であるA氏。
停滞していた会社を再建させた経験から、「情報格差を理由に成長を逃している中小企業と連携すれば、面白い化学反応が起きるはず」と考え、M&Aに関心を持ちました。
TRANBIを通じて別領域の加工会社を買収したことを皮切りに、次々とM&Aに挑戦。その狙いは「自分たちの強みを持つ製造業のなかで、地域や扱う製品や業界を分散させてバランスをとる」ことにあります。
「M&Aをすることで逆に安定していくんです」と語るA氏。
個々の会社が景気に左右されても、グループ全体で見れば安定するポートフォリオを構築。今ではグループ内取引の最適化で利益率を改善しました。
この事例は、M&Aが後継者問題の解決だけでなく、未来を創るための「成長戦略」としても極めて有効であることを示しています。
TRANBIなら、自社のビジョンに共鳴し、共に成長できるパートナーと出会える可能性があります。
※成約・成功事例インタビュー: 次々とM&Aに挑む若き2代目社長 ~「ものづくり」のM&Aで町工場のイメージを「カッコいい製造業」へ~
【事例2】70歳で後継者探しに数年…TRANBIで出会えた「苦労がわかる創業者」
「社員の雇用と、長年育ててきた事業をどうしても守りたい」。後継者不在に悩む多くの経営者が、同じ想いを抱えているのではないでしょうか。
切削・研磨加工業を営んでいたB社のB社長もその一人でした。
70歳を迎え、体力の限界を感じたB社長は第三者への事業承継を決意。しかし、専門機関に相談しても数年間は進展がなく、途方に暮れていたと言います。
そんな時、金融機関の紹介でTRANBIを知り、登録を決断しました。
「この事業を社員、取引先のために残したいという気持ちのほうが強かった」という想いで全国に買い手を募集した結果、状況は一変。登録後すぐに多くの申し込みがあり、わずか半年足らずで成約に至りました。
決め手となったのは、同じ創業者であり、「事業立ち上げの苦労を理解し合える」と感じた買い手の人柄でした。買い手の財務状況も決算書でしっかり確認し、安心して会社を託すことができたと言います。「ともかく何よりも心配だった社員の雇用が守られたのは、ひと安心です。このM&Aは満足の一言ですね」。
この事例は、条件に合う相手がなかなか見つからなくても、TRANBIのように全国規模で探せるプラットフォームを活用することで、理想の相手とスピーディーに出会える可能性を示しています。
※成約・成功事例インタビュー: 「社員の雇用と事業を守るM&Aに成功!~製造業を営む売り手がこだわった事業承継の条件とは?」
【事例3】84歳の創業者が見つけた「事業をさらに伸ばしてくれる」後継者
「長年守ってきた会社を、自分の代で終わらせるしかないのか…」。後継者問題は、経営者にとって最も深刻な悩みのひとつです。
創業50年のC製作所、代表のC氏(84歳)も、予定していた親族への承継が白紙となり、M&Aを決意しました。
C製作所の強みは、365日24時間体制で稼働できる生産体制と、大手企業とも取引のある高い技術力。金融機関からも「これなら買い手は見つかる」と太鼓判を押されていました。複数の候補企業と面談する中で、最終的に同業のグループ会社を持つ企業への売却が決まります。
決め手は、40代の若い社長の熱意と、事業への深い理解でした。驚くべきことに、M&Aの交渉中に買い手候補から「うちで受けきれない仕事を依頼できないか」と打診があり、実際の取引がスタート。この取引を通じてC製作所の技術力が高く評価されると共に、C氏も「この相手となら今後の大きな需要も見込める」と確信を深めました。
「せっかくここまで事業を育ててきましたし、従業員も一生懸命働いてくれているので、残したいなと、決断しました」
その想いは見事に叶い、売却後は買い手からの発注も増え、事業はさらに成長しています。
この事例は、自社の価値を正しく評価し、未来の成長まで考えてくれる相手を見つけることの重要性を示しています。技術力や取引実績といった強みがあれば、TRANBIを通じて新たな事業展開のチャンスを掴むことも可能です。
※成約・成功事例インタビュー: 「創業50年の製作所、一度は後継者が白紙になるも金融機関が『これなら相手が見つかる』と確信した2つの理由とは?」
製造業M&Aのよくある質問

ここでは、製造業のM&Aを検討する経営者様から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
具体的な疑問点を解消し、M&Aへの理解をさらに深めるためにお役立てください。
製造業のM&Aにはどれくらい期間がかかる?
一般的に、相談から最終契約まで半年から1年以上かかるケースが多いです。相手探しや交渉の状況によって期間は大きく変動します。
後継者がいなくてもM&Aは進められる?
はい、進められます。
むしろ後継者不在こそ、M&Aを検討する最も大きな理由の一つです。多くの企業が事業承継を目的としてM&Aを活用しています。
工場や設備も一緒に譲渡できる?
はい、株式譲渡は会社の法人格がそのまま維持されるため、原則として会社が所有する工場、設備、不動産、従業員、許認可などを引き継ぐことが可能です。ただし、許認可によっては役員変更の届出や事前の承認が必要となる場合があるため、個別の確認が必要です。
M&A後に社員の雇用は守られる?
多くの場合、従業員の雇用が維持される条件で交渉が進められます。
買い手側にとっても、経験豊富な従業員は貴重な財産だからです。ただし、最終的な条件は契約内容によります。
M&A仲介会社の手数料はいくら?
手数料体系は仲介会社によって様々ですが、一般的には譲渡価格に応じて変動する「レーマン方式」という成功報酬体系が採用されることが多いです。事前に複数の会社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
まとめ|製造業M&Aの展望
本記事では、製造業のM&Aについて、その背景からメリット・デメリット、具体的な手続き、成功のための注意点までを網羅的に解説しました。後継者不足や市場環境の変化といった待ったなしの課題に直面する製造業にとって、M&Aは事業の存続と成長を両立させるための極めて有効な戦略的選択肢です。
2025年以降、DXやカーボンニュートラルへの対応といった新たな経営課題が重要性を増す中で、これらに対応するための技術やノウハウ獲得を目的としたM&Aは、業界の垣根を越えてさらに活発化していくでしょう。M&Aの成功には目的の明確化、信頼できる専門家の支援、計画的な進行が欠かせません本記事が検討の出発点としてお役に立てば幸いです。